公務員の離職率は本当に低い?民間比較と辞める理由を徹底解説
「公務員は安定しているから離職率も低い」と耳にすることは多いですが、実際のところ本当にそうなのでしょうか。
待遇や雇用の安定性は魅力である一方で、近年は人員不足や働き方への不満から退職を考える人も増えています。
そこで本記事では、公務員の離職率の実態をデータや具体的な理由とともに解説し、辞めるメリットや防止策、転職時のポイントまで徹底的に紹介します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
公務員の離職率の実態

公務員の離職率は長年安定して低い状態を維持しています。特に地方自治体や行政機関では、安定した職業であるため、長期的な雇用が期待でき、離職者が少ない傾向があります。
また、民間企業の離職率と比較しても、公務員の離職率はかなり低いです。例えば、民間企業では、転職やキャリアチェンジが一般的な文化となっているため、離職率が高くなる傾向にあります。
これに対して、公務員は、安定した職場環境や福利厚生、定年後の年金などの魅力的な条件があるため、離職しづらいという側面があります。
しかし、近年では、公務員でも民間企業と同様に、若い世代を中心に職業に対する価値観の変化が影響しています。若年層において離職を選ぶ人が増えてきており、その割合は徐々に上昇しているのです。
特に、キャリアパスの不透明さや業務内容に対する不満から、公務員を辞める人が増えてきています。このような背景を考慮すると、以前よりも若年層の離職率が上昇していることは注目すべき点です。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
公務員の離職率が低い理由

公務員の離職率が低い背景には、安定した給与や福利厚生、退職後の生活保障など、いくつかの大きな理由があります。
ここでは、公務員の離職率が低い理由について解説します。これから公務員を目指す就活生にとっては、この安定性が大きな魅力となるでしょう。
- 給与や待遇が安定しているため
- 年功序列の仕組みで雇用が守られやすいため
- 景気や社会情勢の影響を受けにくいため
- ワークライフバランスを取りやすいため
- 退職金や年金などの老後の生活保障が充実しているため
①給与や待遇が安定しているため
給与や待遇の安定性は、公務員を選ぶ大きな理由の一つです。公務員は、民間企業に比べて、景気に左右されにくい安定した給与体系を持っています。
これにより、生活基盤がしっかりと支えられ、金銭的な不安を感じにくいことが離職を防ぐ要因となっています。
給与の安定性が確保されているため、長期的に安心して働ける点は、公務員にとって大きな魅力です。特に新卒で就職する場合、給与や待遇の安定感は非常に重要な要素となるでしょう。
②年功序列の仕組みで雇用が守られやすいため
公務員は年功序列の仕組みが強く影響しており、長期間勤務すればするほど昇進や給与が上がりやすい傾向があります。
年齢や経験に応じて昇給が見込まれ、安定した雇用が保証されているため、転職を考える必要性が薄れることが多いです。
このような仕組みは、特に公務員を選ぶ理由の一つであり、若い就活生にとっては、将来的な安定性を感じやすくなります。
また、民間企業であれば成果主義の影響を受けることが多く、競争にさらされることがありますが、公務員は比較的競争が少ないため、長く働くことを前提に安定した環境が整っている点が魅力的です。
③景気や社会情勢の影響を受けにくいため
公務員は、民間企業と異なり、景気や社会情勢の影響を受けにくい特徴があります。
景気の波によって業績が変動することが少なく、安定した職場環境が保たれるため、経済状況が悪化しても仕事に対する不安を感じにくいのです。
これにより、他の業界に比べて仕事が失われるリスクが低く、安心して働き続けることができます。
この点も、特に経済の不安定な時期には、公務員を選ぶ理由として大きな要素となります。
企業の倒産やリストラのリスクを心配する必要がなく、公務員としての職を維持できることは、長期的な安定性を求める人にとって大きな魅力です。
④ワークライフバランスを取りやすいため
公務員の仕事は、民間企業に比べてワークライフバランスを取りやすいとされています。
残業が少ない傾向にあり、休暇や有給も比較的取得しやすいため、プライベートの時間を大切にすることができます。
これにより、過度な労働による疲弊を避け、長期的に健康的に働き続けることが可能となります。
特に、家庭を持つことを考えている人にとっては、公務員の柔軟な勤務時間や安定した労働条件が、離職を防ぐ要因となることが多いです。
ストレスが少なく、仕事と生活をうまく両立できるため、長く続けやすい環境が整っています。
⑤退職金や年金などの老後の生活保障が充実しているため
公務員は退職金や年金が充実しており、老後の生活保障が安定しています。
これは民間企業と比べても大きなメリットです。定年後の生活がしっかりと支えられるため、将来に対する不安が少なくなり、長期的に公務員として働き続ける意欲が高まります。
このような老後の生活保障があることで、特に若い世代が公務員として働く際にも、将来の安心感を感じやすくなり、辞職するリスクが低くなります。
退職金や年金に加えて、その他の福利厚生も充実しているため、安定した老後の生活が保障されていると感じる人が多いです。
適職診断であなたにぴったりな職種を見つけよう!
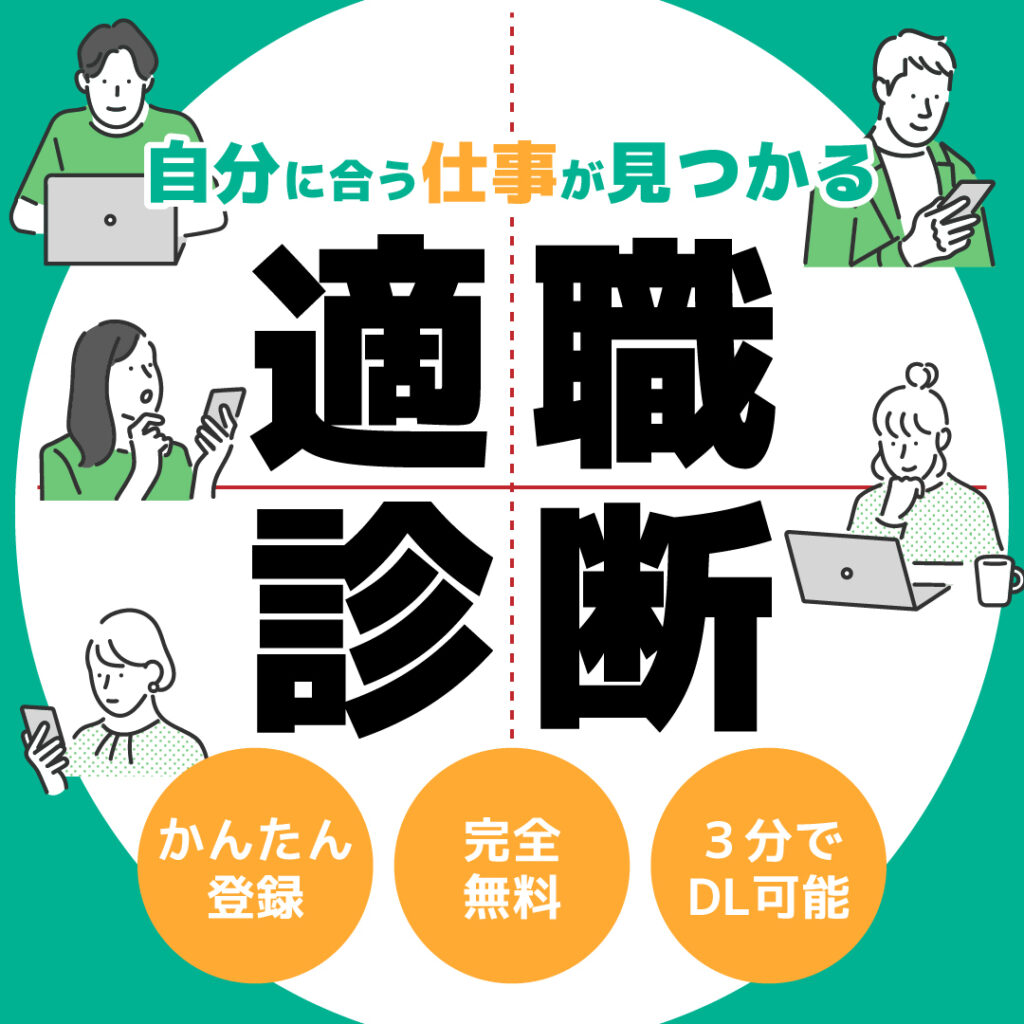
「なんとなく就活してるけど、自分に合う仕事が分からない…」
「選考に応募はしているけど、しっくりこない…」
そんな人にぴったりなのが、就活マガジンが用意している、LINEでできる適職診断です!1
0個の質問にスマホで答えるだけで、あなたの性格や価値観、向いている業界・職種が明確になります。
診断系のツールはパソコンで時間も取られる印象があると思いますが、すべてLINE上で完結するので、移動中やスキマ時間にもサクッと診断ができますよ!
就活に少しでも不安がある人は、まずは気軽に診断してみてください。
公務員が離職する主な理由

公務員が離職する理由はさまざまですが、いくつかの主要な要因があります。公務員として働くことには安定性がありますが、それに伴う課題や不満も存在します。
ここでは、主に公務員が離職を決意する理由を解説し、その背景について詳しく見ていきます。
- 年功序列の仕組みにより成果が評価されにくいため
- デジタル化の遅れで非効率な業務が多く成長を感じにくいため
- ルーティン業務が多く将来的にAIに代替される不安があるため
- 組織主導の人事異動で希望の部署や専門性を選べないため
- 慢性的な人員不足により残業が常態化しているため
- 災害対応や選挙業務で突発的に長時間労働になりやすいため
- 住民からの苦情対応や上層部の方針との板挟みでストレスを感じやすいため
①年功序列の仕組みにより成果が評価されにくいため
年功序列制度が根強く残る公務員の世界では、仕事の成果よりも勤続年数が重視されることが多いです。このため、自己成長を実感しづらく、やりがいを感じられないことがあります。
特に若手の公務員にとっては、年齢や経験に関係なく昇進が決まり、努力が報われにくいと感じることが多いです。
このような制度が原因で、モチベーションが低下し、結果的に離職を考える公務員が増えているのです。
年功序列に対する不満は、特に優れた成果を上げたと感じている人々にとっては大きな問題です。成果を正当に評価してもらえないと、仕事への意欲が減少し、転職を考えるきっかけとなります。
②デジタル化の遅れで非効率な業務が多く成長を感じにくいため
公務員の業務は、民間企業に比べてデジタル化が遅れている場合が多いです。紙ベースの書類管理や手作業が多く、効率が悪いと感じることがあります。
特に若い世代は、デジタル技術に慣れているため、非効率な作業に不満を抱くことが多いです。
また、デジタル化が進まないことで、業務に対する成長を実感できず、モチベーションが低下することがあります。
デジタル化の遅れにより、効率的に業務を進めることができず、自己成長の機会が制限されると感じることが多いです。
これが、業務に対する不満やストレスを増大させ、結果的に離職を考える要因となっています。
③ルーティン業務が多く将来的にAIに代替される不安があるため
公務員の仕事は、ルーチンワークが多い傾向があります。特にデータ入力など、毎日同じ作業を繰り返すことが多いです。そのため、AIやロボット技術の進化により、これらの仕事が自動化されることへの不安もあります。
このような不安は、将来的に自分の仕事がなくなるのではないかという危機感を生み、離職を考えるきっかけとなります。
AIや自動化技術が進展する中で、ルーチン業務が多い仕事は代替される可能性が高いと考える人が増えてきました。これにより、将来の不安が募り、転職を考える公務員が増加しているのです。
④組織主導の人事異動で希望の部署や専門性を選べないため
公務員は、組織主導で人事異動が行われるため、自分の希望や専門性に合った部署に配属されることは少ないです。
このため、自分のやりたい仕事をすることが難しく、転職を考える公務員が多くなります。
特に専門的なスキルを持っている場合、それを活かせる部署に配属されないことが不満につながり、結果的に離職を考える理由となります。
希望する部署に異動できないことは、キャリアの成長を妨げる要因となり、職場に対する不満を高めます。このような状況に直面した場合、自分の能力を最大限に活かすために転職を考える人が増えるのです。
⑤慢性的な人員不足により残業が常態化しているため
公務員の多くの部署では、慢性的な人員不足が問題となっており、そのために残業が常態化しています。特に地方自治体などでは、業務量が多く、限られた人数でこなさなければならないことが多いです。
このような状況では、過労やストレスが積み重なり、仕事に対する不満が大きくなります。残業が多くなることで、プライベートの時間も奪われ、仕事と生活のバランスが崩れてしまいます。
残業が続くことで心身ともに疲弊し、辞職を考えるようになる公務員が増えることがあります。特に、ワークライフバランスを重視する人にとっては、残業が常態化している職場環境が大きな問題となります。
⑥災害対応や選挙業務で突発的に長時間労働になりやすいため
公務員の仕事には、災害対応や選挙業務など、突発的に長時間労働を強いられることがあります。これらの業務は、急な対応が求められ、通常の業務に加えて多くの時間と労力を費やすことになります。
特に若手職員にとっては、これらの突発的な業務が予測できないため、負担が大きく感じられることがあります。
突発的な長時間労働に対する不満が積み重なり、離職を考える公務員が増える原因となります。このような状況に直面した場合、仕事に対するストレスが高まり、退職を決意することがあるのです。
⑦住民からの苦情対応や上層部の方針との板挟みでストレスを感じやすいため
公務員は、住民からの苦情や要望に対応することが多く、時には上層部の方針と住民のニーズが食い違うこともあります。このような状況で板挟みになり、ストレスを感じることが多いです。
特に、解決策が見つからない場合や住民の反発を受けた場合は、精神的な負担が大きくなります。
住民対応や上層部との調整でストレスが溜まり、仕事に対する不満が大きくなると、最終的に離職を選ぶことがあります。
このような状況を避けるためには、ストレスマネジメントや職場環境の改善が求められます。
公務員離職を防ぐための対策

公務員の離職を防ぐためには、職場環境や働き方に対する改善が必要です。従業員が快適に働ける環境を作ることで、離職率を低く抑えることができます。
そして、近年、一部の自治体では公務員の離職率を減少させるための取り組みが始まっています。ここでは、公務員の離職を防ぐために講じられている具体的な対策について紹介します。
- 職場環境を整えて働きやすさを高める
- 働き方改革で長時間労働を是正する
- デジタル化を進めて業務効率を改善する
- 多様な働き方を選べる制度を導入する
- キャリア形成を支援する仕組みを整える
- 人材育成のための研修を充実させる
①職場環境を整えて働きやすさを高める
一部の自治体では、公務員の離職率を減少させるために、職場環境を整え働きやすさを高める取り組みが進められています。例えば、フレックスタイム制度やテレワークの導入などがその一環です。
これにより、職員は柔軟な働き方ができるようになり、仕事とプライベートのバランスを取ることが可能になります。
さらに、職場内の人間関係を改善するための施策や、コミュニケーションを促進する取り組みも行われています。
これらの取り組みが進むことで、従業員がストレスを感じにくくなり、仕事に対する満足度が向上することが期待されています。
職場環境を整えることで、公務員の離職を防ぐための重要な一歩が踏み出されつつあります。
②働き方改革で長時間労働を是正する
一部の自治体では、長時間労働を是正するための働き方改革が進められています。公務員は過度な残業が常態化していることが多く、その改善が求められています。
例えば、業務の優先順位を見直し、効率的に仕事を進めるためのシステム導入が進んでいます。また、残業時間の上限を設けるとともに、ワークライフバランスを重視する文化の定着を目指しています。
これにより、従業員の負担を軽減し、精神的・身体的な健康を守ることができます。長時間労働の是正は、従業員のストレスを減らし、結果的に離職率を低下させる効果が期待されています。
③デジタル化を進めて業務効率を改善する
公務員の業務の非効率さが離職の原因となることもありますが、デジタル化の取り組みが進んでいる自治体も増えています。
例えば、書類の電子化や業務管理システムの導入が進み、手作業による業務の負担が軽減されています。
これにより、業務の効率化が図られ、従業員はよりクリエイティブな仕事に時間を使うことができます。
また、デジタル化が進むことで、従業員が成長を実感できるようになり、仕事のモチベーションが向上することが期待されています。
デジタル化は公務員の業務の質を向上させるための重要な取り組みとなっています。
④多様な働き方を選べる制度を導入する
一部の自治体では、多様な働き方を選べる制度を導入し、従業員のニーズに応えようとしています。
例えば、フレックスタイム制度や在宅勤務、時短勤務など、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が選べるようになっています。
これにより、家庭や育児、介護などの事情を抱える職員も働きやすくなり、離職を防ぐ一助となっています。また、柔軟な働き方は、仕事の効率を上げ、従業員の満足度を高めることにもつながります。
多様な働き方が認められることで、従業員の定着率を高め、組織全体の活力を維持することが可能になります。
⑤キャリア形成を支援する仕組みを整える
キャリア形成を支援するための取り組みが進められている自治体も増えています。
公務員として働く中で、自分のキャリアの方向性が見えにくくなることがありますが、研修やキャリア相談の制度を充実させることで、職員が自分の成長を実感できるようになっています。
例えば、スキルアップのための研修や、リーダーシップを養うためのプログラムが提供されることが一般的です。
これにより、職員は自分のキャリアの進展を感じながら働き続けることができ、モチベーションが高まります。キャリア支援がしっかりと整備されることで、職員の離職を防ぐことができます。
⑥人材育成のための研修を充実させる
人材育成に力を入れる自治体では、研修制度が充実してきています。公務員は専門的な知識やスキルを求められる職業であるため、定期的な研修や教育プログラムが必要です。
特に、管理職候補やリーダーシップを発揮する人材を育成するためのプログラムを整備することが大切です。これにより、職員は自分の成長を実感し、将来に対する不安を減らすことができます。
人材育成に力を入れることで、職員のスキル向上が期待でき、離職率を低下させる効果があると言えるでしょう。
公務員を辞めるメリット

公務員という安定した職業を選ぶことには多くの利点がありますが、公務員を辞めることで得れる、さまざまなメリットもあります。
これらの変化は、より充実した人生を送るための大きな一歩となるでしょう。ここでは、公務員を辞めることで得られる主なメリットについて紹介します。
- キャリアの選択肢が広がる
- 副業やフリーランスなど多様な働き方に挑戦できる
- ライフスタイルに合わせて働き方を選べる
①キャリアの選択肢が広がる
公務員を辞めると、民間企業や他の業界に転職するチャンスが広がり、キャリアの選択肢が増えます。
公務員としての経験やスキルは、さまざまな業界でも活かせることが多いため、転職市場での選択肢が増えるのです。
特に、専門的な知識やスキルがある場合、それを活かして新たなキャリアを築くことができます。
民間企業では成果主義が強調されるため、自分の実力を発揮しやすく、キャリアアップのチャンスが増えるでしょう。
②副業やフリーランスなど多様な働き方に挑戦できる
公務員を辞めると、副業やフリーランスとして働く選択肢も広がります。近年、副業を許可する企業も増えており、時間を有効に使って他の仕事をすることが可能です。
フリーランスとして独立すれば、自由な時間を使って自分のペースで仕事を進めることができます。
このような働き方は、ライフスタイルに合わせて柔軟に働けるため、より充実した生活を送ることができるでしょう。
③ライフスタイルに合わせて働き方を選べる
公務員を辞めることで、仕事と生活のバランスを自分のライフスタイルに合わせて調整することができます。
民間企業やフリーランスでは、テレワークやフレックスタイム制度、時短勤務など、柔軟な働き方を選べる場合が多いため、家庭やプライベートの時間を大切にしながら働けます。
自分に合った働き方を選ぶことで、ストレスが減り、心身の健康を保ちながら働くことができます。このような選択肢が広がることは、公務員を辞める大きなメリットと言えるでしょう。
公務員を辞めたいと感じるときの対処法

公務員を辞めたいと感じることがある場合、いくつかの対処法を試してみることが有効です。自分に合った方法を見つけることで、無理に辞める必要なく、仕事に対する不満を解消できることがあります。
ここでは、公務員を辞めたいと思ったときに試すべき対処法を紹介します。
- 異動を希望する
- 休職制度を利用して立て直す
- 他の業種の公務員へ転職する
- 民間企業への転職する
- 独立や起業に挑戦する
①異動を希望する
公務員として働く中で、特定の部署や業務内容に対する不満が生じることがあります。その場合、まずは異動を希望してみるのが一つの方法です。
公務員は通常、一定期間ごとに異動がありますが、自分の希望に合った部署への異動を希望することで、新しい業務に挑戦することができます。
異動によって、職場環境や業務内容が変わり、仕事に対するやりがいを再発見できるかもしれません。
異動が難しい場合でも、その希望を人事部門に伝えることで、今後のキャリアの方向性を考え直すきっかけになるでしょう。
②休職制度を利用して立て直す
心身の疲れやストレスが原因で辞めたいと感じている場合、休職制度を活用することも選択肢の一つです。公務員には、一定の条件で休職できる制度があります。
休職することで、心身を回復させ、改めて仕事に向き合える状態になることができます。
この時間を使って、自分のキャリアや将来について考え直すことができるため、無理に辞める前に試してみる価値があります。
休職制度を利用することで、必要な休息を取りつつ、再度働く意欲を取り戻すことができる場合もあります。
③他の業種の公務員へ転職する
もし現在の業務内容が自分に合わないと感じる場合、他の業種や部署の公務員に転職することも検討してみましょう。公務員の職場は業種や部署ごとに異なります。
例えば、地方自治体で働いている場合、別の省庁や公共団体に転職することで、新たな挑戦ができます。この方法により、安定した職業を維持しながら、業務内容や環境を改善することができます。
他の業種の公務員に転職することで、より自分に合った仕事を見つけることができる可能性があります。
④民間企業への転職する
公務員としての仕事に限界を感じている場合、民間企業への転職も一つの方法です。民間企業では、公務員とは異なる働き方やキャリアアップの機会が広がっています。
特に、成果主義が強調されるため、自分の能力を発揮しやすくなるはずです。また、民間企業の仕事では、より自由な環境でキャリアを築くことができるため、自分に合った働き方を選びやすくなります。
転職を考える際には、事前にどの業界や職種に興味があるかを明確にし、自分の目標に合わせた選択をすることが重要です。
⑤独立や起業に挑戦する
もし自分のビジョンがある場合、独立や起業に挑戦するのも一つの選択肢です。公務員の経験を活かして自分の事業を立ち上げることができれば、自由な働き方が可能になります。
独立や起業にはリスクが伴いますが、成功すれば大きな達成感を得ることができます。起業に挑戦することで、自分の理想のライフスタイルを手に入れることができるかもしれません。
起業を決意する際には、ビジネスプランや市場調査、資金調達方法などを計画的に進めることが重要です。
公務員を退職する際に注意すべき点

公務員を退職する際には、慎重な計画が重要です。辞める前に後悔しないためにしっかりと検討し、転職活動をスムーズに進める準備を整える必要があります。
また、退職後の生活に支障をきたさないよう、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、公務員を退職する際に注意すべき点について解説します。
- 辞めたあとに後悔しないか検討する
- 在職中は転職活動を秘密に進める
- 生活費や転職活動費の貯金を確保する
- 退職のタイミングを慎重に見極める
①辞めたあとに後悔しないか検討する
公務員を辞めることは大きな決断です。辞職後に後悔しないよう、まずは自分の気持ちをしっかりと整理しましょう。
辞めたい理由が本当に自分にとって大切なものであるか、他に解決方法がないかを考えることが重要です。
たとえば、職場環境や業務内容に不満があっても、異動や転職という他の選択肢があるかもしれません。冷静に自分の状況を見直すことで、後悔しない選択ができるようになります。
また、退職後のキャリアや生活設計についても考慮しておくことが大切です。転職先が決まっていない段階で辞めると不安が増します。しっかりと準備を整えた上で、最良の選択をしましょう。
②在職中は転職活動を秘密に進める
転職活動を行う際、現在の職場に知られないように注意しましょう。在職中に転職活動をしていることが明らかになると、評価に影響を与える可能性があります。
退職前に転職先が決まっていない場合、転職活動を外部で秘密裏に進めるのがおすすめです。職場での関係を維持しながら、慎重に次のステップに進むことができます。
また、転職活動を進める際には、現在の職務に対しても責任を持って取り組むことが大切です。良好な評価を受けることで、今後のキャリアにも良い影響を与えることができます。
③生活費や転職活動費の貯金を確保する
退職後の生活に不安を感じる場合、転職活動のために貯金をしておくことが重要です。生活費や転職活動費を確保しておけば、収入が途絶える期間があっても安心できます。
特に転職活動が長期化する可能性もあるため、3ヶ月分以上の生活費を準備しておくのがおすすめです。また、転職活動には予想以上の費用がかかることもあります。
例えば、面接時の交通費やスーツの購入費、転職エージェントを利用する場合の手数料などです。これらの費用も計算しておき、必要な貯金を確保しておくと安心です。
④退職のタイミングを慎重に見極める
退職手続きに時間がかかることが多く、早めに準備を始めることが重要です。退職願が承認されるまでの期間も含め、退職のタイミングは慎重に見極める必要があります。
公務員が離職する際には、民間企業とは異なり、まず「退職願」を提出し、その後、上司の承認が降りた後に「退職届」を提出するという流れになります。
特に、転職先が決まっていない場合、退職後に収入が途絶えることがないよう、転職先が決定してから退職するのが理想的です。
また、現在の職場に繁忙期や重要なプロジェクトがある場合、その時期を避けて退職することが円満な辞職に繋がります。
公務員の退職手続きは時間がかかるため、十分に計画を立てて退職のタイミングを決めることが大切です。
公務員から転職を成功させるポイント

公務員から民間企業への転職を成功させるためには、事前にいくつかのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、転職を成功させるためのポイントを紹介します。
- 退職理由と転職先での志望動機を明確にする
- 自分のスキルや経験を活かせる仕事を選ぶ
- 転職エージェントを活用する
①退職理由と転職先での志望動機を明確にする
転職を決める前に、まずは自分の退職理由と転職先での志望動機をしっかりと整理しましょう。退職理由が具体的であれば、転職活動を進める際に迷いがなくなります。
また、転職先に求める条件を明確にしておくことで、どの企業や職種が自分に適しているのかを判断しやすくなります。
面接の際には、自分の志望動機をしっかりと伝えることができ、相手に納得感を与えることができます。退職理由や志望動機を整理することは、転職活動を成功させるための第一歩です。
②自分のスキルや経験を活かせる仕事を選ぶ
公務員としてのスキルや経験を民間企業で活かせる仕事を選ぶことが、転職成功のカギを握ります。
公務員として培った調整力や問題解決能力、組織内でのコミュニケーション能力などは、民間企業でも十分に活かせるスキルです。
自分がどの分野で活躍できるかを理解し、それに合わせた企業を選びましょう。また、転職先では、どのように自分の強みをアピールできるかを考え、自己アピールをしっかり行うことが重要です。
自分のスキルを活かせる職場であれば、転職後も充実感を感じながら働けるでしょう。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
③転職エージェントを活用する
転職活動をスムーズに進めるためには、転職エージェントの活用が非常に有効です。
転職エージェントは、求人情報の提供にとどまらず、履歴書や面接のアドバイス、条件交渉まで幅広いサポートを行ってくれます。
公務員から民間企業への転職は、特にサポートが必要となる場合が多いため、転職エージェントの力を借りることで、効率的に転職活動を進めることができます。
自分に合った転職エージェントを選ぶことで、転職活動が円滑に進み、理想の転職先を見つける手助けになります。
公務員の離職率とその実態

公務員の離職率は低いものの、時には離職すべきか悩む職員もいます。公務員が離職する主な理由として、年功序列の評価制度や、業務の非効率さ、長時間労働の常態化などが挙げられます。
これに対し、公務員の離職を防ぐための対策としては、職場環境の改善や、デジタル化の推進、働き方改革が講じられています。
さらに、公務員を辞めるメリットとしては、キャリアの選択肢が広がり、ライフスタイルに合わせた働き方を選べる自由が得られることもあります。
転職を成功させるためには、退職理由を明確にし、自分の経験を活かせる仕事を選ぶことがポイントとなります。
公務員の離職を防ぐための対策や、辞めるメリットを理解し、しっかりと準備を整えることが転職活動を成功させる鍵です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












