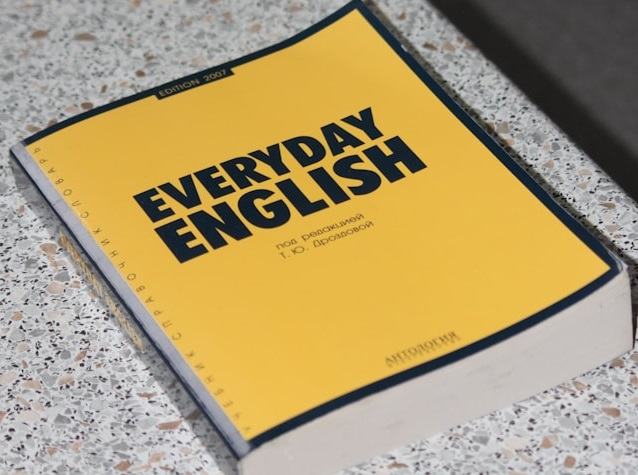【保存版】就活でやること一覧|準備・対策・行動を時期別に整理
「就活のやることが多すぎて、何から始めればいいのか分からない…」
そんな不安を抱く方も多いと思います。自己分析や業界研究、エントリーシートの準備など、やるべきことは時期や学年によっても大きく変わります。
そこで本記事では、就活において学年別・状況別に取り組むべき準備の内容を徹底整理。効率的に進めるコツと具体的な手順を、わかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活の全体像

ここでは、就活の基本的な流れを整理し、自分に合った行動計画を立てるための土台をつくっていきましょう。
就活は「自己分析」「業界・企業研究」「エントリー」「選考対策」「内定承諾」の5段階に分けられます。まず、自己分析では、自分の価値観や強みを言語化することが重要です。
ここが曖昧なままでは、企業選びや志望動機に一貫性が出ず、選考でも説得力に欠けてしまいます。次に、業界や企業について情報を集め、興味のある分野を比較しながら特徴を把握していきます。
インターンや説明会を活用することで、実際の雰囲気もつかみやすくなるはずです。エントリーの段階に入ったら、複数企業への応募に備えてスケジュール管理が欠かせません。
エントリーシートや履歴書は早めに準備し、可能であれば第三者に見てもらって内容をブラッシュアップしてください。選考対策では、SPIや面接練習などの実践的な準備を重ねておくと安心です。
そして内定を得たあとも、どの企業に進むかを見極める判断力が求められます。将来の姿を描きながら、納得のいく選択をしていきましょう。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
【大学1〜2年生】就活準備期にやること

大学1〜2年生の段階は、就活の基盤を築くための大切な準備期間です。早めに行動を始めることで、3年生以降にゆとりを持って選考に臨めます。
ここでは、今のうちに取り組んでおきたい具体的な行動を紹介します。
- 自己分析と将来像の整理を進める
- 学業・サークル・アルバイトでガクチカづくりを進める
- 資格取得・語学学習によるスキル強化を進める
- オープンカンパニー・キャリア教育への参加を進める
- OB・OG訪問や社会人交流の機会づくりを進める
- 業界・職種の情報収集と選考スケジュール把握を進める
- 学生生活の振り返りと経験の言語化練習を進める
①自己分析と将来像の整理を進める
自己分析は、就活の方向性を決めるうえで非常に重要な作業です。自分がどんな価値観を持ち、どんな環境で力を発揮できるかを理解しておくと、企業選びや面接の受け答えに一貫性が生まれるからです。
自己分析が不十分だと、エントリー企業の選定や志望動機が曖昧になり、説得力に欠ける結果につながりやすいでしょう。振り返りには、過去の出来事や達成体験を書き出す作業が効果的です。
また、友人や家族に客観的な意見を求めることで、新たな自分の一面に気づくこともあります。今のうちから少しずつ掘り下げていくことで、本番でも慌てずに自分を言葉で伝えられるようになりますよ。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②学業・サークル・アルバイトでガクチカづくりを進める
ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」を意味し、多くの企業で必ず聞かれる質問です。目立つ経験がなくても構いません。
大切なのは、自分なりに目標を立てて工夫や努力を重ねた経験があるかどうかです。
たとえば、アルバイトで後輩の教育に取り組んだ、サークルでイベントを成功に導いた、ゼミで難題に挑戦したなど、日常のなかにも語れる材料は数多くあります。
今から意識的に行動しておけば、将来の就活で堂々と自信を持ってアピールできるでしょう。実績よりもプロセスを丁寧に振り返る姿勢が評価につながります。
③資格取得・語学学習によるスキル強化を進める
大学1〜2年生のうちは時間に余裕があるため、スキルアップに集中できる貴重な時期です。TOEICや簿記、ITパスポートなどの資格は、業界を問わず基礎的な評価項目として役立ちます。
特に語学力はグローバルな企業や外資系を視野に入れている場合、大きな武器になるでしょう。また、資格取得に向けた継続的な努力の姿勢も、企業は高く評価します。
就活本番ではなかなか時間を割けないため、今のうちに少しずつ取り組んでおくことをおすすめします。小さな積み重ねが、就活での自信につながるはずです。
④オープンカンパニー・キャリア教育への参加を進める
大学1〜2年生向けのオープンカンパニーやキャリアセミナーは、社会や業界の実態を知る貴重な機会です。
こうしたイベントに参加することで、働くことへの理解が深まり、自分の関心がどこにあるのかにも気づきやすくなります。また、実際の企業や社会人と触れることで、就活への意識が一段と高まるでしょう。
大学のキャリア支援課や就活イベントサイトを定期的にチェックして、積極的に行動することが大切です。
参加実績はエントリーシートでもアピール材料になりますので、今のうちから一歩踏み出してみてください。
⑤OB・OG訪問や社会人交流の機会づくりを進める
先輩や社会人との会話は、リアルな仕事観や企業選びの軸を得るチャンスです。ネットには載っていない現場の声を聞くことで、自分に合った働き方や職種がより具体的にイメージできるようになります。
大学の卒業生紹介制度やSNS、リファラル制度を活用すれば、意外と身近に相談できる人が見つかるはずです。
また、社会人との交流を通じて、自分の言葉で質問したり、会話したりする練習にもなります。
今のうちに場数を踏んでおけば、選考時の面談でも堂々と受け答えできるようになるでしょう。
⑥業界・職種の情報収集と選考スケジュール把握を進める
業界ごとに選考時期や求められる資質には違いがあります。たとえば外資系やベンチャーは選考が早く、日系企業は春以降が本格化する傾向です。
そのため、早いうちから各業界の特徴や傾向を知っておくことで、準備の計画が立てやすくなります。業界地図や企業の採用ページ、IR情報、新聞などから情報を集めると良いでしょう。
視野を広げて調べることで、意外な業界に興味を持つこともあります。動き出しのタイミングを逃さないためにも、今のうちから関心を持った業界について調べておくことが大切です。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
⑦学生生活の振り返りと経験の言語化練習を進める
就活では、過去の経験を具体的に説明する力が求められます。どのような場面で、どんな行動を取り、どんな結果を出したのかを伝えられると、面接官の印象に残りやすくなります。
まずは学生生活で印象的だった出来事を紙に書き出し、自分の考えや感情も含めて整理してみてください。この練習を続けることで、自然と表現力や構成力も鍛えられていきます。
文章にするのが難しいと感じる場合は、声に出して説明する練習から始めてみるのもよいでしょう。話す内容を可視化しておくことが、本番の安心感につながります。
【大学3〜4年生】本格的な就活でやること

大学3〜4年生は、選考が本格化するタイミングであり、就活の成否を大きく左右する重要な時期です。
準備の質とタイミングが結果を大きく左右するため、計画的かつ戦略的な行動が求められます。ここでは、この時期にやるべきことを整理して解説します。
- 就活グッズと必要書類の準備を進める
- 就職情報サイト登録とプレエントリーの開始を進める
- 自己分析の深掘りと就活の軸づくりを進める
- 業界研究・企業研究の比較整理を進める
- インターンシップ・会社説明会の参加計画を進める
①就活グッズと必要書類の準備を進める
就活を円滑に進めるには、基本的なツールや書類の準備が欠かせません。スーツやビジネスバッグ、腕時計などは、清潔感と信頼感を与えるための身だしなみとして整える必要があります。
加えて、履歴書・エントリーシート・成績証明書・卒業見込証明書など、企業に提出する書類は早めにそろえておくと安心です。
これらの書類は大学のキャリアセンターや学務課で発行されるため、繁忙期を避けて計画的に申請してください。また、証明写真は市販のスピード写真よりも、プロのカメラマンによる撮影が望ましいです。
高品質な写真は第一印象に影響し、他の応募者との差別化にもつながります。必要な準備を一度に済ませることで、直前で慌てずに済み、精神的な余裕も生まれるでしょう。
②就職情報サイト登録とプレエントリーの開始を進める
情報収集の出発点として、就職情報サイトの活用は欠かせません。マイナビやリクナビをはじめ、各業界に特化したサイトや逆求人型サイトも積極的に利用すると、企業との接点を広げられます。
サイトに登録する際は、自己PRや志望業界、希望勤務地などのプロフィールを具体的に入力しておくことで、スカウトやマッチングの精度が高まるでしょう。
また、プレエントリーは情報収集の第一歩であり、企業からのメルマガやイベント情報を受け取るための鍵になります。
締切やイベント日程を逃さないよう、こまめにチェックしましょう。スケジュール管理アプリなどを使って管理するのもおすすめです。
早い段階で行動を起こすことで、スタートダッシュが可能となり、より多くの選択肢を持って就活に臨めます。
③自己分析の深掘りと就活の軸づくりを進める
自己分析は、自分自身を知るための作業であり、就活全体の基盤となる重要なステップです。
単に「自分の強み・弱み」を挙げるだけでなく、過去の体験を通して得た価値観や意思決定のパターンを深掘りしながら整理することが求められます。
たとえば、部活やアルバイトでの成功・失敗体験を通して「なぜそう考えたのか」「何を感じたのか」と内省することで、自分らしさが見えてきます。
その結果として、企業選びや志望動機の一貫性が生まれ、面接時の説得力も高まるのです。さらに、就活の軸を明確にすることで、内定獲得後に後悔しない企業選びが可能になります。
焦って応募先を増やす前に、まずは自己理解を深め、ブレない就活の土台をつくっておきましょう。
④業界研究・企業研究の比較整理を進める
多くの学生が見落としがちなポイントとして、業界・企業研究の「比較」があります。単に一社一社の情報を集めるだけでは、志望度や適性を見極めるのは難しいものです。
複数の業界を横断的に比較し、それぞれの市場動向・働き方・将来性・求める人材像などを整理することで、より納得感のある選択ができるようになります。
企業研究では、IR情報や社長メッセージ、社員インタビュー記事なども参考になります。また、気になる企業があれば、説明会やOB訪問を通して「リアルな声」を聞いてみるのも効果的です。
調べた情報は、ノートや表にまとめると整理しやすく、選考対策にも役立つでしょう。広く、深く、そして比較して分析することが、後悔のない企業選びのコツです。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
⑤インターンシップ・会社説明会の参加計画を進める
インターンシップや説明会は、企業と学生が直接つながる重要なタッチポイントです。
中でもインターンは、実際の業務を体験しながら企業文化に触れられる貴重な場であり、志望度の高い企業には必ず参加したいところです。
また、会社説明会では、採用担当者や現場社員から直接話を聞くことができ、ホームページでは得られない情報や雰囲気をつかむことができます。
これらのイベントに参加することで、選考対策に活かせる具体的なエピソードも得られるでしょう。参加枠が限られることもあるため、早めの予約とスケジューリングがカギになります。
交通費や宿泊が必要なケースもあるので、事前に計画しておくことが大切です。複数の企業を比較しながら参加していくことで、自分に合う職場像を明確に描けるようになるでしょう。
理系・文系・大学院生・留学生の就活でやること

学生の属性やバックグラウンドによって、就活の準備や戦略には違いがあります。理系・文系・大学院生・留学生、それぞれが直面しやすい課題に対して、適切な対策を取ることが成功への近道です。
ここでは、それぞれの立場に応じたやるべきことを解説します。
- 理系学生の研究両立とポートフォリオ準備のポイント
- 文系学生の職種理解と志望業界選定のポイント
- 大学院生の研究計画・学会時期と学校推薦活用のポイント
- 留学生の日本語対策・就労要件理解のポイント
- 体育会系・長期留学者の時期調整と通年採用活用のポイント
①理系学生の研究両立とポートフォリオ準備のポイント
理系の学生にとって、研究活動と就活の両立は大きな課題です。研究室のスケジュールが不規則で忙しい場合、就活との両立に苦労することが少なくありません。
そのため、事前に教授と相談し、面接や説明会のスケジュールを確保しやすい環境を整えることが大切です。
また、理系ならではの強みとして、研究成果や技術スキルを具体的に示せるポートフォリオの作成も良いでしょう。
プログラム開発、実験データ、論文要旨などを分かりやすくまとめることで、企業側に技術力や論理的思考力をアピールできます。
説明時には専門用語をかみ砕いて伝える練習もしておくと、選考通過率も高まるでしょう。
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
②文系学生の職種理解と志望業界選定のポイント
文系学生は、理系と比べて就職先の選択肢が広く、逆に「どの職種を目指すか」が曖昧になりがちです。
営業、企画、マーケティング、事務など幅広い職種の中から、自分の適性や価値観に合うものを見つけるには、実際の仕事内容の把握が重要です。
OB・OG訪問やインターンを活用して、リアルな業務内容を聞き取り、イメージを具体化しておくとよいでしょう。
さらに、志望業界を絞る際には、自分の興味だけでなく「働き方」や「社会貢献性」などの観点からも評価することが効果的です。
文系の強みであるコミュニケーション力や企画力を、志望理由や自己PRに具体的に落とし込むことで、説得力のある選考対策につながります。
③大学院生の研究計画・学会時期と学校推薦活用のポイント
大学院生の場合、学部生以上に研究や学会への参加が多く、就活の時期と重なりやすい点が特徴です。
研究スケジュールが流動的なこともあるため、早めに年間計画を立て、就活と学会の重複を避ける工夫が求められます。また、理系大学院生に多い「学校推薦制度」は大きなメリットです。
推薦枠での応募は選考プロセスが短縮される場合が多く、内定獲得の確率も高まるため、積極的に活用しましょう。
ただし推薦は一度出すと辞退が難しいことが多いため、自分の希望に合った企業かどうかを十分に確認することが重要です。
研究テーマと企業の技術領域との関連性を明確に伝えることも選考突破の鍵になります。
④留学生の日本語対策・就労要件理解のポイント
留学生にとっての大きな壁は、言語の壁と就労制度の理解です。
ビジネス日本語の運用能力は、書類や面接だけでなく、内定後の業務にも直結するため、JLPT N1レベル以上の日本語力が求められる企業が多くあります。
そのため、就活開始前から日本語能力試験の対策を進めておくことが重要です。また、在留資格や就労ビザの要件を理解しておくことも欠かせません。
企業によってはビザ取得の支援体制が整っていない場合もあるため、説明会や面談時に確認するようにしましょう。
加えて、海外大学とのダブルディグリーや多言語スキルを持つ留学生は、グローバル採用や海外展開を視野に入れる企業からも高い評価を得られるでしょう。
⑤体育会系・長期留学者の時期調整と通年採用活用のポイント
体育会系の学生や長期留学から帰国した学生は、就活の開始が他の学生より遅れることがあります。
そのため、一般的な3月の広報解禁に合わせるのではなく、通年採用や逆求人型サービス、スカウト型サイトを活用することで、出遅れを補う動きが有効です。
また、体育会系ならではの「継続力」や「目標達成志向」、長期留学経験者の「異文化適応力」や「語学力」は、企業にとって魅力的な要素です。
これらをエントリーシートや面接でエピソードとともに具体的に伝えることで、短期間でもインパクトあるアピールが可能です。
限られた時間で最大限の成果を出すためには、戦略的なスケジュール設計と、選考に特化した集中対策がカギとなります。
就活がうまく進まない人がやるべきこと
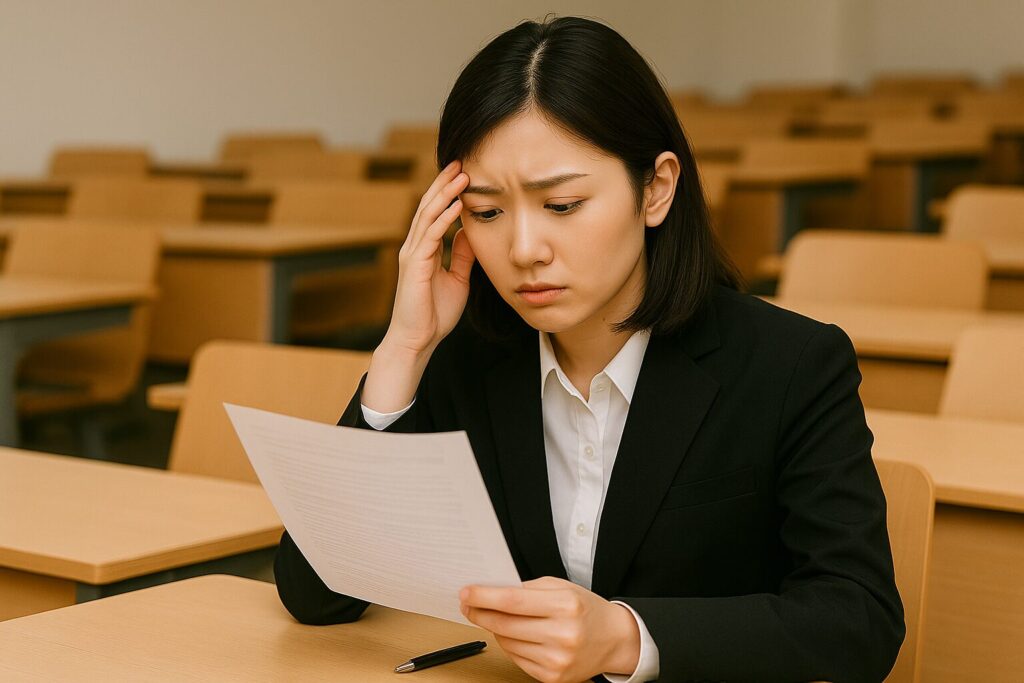
就活が思うように進まないと、不安や焦りが募ります。しかし、適切な見直しと対策を行えば、状況を立て直すことは十分に可能です。
ここでは、選考に落ち続けている人やスタートが遅れてしまった人に向けて、具体的な改善ポイントをご紹介します。
- 自己分析のやり直しと価値観整理の対策
- 応募先ポートフォリオの見直しとターゲット拡張の対策
- エントリーシート・履歴書の構成改善と第三者添削の対策
- 面接フィードバックの活用と回答フレーム強化の対策
- 出遅れリカバリーの短期集中プラン設計の対策
- 大学キャリアセンター・就活エージェント活用の対策
- メンタルケアと学業・就活の両立習慣づくりの対策
①自己分析のやり直しと価値観整理の対策
就活が行き詰まったときこそ、自己分析を最初から見直すことが重要です。表面的な強みやエピソードだけで進めてしまうと、企業とのミスマッチが生まれやすくなります。
そこで、過去の経験を一つひとつ振り返り、「なぜそう行動したのか」「何を感じたか」という内面の価値観にまで掘り下げて考えましょう。
自分のモチベーションの源泉が分かれば、志望動機や自己PRにも一貫性が生まれ、説得力が増します。また、価値観が定まることで企業選びにも迷いが減り、結果的に内定につながる確率が高まるでしょう。
②応募先ポートフォリオの見直しとターゲット拡張の対策
選考が思うように進まない場合、応募先の選び方に偏りがないか見直すことが効果的です。特定の業界や大手企業ばかりに集中していないか、視野を広げて考える必要があります。
例えば、同じ業種でも中堅・ベンチャー企業や地域密着型の企業には、独自の魅力や成長機会があることも多いです。
業界にこだわらず、企業のビジョンや社風、自分との相性を軸に見直すことで、より適した企業に出会える可能性が高まります。応募先の幅を拡張することは、チャンスを広げる第一歩です。
③エントリーシート・履歴書の構成改善と第三者添削の対策
エントリーシートや履歴書で足踏みしている場合は、文章の構成や伝え方を根本から見直すことが必要です。主観的な表現ばかりでは読み手に響きません。
自分の行動に「目的」「結果」「そこから得たこと」の流れを意識して書くことで、論理的かつ具体的な内容になります。
加えて、自分だけでの推敲には限界がありますので、大学のキャリアセンターや信頼できる第三者に添削を依頼しましょう。
客観的な視点からのフィードバックを受けることで、思わぬ改善点に気づけるはずです。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
④面接フィードバックの活用と回答フレーム強化の対策
面接でうまく話せなかった、評価されなかったという場合は、自己流の受け答えに頼っている可能性があります。面接は内容だけでなく、伝え方や構成も問われます。
そこで、「結論→理由→具体例→まとめ」といった回答フレームを意識しながら練習を重ねることが大切です。また、面接後にフィードバックがもらえる場合は必ず確認し、次回に活かすようにしましょう。
模擬面接も有効です。録音や録画を通じて自分の癖や改善点を把握し、磨いていくことで確実に通過率が上がっていくでしょう。
⑤出遅れリカバリーの短期集中プラン設計の対策
就活のスタートが遅れてしまった人は、焦る気持ちが先行しがちですが、まずは戦略的なスケジュールを立てることが優先です。
残り時間を逆算して、短期間で必要な準備を効率よく進める「短期集中プラン」を設計しましょう。
たとえば、1週間ごとに自己分析、企業研究、ES作成、模擬面接といったタスクを配置し、毎日の学業やアルバイトとのバランスも考慮に入れてください。
また、通年採用やスカウト型サービスを活用することで、一般的な選考フローよりも柔軟に就活を進めることができます。動き出しが遅れても、正しい努力をすれば巻き返しは十分に可能です。
⑥大学キャリアセンター・就活エージェント活用の対策
自力での就活に限界を感じたら、外部の支援機関を積極的に活用することが有効です。大学のキャリアセンターでは、ES添削や模擬面接、求人紹介など多くのサポートが無料で受けられます。
利用者が少ない時期を狙えば、丁寧な個別指導も期待できるでしょう。また、就活エージェントに相談することで、自分では見つけにくい企業とのマッチングや選考対策が受けられます。
特に出遅れた学生や非公開求人を狙いたい人には心強い存在です。信頼できる第三者の視点を取り入れることで、新たな視点やチャンスが生まれるはずです。
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
⑦メンタルケアと学業・就活の両立習慣づくりの対策
就活の失敗が続くと、心身に負担がかかり、自己否定感が強まることがあります。こうしたときは、意識的にメンタルケアを行う習慣を取り入れることが大切です。
1日5分でも気持ちをリセットできる時間を設ける、誰かと会話して気分転換するなど、小さな工夫で気持ちの切り替えがしやすくなります。
また、学業やアルバイトとの両立を図るには、スケジュールを可視化し、無理のない計画を立てることがおすすめです。
毎週のタスクを明確にすることで、余裕を持って行動でき、心の安定にもつながるでしょう。
健やかな心と生活習慣が、就活成功の土台になります。
就活を有利に進めるために今やること

就活を少しでも有利に進めたいと考えているなら、情報収集や人脈づくり、特別ルートの活用が鍵になります。ここでは、他の就活生より一歩先んじるための具体的な行動について紹介します。
- OB・OG訪問とリファラル獲得の活用
- IR情報・決算資料リサーチの活用
- 企業SNS・採用広報・社員発信の情報収集の活用
- 長期インターン・ビジネスコンテスト参加の活用
- 逆求人サイト・スカウトサービスの活用
- 早期選考・特別ルート情報の活用
- スケジュール管理ツール・タスク管理の活用
①OB・OG訪問とリファラル獲得の活用
OB・OG訪問は企業理解を深めるだけでなく、実際の選考に役立つ具体的なアドバイスを得る絶好の機会です。
特に、社風や実務内容、選考時に重視されるポイントを知ることで、ESや面接での受け答えに差が出ます。
さらに、社員との信頼関係を築くことで、リファラル(社員推薦)という形で選考ルートが用意される場合もあります。
これは通常ルートよりも早期に進めるチャンスとなるため、できるだけ多くの社会人と接点を持つことが就活成功への近道になります。
②IR情報・決算資料リサーチの活用
企業選びの精度を高めるためには、IR情報や決算書を読むことが有効です。
志望動機を語る際、企業の理念や事業内容だけでなく、「なぜその企業の成長性に惹かれたか」まで語れると、説得力が一段と増します。
たとえば、近年売上が伸びている事業領域に関心がある、自分の強みが新規投資先にマッチしている、など具体的に言及できると良いでしょう。
数字の裏にある戦略や課題を理解していることを示せば、他の就活生との差別化につながります。
③企業SNS・採用広報・社員発信の情報収集の活用
企業のSNSアカウントや採用広報、社員によるブログや動画発信は、公式HPでは得られない「企業のリアル」を知る手段です。
特に若手社員の働き方やキャリアパス、現場の雰囲気は就職後のミスマッチを防ぐうえでも重要な情報源です。
また、面接で「SNSで見た社員の発信が印象的だった」と伝えることで、企業研究の深さをアピールできます。こうした情報を日常的にチェックし、志望企業との親和性を自然に高めていきましょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④長期インターン・ビジネスコンテスト参加の活用
就活の準備段階でスキルや実績を積む手段として、長期インターンやビジネスコンテストの参加は非常に効果的です。実務経験を持っている学生は、企業から即戦力として評価されやすくなります。
特に、IT・コンサル・広告業界などでは、学生時代のプロジェクト経験が選考で問われるケースが多いため、実践の場で成果を出しておくことが有利に働きます。
また、コンテストでの受賞歴や入賞経験は、ガクチカとしても強力な武器になるでしょう。
⑤逆求人サイト・スカウトサービスの活用
企業からのスカウトが届く逆求人型サービスは、受け身にならずに「選ばれる立場」を活用できる戦略の一つです。
プロフィールや自己PRを丁寧に入力することで、あなたに興味を持った企業が直接オファーをくれる仕組みになっています。
特に、就活解禁前の段階で声がかかることも多く、早期内定につながる可能性も高まります。スカウト経由は競争倍率が低い場合もあるため、複数のサービスに登録しておくことをおすすめします。
⑥早期選考・特別ルート情報の活用
特定の学生を対象とした早期選考や、イベント参加者限定の特別ルートを知っておくことは、選考を有利に進めるうえで大きな武器となります。
たとえば、学内説明会、合同企業イベント、逆求人フェアなどでは、企業が早期に学生を囲い込もうとする動きが活発です。
こうしたルートから選考に進むと、通常ルートよりも早く内々定が出ることもあります。情報を逃さずキャッチするには、企業やキャリア支援団体のメルマガ登録も有効です。
⑦スケジュール管理ツール・タスク管理の活用
複数の企業にエントリーしていると、説明会や面接の日程が重なったり、ES提出期限を忘れたりと、管理が煩雑になりがちです。
そこで、スケジュール管理ツールやタスク管理アプリを活用して、すべての選考情報を一元化することが大切になります。
カレンダー形式で可視化することで、優先順位や空き時間が分かりやすくなり、スムーズな対応が可能になるでしょう。
また、タスクを細かく分解することで、今やるべきことが明確になり、精神的な余裕にもつながります。
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
就活の全体像を理解して今やるべき行動を明確にしよう

就活を成功に導くには、自分の立ち位置や準備状況に応じてやるべきことを明確にすることが重要です。
就活は大学1〜2年生の早期準備から始まり、自己分析やガクチカ作成、インターン参加、ES・面接対策、業界研究、選考管理など多岐にわたります。
加えて、理系・文系・大学院生・留学生など属性ごとに求められる対策も異なるため、自分に合った進め方が不可欠です。
思うように進まない場合も、自己分析のやり直しや応募戦略の見直しで挽回できるでしょう。さらに、就活を有利に進めるには、OB・OG訪問や逆求人、インターンなどの積極的な行動も欠かせません。
全体像を把握し、今やるべきことを一つずつ実行することが、納得のいく就職を実現する第一歩です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。