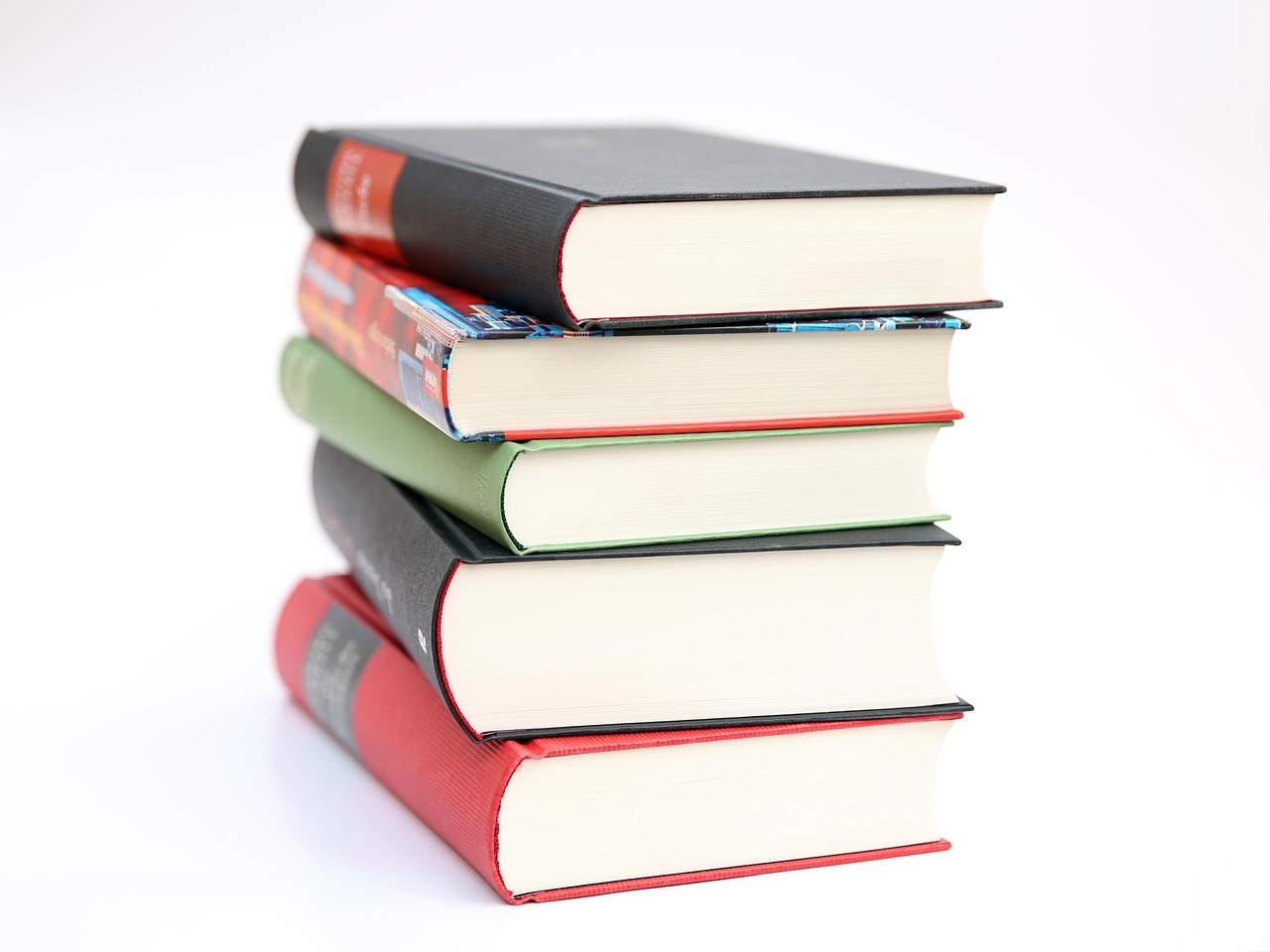一級建築士の平均年収は?年齢・企業別に徹底比較【最新版】
「一級建築士って、どれくらいの年収をもらえるんだろう?」
国家資格の中でも難易度が高く、責任の重い一級建築士。建築業界でのキャリア形成や将来設計を考えるうえで、「収入のリアル」は多くの人が気になるところです。
そこで本記事では、一級建築士の平均年収を年齢・企業・勤務形態別に徹底比較し、実際の収入水準や年収アップのポイントをわかりやすく解説します。
一級建築士の平均年収はいくら?【最新データで徹底解説】

一級建築士の年収は、就職を控えた学生にとって大きな関心ごとです。建築業界の中でも専門性が高く、社会的責任も重い職種であるため、高い収入が期待できる資格といえます。
全体的な平均年収はおよそ650万円〜750万円ほどとされています。初任給では400万円台が多く、経験を積み重ねていくことで着実に年収が上がっていく傾向があるでしょう。
特に大手ゼネコンや設計事務所に勤務する場合は、プロジェクト規模に応じて報酬が高くなり、管理職クラスでは1,000万円を超えるケースも見られます。
一方で、地域密着型の事務所や中小企業に勤務する場合は、やや低めの水準となることもあると言えます。
また、資格を持つことで転職市場での評価も高くなり、キャリアアップや年収アップのチャンスが広がります。
さらに、独立して設計事務所を開業すれば、実績と顧客基盤次第で高収入を得られる可能性もあります。このように、一級建築士は努力や経験がそのまま収入に反映されやすい職業です。
安定した収入に加え、自分の設計が形になる達成感を味わえる点も魅力といえるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」関連データ(PDF)
- 建設業平均年収等(令和5年)
- 企業・求人情報(三菱地所設計)
- 企業・口コミデータ(日本設計)
- 企業・求人データ(積水ハウス)
- 企業年収ランキング(建築・土木業界)
一級建築士と二級建築士の年収差を比較
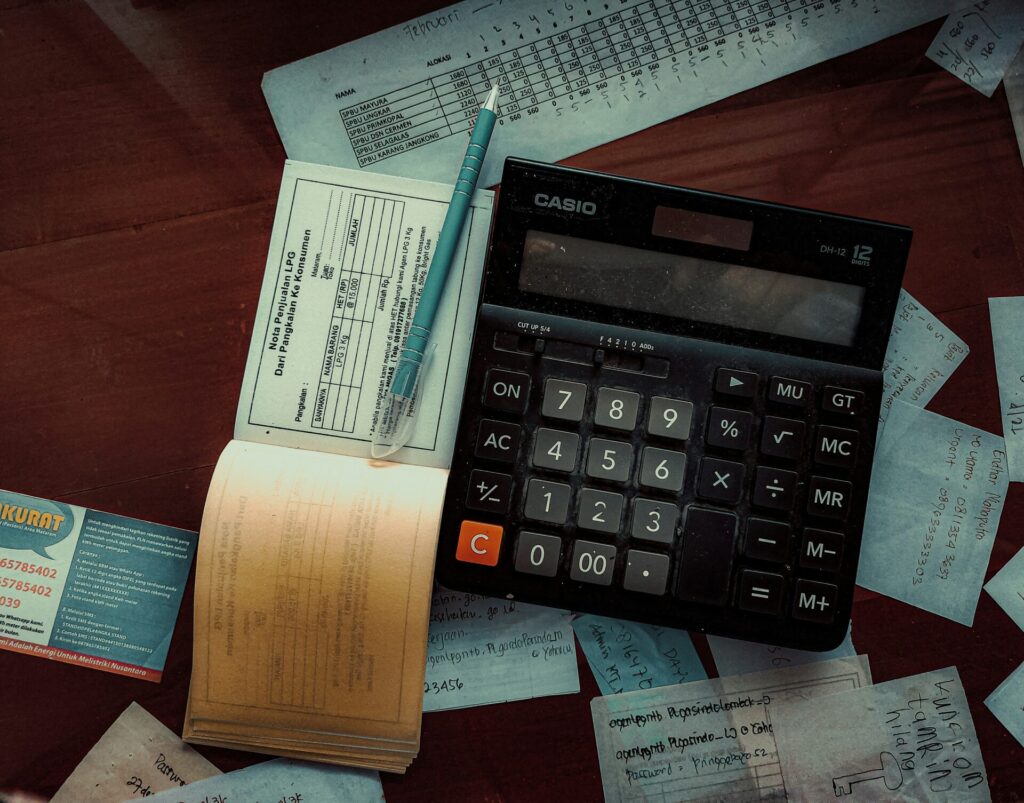
一級建築士と二級建築士の年収差は、建築業界で働くうえで多くの就活生が気にするポイントです。
結論として、一級建築士の平均年収は約600万円前後、二級建築士は約450万円ほどで、およそ150万円の差があります。
一級建築士は、公共施設や高層ビル、商業施設などの大規模案件を手掛けられることが大きな差を産んでいます。こうしたプロジェクトは設計・監理の難易度が高く、責任も大きい分、報酬も高くなるからです。
また、大手ゼネコンや総合設計事務所などでは、一級建築士資格が昇進や資格手当の条件に含まれる場合も多く、年収アップにつながりやすい傾向があります。
実務経験を10年以上積むと、年収700万円を超えるケースも珍しくありません。
一方で、二級建築士は戸建て住宅や小規模店舗などを中心に設計を担当するため、案件単価が低く、平均年収も抑えめになります。
とはいえ、地域に根ざした工務店や設計事務所で安定した仕事を続けられる点は魅力でしょう。年収の差はありますが、どちらの資格も建築業界で重要な役割を果たしています。
結果として、より高い収入やキャリアアップを目指す場合は、一級建築士の取得が有効です。
引用:
経験年数別に見る一級建築士の年収推移
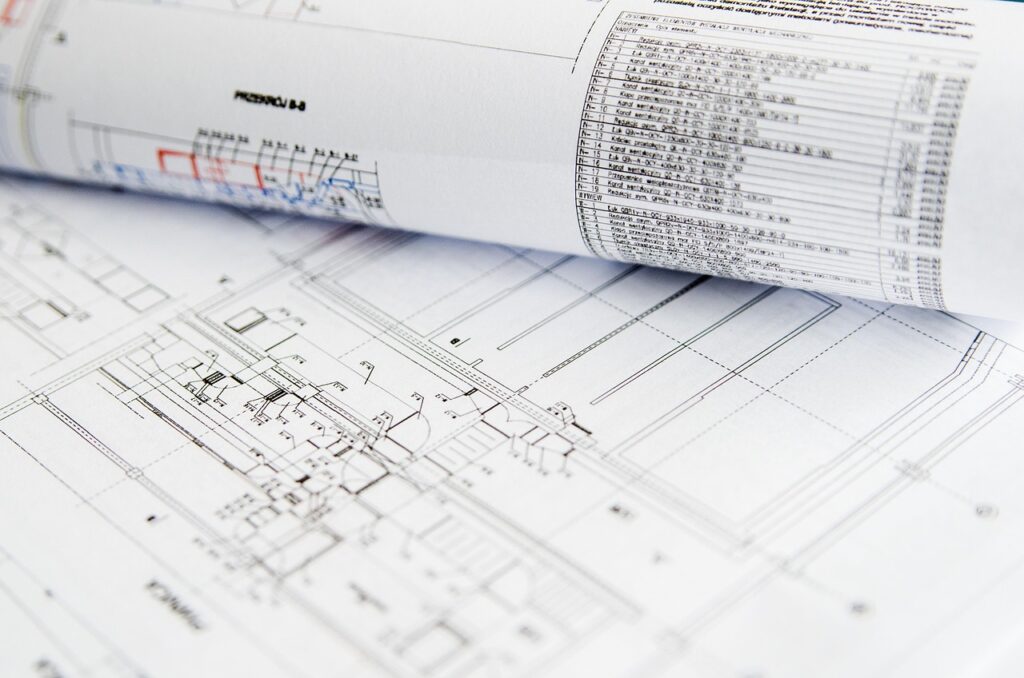
一級建築士の年収は、資格を取得した直後と経験を積んだ後ではかなり変わります。就活前の学生として、「将来どこまで到達できるか」は重要な関心点でしょう。
ここでは、経験年数ごとの年収目安とその理由を具体的に示します。
- 若手(1〜5年目)の年収目安と特徴
- 中堅(6〜15年目)の収入の伸び方
- ベテラン(16年目以降)の年収とキャリアの広がり
①若手(1〜5年目)の年収目安と特徴
経験が浅いうちは、設計補助や図面作成、現場調整などの基礎業務が中心です。判断よりも実行が求められるため、年収はやや抑えられがちです。
建設業全体の平均年収は、厚生労働省のデータで建設業区分で算出されています。若手期ではこの平均を下回る傾向があります。
また、設計事務所の求人例では、経験を重ねた段階で700万〜1,000万円などの提示がされており、成長に伴う飛躍の可能性が見えます。
年収だけでなく、扱う案件の種類・量・指導体制など、将来の成長が期待できる環境かどうかを重視した選び方が望ましいでしょう。
②中堅(6〜15年目)の収入の伸び方
この期間になると、プロジェクト管理、顧客対応、施工調整など責任ある業務を任される機会が増えます。その結果、年収も上昇しやすくなります。
具体的には、設計部門の求人では700万〜1,000万円程度のレンジが設定されることがあります。
ただし、年収の開きは勤務先の規模、案件の種類、業界ポジションに左右されやすいため、自分の専門性と方向性を見定めることが重要です。
③ベテラン(16年目以降)の年収とキャリアの広がり
この時期には、設計部長、技術顧問、経営者(独立)など幅広いキャリアオプションが生まれます。経験と実績次第で、900万円以上を目指す人も少なくありません。
ただし、独立して事務所を運営する場合、受注力・信頼性・営業力などが収入を大きく左右します。安定性よりも実績を積みながら受注が可能な体制をつくることが鍵です。
ある企業の従業員口コミでは、35歳で主任職として年収850万〜900万円という事例も報告されており、高水準を達成する可能性も現実的です。
引用:
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html
- OpenWork:三菱地所設計 年収・給与制度 https://www.openwork.jp/company_answer.php?m_id=a0910000000G2RN&q_no=2
- OpenWork:大東建託 年収・給与制度 https://www.openwork.jp/company_answer.php?m_id=a0910000000Fqfz&q_no=2
- OpenWork:三菱地所設計 年収:1,000万円 給与制度の特徴 https://www.openwork.jp/one_answer.php?vid=a0A2x00000B19rI&qco=2
- OpenWork:三菱地所設計 平均年収比較 https://www.openwork.jp/a0910000000Frqz/compa/a0910000000Fqfz/
企業規模による一級建築士の年収の違い

一級建築士の年収は、勤める企業の規模によって大きく変わります。大企業では平均年収が高く、昇給や賞与制度も整っているケースが多いでしょう。
一方で、中小企業や設計事務所では収入がやや低めになる傾向がありますが、裁量の広さや自由度が高い点が魅力といえます。
公的統計によると、企業の規模が大きくなるほど年収水準が上がる傾向が見られます。
実際に、従業員数が1,000人を超える企業では年収900万円前後となるケースもある一方、100人未満の企業では500万円台にとどまることが多いです。
ただし、必ずしも「大企業=高収入」とは限りません。経験年数、専門性、役職、そして実績によっては、中小企業でも高収入を得ることが可能です。
さらに独立して自分の設計事務所を構えれば、年収1,000万円を超えることもあります。重要なのは、年収だけにとらわれず、成長環境ややりがいを基準に企業を選ぶ姿勢です。
自分に合った働き方を見極めることで、長期的なキャリアの満足度も高まるでしょう。
引用:
男女別に見る一級建築士の年収と女性の活躍状況

一級建築士の年収には性別による差が見られると感じる人も多いでしょう。実際には、厚生労働省の公的データからも、男性・女性間で年収水準に開きが確認されています。
ここでは、女性一級建築士の平均年収、男女差の要因、そして業界での支援・今後の展望について整理していきます。
- 女性一級建築士の平均年収
- 男性との年収差とその要因
- 女性建築士の活躍支援と今後の展望
①女性一級建築士の平均年収
厚生労働省の統計によると、女性一級建築士の平均年収はおおよそ500万円台半ばとなっています。男性よりやや低い傾向がありますが、近年は上昇傾向にあります。
育児と両立しやすい働き方が広がったことや、設計事務所やゼネコンでの管理職登用が進んできたことが背景にあるでしょう。
都市部ではフレックスタイムやリモート勤務を導入する企業が増え、女性が長く働ける環境が整いつつあります。
一方で、地方や中小企業では給与水準が全体的に低く、経験を積んでも昇給が限定的な場合も少なくありません。年収アップを目指すなら、スキルを広げて待遇の良い職場に転職する選択も有効です。
建築士としての専門性を磨きつつ、働き方の幅を持つことが安定したキャリアにつながります。
②男性との年収差とその要因
一級建築士の男女間には、平均でおよそ90〜100万円ほどの年収差があるといわれています。この差の主な原因は、勤務形態や担当業務の違いにあります。
男性は現場管理やプロジェクト責任者など、時間外労働が多い職務に就くことが多いため、結果的に年収が高くなりやすい傾向です。
対して女性は、設計やコーディネートなど家庭との両立がしやすいポジションを選ぶ傾向があり、収入差が生まれやすい構造になっています。
しかし近年は、企業側でもダイバーシティ推進の一環として、女性の管理職登用や報酬制度の見直しを進めています。
成果に基づく評価制度が整えば、今後は性別に関係なく平等な報酬が得られる時代が訪れるでしょう。自身のキャリアを主体的に築く姿勢が、将来の年収差を縮める大きな鍵となります。
③女性建築士の活躍支援と今後の展望
建築業界では、女性建築士のキャリア継続・活躍を支える取り組みが徐々に進んでいます。
国や自治体、建築関連団体による研修制度やネットワーク支援、復職支援制度、在宅勤務制度の導入などがその例です。
こうした制度整備により、女性が長期的・継続的に働きやすい環境が拡充されつつあります。
また、企業側も男女の待遇差に対する世間の関心を受け、OpenWorkなどで評価の公表やギャップ縮小をアピールする動きがあります。
将来的には、建築デザインや都市計画の分野で、女性ならではの視点やセンスがより評価される場面が増えるでしょう。
専門性を磨くとともに、柔軟な働き方を前提としたキャリア設計を志す姿勢が、安定した活躍につながるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査(平成29年)」
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和元年)」
- OpenWork「男女間の待遇満足度のギャップが少ない企業ランキング」
- OpenWork 企業ページ(建築士業界の口コミ・評価)
一級建築士が年収を上げるための具体的な方法
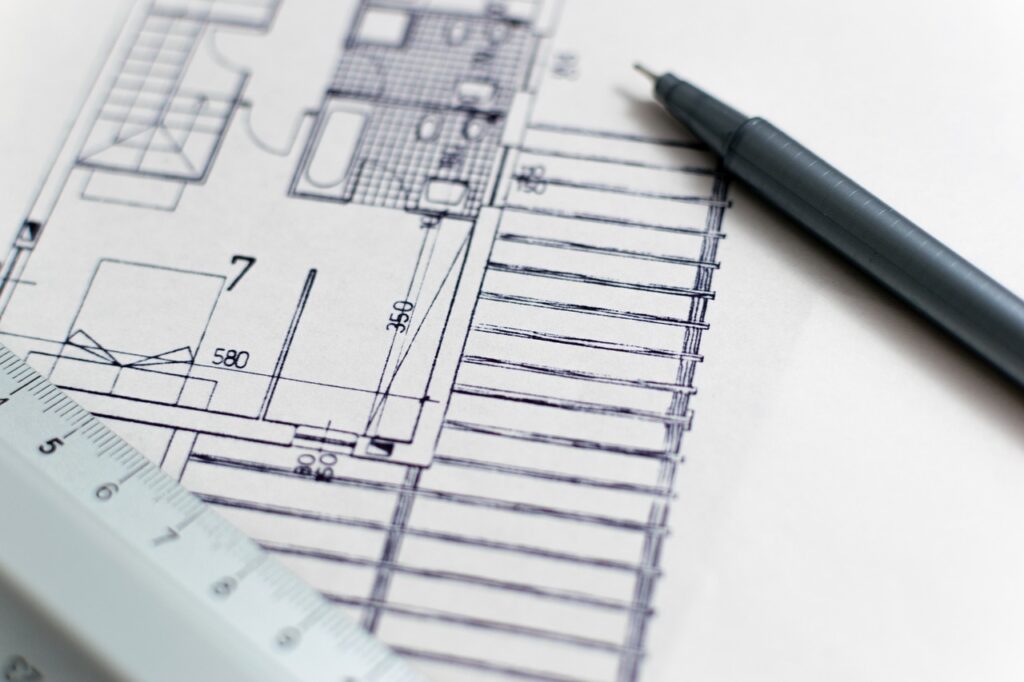
一級建築士として働く中で、「どうすればより高い年収を得られるのか」と考える人は多いでしょう。実際、同じ資格を持っていても経験や働く環境によって収入差が大きく開くのがこの職種の特徴です。
ここでは、キャリア戦略から独立、専門分野の強化、副業まで、年収を上げるための具体的な方法を詳しく紹介します。
- 年収を上げるためのキャリア戦略
- 大手ゼネコンや設計事務所への転職ポイント
- 独立・開業で成功するための準備と戦略
- 専門分野を極めて高単価案件を受注する方法
- 人脈・実績づくりによる収入アップのコツ
- 資格やスキルを活かした副業・複業の可能性
①年収を上げるためのキャリア戦略
建築士として収入を伸ばすには、明確なキャリア戦略が欠かせません。最初の一歩は、自分の得意分野を見極めることです。
住宅、商業施設、都市計画など、どの領域で専門性を磨くのかを明確にすると方向性が定まり、成長が加速します。次に意識したいのは、マネジメント力の向上です。
プロジェクトをまとめる力を身につけることで、主任や管理職といった高収入ポジションに手が届くようになります。
また、職場選びも大切な要素です。短期的な給与額よりも、どのようなスキルを5年後に得られるかを基準に選ぶと良いでしょう。
業務を通じて知識を深め、資格取得や社外活動にも挑戦することで、より価値の高い人材として評価されるはずです。
②大手ゼネコンや設計事務所への転職ポイント
大手ゼネコンや有名設計事務所への転職は、年収を大きく上げるチャンスです。ただし、採用基準が高いため、入念な準備が必要です。特に重視されるのがポートフォリオです。
自分が担当した案件を時系列で整理し、企画・設計・施工の流れを明確に示してください。その際、課題解決の工夫や設計意図を具体的に説明できるようにすると印象が良くなります。
さらに、企業ごとの強みを理解し、自分のスキルがどの分野で活かせるかを明確にしておくことが大切です。たとえば、耐震設計に強い企業なら、その分野での実績を重点的にアピールしましょう。
面接では専門知識だけでなく、チームでの連携力やコミュニケーション能力も評価されます。企業研究を怠らず、自分の価値を伝える準備をしておくことが成功への鍵です。
③独立・開業で成功するための準備と戦略
独立は、一級建築士にとって大きな目標であり、年収を大幅に伸ばせる可能性を秘めています。しかし、準備不足のまま開業すると、安定するまでに長い時間がかかってしまいます。
まずは在職中から人脈を広げ、信頼できる協力会社や職人、顧客との関係を築いておくことが不可欠です。次に、事業計画書を作成し、自分の強みやターゲット層、市場の動向を分析しておきましょう。
特に開業初期は「地域密着型」や「リノベーション専門」など、特定の分野に絞ることで顧客を獲得しやすくなります。資金計画も忘れてはいけません。
開業資金だけでなく、半年分ほどの生活費を確保しておくと安心です。さらに、SNSやホームページで情報発信を行うと知名度が上がり、依頼が増える傾向があります。
安定した顧客基盤を築くことが、長期的な成功につながるでしょう。
④専門分野を極めて高単価案件を受注する方法
高単価案件を受けるには、特定の分野で「この人に頼みたい」と思われる存在になることが重要です。
省エネ設計や木造耐火建築、サステナブル建築など、社会的な注目が集まるテーマに取り組むと需要が高まります。
専門性を磨くには、継続的な学びが欠かせません。学会やセミナーに参加し、最先端の技術を吸収してください。研究発表や資格取得を重ねることで信頼性が高まり、指名案件が増える傾向にあります。
また、自分の実績を外部に発信することも大切です。SNSやWebサイトで施工事例や設計コンセプトを紹介すると、クライアントから直接声がかかることもあります。
さらに、海外の建築トレンドやデザイン思想を学ぶことで新しい視点を得られ、提案力が向上します。専門性と発信力を掛け合わせることが、高単価案件をつかむ最大の武器です。
⑤人脈・実績づくりによる収入アップのコツ
建築士にとって、人脈と実績は収入を左右する大きな要素です。新しい案件の多くは紹介から生まれるため、信頼関係の構築が欠かせません。
まずは業界団体のセミナーや勉強会、展示会などに積極的に参加して顔を売りましょう。現場で知り合った職人や協力業者と良好な関係を保つことも大切です。
仕事の質が評価されれば、次の依頼や推薦につながります。また、完工後にクライアントへアフターフォローの連絡を入れると信頼が深まり、リピートや口コミ紹介が増えるでしょう。
自分の実績を発信する際は、写真やデータを活用して成果を具体的に示してください。実績が積み重なるほど単価交渉もしやすくなり、安定した高収入を実現しやすくなります。
日々の誠実な対応と努力の積み重ねが、結果的に大きな収入差を生むのです。
⑥資格やスキルを活かした副業・複業の可能性
一級建築士の資格は、副業や複業でも大きな武器になります。
たとえば、CAD講師、建築系ライター、住宅相談のオンラインアドバイザー、建築申請サポートなど、専門知識を活かした仕事は多岐にわたります。
特に近年はリモート業務が増え、全国どこからでも仕事を請け負える環境が整いました。本業で得た知識を副業に活かすことで、新しいスキルやネットワークが広がるでしょう。
また、副業によって得た経験が本業にプラスになることも多いです。収入の分散にもつながり、安定感が増すでしょう。
ただし、勤務先によっては副業を制限している場合があるため、必ず就業規則を確認してください。
自分の得意分野を活かし、無理のない範囲で活動を広げていけば、将来的な独立やキャリアの幅も確実に広がります。
一級建築士試験に合格するためのポイント

一級建築士試験は、建築業界で高い専門性を示す国家資格であり、就活時の大きな強みになります。しかし、難関資格であるため、正しい学習戦略を立てなければ合格は難しいのも事実です。
ここでは、出題傾向の理解からモチベーション維持まで、合格に近づくための実践的なポイントを詳しく解説します。
- 試験の出題傾向を理解する
- 学科と製図の対策を分けて進める
- 効率的な勉強スケジュールを立てる
- 過去問と模試を活用して実力を測る
- 予備校や通信講座を活用して合格率を上げる
- モチベーションを維持して最後までやり切る
①試験の出題傾向を理解する
一級建築士試験に合格するには、まず出題傾向を深く理解することが不可欠です。出題範囲は広いものの、実際に毎年繰り返し問われる分野はある程度決まっています。
特に法規・構造・計画・環境設備の4分野では、建築基準法や構造計算、建築史などの重要項目が頻出です。過去3〜5年分の問題を分析し、どのテーマが重点的に出ているかを確認しましょう。
単に答えを覚えるのではなく、なぜその答えになるのかを理解することが重要です。また、過去問を整理して「頻出」「要確認」「苦手」に分類することで、効率的に学習を進められます。
こうした分析を繰り返すことで、出題者の意図を読み取りやすくなり、本番での対応力が格段に向上するでしょう。
②学科と製図の対策を分けて進める
一級建築士試験は、学科と製図の2段階に分かれており、求められる能力がまったく異なります。
学科試験では、正確な知識と素早い判断力が求められ、製図試験では設計力とプレゼンテーション能力が鍵となります。
この2つを同時に対策しようとすると、どちらも中途半端になってしまうケースが多いです。そのため、まずは学科に集中し、基礎知識を確実に固めてから製図に取り組むことをおすすめします。
学科合格後は、製図に特化した時間を確保し、過去課題を分析しながら図面の完成度を高めていくとよいでしょう。段階的な学習法を取ることで、無駄を省き、確実にステップアップできます。
焦らず計画的に進めることが、最終的な合格につながります。
③効率的な勉強スケジュールを立てる
試験対策を成功させるには、長期的かつ現実的な勉強スケジュールを立てることが欠かせません。まず試験日から逆算し、年間・月間・週間の3段階で目標を設定しましょう。
学科試験までは知識の定着を重視し、製図対策期間では手を動かす練習時間を確保するのが理想です。平日は短時間でも継続できる範囲に絞り、休日に復習や実践演習を行うと効率が上がります。
また、進捗を可視化することで達成感を得やすく、学習意欲も維持しやすくなります。勉強計画は固定せず、模試の結果や理解度に応じて柔軟に修正することが重要です。
特に直前期には復習を中心に切り替え、知識の整理と弱点克服を徹底してください。計画的に進めることで焦りを減らし、自信を持って試験本番に臨めるでしょう。
④過去問と模試を活用して実力を測る
一級建築士試験の勉強では、過去問と模試の活用が最も重要です。過去問は出題者の意図を読み解く鍵であり、同時に自分の弱点を見つける最高の教材です。
単に解くだけでなく、正答率や理解度を記録して分析すると、学習の精度が高まります。さらに、模試を定期的に受けることで、試験当日の時間配分や緊張への耐性も養えます。
模試の結果を放置せず、間違えた箇所をノートにまとめて復習する習慣をつけましょう。これにより、学んだ内容が定着しやすくなります。
また、模試は本番同様の環境で受けることで集中力を鍛える機会にもなります。過去問で知識を、模試で実践力を磨くというサイクルを繰り返すことが、確実な実力アップにつながるでしょう。
⑤予備校や通信講座を活用して合格率を上げる
独学で合格を目指す人も多いですが、限られた時間で効率よく合格したいなら予備校や通信講座の利用がおすすめです。
講師による体系的な指導や、最新の出題傾向に基づく教材を使うことで、独学では得られない効率性を実感できます。また、添削指導や質問サポートを活用すれば、理解が浅い部分をすぐに解消できるでしょう。
通信講座であれば、自宅や移動中でもスマホやタブレットで学べるため、時間を有効に使えます。さらに、模試付き講座を選べば、自分の学力を定期的に確認でき、弱点克服にも役立ちます。
費用はかかりますが、自己流で迷走するリスクを減らせる点で大きなメリットがあります。自分に合った学習スタイルを選ぶことが、合格への最短ルートになるでしょう。
⑥モチベーションを維持して最後までやり切る
一級建築士試験の勉強期間は長く、途中でモチベーションが下がる人も少なくありません。モチベーションを維持するためには、短期的な目標と長期的な目標を組み合わせるのが効果的です。
たとえば、「今週中に法規を終える」「来月までに模試で60点を取る」など、達成感を得られる小さな目標を積み重ねましょう。
また、勉強仲間を作って進捗を共有したり、SNSで記録を発信したりすることで、励まし合いながら継続しやすくなります。疲れを感じたときは無理せず休息を取り、気持ちを切り替えることも大切です。
さらに、将来のキャリアを具体的に想像し、「建築士としてどんな仕事をしたいのか」を意識すると、努力の意味を再確認できます。
合格への道は長いですが、自分を信じて継続する力が最終的に成功をつかむ鍵となります。
一級建築士の仕事内容

一級建築士の仕事は幅広く、建物の設計から施工、維持管理までを総合的に担当します。ここでは代表的な業務内容を8つの観点から紹介します。
それぞれの役割を理解することで、将来のキャリアイメージがより具体的になるでしょう。
- 意匠設計
- 構造設計
- 設備設計
- 施工監理
- 建築確認申請業務
- プロジェクトマネジメント
- 耐震診断・改修設計
- リノベーション・リフォーム設計
①意匠設計
意匠設計は、建物の外観や内部空間の美しさ、そして使いやすさを形にする仕事です。クライアントの希望を聞き取り、デザインと機能性、コストのバランスを考えながら設計を行います。
重要なのは見た目の美しさだけでなく、日常生活での快適さや安全性を両立させることです。また、立地条件や周囲の景観に調和するデザインも欠かせません。
環境に配慮したエコデザインやユニバーサルデザインの導入が求められるなど、社会的意識の高まりとともに意匠設計の役割も進化しています。
アイデアを形にする創造性と、現実的な制約を踏まえた判断力の両方が必要です。意匠設計は、建物の印象を決める「顔」をつくる仕事といえるでしょう。
②構造設計
構造設計は、建物を安全に支える骨組みを考える仕事です。地震や風などの自然の力に耐える強度を計算し、安心して利用できる建築を実現します。
鉄筋コンクリートや鉄骨、木造といった構造形式ごとに特性が異なり、最適な構造を選ぶ専門知識が欠かせません。
建築基準法をはじめとした法令や技術基準に従うことはもちろん、コスト面や施工性も考慮して設計を行います。さらに、設計者や施工者と連携しながら、デザインと安全性の両立を図る調整力も求められます。
耐震・制震技術や新素材の活用など、最新技術を取り入れることで、構造設計の可能性は年々広がっています。見えない部分を通じて命と暮らしを守る、社会的責任の大きな仕事です。
③設備設計
設備設計は、建物内の快適な環境づくりを支える要の仕事です。空調・電気・給排水・通信などのシステムを総合的に計画し、快適で省エネな空間を実現します。
設備の配置や容量を誤ると、快適性やエネルギー効率が低下するため、緻密な計画が必要です。特にオフィスや病院などでは、用途に応じた設備設計が欠かせません。
最近では、IoT技術やスマートビルディング化が進み、エネルギー管理や自動制御の分野で新しい知識が求められています。設計段階から施工、メンテナンスまで見通す視点を持つことが重要です。
設備設計は、目には見えにくい部分でありながら、人々の快適さを左右する「建物の生命線」といえる仕事です。
④施工監理
施工監理は、設計図どおりに建物が完成するよう、現場を指揮・確認する重要な仕事です。工事の進捗や品質、安全管理を徹底し、問題があれば即座に対応します。
建築士が現場に立ち会うことで、図面上の理想を現実の構造物として実現できるのです。現場では施工業者や職人、施主とのやり取りも多く、的確な判断と柔軟な対応が求められます。
また、コストや納期を管理する調整力も欠かせません。さらに、現場特有の課題に対して迅速に解決策を見つけ出す対応力が重要です。
施工監理は、設計者の意図を最終的に形にし、品質を確保するための「最後の砦」といえるでしょう。完成した建物を目にした瞬間の達成感は、この仕事ならではの魅力です。
⑤建築確認申請業務
建築確認申請業務は、設計した建物が法律や条例に適合しているかを確認し、行政機関に申請する手続きです。建築基準法、消防法、都市計画法など複数の法令を理解し、書類を正確に作成します。
1つのミスが工事の遅延につながることもあるため、慎重さと正確さが何より大切です。特に都市部では地区ごとの規制や用途制限が多く、最新の法改正情報を把握しておく必要があります。
近年は電子申請が増えており、デジタル知識も求められるようになりました。地味に見える仕事ですが、建築物の安全と信頼を守る重要な工程です。
申請業務を通じて法的な裏づけを確保することで、安心して建築を進められる環境を整えます。
⑥プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメントは、建築計画全体を統括し、スケジュール・コスト・品質を総合的に管理する仕事です。
建物の完成までには多くの専門家が関わるため、それぞれの役割を調整するリーダーシップが求められます。
設計段階から施工、引き渡しまで一貫して全体を見渡し、問題があれば迅速に対処する判断力が必要です。大規模案件では、クライアントとの交渉やコスト削減策の提案も行います。
設計者としての専門性に加え、経営感覚やコミュニケーション能力も発揮する場です。プロジェクト全体を成功に導くこの仕事は、一級建築士としての経験と総合力が試される舞台といえるでしょう。
円滑な進行と高品質な成果を両立させることが、最大の使命です。
⑦耐震診断・改修設計
耐震診断・改修設計は、既存建物の安全性を調査し、必要に応じて補強設計を行う仕事です。日本は地震が多いため、この分野の需要は年々高まっています。
診断では、建物の構造や老朽化の状態を調べ、強度を数値的に分析します。改修設計では、補強材の選定や補修計画を立て、安全性とコストの両立を図ります。
場合によっては建物の利用を続けながら工事を行うこともあり、実務的な工夫が欠かせません。また、耐震性を高めるだけでなく、断熱や省エネ性能を向上させる改修を提案することもあります。
地域の防災力を高め、人々の暮らしを守る社会貢献性の高い仕事です。耐震設計の知識は、今後の建築士にとって欠かせないスキルといえるでしょう。
⑧リノベーション・リフォーム設計
リノベーション・リフォーム設計は、既存の建物を新たな価値ある空間へと再生させる仕事です。老朽化した建物に新しい用途やデザインを与えることで、資産価値を高めます。
単なる修繕ではなく、空間の使い方そのものを変える発想が求められます。近年は、古民家再生やオフィスリノベーションなど、時代のニーズに合わせた多様な案件が増えています。
構造の安全性を確保しつつ、デザイン性や快適性を向上させるバランス感覚が重要です。また、環境負荷を減らす再利用の観点からも注目されています。
リノベーション設計は、過去と未来をつなぎ、人と建物の新しい関係を生み出す創造的な仕事です。柔軟な発想と確かな技術力が求められます。
一級建築士という仕事の魅力とやりがい

一級建築士は建築業界の中でも特に専門性と信頼性が高く、社会的評価の高い資格です。建物の安全を守り、街の景観をつくる重要な役割を担うことから、多くの就活生が憧れる職業でもあります。
ここでは、一級建築士として働くうえでのやりがいや魅力を具体的に紹介します。
- 社会的信頼と責任の大きさ
- 建築を通じて社会に貢献できる魅力
- 自分の設計が形になる達成感
- 長期的なキャリア形成と自己成長の実感
- 働きがいとプライベートの両立
- 一級建築士としての将来性と展望
①社会的信頼と責任の大きさ
一級建築士は、国家資格の中でも特に社会的信頼が厚い職業です。建築物の安全性を守る仕事である以上、日々の業務には常に緊張感と責任が伴います。
設計上の判断ひとつが建物の安全に影響するため、専門知識と経験を積み重ねながら、正確で冷静な判断力を磨く必要があります。
その一方で、社会からの期待も大きく、クライアントや地域の人々から感謝の言葉を受けることも多いでしょう。
大規模プロジェクトでは、行政や専門業者との調整役として中心的な存在になり、チーム全体を導くリーダーシップも求められます。
責任の重さは確かに大きいですが、それを果たすたびに得られる信頼はかけがえのない財産です。自分の専門性が社会の安心や発展につながるという実感こそ、この仕事の本当の魅力といえます。
②建築を通じて社会に貢献できる魅力
一級建築士の魅力のひとつは、設計という専門技術を通じて社会全体に貢献できる点です。建築は単なるモノづくりではなく、人々の生活を支えるインフラでもあります。
たとえば、災害時に避難所となる公共施設や、環境にやさしいエコ住宅を設計することで、誰かの安心や快適さを生み出すことができます。
また、近年はバリアフリー設計やユニバーサルデザインなど、誰もが利用しやすい建物づくりが重視されています。
こうした取り組みを通じて、社会の多様なニーズに応えることができるのもやりがいのひとつです。
自分の仕事が「社会に必要とされている」と感じられる瞬間が多く、建築士としての使命感を強く持てるでしょう。建築を通じて人の笑顔や感謝に触れられることは、何よりも大きなモチベーションになります。
③自分の設計が形になる達成感
設計した建物が完成し、実際に人々の生活の場として使われる瞬間は、一級建築士にとって最高の喜びです。
自分の頭の中で描いた構想が、図面を経て、現実の建物として立ち上がるまでのプロセスには多くの苦労が伴います。
クライアントの要望、法規制、コストや環境条件など、さまざまな制約を乗り越える必要があります。
しかし、それらをすべてクリアして完成を迎えた瞬間、苦労が一気に報われるような達成感を味わるでしょう。
さらに、自分の設計した建物が街の一部として残り、時間が経っても人々に利用され続けることは、大きな誇りとなります。
建築士として「自分の仕事が社会に形として残る」という経験は他の職種では得がたいものです。挑戦の多い職業ですが、そのぶん成果が目に見える形で実感できる点が魅力といえるでしょう。
④長期的なキャリア形成と自己成長の実感
一級建築士のキャリアは、資格を取得した後も続く学びと挑戦の連続です。若手のうちは現場で経験を積み、設計や法規、構造、施工など多方面の知識を身につけていきます。
その後、経験を重ねることでプロジェクトマネージャーやデザインリーダーなど、より責任のあるポジションへとステップアップしていくことができます。
また、キャリアの幅が広いのも特徴です。設計事務所での勤務を経て独立する人もいれば、企業の建設部門や行政機関で働く人もいます。
どの道を選んでも、自らの努力次第で専門分野を深めたり、マネジメントスキルを高めたりすることが可能です。さらに、社会の変化に合わせて新しい技術や価値観を取り入れる柔軟さが求められます。
学び続ける姿勢が、自分の成長とキャリアの安定につながる職業といえるでしょう。
⑤働きがいとプライベートの両立
建築業界は忙しい印象を持たれがちですが、近年は働き方改革やデジタルツールの導入により、効率的に働ける環境が整いつつあります。
特に一級建築士は専門性を活かして多様な働き方を選べる点が大きな魅力です。企業に勤めながらプロジェクト単位で働く人もいれば、フリーランスとして柔軟に案件を選ぶ人もいます。
自分の得意分野を活かして仕事を調整すれば、家庭や趣味との両立も十分に可能です。たとえば、在宅ワークを取り入れて設計業務を進めるケースも増えています。
プロジェクトごとに明確な区切りがあるため、オンとオフの切り替えがしやすく、精神的にも充実しやすいでしょう。
働き方の多様化が進む今、一級建築士は自分のライフスタイルに合った働き方を実現しやすい職業です。
⑥一級建築士としての将来性と展望
一級建築士の需要は今後も続くと考えられます。老朽化したインフラの改修や災害対策、省エネ建築や再生可能エネルギー対応の設計など、新しい分野での活躍が増えています。
また、AIやBIM(建築情報モデリング)といったテクノロジーが普及し、設計の効率化や品質向上が進んでいます。
こうした変化に柔軟に対応できる建築士は、今後ますます高い評価を得るでしょう。さらに、国内だけでなく海外のプロジェクトに関わる機会も増えつつあり、グローバルに活躍できる可能性も広がっています。
資格を持つことでキャリアの安定性を確保できるのはもちろん、新しい技術や社会課題に挑戦できる職業でもあります。一級建築士は、未来の街づくりを担う重要な存在として、長く活躍できる仕事です。
一級建築士の年収とキャリアの展望を知っておこう!

一級建築士の平均年収は約600万~800万円と高水準で、経験年数や企業規模によって収入は大きく変わります。
二級建築士との差は専門性や責任範囲に比例し、キャリアを積むほど年収アップが期待できます。特に大手ゼネコンや設計事務所では、経験豊富な建築士が高年収を得る傾向にあります。
さらに、女性一級建築士の活躍も増え、働き方の多様化が進行中です。年収を上げるには、転職や独立、副業などの戦略的キャリア設計が重要です。
建築士として専門性を高め、人脈と実績を積み重ねることで、安定した高収入とやりがいの両立が可能になります。社会的信頼を得られる一級建築士は、今後も高い将来性を持つ職業といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。