自己推薦書とは?就活で役立つ書き方と職種別例文を徹底解説
就活を進める中で、「自分の強みをしっかり企業に伝えたい」と思う一方で、履歴書やエントリーシートだけでは自分を十分にアピールできないと感じる方は多いでしょう。
そんなときに活用できるのが自己推薦書です。自己推薦書は、自分の経験や強みを具体的に示し、企業とのマッチングを伝える重要な書類です。
本記事では、自己推薦書の役割や書き方、効果的に仕上げるポイントから職種別・PRポイント別の例文まで、内定獲得に直結する内容を詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
自己推薦書の役割を理解して内定を狙おう

自己推薦書は、履歴書やエントリーシートとは違い、自分の強みや経験を主体的に伝えるための書類です。
企業が求める人物像にどの程度合っているかを示すだけでなく、応募者の主体性や思考の深さを知るための判断材料にもなります。
就活生にとっては、自己推薦書を軽視してしまうと、他の応募書類では伝えきれない自分の魅力を出せず、内定の機会を逃すことになりかねません。
だからこそ、まずは自己推薦書の役割を正しく理解し、企業側の視点に立って自分をどう表現すべきかを整理することが大切です。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
自己推薦書とは?

自己推薦書とは、自分の強みや経験を言葉で表し、企業に自分を採用する価値があることを示すための書類です。
エントリーシートや履歴書と似ていますが、自己推薦書はより主体的に自分をアピールできる点が特徴でしょう。
そのため、自己推薦書では過去の経歴を並べるだけでなく、行動の背景や考え方を踏まえて「なぜその経験が社会で役立つのか」を伝えてください。
自己推薦書と他書類との違い
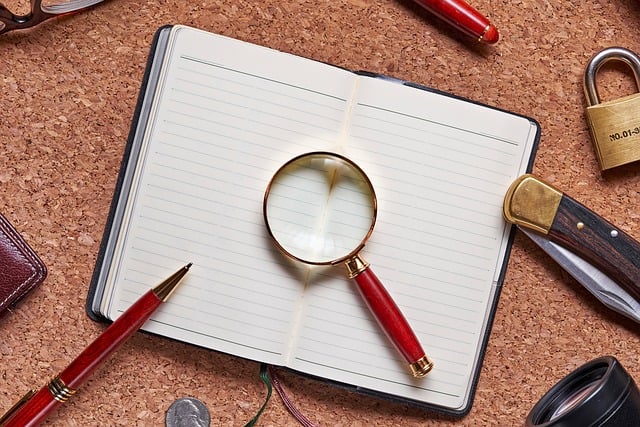
自己推薦書は就職活動で提出を求められる書類の中でも、自分の考えや強みを主体的に伝える特別な役割を持っています。
他の書類と混同すると、意図した評価につながらないおそれがあるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。ここでは代表的な4つの書類と自己推薦書の違いを確認していきましょう。
- 履歴書
- エントリーシート
- 自己PR文
- 推薦状
①履歴書
履歴書は学歴や職歴、資格などを時系列で整理し、基本的なプロフィールを伝えるための書類です。形式が決まっていることが多く、個性を強く出すのは難しいでしょう。
一方で自己推薦書は、経験から得た強みや考え方を自分の言葉で深く伝えられます。つまり履歴書は「客観的な事実の整理」が中心で、自己推薦書は「主観的な魅力の表現」が目的です。
両者の役割を混同すると、同じ内容を繰り返してしまい、採用担当者から準備不足と見なされるかもしれません。
履歴書では正確な事実を記載し、自己推薦書では具体的な体験を交えて自分の強みを示してください。そうすることで全体のバランスが整い、説得力のある応募書類に仕上がるでしょう。
②エントリーシート
エントリーシートは企業ごとに設問があり、志望動機や学生時代の経験などを答える形式です。企業が求める情報を直接引き出すためのものであり、端的に答える姿勢が必要になります。
それに対して自己推薦書は、形式に縛られず自由に構成できる点が大きな違いです。この違いを理解せずに書くと、自己推薦書が「設問のないエントリーシート」に見えてしまいます。
重要なのは、エントリーシートの内容を補足し、さらに深い自己分析を盛り込むことです。自由度を活かして自分の個性を表現すれば、「自分の考えを持つ人材だ」と評価される可能性が高まります。
その結果、他の応募者との差別化につながるはずです。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
③自己PR文
自己PR文は自分の強みを簡潔にまとめ、書類選考や面接でアピールする短い文章です。多くの場合は数百字程度で、要点を凝縮して伝えることが前提となります。
これに対して自己推薦書は、より長い文章で背景や具体的な体験を盛り込み、自分の魅力を丁寧に示すものです。
自己PR文が「要点を伝える名刺」のような存在だとすれば、自己推薦書は「人物像を描くレポート」に近いでしょう。両者を同じように扱うと、中途半端な印象を与えてしまいます。
そこで、自己PR文では強みの核を端的に示し、自己推薦書ではその強みを裏付ける体験や背景を詳しく書くようにしてください。この使い分けにより、全体として一貫性のある自己アピールにつながります。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
④推薦状
推薦状は教授やゼミの指導教員など、第三者が学生を評価して作成する書類です。本人が書くのではなく、客観的な評価が中心になる点が特徴といえます。
それに対して自己推薦書は、自分の言葉で主体的にアピールする書類です。ここで注意したいのは、推薦状と自己推薦書の内容を同じにしないこと。
もし似た内容になれば「新しい一面が見えない」と判断されかねません。推薦状では第三者からの信頼や実績を示し、自己推薦書では自分の考えや行動を語ることで補い合うようにしましょう。
そうすれば両者の役割が明確に分かれ、より説得力のある応募書類になります。
企業が就活で自己推薦書を求める理由

就職活動で企業が自己推薦書を提出させるのは、単なる形式的な手続きではありません。企業は応募者の人物像や思考の深さを知るために、多角的な情報を求めているのです。
ここでは、企業がどのような観点から自己推薦書を評価しているのかを解説します。
- 応募者の強みや長所を客観的に把握するため
- 自社に合う人物像かどうかを判断するため
- 文章構成力や論理的思考力を確認するため
- 採用後の成長や活躍を予測するため
- 履歴書やESだけでは分からない部分を知るため
①応募者の強みや長所を客観的に把握するため
企業が自己推薦書を求める理由の1つは、応募者の強みを客観的に把握したいからです。履歴書やエントリーシートにも自己PR欄はありますが、限られた文字数では深い表現が難しいでしょう。
自己推薦書なら1つの経験を掘り下げて書けるため、具体性が増します。その結果、採用担当者は強みが本物かどうかを判断しやすくなるのです。
評価につなげるためには、エピソードを具体的に展開し、そこで得た学びや成果を明確に示すことが重要。
就活生はスキルを並べるだけではなく、自分がどう考え、どのように行動したのかを丁寧に言葉にしてください。
②自社に合う人物像かどうかを判断するため
企業は能力だけでなく、社風や価値観に合うかどうかを重視するでしょう。自己推薦書はその判断材料として使われます。
例えば同じ「リーダー経験」を書いても、全体をまとめる人と、課題解決を分析で支える人では性格も適性も異なるでしょう。企業はこうした違いを読み取り、自社に適した人物を探します。
応募者にとっては「企業が求める人材像」と「自分の特性」が一致する部分を意識して書くことが必要です。ここを外すと、せっかくの魅力が伝わらず、アピールが弱まってしまうかもしれません。
③文章構成力や論理的思考力を確認するため
自己推薦書は、自分の考えを分かりやすく伝える力を測る試験でもあります。採用担当者は、文章の流れや論理の一貫性を通じて応募者の思考力を見ているのです。
たとえば「結論→理由→具体例→再度結論」といった形で書かれていれば、説得力が増して理解しやすいでしょう。反対に、思いつきを並べただけの文章では、内容が良くても評価が下がる可能性があります。
論理性や整理力は仕事に直結するため、企業は重視しているのです。就活生は経験をただ述べるのではなく、読み手が納得できる形に整理して伝える工夫をしてください。
文章力の向上自体が、社会人として大切な力の習得にもつながります。
④採用後の成長や活躍を予測するため
企業は自己推薦書から、応募者が入社後にどう成長し活躍できるかを見ています。経験を振り返るときに「何を学び、どう次に活かしたのか」を示せば、ポテンシャルを伝えられるでしょう。
成果だけでなく、改善点や今後の意識を書けば、主体的に学ぶ姿勢が伝わります。これこそが「伸びしろ」を判断する基準です。
就活生にとっては、完璧な実績がなくても、学びを次につなげる姿勢を誠実に表すことが大切。失敗からの学びを避けると、自己評価が浅く見えてしまい、魅力が十分に伝わらない恐れがあります。
⑤履歴書やESだけでは分からない部分を知るため
最後に、自己推薦書は履歴書やエントリーシートでは分からない個性を知る手段になります。履歴書はフォーマットが決まっており、学歴や経歴といった事実に限られやすいです。
そのため、考え方や価値観は伝わりにくいでしょう。自己推薦書は自由度が高く、自分の言葉で表現できる場です。応募者が何を大切にしてきたか、どう行動してきたかが見えてきます。
ここで自分らしさを素直に表現すれば、企業は履歴書やエントリーシートと合わせてより立体的に理解できるのです。その結果、面接での会話も深まりやすくなるでしょう。
自己推薦書を書く前に必要な準備

自己推薦書を効果的に仕上げるには、いきなり書き始めるのではなく事前の準備が欠かせません。準備を怠ると内容が浅くなり、企業に伝わる力も弱くなってしまうでしょう。
ここでは、自己推薦書に取り組む前に行うべき具体的な準備の流れを紹介します。
- 自己分析を行い強みを明確にする
- 他己分析で客観的な意見を取り入れる
- 企業研究を通じて求める人物像を理解する
- 過去の経験やエピソードを整理する
- 志望動機との一貫性を意識する
①自己分析を行い強みを明確にする
自己推薦書でまず大切なのは、自分の強みを正しく理解することです。強みがあいまいなままでは、読み手に伝わりにくいでしょう。自己分析をすると、自分の行動や考え方の特徴が見えてきます。
例えば「粘り強さ」を強みとする場合、どんな場面で発揮したかを具体的に示すと説得力が高まるのです。逆に分析をおろそかにすると抽象的な表現ばかりになり、他の応募者と差が出ません。
過去を振り返り、体験と結びつけて強みを言葉にしてください。こうした作業が「自分を理解している」と感じさせる基盤になるのです。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②他己分析で客観的な意見を取り入れる
自分だけで分析すると、思い込みや偏りが入りやすいものです。そこで有効なのが他己分析です。友人や先輩、教員などに自分の印象を聞けば、新しい気づきを得られます。
例えば自分では当然と思っている行動が「責任感が強い」と評価されることも。他人の視点を取り入れることで、推薦書に客観性が生まれるでしょう。
反対に他己分析をしないと、内容が独りよがりになりかねません。客観的な意見を参考にしつつ、自分の強みを裏づけるエピソードを整理してください。そうすれば文章の信頼性も高まります。
③企業研究を通じて求める人物像を理解する
企業研究は自己推薦書の質を決める重要な準備です。企業ごとに価値観や方針が異なり、求める人物像も違います。その理解が浅いと的外れなアピールになり、評価が下がる原因になってしまうのです。
公式サイトや採用情報、OB・OG訪問などで情報を集め、自分の強みと重なる部分を見つけましょう。例えば「挑戦心を重視する企業」なら、新しいことに取り組んだ経験を強調するのが効果的です。
企業研究を徹底することで、単なるアピールではなく「この企業に合う人材だ」と伝えられるようになり、内定に近づく可能性が高まります。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④過去の経験やエピソードを整理する
自己推薦書では強みを裏づける具体的な経験が必要です。準備不足のまま書くと、内容が抽象的になり説得力を欠きます。学生生活やアルバイト、ボランティアなどから、自分を表す体験を整理してください。
その際は「課題に直面した状況」「どのように行動したか」「結果として得たこと」という流れでまとめると、一貫性のある文章になります。
経験を具体的に描けば描くほど、読み手はあなたの人物像を鮮明に思い浮かべられるでしょう。丁寧に過去を振り返ることが、心に残る推薦書づくりにつながります。
⑤志望動機との一貫性を意識する
自己推薦書は単独で評価されるものではなく、志望動機や他の書類との一貫性が求められます。強みの内容が志望動機と結びついていなければ、矛盾を感じさせてしまうでしょう。
例えば「協調性」を強みとするなら、それが志望する企業や職種でどう活かせるかを意識してください。一貫性を軽視すると「伝えたいことがばらばら」と受け取られる恐れがあります。
推薦書を仕上げる前に志望動機と照らし合わせ、自然に関連づけられているか確認してください。この整合性を意識することで、全体がまとまり、強い説得力を持つようになります。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
自己推薦書の基本的な構成

自己推薦書は自分を効果的に伝えるための書類であり、構成の工夫が合否を左右するほど大切です。読みやすく説得力のある内容に仕上げるには、一定の流れに沿って整理することが欠かせません。
ここでは、自己推薦書に盛り込むべき基本の5つの要素を順を追って紹介します。
- 冒頭で結論(自分の強み)を伝える
- 強みを裏付ける具体的なエピソードを書く
- 企業との接点やマッチングを示す
- 将来の展望や貢献意欲を伝える
- 締めでまとめと感謝の言葉を入れる
①冒頭で結論(自分の強み)を伝える
自己推薦書は冒頭で自分の強みを端的に伝えることが重要です。最初に結論を示すことで、採用担当者が内容を理解しやすくなります。
例えば「私の強みは課題解決に向けて粘り強く取り組む姿勢です」と書けば、その後の文章も展開しやすいでしょう。ここが曖昧だと話の軸が見えなくなり、読みにくい印象になりかねません。
大切なのは「一番アピールしたい点は何か」を決めてから書き始めることです。冒頭で強みをはっきりさせることで、最後まで一貫性のある文章になり、説得力も高まります。
②強みを裏付ける具体的なエピソードを書く
強みを述べるだけでは説得力が弱いため、それを裏付ける経験を示す必要があります。採用担当者は「本当にその強みがあるのか」を知りたいので、具体的な出来事を通じて説明してください。
例えば「大学での研究プロジェクトで困難に直面したが、仲間と協力して成果を出した」という流れなら、粘り強さや協調性を伝えやすいです。エピソードは1つに絞り、細かすぎる説明は避けましょう。
分かりやすい事例を取り上げ、自分がどう考え、どう行動したかを丁寧に伝えてください。具体性があることで文章全体の信頼性が増し、強みが根拠を持ったものとして伝わります。
③企業との接点やマッチングを示す
自己推薦書は自分の魅力を伝えるだけでなく、企業に合う人材であることを示す役割も持ちます。どんなに優れた強みを語っても、企業の方向性に合っていなければ響きません。
自分の強みや経験を「この企業でどう活かせるか」という視点で結びつけることが大切。例えば「課題解決力を生かして貴社の新規事業に貢献したい」といった形です。
企業研究を十分に行い、社風や事業内容に沿ったアピールを盛り込めば、相性の良さが伝わりやすくなります。
ここを意識すれば、単なる自己PRではなく、採用担当者が納得できる推薦書に仕上げられるでしょう。
④将来の展望や貢献意欲を伝える
自己推薦書には、入社後の成長や貢献の意欲を盛り込むことも求められます。企業は応募者の現在だけでなく、将来の伸びしろを重視するからです。
例えば「学んだ知識を活かして専門性を高めたい」「リーダーシップを発揮してチームを支える存在になりたい」といった将来像を示すと好印象になります。
ただし、漠然とした夢ではなく、企業の事業や方針に関連づけることが必要です。具体的な展望を語ることで、採用担当者に入社後のイメージを持たせやすくなります。
意欲が伝われば「この人なら活躍してくれるだろう」と期待を抱いてもらえるはず。
⑤締めでまとめと感謝の言葉を入れる
最後の締めくくりでは、これまでの内容を簡潔にまとめ、感謝の言葉を添えると良いでしょう。例えば「以上の経験を通じて培った粘り強さを貴社の業務で発揮したいと考えています。
ご一読いただきありがとうございます」といった形です。感謝を伝えることで誠実さが表れ、文章としてもきれいに締まります。長くまとめる必要はなく、要点を短く整理すれば十分です。
最後まで読み手を意識し、礼儀を大切にした文章で終えることが、全体の印象を高めるポイントになります。
自己推薦書を書くためのステップ

自己推薦書は準備不足で書き始めると、内容が散らかり伝わりにくくなってしまいます。効率よく仕上げるには、段階を踏んで進めることが大切です。
ここでは5つのステップに分けて、順序とポイントを分かりやすく解説します。
- ステップ① 自己分析と強みのリスト化をする
- ステップ② アピールポイントを一つに絞る
- ステップ③ 文章の構成を考える(PREP法など)
- ステップ④ 下書きを作成して推敲する
- ステップ⑤ 清書して完成させる
①自己分析と強みのリスト化をする
自己推薦書の出発点は、自分の強みを理解することです。強みがはっきりしていなければ、文章は説得力を持ちません。自己分析をすることで、自分の行動や考え方の特徴が見えてきます。
例えば「粘り強さ」を強みとするなら、どんな状況で発揮したかを具体的に書くと伝わりやすいでしょう。逆に分析を省くと、抽象的な言葉ばかりになり、差別化が難しくなります。
強みをリスト化して整理し、体験と結びつけて言語化してください。丁寧な準備が「自分を理解している人」という印象につながります。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
②アピールポイントを一つに絞る
強みが複数あっても、自己推薦書で取り上げるのは1つに絞ることが効果的です。あれこれ並べると焦点がぼやけ、読み手に残る印象が薄れてしまいます。
強みを1つに定めれば、具体的なエピソードを掘り下げやすくなり、文章に厚みが出るでしょう。選ぶ際には、企業が求める人物像と合っているかを意識してください。
例えば協調性を重んじる企業なら「チームワーク」、挑戦を評価する企業なら「積極性」といった具合です。強みを一点に絞ることで「この人は何が得意か」が明確になり、担当者の記憶に残りやすくなります。
③文章の構成を考える(PREP法など)
内容を整理したら、次は文章の構成を決めましょう。おすすめはPREP法です。「結論→理由→具体例→結論」の流れで展開すると、分かりやすい文章になります。
例えば「私は協調性があります」と最初に伝え、その理由を説明し、グループ活動での実例を紹介して最後に「だから協調性を活かして貢献できます」とまとめれば説得力が高まるでしょう。
構成を決めずに書くと、話が前後して読みにくくなることが多いです。最初に流れを設計しておけば、読みやすく筋の通った推薦書が完成するでしょう。
④下書きを作成して推敲する
構成が決まったら、下書きを作成してください。完成度を意識せず、とにかく文章にしてみることが大切です。その後、繰り返し読み直して推敲しましょう。
表現の重複や不自然な言い回しを直し、流れを滑らかにしてください。声に出して読むと違和感を見つけやすくなります。さらに信頼できる人に見てもらえば、新しい改善点に気づけるでしょう。
下書きをおろそかにすると、全体が浅くなりやすいです。何度も推敲を重ねることで、文章が磨かれ、心に残る推薦書に仕上がります。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
⑤清書して完成させる
推敲を終えたら清書に移ります。ここで大切なのは、内容だけでなく形式の整え方です。誤字脱字や句読点の位置、余白や行間の見やすさまで確認してください。
清書が雑だと、どれほど内容が良くても印象が悪くなる恐れがあります。反対に整った文章は、誠実さや真剣さを伝える力を持っているのです。最後まで時間をかけ、丁寧に仕上げてください。
完成した推薦書は、あなた自身を映す鏡のような存在です。しっかり整えた状態で提出すれば、自信を持って選考に臨めるでしょう。
自己推薦書を効果的に仕上げるポイント

自己推薦書は内容を整理して書くだけでなく、相手に伝わりやすくする工夫が欠かせません。採用担当者が納得できる形に整えることで、評価につながるでしょう。
ここでは文章をさらに洗練させるための3つの具体的なポイントを紹介します。
- 数字や実績を入れて説得力を高める
- 企業目線を意識して内容を調整する
- 誤字脱字や不自然な表現を見直す
①数字や実績を入れて説得力を高める
自己推薦書で強みを伝える際、抽象的な表現だけでは説得力が弱くなってしまいます。そこで役立つのが、数字や実績を盛り込む方法です。
例えば「アルバイトで売上を上げました」と書くよりも「接客改善を行い、3か月で売上を120%に伸ばしました」と記載する方が成果が明確に伝わるでしょう。
採用担当者は数値を見ることで、行動と結果を客観的に理解できます。すべてを数字化する必要はありませんが、工夫して数値化できる部分を入れてください。
強みの裏付けが示されることで文章全体に信頼性が増し、完成度の高い自己推薦書になるはずです。
②企業目線を意識して内容を調整する
自己推薦書は自分の魅力を語る場でありながら、それを企業がどう受け取るかを考えることが欠かせません。強みや経験を並べるだけでは響かない可能性があります。
重要なのは「この企業がどのような人材を求めているのか」を理解し、それに合わせて内容を調整することです。
例えば「チームで協力して成果を出した経験」を強調する場合でも、協調性を重んじる企業とリーダーシップを評価する企業とでは伝え方を変える必要があります。
企業研究を十分に行い、求める人物像に自分の強みを結びつけると効果的です。そうすれば「この人材は自社に合うだろう」と感じてもらいやすくなるでしょう。
③誤字脱字や不自然な表現を見直す
どれほど内容が優れていても、誤字脱字や不自然な表現が残っていると評価は下がってしまいます。採用担当者は文章を通じて応募者の丁寧さや誠実さを見ているため、確認を怠れば大きなマイナスです。
完成したらすぐに提出せず、時間を置いて見直すと客観的に確認できます。また、自分では気づけないミスが残ることもあるので、家族や友人に読んでもらうのも有効です。
さらに音読をすれば、表現の違和感や文章のリズムの乱れに気づきやすくなります。細部まで整った文章は誠実さや責任感を示し、最終的な評価を高める要因になるでしょう。
【職種別】自己推薦書の例文

自己推薦書を書くとき、志望する職種ごとにどのように表現すればよいか迷う人は多いでしょう。ここでは代表的な職種を例に取り、実際の文例を参考にしながら伝え方のポイントを整理して紹介します。
①営業職を志望する場合の例文
営業職は人との関わりや成果への姿勢を重視されやすいため、学生時代の活動や経験を具体的に示すことが効果的です。ここではアルバイト経験をもとにした例文を紹介します。
| 私は大学時代、飲食店でのアルバイトを通じて人と信頼関係を築く大切さを学びました。 最初は注文を取るだけで精一杯でしたが、常連のお客様の好みを覚えたり声をかけたりすることで、次第に笑顔で話しかけてもらえるようになったのです。 売上を上げるためにどうすればよいかを考え、スタッフ同士で意見を出し合いながらキャンペーンを工夫した結果、前年同月比で来店者数を20%増やすことに成功しました。 この経験を通じて、相手の立場に立って行動することや小さな努力の積み重ねが成果につながると強く実感しています。 今後はこの姿勢を営業の仕事に活かし、お客様から信頼される存在として貢献していきたいと考えています。 |
この例文では、アルバイトでの具体的な成果を数字で示し、営業職に必要な姿勢へ結びつけています。
同じテーマを書く際は、経験から得た気づきを「どう仕事に活かすか」まで述べると評価されやすくなるでしょう。
②企画職を志望する場合の例文
企画職ではアイデアを形にし、周囲を巻き込みながら成果を出す力が求められるのです。ここでは学園祭での実行委員としての経験を基にした例文を紹介します。
| 私は大学の学園祭で実行委員を務め、模擬店の企画を担当しました。最初は参加者の数が伸びず苦戦しましたが、仲間と一緒にターゲットを絞り、宣伝方法を工夫することで状況を改善できたのです。 具体的にはSNSを活用してキャンペーンを行い、学生だけでなく地域の方にも来てもらえるよう呼びかけた結果、前年より来場者数を30%増やすことに成功しました。 この経験を通じて、課題に直面したときに現状を分析し、解決に向けて柔軟に考える姿勢の大切さを学んでいます。 今後はこの力を活かし、より多くの人に価値を感じてもらえる企画を生み出すことで貢献していきたいと考えています。 |
この例文は、課題をどう解決したかを具体的に示し、企画職に必要な思考力や行動力へつなげています。似たテーマを書く際は、数値や成果を交えて工夫の過程を明確にすると説得力が高まります。
③事務職を志望する場合の例文
事務職は正確さや気配りが求められる職種です。ここではサークル活動での役割を通じて、事務職に必要な力をアピールする例文を紹介します。
| 私は大学で所属していたサークルで会計を担当しました。活動費の管理や領収書の整理を任され、最初はミスをしないようにとても緊張していたものです。 しかし記録方法を見直し、表を作って支出と収入を分かりやすくまとめるように工夫した結果、誰が見ても理解できる資料を作れるようになりました。 さらに月に1度の報告会ではメンバーに丁寧に説明し、透明性を高めることを意識したところ、活動費の使い道が明確になり、安心して任せられると言われたことが大きな自信につながりました。 この経験を通じて、地道な作業を正確に積み重ねる大切さを学んでいます。今後はこの姿勢を事務職での仕事に活かし、組織の円滑な運営に貢献していきたいと考えています。 |
この例文は、数字管理や資料作成を通じて正確性と工夫を示しています。同じテーマを書く場合は「工夫した点」と「周囲からの評価」を盛り込むと、事務職への適性が強調できます。
④技術職を志望する場合の例文
技術職では専門知識だけでなく、課題を発見し解決に取り組む姿勢が重視されるでしょう。ここでは研究活動を通じて培った経験をもとにした例文を紹介します。
| 私は大学のゼミで製作したロボットプロジェクトに参加し、プログラム部分を担当しました。 最初は思い通りに動作せず苦労しましたが、問題の原因を一つずつ確認し、仲間と協力して改善策を考えることで徐々に精度を高められたのです。 最終的には学内の発表会で実演を行い、教授や他の学生から高い評価をいただき、大きな成果につながりました。 この経験を通して感じたのは、技術は知識だけでなく粘り強い取り組みや仲間との協力によって実を結ぶということです。 今後はこの学びを活かし、現場で必要とされる課題解決力を発揮しながら、社会に貢献できる技術者として成長していきたいと考えています。 |
この例文は、課題解決のプロセスと仲間との協力を強調しました。似たテーマを書くときは、失敗からどう改善したかを具体的に述べることで、技術職に必要な粘り強さが伝わりやすくなります。
⑤金融業界を志望する場合の例文
金融業界では責任感や数字に強い姿勢に加えて、信頼される人柄が求められるでしょう。ここではゼミ活動で培った経験を基にした例文を紹介します。
| 私は大学で所属していた経済学ゼミで、地域の中小企業を対象にした市場調査に取り組みました。データ収集や分析を担当し、数値の正確さを確保するために何度も確認を重ねたのです。 その過程で、数字の裏にある背景を理解しなければ正しい判断ができないことを学びました。 また、調査結果をまとめる際には分かりやすい資料を作成し、企業の担当者に丁寧に説明したところ、「信頼できる」と評価を頂けました。 この経験を通じて、誠実に取り組む姿勢と数字に基づいた分析力を培ったと感じています。今後はこれらを活かし、金融業界でお客様の信頼を得られる存在として貢献していきたいです。 |
この例文は、数字の扱いと信頼関係の構築を具体的に示しました。似たテーマを書く場合は「正確さへの工夫」と「周囲からの評価」を入れると金融業界での適性が伝わりやすくなります。
【PRポイント別】自己推薦書の例文
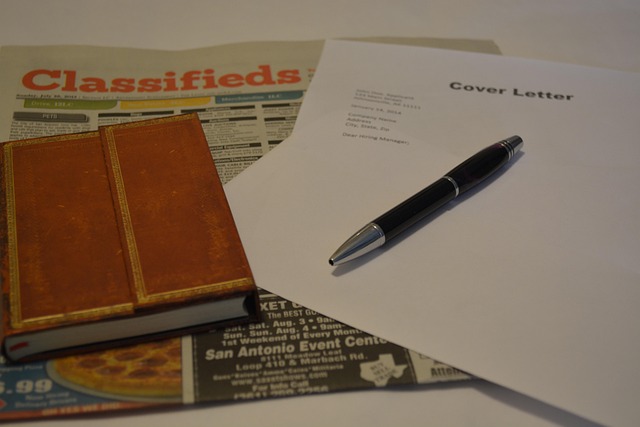
自己推薦書を書くとき、自分の強みをどう表現すればよいか悩む人は多いでしょう。ここでは代表的なPRポイントごとに例文を紹介し、効果的な書き方を理解できるようにまとめています。
①協調性をアピールする場合の例文
協調性を強みとして示すときは、グループ活動やアルバイトでの経験を取り上げると効果的です。ここでは大学生活の中でよくある場面を使った例文を紹介します。
| 私は大学でのゼミ活動において、チームで行う研究発表の準備を通じて協調性を培いました。 メンバーそれぞれが得意分野を活かして取り組む一方で、意見の違いから議論がまとまらない場面もあったのです。 その際には、まず全員の意見を丁寧に聞き、共通する目的を確認することを意識しました。 結果として役割分担を見直したことで効率が上がり、全員が納得できる発表内容へと仕上げられました。 この経験を通じて、多様な考えを尊重しながら目標に向かう姿勢が自分の強みだと実感しています。今後も周囲との連携を大切にし、協力し合いながら成果を出していきたいです。 |
協調性を伝える際には「課題をどう解決したか」を具体的に入れると説得力が増します。単なる仲の良さではなく、成果につながる姿勢を意識してください。
②粘り強さをアピールする場合の例文
粘り強さを示すときは、長期的に努力を重ねた経験や困難を克服した出来事を選ぶと効果的です。ここでは大学生に多い勉強や課外活動を例にした文章を紹介します。
| 私は大学での英語学習を通じて、粘り強さを身につけました。入学当初はリスニングが苦手で、授業の内容を理解できないことが多く、自信を失いかけたのです。 しかし毎日30分のリスニング練習を続け、半年後には英語での発表にも挑戦できるまでに成長しました。 特に発音やスピードに慣れるまでは何度も挫折しそうになりましたが、友人と学習会を開き励まし合いながら継続できたことが大きな支えになったのです。 その結果、ゼミの発表で教授から「以前よりも表現力が向上した」と評価をいただき、自分の努力が実を結んだと強く感じています。 この経験を通じて、困難に直面しても諦めず努力を重ねる力が自分の強みです。 |
粘り強さを伝えるには「困難の具体的な場面」と「継続した工夫」を盛り込むと良いです。成果に至る過程を丁寧に描くことで信頼性が高まります。
③柔軟性をアピールする場合の例文
柔軟性を伝えるには、状況に応じて対応を変えた経験を具体的に示すと効果的です。ここでは大学生活でよくある活動の場面を題材にした例文を紹介します。
| 私は大学のサークル活動において、柔軟性を発揮しました。文化祭の準備を進める中で、予定していた企画が直前に使用できなくなるという問題が起こったのです。 その際、私はメンバーと意見を交換し、限られた時間でも実現可能な代替案を考えました。 結果的に内容を少し縮小して実施することになりましたが、来場者からは「工夫が感じられて面白かった」と好意的な感想をいただき、大きな達成感を得られたのです。 この経験を通じて、状況に合わせて考え方を変え、行動を修正できることの大切さを実感しています。今後も変化に臨機応変に対応しながら、周囲と協力して成果を出せる人材になりたいです。 |
柔軟性を強調するときは「予期せぬ問題」と「対応の工夫」を必ず盛り込みましょう。状況を前向きに変える力を具体的に表すと説得力が増します。
④几帳面さをアピールする場合の例文
几帳面さを伝えるには、小さな作業や日常的な取り組みの中で注意深く取り組んだ経験を具体的に示すと効果的です。ここでは大学生活の中で多くの学生が経験する場面を用いた例文を紹介します。
| 私は大学の図書館でアルバイトをする中で、几帳面さを発揮しました。返却された本の整理や予約資料の管理を担当していましたが、最初は分類の手順が複雑で戸惑うことも多かったのです。 そこで私は独自に一覧表を作り、確認しながら作業を進める工夫を続けました。その結果、作業時間を短縮できただけでなく、ミスもなく正確に対応できるようになったのです。 利用者の方から「探していた本がすぐに見つかって助かりました」と感謝の言葉をいただいたとき、自分の細かな配慮が人の役に立つと強く感じました。 この経験を通じて、丁寧に物事へ取り組む姿勢が自分の強みであると実感しています。今後も責任を持って仕事に向き合い、組織に貢献していきたいです。 |
几帳面さを表すときは「工夫した手順」や「改善の効果」を書くと伝わりやすいです。単に丁寧さを語るのではなく、周囲に与えたプラスの影響まで盛り込みましょう。
⑤ポジティブ思考をアピールする場合の例文
ポジティブ思考を示すには、困難な状況でも前向きに取り組んだ経験を具体的に伝えることが効果的です。ここでは大学生活でよくある活動を題材にした例文を紹介します。
| 私は大学でのテニスサークル活動を通じて、ポジティブに物事へ取り組む姿勢を培いました。大会前に主力メンバーがけがをしてしまい、チームの雰囲気が落ち込んでいたのです。 そのとき私は「できることを一つずつ積み重ねよう」と声をかけ、練習内容を工夫して士気を高めるよう努めました。具体的には、苦手分野を重点的に練習し、全員が役割を意識できるように調整。 その結果、思った以上にチーム全体が成長し、当日の試合では入賞を果たすことに成功しました。 この経験を通じて、逆境を前向きに捉え、周囲を巻き込みながら行動する力が自分の強みだと実感しています。今後も困難な場面を前向きに受け止め、挑戦を続けていきたいと考えています。 |
ポジティブ思考を伝えるときは「困難な状況」と「前向きな行動」をセットで書くと効果的です。周囲に良い影響を与えた点を盛り込むと印象が強まります。
自己推薦書の役割を理解して内定を狙おう

自己推薦書は履歴書やエントリーシートでは伝えきれない強みや人柄を表現できる重要な書類です。なぜ企業が求めるのか、その理由を理解すれば、書くべき方向性が見えてきます。
実際に自己分析や他己分析を通じて強みを明確にし、企業研究で求める人物像を把握することで、自分の経験を効果的に言葉にできるのです。
さらにPREP法を用いた基本構成に沿って整理し、数字や実績を交えて具体性を高めれば、より説得力のある文章になるでしょう。
例文を参考に職種やPRポイントごとのアピール方法を学び、自分らしさを盛り込むことで内定に近づけますよ。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













