就活の一般常識問題とは?出題範囲・例題・勉強法を徹底解説
「一般常識の勉強って、就活で本当に必要なの?」 企業の選考過程で筆記試験が課されることも多く、その中でもよく出題されるのが「一般常識」です。
社会人としての基礎知識だけでなく、新聞やニュースに目を通す習慣も問われるため、不安を感じる方も少なくありません。
そこで本記事では、就活における一般常識の出題範囲や例題、効果的な勉強法を具体的に解説していきます。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活における一般常識問題とは?
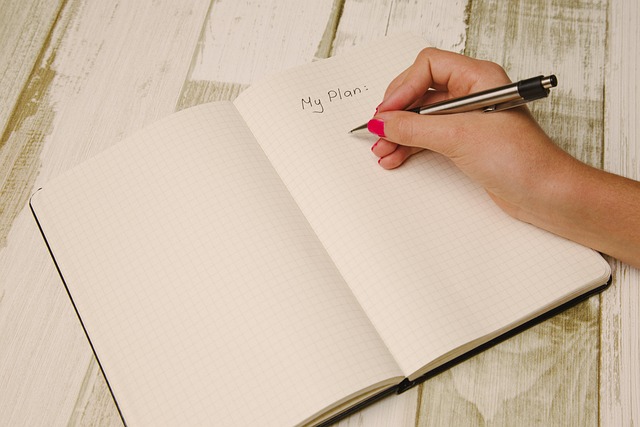
就活で出される一般常識問題は、多くの学生が「どんな内容が出るのか」と不安を抱く場面でしょう。SPIなどの適性検査と混同されやすいですが、役割や目的は違います。
企業は社会人として必要な基礎知識を持っているかを確認するために実施しています。ここで理解しておけば、対策の優先度を間違えずに済むでしょう。
特徴としては、幅広い分野から出題される点が挙げられます。政治や経済、時事ニュースに加え、国語や数学、英語など学校教育で学んだ内容も含まれます。
そのため特定の知識だけに偏ると、思わぬ問題に対応できない恐れがあるのです。SPIが能力や性格を測るのに対し、一般常識問題は「社会に出る前の基礎力確認」という色合いが強いでしょう。
一定の正答率を取れれば「安心して任せられる人材」と見なされやすいです。つまり、この試験は知識量だけでなく「準備を怠らない姿勢」を見る役割もあります。
普段からニュースや基礎学習を続けて幅広く知識をカバーしておけば、本番も落ち着いて臨めるでしょう。
企業が就活で一般常識問題を出題する理由

一般常識問題は「なぜ企業がわざわざ導入しているのか」と疑問に思う人も多いでしょう。
実際には学力や知識レベルの確認だけでなく、社会への関心やビジネスへの適応力など幅広い面を測るために使われているのです。ここでは主な理由を5つに分けて解説します。
- 学力や知識レベルを確認するため
- 社会問題や時事への関心を測るため
- 基本的な教養や常識を評価するため
- 多くの応募者を効率的に選考するため
- ビジネス場面での適応力を確認するため
①学力や知識レベルを確認するため
企業が一般常識問題を課すのは、応募者の基礎的な学力や知識レベルを知るためです。履歴書や面接だけでは十分に測れないため、客観的な試験で判断します。
例えば国語の読解力や数学の計算力は、資料を扱うときや会議で発言するときに直結。これを確認することで、入社後の業務をスムーズにこなせるかを見ているのです。
もちろん専門的な知識を問うわけではなく、社会人として最低限必要な基礎力を対象としています。幅広く復習しておけば安心につながるでしょう。基礎を押さえていることが信頼を得る近道です。
②社会問題や時事への関心を測るため
一般常識問題には、社会問題や時事ニュースに関する内容が盛り込まれることがあります。これは応募者が社会の動きを把握しているかを確認するためです。
企業は常に経済や国際関係の影響を受けており、社員にも一定の関心を求めます。例えば選挙制度や国際情勢を問う問題は、話題を共有できるかを測る指標となるでしょう。
必要なのは深い専門知識ではなく、日頃から情報に触れている姿勢です。ニュースや新聞を習慣的に見ておけば、自然と対応力は高まります。
社会の動きに敏感であることが、信頼される社会人への第一歩になるでしょう。
③基本的な教養や常識を評価するため
一般常識問題は、応募者の教養や常識を確かめる場でもあります。敬語やマナー、歴史や文化など幅広いテーマが出題されるのは、社会人として基礎を持っているかを見るためです。
社会に出ると年齢も背景も異なる人と関わります。そのとき知識や常識が不足していると、信頼を得にくくなる場合があるでしょう。だからこそ企業は、最低限の教養を備えているかを確認するのです。
完璧な知識を求めているわけではなく、基礎を押さえている姿勢が評価されます。油断せず学んでおけば、安心感を与えられるでしょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
④多くの応募者を効率的に選考するため
採用では応募者が数百人にのぼることもあります。そのため企業は、効率的に候補者を絞る方法を必要としているでしょう。
一般常識問題は短時間で基準を設けられるため、選考の入口として活用されているのです。点数で足切りを行うことで、面接に進む人を公平に選べます。
応募者からすると厳しく見えるかもしれませんが、客観的な基準があることで透明性は保たれるでしょう。受験者はこの仕組みを理解し、限られた時間で実力を発揮できるよう準備しておくべきです。
ここを突破できるかどうかが次の選考への鍵になります。
⑤ビジネス場面での適応力を確認するため
最後に、一般常識問題は応募者がビジネスの場に適応できるかを測る役割も担っています。社会人になると数字や文章を扱い、時事問題に意見を求められることも少なくありません。
基礎的な知識を持っていれば、早期に活躍できる人材と見なされます。企業は問題を通じて「実務に必要な土台を備えているか」を確かめているのです。
例えば資料を読む力や数値を理解する力は、会議や顧客対応に欠かせません。一定の力を示せれば、柔軟に対応できる人材として評価されます。
基礎力と適応力を兼ね備えていることが、就活での大きな強みになるでしょう。
就活の一般常識問題の出題範囲

一般常識問題は幅広い分野から出題されるため、どこまで勉強すべきか迷う就活生も多いでしょう。ここでは実際に多くの企業で取り上げられる範囲を整理し、効率的に準備するためのポイントを解説します。
- 国語の基礎知識
- 数学の基礎知識
- 英語の基礎知識
- 理科の基礎知識
- 社会の基礎知識
- 時事問題の知識
- ビジネスマナーの知識
- 文化に関する知識
①国語の基礎知識
国語では文章読解や語彙、漢字の読み書きが中心に問われます。難易度は高くありませんが、社会人として正しい日本語を扱えるかを確認する意図があるため、油断はできないです。
例えば四字熟語や敬語の使い方は筆記試験だけでなく面接にも関わります。誤用が多いと、学力だけでなく社会性に疑問を持たれるおそれも。
対策としては、高校レベルの国語問題集や新聞コラムを活用し、要点を整理して読む習慣を身につけることが効果的です。
特に要約練習を重ねると論理的に説明する力が育ち、面接での受け答えにも良い影響が出るはず。国語力は就活全体を支える基盤といえるため、意識的に鍛えておくことが望ましいです。
②数学の基礎知識
数学では計算力やデータの読み取り力が試されます。出題は高校レベルの基礎が中心で、難問はほとんど見られません。割合や比率、確率、グラフの解釈といったテーマが代表例です。
社会に出れば売上や統計データを扱う場面は多く、数値を正しく理解できる力は欠かせないもの。苦手意識を持つ学生は少なくありませんが、中学から高校の復習で十分対応できます。
スピードよりも正確性が重視されるため、焦らず着実に解く姿勢が必要です。ニュースやスポーツのデータを題材に練習すれば理解が深まりやすく、実生活とのつながりを感じながら勉強を続けられるでしょう。
数字を感覚として捉えられるようになると、応用力も高まります。
③英語の基礎知識
英語では単語力や基本文法、短文読解が中心です。難解な内容は出にくく、中学や高校で学んだ範囲を振り返れば十分対応できるレベルといえます。
ただし基礎を軽視すると、思わぬ失点につながる場合があるでしょう。特にビジネスに関連する基礎単語やTOEIC初級レベルの表現は出やすいため、日頃から意識して覚えておくと安心です。
外資系や海外事業を展開する企業では重視されやすいため、差をつけられる分野でもあります。新聞の簡単な英文記事を音読したり、アプリで単語を毎日学んだりする方法がおすすめですよ。
基礎を整えておくことで、努力を継続できる姿勢が企業から評価されるでしょう。
④理科の基礎知識
理科は物理・化学・生物・地学の基礎から幅広く出題されます。ただし難問よりも常識レベルの内容が中心です。光合成の仕組みや物質の状態変化、地震の規模を示す単位などが典型例です。
理系以外の学生は不安を感じやすいですが、教科書レベルを押さえれば十分対応できます。重要なのは、単なる暗記ではなく仕組みや原理を理解して覚えることです。
理解を伴わない暗記は記憶が残りづらく、本番で混乱を招く原因となります。高校理科の参考書や図解付きの本を活用し、視覚的に覚えると効果的ですよ。
理科の知識はニュースや解説番組でも取り上げられるため、普段から興味を持って学ぶと記憶に定着しやすいでしょう。
⑤社会の基礎知識
社会分野は政治、経済、歴史、地理など広範囲に及びます。特に就活で重視されるのは現代社会に関する理解です。憲法や政治制度、経済指標、国際関係は多くの企業で出題されます。
また歴史や地理の基本的な知識も確認される場合があるでしょう。大切なのは暗記だけでなく、社会の動きを理解する姿勢です。
例えばGDPや株価のニュースを見たときに意味や影響を考えられるかどうかが実力の差になります。新聞やニュースサイトを利用し、現実の社会問題と結びつけて学ぶと記憶に残りやすいでしょう。
社会分野の基礎を押さえることは、筆記試験対策だけでなく面接時の会話力向上にも直結しますよ。
⑥時事問題の知識
時事問題は出題頻度が高く、最新のニュース理解が学生の社会への関心度を測る指標になります。政治や経済はもちろん、スポーツや国際イベント、環境問題など幅広い分野から出題されるのが特徴です。
対策を怠ると「社会に関心が薄い」と見られてしまう可能性があります。毎日の新聞やニュースアプリを使い、情報を更新する習慣を持つことが効果的です。
特に「なぜ起きたのか」「社会にどう影響するのか」を意識して読むと理解が深まります。予想問題集や模擬試験を活用すれば、知識の定着度を確認できるでしょう。
時事問題は短期間でも得点を伸ばしやすいため、直前期にも取り組む価値があります。
⑦ビジネスマナーの知識
ビジネスマナーは軽視できない分野です。敬語の使い方、電話応対、名刺交換など社会人として必須の行動が問われます。知識不足が目立つと、入社後の適応力に不安を持たれる可能性もあるでしょう。
例えば上司へのメールでの誤用は信頼を損なう原因になりかねません。基本を押さえるにはマナー本や就活サイトを活用するのが有効です。
さらに先輩や指導者の振る舞いを観察し、実際に真似することで理解が深まります。マナーは筆記試験だけでなく面接やインターンでも評価されるため、早めに習得しておくと安心。
正しい知識を身につけることで、社会人生活のスタートを自信を持って迎えられますよ。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
⑧文化に関する知識
文化に関する問題は出題頻度こそ低めですが、意外な盲点になる場合があります。文学や芸術、伝統行事、国際的な文化イベントが出題対象です。
企業は幅広い知識を持ち、多様な話題に対応できる人材を求めているため、文化的素養を確認する意味合いがあります。
国語や社会と関連づけて出題されることも多く、他分野との結びつきを意識すると理解が進みやすいです。新聞の文化欄や美術館の展示情報をチェックするのがおすすめ。
知識として得るだけでなく、実際に体験することで深く身につきます。文化的な背景を知っておくことは、教養として面接で話題にできる強みとなるでしょう。
就活で一般常識問題を受ける際のポイント

一般常識問題は知識の多さだけでなく、当日の取り組み方も結果を左右します。勉強していても焦ったりケアレスミスをしたりすると、本来の力を出せません。
ここでは安心して臨めるように、実践的なポイントを5つ紹介します。
- 時間配分を意識して解答する
- 難問にこだわらず得点源を確保する
- 正確にマークシートを記入する
- 試験前に持ち物を準備しておく
- 落ち着いて問題に取り組む
①時間配分を意識して解答する
一般常識問題には制限時間があり、最後まで全問を解き終えられないことも珍しくありません。そのため、事前に「1問あたりの目安時間」を設定しておくことが重要です。
例えば50分で50問なら、1問にかけられるのは1分前後です。こうした基準を持つと、難しい問題に出会っても割り切って次に進みやすくなります。
特定の設問に時間を使いすぎると、後半の基礎問題を落とすリスクが高まるでしょう。模試形式で繰り返し練習すれば、自分のペースをつかめるでしょう。
時間を意識する習慣を持つことが、安定した得点につながります。
②難問にこだわらず得点源を確保する
試験で難問に出会うと、つい解こうと粘ってしまいがちです。しかし一般常識問題は幅広い分野から出題されるため、すべてを完璧に答える必要はありません。
むしろ基礎的な問題を確実に解く方が得点を伸ばせます。自分の得意分野や見慣れた形式の問題を優先して進め、解けないものは飛ばして後から見直す判断が大切です。
解答できる問題を積み上げる姿勢が合格への近道になりますよ。冷静に取捨選択ができれば、限られた時間でも効率よく点数を獲得できるでしょう。
③正確にマークシートを記入する
マークシート方式の試験では、知識や計算力よりも記入の正確さが重要になる場面があります。答えを導けても、マーク欄がずれてしまえば得点は0点です。
特に集中力が落ちている後半に起きやすいので注意が必要。数問ごとに解答番号を確認する、最後に必ず全体を見直すなど、簡単な工夫で防げますよ。
また、鉛筆の濃さや消しゴムの使い方など、実務的な準備も欠かせません。正しく記入する意識を徹底することで、努力を確実に点数に結びつけられるはずです。
④試験前に持ち物を準備しておく
当日に慌てないためには、前日までに持ち物を確認することが欠かせません。筆記用具や時計、受験票はもちろん、予備の鉛筆や替えの消しゴムも準備しておくと安心です。
意外と多いのが、持ち物を忘れて余計な不安を抱え、集中力を乱してしまうケース。チェックリストを作成して鞄に入れ、当日は余裕を持って会場へ向かいましょう。
早めに到着して会場の雰囲気に慣れることも、落ち着いて試験に取り組む大切な準備になります。
⑤落ち着いて問題に取り組む
最後に最も大事なのは、落ち着いた気持ちで問題に向き合うことです。焦りや緊張で読み間違えたり、早合点で答えてしまったりすると、本来解けるはずの問題を落とす原因になります。
難問に直面したときは「後で取り組めばいい」と切り替える余裕を持ちましょう。深呼吸をして心を整えれば、本来の力を発揮できます。
こうした冷静さは試験だけでなく、面接やグループディスカッションなど、他の就活場面でも役立つスキルです。
普段から意識して練習することで、どんな場面でも安定したパフォーマンスを発揮できるでしょう。
就活一般常識問題の例題

就活における一般常識問題は、学力だけでなく社会人としての基礎知識や関心度を測る大切な試験です。出題範囲が広いため、具体的な例題を知ることで効率的に準備できるでしょう。
ここでは科目ごとに代表的な例題を紹介します。
- 国語の例題
- 数学の例題
- 英語の例題
- 理科の例題
- 社会の例題
- 時事問題の例題
- ビジネスマナーの例題
- 文化問題の例題
①国語の例題
国語の問題は語彙力や読解力を確認する目的があります。例えば「的を得る」と「的を射る」の正しい表現を問う問題や、四字熟語の意味を選択させる設問が代表的です。
《例題》
| 「次の中で正しい表現はどれか」 1. 的を得る 2. 的を射る → 正解は「的を射る」。 |
正しく答えられないと基礎的な日本語力に不安を持たれるおそれがあるでしょう。対策としては、普段から新聞や記事を読み、使われている語句を辞書で確認する習慣を持ってください。
②数学の例題
数学は基本的な計算やデータ処理能力を見ています。例えば「売上100万円のうち利益率20%の場合、利益額はいくらか」といった設問がよく出題されるのです。
《例題》
| 「売上100万円で利益率20%のとき、利益額はいくらか」 → 正解は20万円。 |
難しい数式は不要ですが、割合や比率を正しく理解していないと対応できません。普段から電卓に頼らず計算練習を続けると、正確性とスピードを両立できます。
③英語の例題
英語は基礎的な単語や文法が中心です。例えば「次の日本語を英語に訳しなさい:私は昨日図書館に行きました」という問題が典型。
《例題》
| 「私は昨日図書館に行きました」を英訳せよ。 → 正解は I went to the library yesterday. |
難易度は高くありませんが、基礎をおろそかにすると得点を落としかねません。高校レベルの文法を復習しておくと安心です。
④理科の例題
理科では身近な自然現象や基礎知識が問われます。例えば「水が0度で氷になる現象を何というか」という中学理科レベルの設問が多いです。
《例題》
| 「水が0度で氷に変わる現象を何というか」 → 正解は「凝固」。 |
暗記で解ける問題もありますが、仕組みを理解して覚える方が応用が利きます。
⑤社会の例題
社会は政治や経済、歴史など幅広い分野から出題されます。例えば「日本の国会は何院制か」といった設問が定番です。
《例題》
| 「日本の国会は何院制か」 → 正解は「二院制」。 |
普段からニュースを見て用語の意味を確認しておくことが重要です。
⑥時事問題の例題
時事問題は最新ニュースを中心に出題されます。例えば「今年開催された国際的なスポーツ大会は何か」といった設問が代表的です。
《例題》
| 「2024年の夏季オリンピックが開催された都市はどこか」 → 正解は「パリ」。 |
背景や影響まで理解しておくと、面接でも会話に活かせます。
⑦ビジネスマナーの例題
ビジネスマナーは盲点になりやすい分野です。例えば「初めて名刺を渡すときの正しい手順はどれか」といった問題が出ます。
《例題》
| 「名刺を渡すときに正しいのはどれか」 1. 相手より先に座ってから渡す 2. 両手で持って立ったまま渡す 3. 机越しに片手で渡す → 正解は「2」。 |
知識だけでなく、実際に練習することが効果的です。
⑧文化問題の例題
文化問題は出題頻度は低いものの油断できません。例えば文学や芸術に関する基礎的な知識が問われます。
《例題》
| 「夏目漱石の代表作を次の中から選べ」 1. 吾輩は猫である 2. 雪国 3. 羅生門 → 正解は「吾輩は猫である」。 |
普段から文化的な話題にも関心を持っておくと安心です。
就活の一般常識問題の勉強方法

一般常識問題の対策は一夜漬けでは対応しきれません。日常的に知識を広げながら問題を解き、定着させることが大切です。ここでは具体的な勉強方法を5つの視点から紹介します。
- 新聞やニュースを日常的にチェックする
- 問題集を繰り返し解いて理解を深める
- アプリやWEBテストで模擬練習をする
- 友人や家族と時事問題を話し合う
- 公式や基礎知識を暗記しておく
①新聞やニュースを日常的にチェックする
一般常識問題では時事的なテーマが多く出題されます。そのため普段から新聞やニュースを確認する習慣を持つことが効果的です。
経済や政治、国際情勢など幅広い分野を意識して見ておくと、試験の出題に対応しやすくなります。最初はすべて理解する必要はなく、気になる記事だけでも読む習慣を続けることが大事です。
定期的にニュースに触れることで社会の流れに敏感になり、自然と背景知識が身につきます。単に読むだけでなく「自分の言葉で説明できるか」を意識すると、理解度も深まるでしょう。
②問題集を繰り返し解いて理解を深める
問題集は学習に欠かせない教材です。一度解いただけでは定着しにくいため、繰り返し取り組むことが必要になります。
間違えた問題は解説を読み、なぜ誤ったのかを理解しておけば、次に同じミスを防げます。特に苦手分野は重点的に繰り返すことで自信につながるでしょう。
問題集を進める中で出題パターンを把握できれば、本番でも落ち着いて対応できます。正解することだけを目的にせず「理由を理解すること」を意識すると、知識の応用力も身につくはずです。
③アプリやWEBテストで模擬練習をする
スマートフォンのアプリやWEBテストを活用すれば、スキマ時間を使って効率的に勉強できます。通学や休憩の時間に手軽に取り組めるのが大きな利点です。
タイマー付きの模擬問題で練習すれば、制限時間を意識した実践力も磨けます。さらに最新の時事問題を扱うアプリもあるため、新しい情報を取り入れやすいのも魅力です。
ただし便利さに頼りきらず、紙の問題集と組み合わせて学ぶと理解のバランスが取れます。両方を活用することで、より実戦的な力を身につけられるでしょう。
④友人や家族と時事問題を話し合う
知識を一方的に覚えるだけでなく、誰かと話し合うことで理解が深まります。
友人や家族と時事ニュースをテーマに意見交換すれば、自分の考えを整理できるだけでなく、相手の視点を知ることもできるのです。
ニュースを共有して議論する習慣を持てば、面接での受け答えにも役立つでしょう。また、言葉にして説明することで記憶としても定着しやすくなります。
受け身の勉強から一歩進み、積極的に話す姿勢が本番での強みに変わるのです。
⑤公式や基礎知識を暗記しておく
最後に、基礎的な知識を暗記することも欠かせません。四則演算や簡単な計算公式、歴史の重要年号、政治制度の基本などは繰り返し出題されるため、確実に覚えておく必要があります。
丸暗記ではなく、問題演習で実際に使いながら身につけると効果的です。基礎知識を持っていれば応用問題にも対応しやすくなり、自信を持って試験に臨めます。
基礎を固めることが得点力を底上げする近道でしょう。
就活の一般常識問題を攻略するために

就活における一般常識問題は、単なる知識確認ではなく、企業が応募者の基礎力や社会への関心を判断する大切な要素です。SPIとの違いを理解し、出題範囲を把握することで効果的に準備できます。
実際の問題は国語・数学・英語といった基礎科目から、時事問題やビジネスマナーまで幅広く出題されるため、日々の学習習慣が重要です。さらに、試験当日は時間配分や冷静な対応が結果を左右します。
だからこそ、新聞やニュースのチェックや問題集での反復練習を通じて自信を高めておくことも大切ですよ。就活の一般常識問題を正しく理解し計画的に対策することが、内定への近道となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












