フェルミ推定とは?基礎知識から例題・やり方・対策方法まで解説
「フェルミ推定ってどうやって答えればいいの?」
コンサルティング業界や総合商社の面接でよく出題されるフェルミ推定。
聞いたことはあっても、実際に挑戦すると「正解がわからない」「どう考えを組み立てればいいのか難しい」と感じる学生は少なくありません。
そこで本記事では、 基礎知識から例題、やり方のステップ、面接対策まで徹底的に解説します。
初めて取り組む方でも理解しやすいように具体例を交えながら紹介するので、就活やケース面接に備えたい方はぜひ参考にしてくださいね。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
フェルミ推定とは?

フェルミ推定とは、限られた情報をもとに論理的に数値を導き出す思考法です。就活の面接やケース面接でよく出題されるため、不安に感じる学生も多いでしょう。
しかし実際には特別な知識よりも、筋道を立てて考える姿勢そのものが重視されます。正確な数値を出すことが目的ではなく、前提条件を整理しながら結論に近づく過程を示すことが評価のポイントです。
例えば「東京にあるコンビニの数」といった一見答えが分からないような問題でも、人口や生活圏の広さといった要素を分解して組み合わせれば、妥当な推定値にたどり着けます。
この思考の流れこそが論理的な構築力を示す材料になり、企業はそこから候補者の柔軟さや地頭力を見ているでしょう。
最初は難しく見えるかもしれませんが、基本の考え方を理解すれば誰でも取り組めるものです。普段の生活で「電車の乗客数」や「駅前にある飲食店の利用者数」などを考えてみると、自然と練習になります。
事前にこうした習慣を身につけておけば、本番でも落ち着いて対応できるはずです。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
フェルミ推定の目的
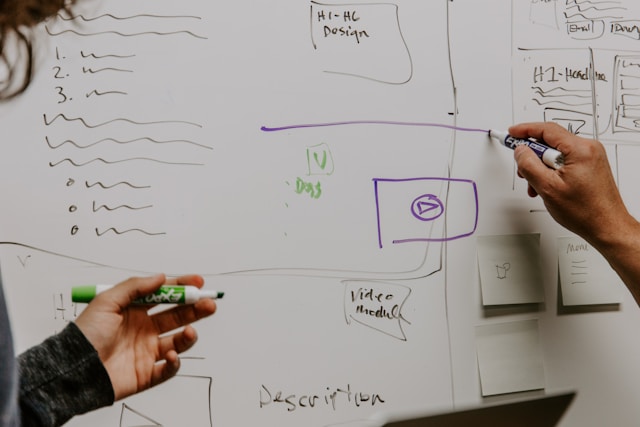
就職活動でよく登場する「フェルミ推定」とは、答えが明確に存在しない問いに対して合理的な仮定を置き、筋道を立てて数値を導き出す練習です。
このスキルは単なる暗記や計算力ではなく、限られた条件から本質を捉える力を問うため、多くの企業で選考プロセスに取り入れられているのです。
ここでは、フェルミ推定の目的を複数の観点から整理し、それぞれが就活生にとってどのように役立つのかを解説します。
- 限られた情報から合理的に推定すること
- 論理的思考力を養うこと
- 問題解決力を鍛えること
- 面接官に説明する力を示すこと
- ビジネスの意思決定に役立てること
①限られた情報から合理的に推定すること
面接でフェルミ推定が課される理由の1つは、正解のない問題にどう取り組むかを確認するためです。
現実のビジネスではすべてのデータが揃っている状況は少なく、断片的な情報から仮説を立てる力が求められます。
たとえば「東京都内にあるコンビニの数」を推定する際には、人口やエリア特性を手がかりに段階的に考えることが有効でしょう。つまり、数値の正確さよりも思考の筋道が評価されるのです。
この姿勢を身につければ、実際の業務でも不確定な情報に落ち着いて対応できますし、面接での印象も変わります。
②論理的思考力を養うこと
フェルミ推定を通じて得られる大きな効果は、論理的思考力の強化です。問題を分解し要素ごとに整理しながら、前提を設定して数字を積み上げていく過程そのものがトレーニングになります。
就活生は「突拍子もない答えを出してはいけない」と考えがちですが、実際は論理が一貫していれば数値が多少ずれても評価されます。
この点を理解しておけば、答えにとらわれず自分の考えを堂々と説明できるでしょう。さらに、この思考法はグループディスカッションやエントリーシートにも活かせるため、就活全体で強みとなります。
③問題解決力を鍛えること
ビジネスの現場では、課題が複雑で明確な答えが存在しない場合がほとんどです。フェルミ推定はその縮図であり、与えられた条件から「どうすれば実現可能な解を導けるか」を試されます。
練習を積むことで、物事を多面的に見る力や、柔軟に仮説を修正する習慣が自然と身につくはずです。数値が大きくずれたとしても、その理由を整理し改善策を示せば高評価につながります。
つまり、問題解決に向けた姿勢そのものが伝わるため、日常的にシミュレーションして備えておくことが大切です。
④面接官に説明する力を示すこと
フェルミ推定は「答え」以上に「説明の仕方」が重視されます。論理に飛躍がなく、相手が理解しやすい順序で話を組み立てられるかどうかが評価の焦点です。
たとえば、最初に前提条件を明示し、その後に計算過程を丁寧に説明すれば、面接官は思考の透明性を確認できます。逆に結論だけを伝えると、理解力や説得力に疑問を持たれるかもしれません。
この点を意識すれば「話し方が分かりやすい学生」という印象を与えられるでしょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
⑤ビジネスの意思決定に役立てること
最後に重要なのは、フェルミ推定が実社会でも活きる実践的スキルである点です。
新規事業の市場規模を予測する場面や、コスト削減の効果を見積もる場面など、限られたデータで素早く結論を出す必要は多くあります。
就活生の段階でこの思考法を身につけておけば、入社後の成長にも直結するでしょう。面接官がこの課題を出す背景には「入社後すぐに考え行動できる人材かどうか」を確かめたい意図もあります。
したがって、就職活動の準備と並行して、社会人としての将来を見据えた練習を積み重ねてください。
フェルミ推定の評価ポイント

フェルミ推定では正解よりも、思考の流れや論理の一貫性が重視されます。採用担当者は学生が答えに至る過程を観察し、論理的な姿勢や仮説の立て方を確認しています。
ここでは評価時に注目されるポイントを整理してみましょう。
- 論理的な思考プロセスができているか
- 前提条件を整理できるか
- 数値の根拠を示せるか
- 説明がわかりやすいか
- 時間配分や効率性を意識できているか
①論理的な思考プロセスができているか
フェルミ推定では答えの正確さより、導き方そのものが大切です。面接官は「なぜその数値を出したのか」を知りたいと考えています。
例えば東京の飲食店数を推定する際には、まず人口を考え、次に外食頻度を仮定し、最後に店舗数へ落とし込むといった段階的な流れが必要でしょう。このように一歩ずつ積み上げる姿勢が評価されます。
逆に、数値を突然提示すると根拠がなく説得力を欠いてしまいます。論理性を意識することで、考え方の筋道が相手に伝わりやすくなるのです。
面接で見られるのは答えそのものではなく、合理的に導ける力です。普段から日常の出来事を数字で考える習慣を持っておくと、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。
②前提条件を整理できるか
フェルミ推定の問題は曖昧な形で出題されることが多いため、自分なりに条件を整理して示す必要があります。
例えば「1日のカフェ利用者数」を推定する場合、都市規模や人口構成、利用頻度などを条件として設定してから考えると、数値に一貫性が出ます。
条件を抜いたまま進めると答えが飛躍し、論理性を失ってしまうでしょう。面接官は条件の立て方から思考の柔軟さや着眼点を見ています。条件を適切に言語化できるかが評価の分かれ目になります。
日頃から事例で練習し、短時間で条件を整理する習慣をつけておくと安心です。条件を明確にすることは解答の土台を築く大事な工程といえます。
③数値の根拠を示せるか
フェルミ推定では数値を提示するとき、必ず「なぜそう考えたのか」という根拠が求められます。根拠のない数値はただの勘に過ぎず、信頼性を失ってしまうのです。
例えば「1店舗あたり1日300人が来客」と仮定するなら、「駅前の店舗を観察すると昼と夜で合計300人ほど入っている印象がある」といった現実的な理由を添えると納得感が増します。
必ずしも正しいデータでなくてもよく、自分なりの論理を明示することが重要です。根拠を伝えることで思考の筋道がより明確になり、面接官の安心感にもつながるでしょう。
普段から身近な出来事を数字に置き換えて考える習慣を持つと、自然と根拠を提示できる力が育ちます。
④説明がわかりやすいか
論理的に考えていても、伝わらなければ評価は下がります。そのため説明の分かりやすさも大切です。
過程を説明する際は段階ごとに区切ったり、結論から話して補足を加えたりすると理解されやすいでしょう。難しい表現や専門的な言葉を避け、誰にでも分かる言葉で伝えることが必要です。
特に面接では限られた時間しかないため、簡潔で整理された話し方が評価されます。また声の大きさや抑揚も理解度に影響します。友人や先輩に模擬練習をお願いし、改善点を見つけると良いでしょう。
結局のところ「伝える力」も、数値の妥当性と同じくらい重視される評価基準です。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
⑤時間配分や効率性を意識できているか
フェルミ推定は制限時間のある中で取り組むことが多いため、時間の使い方や効率性も評価対象です。考え込みすぎて時間切れになってしまうと結論に至れません。
そのため、最初に全体の枠組みを作り、重要部分に重点を置く姿勢が必要です。
例えば「最初の2分で前提条件を整理し、次の5分で推定を進め、残り3分でまとめる」といった配分を意識すると、スムーズに進行できます。効率を考える力は就活だけでなく実際の仕事でも役立ちます。
限られた時間で成果を出す力をアピールできる点で、この観点は重要だといえるでしょう。時間管理を意識した練習を積み重ねれば、本番でも安定したパフォーマンスを発揮できるはずです。
フェルミ推定のやり方ステップ

フェルミ推定は就職活動の面接やケース面接でよく出題されるテーマであり、解き方の流れを理解しているかどうかが評価を左右します。
手順を意識して進めれば、論理が飛躍せずに自信を持って答えを出せるでしょう。ここでは具体的なステップごとに解説します。
- 前提条件を設定する
- 問題を分解してアプローチを決める
- モデル化を行う
- 数値を代入して計算する
- 結果を評価・検証する
①前提条件を設定する
フェルミ推定で最初に重要なのは前提条件をはっきり示すことです。前提がないまま計算を始めると根拠の薄い推定になり、面接官の評価も下がってしまいます。
たとえば「東京のカフェの数」を推定するなら「人口は約1,400万人」「1店舗あたり1日100人利用する」といった条件を置くと進めやすくなります。
必ずしも正確な統計でなくてもかまいませんが、説明できる理由が必要です。前提を伝えることで思考の筋道が見え、論理的に考えていることを示せるでしょう。
普段から身近なことを題材に仮定を考える習慣をつけておくと安心です。
②問題を分解してアプローチを決める
前提を決めた後は問題を細かく分け、どんな手順で解に近づくかを考えます。この工程を省くと複雑さに迷い、答えにたどり着けなくなる恐れがあります。
たとえば「全国の美容室の数」を推定する場合は「人口」→「1世帯の人数」→「世帯ごとの利用頻度」→「1店舗あたりの顧客数」という流れに整理できます。
分解すれば道筋が明確になり計算も進めやすくなります。この段階で口頭で流れを説明できると、面接官に理解されやすく評価も高まるでしょう。日頃から身近な疑問を分けて考える習慣を持ってください。
③モデル化を行う
分解したあとはシンプルなモデルを作り、数字を扱いやすくします。現実の状況は複雑ですが、すべてを考慮すると解が出せません。
そこで「平均的な家庭」「標準的な店舗」といったモデルを設定し、その枠で計算を進めると効率的です。
たとえば「映画館の観客数」を推定する際に「大規模館」と「小規模館」に分け、標準的な動員数を仮定する形にすると整理できます。
モデル化がうまくできると複雑さをまとめられ、思考に一貫性を持たせやすいです。面接官もその工夫を評価するでしょう。
④数値を代入して計算する
モデルができたら、仮定した数値を代入して推定を行います。この段階では計算を正確に行うことよりも、根拠を持って数値を選ぶことが大切です。
たとえば「駅前の飲食店の売上」を推定する場合は「1日あたりの来客数×客単価」で計算すると簡潔です。計算ミスを恐れる必要はなく「なぜその数値を選んだのか」を伝えるほうが評価されます。
練習を重ねれば暗算力も鍛えられ、本番で焦らずに取り組めるでしょう。面接官は計算結果よりも導き方を重視している点を意識してください。
⑤結果を評価・検証する
最後に必要なのは出した答えが現実的かどうかの検証です。もし結果が極端に大きすぎたり小さすぎたりするなら、前提や分解の仕方に無理があった可能性があります。
たとえば「東京都のタクシー台数」が数百万台と出れば不自然であり、見直しが必要でしょう。検証を怠ると論理性に欠ける印象を与えてしまいます。
一方で「この数値は大きすぎるため、前提を修正すると現実的になる」と補足できれば柔軟な思考として評価されるはずです。最後まで粘り強く考える姿勢を示してください。
フェルミ推定の例題
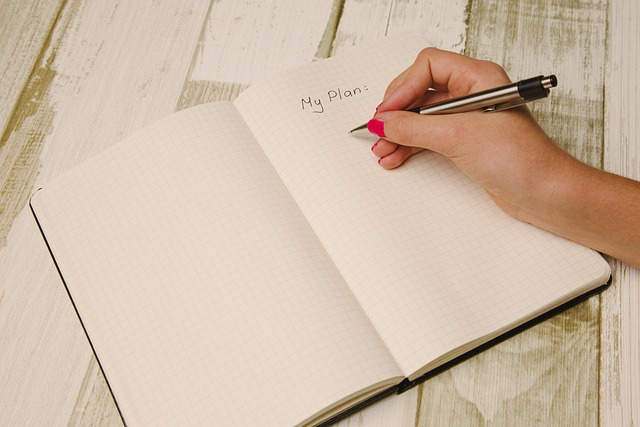
フェルミ推定を理解するには、具体的な例題を通じて思考の流れを体験することが効果的です。ここでは面接でよく出る定番のパターンから、応用力を求められる問題まで幅広く紹介します。
- 市場規模を推定する例題
- 人口や世帯数を用いた例題
- 売上や利益を推定する例題
- 身近な数量を推定する例題
- ユニークな発想が問われる例題
①市場規模を推定する例題
市場規模を推定する問題は、ビジネスの感覚を持って考えられるかを試す典型的な形式です。
例えば「国内のスマートフォン市場規模を推定してください」という設問では、人口や普及率、買い替え周期といった要素を組み合わせる必要があります。
大切なのは細かな数値を暗記していることではなく、全体をどう分解して計算するかです。日本の人口を約1億2,000万人と仮定し、普及率を70%とすると利用者は8,400万人になります。
さらに買い替え周期を3年、1台の価格を10万円と置けば、年間の市場規模はおよそ2兆8,000億円と導けるでしょう。このように段階的に整理して考える力が評価されます。
日常から市場規模を意識する練習をしておくと、本番でも落ち着いて対応できるはずです。
| 実際の例題:国内のタブレット端末市場規模を推定してください。 |
②人口や世帯数を用いた例題
人口や世帯数を基にした問題は、基礎的でありながら応用範囲が広いものです。例えば「東京都にあるコンビニの数を推定してください」という問いでは、人口と利用頻度を手掛かりに考えます。
東京都の人口を約1,400万人と置き、1世帯平均2.5人とすると世帯数は560万世帯です。次に1世帯あたり週に何回コンビニを利用するかを仮定し、総利用回数を出します。
仮に週2回とすれば年間で5億8,000万回程度になります。これを1店舗の年間利用者数で割れば、店舗数の推定が可能です。この方法は他の題材にも応用しやすいため、練習を重ねておくと良いでしょう。
普段から「この地域にスーパーは何軒あるか」と考えてみると、柔軟な発想力が身につきます。
| 実際の例題:大阪市にある美容院の数を推定してください。 |
③売上や利益を推定する例題
売上や利益を推定する問題は、企業活動を理解しているかを確認する意図で出題されます。
例えば「ファストフード店1店舗の年間売上を推定してください」という問題では、来店客数と単価を組み合わせる必要があるでしょう。
仮に1日の来店客数を500人、単価を800円とすると、1日の売上は40万円です。これを365日で計算すると、年間で約1億4,600万円になります。さらに利益を出す場合には、原価率や人件費を仮定。
例えば原価率30%、固定費などで40%とすると、利益率はおよそ30%程度でしょう。この流れを意識することで、単なる計算ではなく、ビジネスを理解している姿勢を示せます。
こうした問題は企業理解の練習にも直結するのです。
| 実際の例題:全国チェーンのカフェ1店舗が1年間で得る利益を推定してください。 |
④身近な数量を推定する例題
日常生活に関する数量を推定する問題もよく出題されるでしょう。例えば「日本で1日に消費される卵の数を推定してください」という問いがあります。
人口を1億2,000万人と仮定し、1人が1週間に3個食べるとすると、1週間で約3億6,000万個です。これを1日で割ると、5,000万個程度になります。
身近なテーマは数値を想像しやすいため、仮定の置き方によって答えに幅が出やすいのが特徴です。面接官は数値の正確さではなく、そこに至るまでの筋道を重視しています。
普段から「駅を利用する人数」や「家庭で出るごみの量」などを考える習慣をつけると、柔軟に対応できるでしょう。こうした題材は取り組みやすく、練習に適しています。
| 実際の例題:日本で1日に消費されるペットボトル飲料の本数を推定してください。 |
⑤ユニークな発想が問われる例題
一見突飛に思える題材で発想力を試す問題もあります。例えば「世界で同時に飛んでいる飛行機の数を推定してください」という問いです。この場合は柔軟な発想が必要になります。
世界人口を80億人と置き、1日に航空機を利用する人数を1億人と仮定。平均飛行時間を2時間とすると、同時に飛んでいる人数を割り出せます。
さらに1機あたりの乗客数を200人とすれば、同時に飛んでいる飛行機の数を導けるのです。このように段階を踏めば、想像しにくい問題でも答えに近づけます。
ユニークな例題では条件整理だけでなく、自分なりの視点をどう示すかが評価の分かれ目になるでしょう。
| 実際の例題:世界で同時に稼働しているエレベーターの数を推定してください。 |
フェルミ推定の問題を突破するコツ

フェルミ推定は面接やケース問題で出されることが多く、解答の進め方そのものが評価の対象になります。正しい知識と手順を理解すれば不安を減らし、落ち着いて答えを導けるでしょう。
ここでは突破のための具体的なコツを紹介します。
- 基礎知識を覚える
- 問題を要素に分解する
- 概算で大枠を捉える
- 制限時間を意識して取り組む
- 答えよりもプロセスを重視する
①基礎知識を覚える
フェルミ推定に取り組むには、日常的な数値感覚を身につけておくことが欠かせません。人口や世帯数、学校や企業の規模といった基本的な数字を知っていれば、問題に取りかかるスピードが上がります。
たとえば「東京都の人口は約1,400万人」「日本の世帯数は約5,000万」といった数字を覚えておけば、前提を置く際に迷わず進められるでしょう。
逆に基礎が不足していると、仮定が不自然になり全体の推定もぶれてしまいます。ここでは、よく使う指標を10~20個に絞り、スプレッドシートや単語帳にまとめる方法が有効です。
数字は丸めて覚えると再現性が高まり、緊張しても思い出しやすくなります。暗記に偏りすぎる必要はありませんが、目安となる“アンカー数値”を用意しておくと組み立てが安定するでしょう。
日頃からニュースの見出しを数値目線で読み、気になる数を1つだけ記録する習慣を続けてください。継続が力になります。
②問題を要素に分解する
問題をそのまま解こうとすると複雑に感じて進まないことがあります。そこで必ず要素に分けて整理することが大切です。
たとえば「日本で1年間に食べられるピザの枚数」を考える場合、「人口」→「ピザを食べる人の割合」→「1人あたりの年間消費量」と順に分けると理解しやすくなります。
この過程を踏むと思考が整理されるだけでなく、面接官に論理的に進めていることを伝えられるでしょう。分け方を説明しながら進めれば説得力も増し、結果が多少ずれても評価を得やすくなります。
さらに、要素は“もれなく・ダブりなく”を意識すると精度が上がるでしょう。依存関係の強い要素は先に固定し、後続の仮定が動いても全体が崩れない順序にすると安全です。
中間指標を1本置くと計算が簡潔になり、ミスも減ります。分解の型を3~4通り持っておくと、どのテーマでも落ち着いて対応できるでしょう。
③概算で大枠を捉える
フェルミ推定では正確な数字を出すより、概算で全体像をつかむことが評価されます。細かい計算にこだわると時間を消費し、結論にたどり着けない危険があるでしょう。
たとえば「全国のガソリンスタンドの数」を推定する場合、「車の台数」や「1台あたりの給油頻度」を概算し、店舗数に置き換えると大枠を把握できます。
大まかな数字から全体をとらえることで、現実的な答えに近づけるのです。ここでは、端数は積極的に丸め、桁をそろえると計算が滑らかになります。
10のべきでオーダー感を見ると、極端な誤差にすぐ気づけるのです。途中で“ざっくり検算”をはさみ、結果が直感とかけ離れていないかを確認してください。
感度が高い前提を1つ見つけ、上下に振っても結論が致命的に崩れないかを確かめると安心です。普段から“封筒の裏計算”を意識し、1分で粗い答え、3分で調整という癖を作りましょう。
④制限時間を意識して取り組む
面接で出されるフェルミ推定には必ず時間制限があります。時間を気にせず考え込みすぎると、答えにたどり着けず評価が下がる恐れがあるでしょう。
大切なのは大きな流れを先に作り、その上で計算に入ることです。途中で時間が切れても、アプローチをきちんと説明できれば十分評価されます。
普段から時間を区切って練習すれば、本番でも焦らず対応できるでしょう。「ここまでの仮定に基づくとおおよそこの規模になります」とまとめる意識が効果的です。
加えて、開始30秒で課題の再定義、次の90秒で分解とモデル化、残りで計算と検証という配分を目安にすると迷いません。
計算が重い箇所は先に単位と式だけ口頭で宣言し、面接官の同意を得てから進めてください。最後の30秒は必ず結果の妥当性チェックに使うこと。時間管理も評価対象です。
⑤答えよりもプロセスを重視する
フェルミ推定で見られているのは最終的な答えよりも、考えに至るまでの流れです。数値が極端に外れていても、筋道が通っていれば評価されます。逆に答えが近くても説明が不十分なら高く評価されません。
面接官は「この学生がどう考えるか」を見ているため、結論を急ぐより仮定や計算の流れを丁寧に示すことが重要です。
普段から自分の思考を声に出して整理する練習をしておくと、面接でも落ち着いて話せるでしょう。
ここでは、前提→式→計算→検証の順で“見出し語”を口にし、区切りごとに短く要約すると伝わりやすくなります。途中で前提が弱いと感じたら、その場で修正を宣言し、影響範囲を簡潔に述べてください。
透明性の高いプロセス。これこそが評価の核心です。
フェルミ推定の対策方法

フェルミ推定を克服するには、知識の暗記ではなく考え方を習慣化することが大切。面接で評価されるのは正解ではなく、限られた時間の中で論理的に筋道を立てられるかどうかです。
ここでは本番に強くなるための具体的な方法を整理しました。
- ロジカルシンキングを鍛える
- 頻出テーマに繰り返し取り組む
- 書籍や問題集を活用する
- 実際に声に出して説明する練習をする
- ケース面接を想定した練習を重ねる
①ロジカルシンキングを鍛える
フェルミ推定で評価されるのは論理の一貫性です。そのためにはロジカルシンキングを身につけることが欠かせません。具体的には大きな課題を分解して整理し、順序立てて結論に近づく練習が有効です。
例えば「国内で販売される靴の数」を考えるなら、人口から年齢層ごとの保有数を仮定し、買い替え周期を加えて導きます。このように繰り返すことで自然に筋道を立てられるようになるでしょう。
本番でも型を頭に入れておけば、焦らず対応できます。日常の題材を使って「駅を利用する人数」などを考えると、楽しみながら鍛えられるでしょう。
さらに、数値の根拠を1つひとつ確認しながら積み上げる癖を持つと、論理が途切れにくくなります。慣れてきたら短時間で答えを導くトレーニングを行い、思考の瞬発力も養ってください。
基礎力とスピードを両立させることが、本番での安心感につながります。
②頻出テーマに繰り返し取り組む
フェルミ推定にはよく出るテーマがあります。市場規模、人口や世帯数、飲食店やコンビニの数といった身近な題材です。
こうしたテーマを繰り返すことで、正確さよりも思考の流れを素早く整える習慣がつきます。初めての問題では前提を考えるのに時間がかかりがちですが、練習済みのテーマなら応用が利くでしょう。
また「この数値なら自然か」という感覚も磨かれます。大切なのは1度で満足せず、何度も取り組むことです。積み重ねが本番での安定につながります。
さらに、練習の際は同じテーマでも異なる切り口から解いてみることが効果的です。
例えばコンビニの数を「人口から推定する方法」と「利用者の頻度から推定する方法」の両方で考えてみれば、柔軟性が鍛えられます。
反復しながら多角的に取り組むことで、未知の問題にも自信を持って挑めるようになるでしょう。
③書籍や問題集を活用する
独学だけでなく、市販の書籍や問題集を使うと効率的に学べます。特に就活向けの教材には頻出の例題や解法がまとめられているため、初心者でも取り組みやすいでしょう。
解答例を参考にすると、自分の考えとの違いに気づけるのも利点です。ただし答えを覚えるだけでは意味がありません。
大事なのは「なぜこの前提を置くのか」「どうしてこの数字なのか」という理由を理解することです。問題を解いた後は必ず自分の言葉で説明し直し、理解を定着させてください。
教材を活用すれば効率よく力を伸ばせます。さらに、複数の教材を比較して使うと多様なアプローチを学べるのです。
著者や出版社ごとに解法のスタイルが異なるため、自分に合った型を見つけられるでしょう。演習後には振り返りノートを作成し、改善点を記録することを習慣化してください。
これにより知識の再利用性も高まり、短期間で実力を引き上げられます。
④実際に声に出して説明する練習をする
頭の中で解けても、口頭で説明できなければ評価は得られません。面接官は数値そのものよりも「どう考えたか」を聞きたいのです。だからこそ声に出して練習することが効果的。
例えば「東京の電車利用者数」を考えるとき、人口や通勤者の割合を仮定して声に出して説明します。口にすることで曖昧さや順序の不自然さに気づけるでしょう。
さらに時間を意識してまとめる力も鍛えられます。友人に聞いてもらえば、伝わりやすさについてフィードバックが得られるでしょう。声に出す習慣を持つことで、本番の緊張も和らぐはずです。
加えて、録音や動画で自分の説明を確認する方法も有効。客観的に聞き直すことで「話が長すぎる」「根拠が伝わっていない」など改善点を見つけられます。
繰り返すうちに論理展開と表現力が自然に磨かれ、安心して本番を迎えられるでしょう。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
⑤ケース面接を想定した練習を重ねる
実戦力を高めるには、ケース面接を意識した練習が有効です。フェルミ推定は単独で出題されるだけでなく、ケース面接の一部としても問われます。
限られた時間で結論をまとめ、相手に納得してもらう力が必要です。そのため模擬面接をしたり、仲間と問題を出し合ったりすると実践感覚が磨かれます。
本番に近い形で練習すれば、時間配分や説明の工夫が自然に身につくでしょう。また他人の考え方に触れることで、自分にない発想を取り入れるきっかけにもなります。
繰り返しケース形式で取り組むことが、自信につながる近道です。さらに、実際に企業の過去のケース問題を題材に練習すると、実戦性が一段と高まります。
難易度の高い問題に慣れておけば、本番で出題された際にも冷静に対応できるでしょう。チーム形式での練習を取り入れると協調性やリーダーシップも養え、総合的な力を伸ばすことが可能です。
フェルミ推定を就活で活かすために

フェルミ推定とは、限られた情報から合理的に数値を導き出す思考法であり、就職活動の面接やケース問題で多く問われます。
目的は論理的思考力や問題解決力を示すことであり、評価されるのは正しい答えそのものではなく、前提条件の整理や説明の明確さ、時間配分を含む思考のプロセスです。
実際のやり方は、前提を設定し問題を分解してモデル化し、数値を代入して検証する流れが基本になります。例題を通じて感覚を磨き、基礎知識を覚えておけば突破力が高まるでしょう。
さらにロジカルシンキングを鍛え、頻出テーマを繰り返し練習することで、自信を持って答えられるようになります。フェルミ推定の本質を理解し準備を積み重ねれば、就活の大きな武器になるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












