放課後児童支援員の資格とは?仕事内容や資格の取得方法を解説
「子どもと関わる仕事がしたいけれど、どんな資格が必要なんだろう?」
そんな疑問を持つ方に注目されているのが 「放課後児童支援員資格」 です。学童保育の現場で子どもたちの成長を支える専門職として、安心・安全な居場所づくりに欠かせない役割を担っています。
とはいえ、「学童保育指導員と何が違うの?」「どうやって資格を取るの?」と迷う人も少なくありません。
そこで本記事では、放課後児童支援員の定義や仕事内容、必要な資格や取得方法、さらに給料事情や将来性まで徹底解説します。子どもに関わるキャリアを考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
放課後児童支援員とは?

放課後児童支援員は、主に放課後に子どもたちの学びや遊びをサポートする役割を担う職業です。学校が終わった後、家庭での時間を過ごす子どもたちに、安全で有意義な時間を提供することが求められます。
この職業は、子どもたちの健全な育成を支援し、放課後の時間を充実させる重要な役割を果たします。
なぜこの職業が重要なのかというと、放課後は多くの家庭で親が仕事をしており、子どもたちが一人で過ごす時間が長くなります。
そのため、子どもたちに安全な環境を提供し、学習や遊びを通じて心身の成長を助けます。この仕事は、子どもたちの遊びや学びを支援する専門的な役職であり、資格を持つことが求められます。
そのため、資格を取得し、スキルを活かして子どもたちを支援できることが、この職業の大きな魅力と言えるでしょう。
学童保育指導員との違い

どちらも子どもたちの放課後の時間をサポートする職業ですが、役割や資格要件に違いがあります。まず、放課後児童支援員は、専門的な資格を持つことが前提となる職業です。
資格取得には、福祉や教育に関する一定の学びが必要で、子どもたちの発達段階に応じた支援を行うことが求められます。
放課後児童支援員は、放課後や学校の休暇期間中に、子どもたちの遊びや学習を支援し、個別のニーズに応じた指導や支援を提供します。
一方学童保育指導員は、主に子どもたちの放課後の安全を守り、遊びや学びを見守る役割を果たします。
資格がなくても働けることが多いものの、経験や知識が求められるため、保育や教育に関するスキルを持つ人が求められます。
自分が目指す職業の特性をよく理解し、どの資格が必要であるか、またはどのスキルを身につけるべきかをしっかりと把握することが、就職活動を進める上で重要です。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
放課後児童支援員の仕事内容

放課後児童支援員は学童保育の現場で子どもたちの成長を支える重要な役割を担っています。具体的には、学校が終わった後の時間に、子どもたちの遊びや学習を支援し、安心して過ごせる環境を提供する仕事です。
子どもたちにとっては、放課後の安心できる居場所を提供するだけでなく、親にとっても大切な時間帯に信頼できるサポートをする役割を果たします。ここでは具体的な仕事について紹介します。
- 主要業務と日常業務
- 子どもたちとの接し方と支援方法
- 放課後児童支援員の1日の流れ
①主要業務と日常業務
主な業務には、子どもたちの遊びのサポートや学習支援があります。子どもたちが放課後に安心して過ごせるように、安全な環境を整えることが求められます。
遊びのサポートでは、子どもたちが自由に楽しめる時間を確保し、協力やコミュニケーションを学べるような活動を取り入れることが重要です。
学習支援については、宿題の手伝いや個別の学習プランを作成することが求められます。また、保護者との連絡や相談も日常的に行われ、家庭との協力体制を築いていくことも重要な業務です。
これらの業務を通じて、放課後児童支援員は、子どもたちの成長を支え、日々の生活を豊かにする役割を果たします。
②子どもたちとの接し方と支援方法
この職に就くうえで重要なのは、子どもたちとの信頼関係を築くことです。子どもたちが安心して過ごせるように、まずは自分自身がしっかりとした姿勢で接することが大切です。
子どもたちは感情を敏感に感じ取るため、温かく、優しさを持って接することが基本となります。その上で、子どもたちの自主性を尊重し、自由な時間を確保することが大事です。
また、個別の支援も行い、各子どものペースに合わせた学習サポートを行います。グループ活動では、協力やコミュニケーションを学ぶ機会を提供し、集団の中でのルールやマナーを教えることが必要です。
こうした支援方法により、子どもたちは成長し、社会性を身につけていくことができます。
③放課後児童支援員の1日の流れ
この職業の1日は、通常午後から始まります。学校が終わると、子どもたちが学童保育に集まり、放課後の活動がスタートします。
最初に、子どもたちが来た時点で、健康チェックや個別の予定の確認を行い、その日のプランを立てます。その後、子どもたちが自由に遊べる時間を提供しつつ、必要に応じて学習支援を行います。
子どもたちが宿題をしている間に、個別にサポートが必要な子にはアドバイスや手伝いをすることもあります。
遊びの時間には、屋外でのスポーツやゲームを行うこともあり、体を動かす活動を通じて、子どもたちの心身の健康を支えます。
最後には、帰宅する時間が近づくと、子どもたちに今日の振り返りをしてもらい、保護者に連絡して帰宅をサポートします。子どもたちが安心して過ごせるように、1日の流れをきちんと見守り、支援します。
放課後児童支援員になるために必要な資格
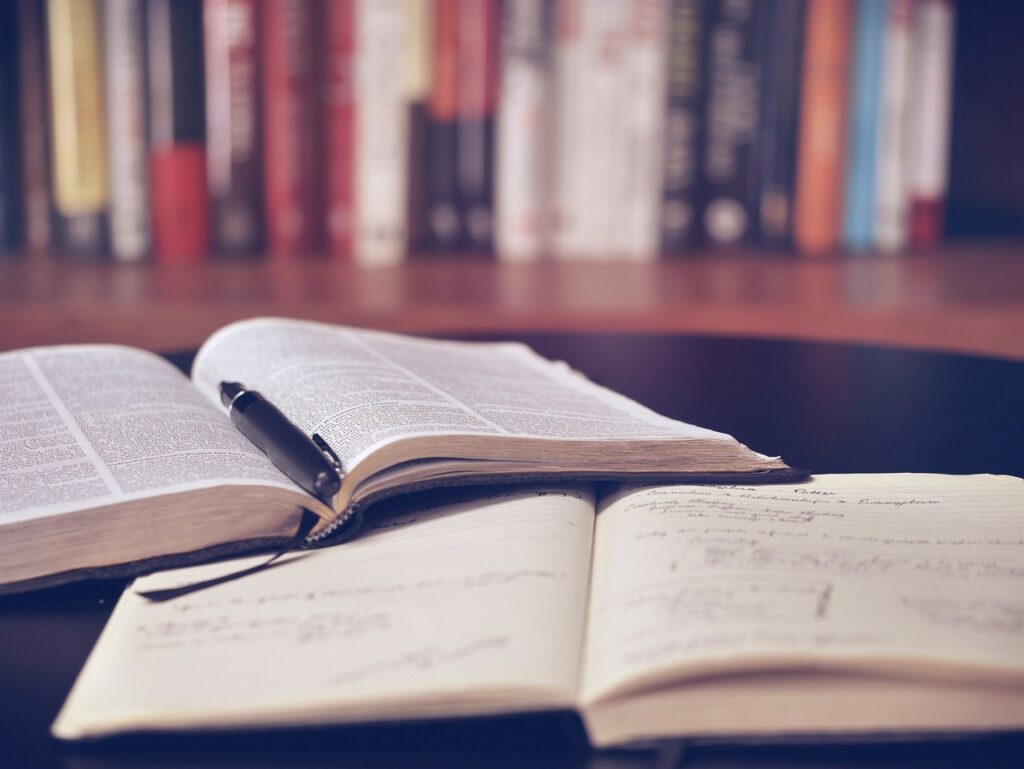
近年、働く親が増える中で、放課後の子どもたちを安全に育成し、支援する役割の重要性が高まっています。
そのため、放課後児童支援員としての資格は、求められるスキルや知識を証明するものとして重要です。ここでは、この職業に就くために必要な資格について詳しく説明します。
- 放課後児童支援員資格
- 放課後児童育成支援師資格
- 放課後児童専門育成支援師資格
- 放課後児童高度育成支援師資格
①放課後児童支援員資格
放課後児童支援員資格は、学童保育施設や放課後児童クラブで働くために必要な基本的な資格です。
この資格を持っていると、施設内で子どもたちの学習支援や遊びの指導、さらには安全管理が適切に行えることを証明できます。
放課後児童支援員の主な仕事は、子どもたちが放課後に安全に過ごすための環境を提供し、彼らの心身の成長をサポートすることです。
この資格を取得するためには、所定の研修を受け、試験に合格する必要があります。
研修内容は、子どもたちへの支援方法や法律、保護者とのコミュニケーション術などが含まれており、実際の現場で役立つ知識が身につきます。
合格後は、放課後児童支援員として、子どもたちの放課後をより豊かで安全なものにするために、さまざまな活動を行うことができます。
②放課後児童育成支援師資格
放課後児童育成支援師資格は、放課後児童支援員資格を取得した後、さらに専門的な内容を学び、より高度な支援を行えるようになるための資格です。
この資格を持つことで、特に発達に配慮が必要な子どもや個別の支援が求められる子どもたちに対して、きめ細かな対応ができるようになります。
育成支援師の役割は、子ども一人ひとりの個性を尊重し、その成長に合わせた支援を行うことです。
例えば、学習のサポートや情緒的な支援、さらには問題行動を持つ子どもへの対応方法についての知識が深まります。この資格を手に入れるには、追加の研修を受け、試験に合格する必要があります。
育成支援師として活躍することで、より多くの子どもたちに適切なサポートを提供し、放課後の時間をより実りあるものにすることができます。
③放課後児童専門育成支援師資格
放課後児童専門育成支援師資格は、放課後児童育成支援師資格をさらに深めた内容で、特に専門的な支援が求められる場合に必要とされる資格です。
この資格を持っていると、障がいを持つ子どもや、家庭環境に問題を抱える子どもへの支援ができるようになります。
放課後児童専門育成支援師は、子どもたちが直面している困難を理解し、より具体的な支援計画を立てて実行する役割を担います。
具体的には、個別の学習プランの作成や、行動上の問題を改善するための方法を提案・実践することが求められます。
この資格を取得することで、支援対象の幅が広がり、より多くの子どもたちの発達を促進するための支援が可能となります。
専門育成支援師としての知識や技術を活かして、より深いレベルでの支援が求められる現場で活躍できるようになります。
④放課後児童高度育成支援師資格
放課後児童高度育成支援師資格は、放課後児童支援員としてキャリアを積んだ後、さらに専門性を高め、リーダー的な役割を果たすために必要な資格です。
この資格は、放課後児童支援におけるリーダーシップを発揮し、支援員の指導や運営管理に携わることができる能力を証明します。
高度育成支援師は、支援活動の計画やスタッフの教育・指導を行い、放課後児童支援の質を向上させる役割を担います。
また、子どもたちへの支援だけでなく、保護者や地域との連携を強化することも求められます。資格取得には、実務経験とともに専門的な研修を受け、試験に合格する必要があります。
高度育成支援師として活躍すれば、放課後児童支援員の現場でリーダーシップを発揮し、組織全体の支援能力を高める重要な役割を担うことができます。
放課後児童支援員の資格の取り方

この資格を取得することで、放課後の子どもたちの学びの場をより良いものにできます。資格取得のためには、研修を受ける必要があります。
ここでは、放課後児童支援員資格を取得するための研修について、受講資格、研修の日数・期間、受講費用や申込方法など、必要な情報を詳しく説明します。
- 研修を受ける
- 受講資格
- 研修日数と期間
- 受講費用と申込方法
- 終了証を受け取る
①研修を受ける
放課後児童支援員として働くためには、専門的な知識やスキルを身につける必要があります。そのため、資格を取得するためには必ず研修を受けることが求められます。
この研修は、子どもたちと接する際に必要なスキルや知識を体系的に学べる機会であり、ただの座学にとどまらず、実技や実習を通じて実践的な力を養うことができます。
研修内容には、子どもの発達心理や安全管理、教育プランの立て方などが含まれます。これにより、資格取得後に現場で直面するであろう様々な課題に対応できる力をつけることができます。
各地の自治体や研修機関が主催しており、参加者にとって身近でアクセス可能な場所で実施されることが多いので、無理なく参加しやすいのも大きな魅力です。
②受講資格
放課後児童支援員の研修には、特定の受講資格が設けられています。
一般的には、保育士資格や幼稚園教諭免許を持っている人が優遇される場合がありますが、必ずしもこれらの資格を持っていなくても受講は可能です。
多くの研修プログラムでは、特定の学歴や職務経験を条件に誰でも受講できるようになっている場合があります。例えば、教育や福祉関連の学部を卒業した人や、子どもと関わる職務経験がある人などです。
しかし、資格や経験がなくても参加できるプログラムも多く、これから資格取得を目指す人にとっては安心して挑戦できる環境が整っています。
事前に各研修機関の受講条件を確認し、自分が応募できるかどうかをチェックすることが重要です。
③研修日数と期間
放課後児童支援員の研修は、開催される研修機関や地域によって異なりますが、一般的に数日間から数週間にわたることが多いです。
例えば、短期間の集中的な研修であれば数日で完結するものもありますが、より詳しい内容を学ぶために、数週間のプログラムが組まれていることもあります。
研修の内容が深く、実技や現場での体験が含まれる場合は、比較的長期間にわたることが予想されます。
また、研修は通常、平日の夜間や土日を中心に開催されることが多く、学生や社会人の方でも参加しやすい日程が組まれています。
自分のライフスタイルに合わせて、スケジュールを調整しやすいプログラムを選ぶことができます。参加する研修の期間や日程を事前に確認し、自分のスケジュールに合わせて準備をしておくことが大切です。
④受講費用と申込方法
放課後児童支援員の研修を受ける際には、費用がかかることが一般的です。研修の費用は、内容や地域によって異なりますが、おおよそ数千円から数万円程度です。
価格が高い場合でも、質の高い研修を受けることができるため、費用対効果をしっかりと考慮して選ぶことが大切です。
加えて、自治体によっては、研修の費用を補助する助成金制度が設けられている場合もあります。
こうした支援を活用することで、自己負担を軽減できる場合もあるため、事前に助成金の有無を確認しておくとよいでしょう。
また、研修の申込方法は、各研修機関の公式サイトでオンライン申し込みが可能な場合が多く、簡単に手続きを行うことができます。申込みの際は、定員に達する前に早めに申し込むことをおすすめします。
⑤終了証を受け取る
研修を無事に修了した後には、放課後児童支援員としての資格を証明する「終了証」を受け取ることができます。
この終了証を受け取ることで、放課後児童支援員として正式に認められ、実際に学童保育などの現場で働くことができるようになります。
終了証を取得した後も、資格を活かして子どもたちと積極的に関わり、現場での実践経験を積んでいくことが大切です。終了証が手に入ることによって、就職活動や転職活動を行う際にも有利に働きます。
資格取得後は、引き続きスキルを磨き、さらに高い専門性を持った支援員を目指すことが求められます。
放課後児童支援員の給料について

放課後児童支援員として働く際、給料については気になるポイントの一つです。この職業は、子どもたちの発達を援助する重要な役割を果たしていますが、給与水準はどのようなものなのでしょうか。
具体的な年収や給与体系、さらには地域差や勤務形態が給料にどのように影響するのかを知っておくことは、就職活動を進める上で大切です。
ここでは、放課後児童支援員の給料に関する基礎知識を深めていきます。
- 平均年収と給与体系
- 給料の地域差と勤務形態
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①平均年収と給与体系
放課後児童支援員の平均年収は、一般的に300万円から400万円程度です。しかし、この金額はあくまで目安であり、実際の年収は勤務地や勤務年数、職場の規模や役職によって大きく異なります。
例えば、大都市圏で働く場合や大規模な施設に勤務する場合は、高めの給与が期待できることが多いです。
給与体系は主に月給制や時給制が一般的で、パートタイムとして働く場合、時給換算ではおおよそ1000円から1500円が相場となります。特にフルタイム勤務の場合、月給で20万円から30万円程度が相場です。
しかし、給与額が高いほど、仕事の負担が増すこともあるため、就職活動時には労働環境も確認しておくことが重要です。
給与は、役職や責任範囲に応じて増加することもあり、経験を積むことで給与が上がる可能性もあります。
また、ボーナスや各種手当が支給される場合もあるため、実際の年収はさらに増加することがあるでしょう。
②給料の地域差と勤務形態
放課後児童支援員の給与には地域差が存在します。大都市圏では生活費が高いため、給料もそれに応じて高めに設定されていることが多いです。
特に東京や大阪などの都市では、給与が高く、同じ仕事でも地方に比べて高収入を得やすい傾向があります。都市部では、求人が多いため、選択肢も広がり、給与水準も安定しています。
また、勤務形態によっても給与に差があります。
正社員の場合は安定した給与が得られる一方で、パートタイムや契約社員として働く場合は、勤務時間に応じて給料が支払われるため、収入が不安定になることがあります。
パートタイム勤務では、時間帯や曜日によって給与が変動する場合もありますが、フルタイムで働くことで、生活基盤を安定させることができます。
また、勤務形態が変われば、福利厚生や昇給制度も異なるため、働き方に応じた生活設計が必要です。
放課後児童支援員に向いている人の特徴

放課後児童支援員は、学童保育や放課後の子どもたちをサポートする役割を担っています。
この職業に向いているのは、子どもと接することが得意な人、体力がありコミュニケーション力に自信がある人、柔軟な考え方で問題を解決できる人などです。
ここでは、この職業に必要な特徴をいくつかのポイントに分けて紹介します。自分がどのような人物かを見つめ直しながらご覧ください。
- 子どもが好きで教育に興味がある人
- 体力とコミュニケーション力に自信がある人
- 問題解決能力と柔軟性を持つ人
- チームワークを大切にする人
- 責任感が強く自己管理ができる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①子どもが好きで教育に興味がある人
放課後児童支援員は、日々多くの子どもたちと接する仕事です。子どもが好きで、教育に対する興味を持っていることは、この職業に必要な基本的な素質です。
学童保育においては、学童の成長を支援するだけでなく、彼らが学ぶ環境を整える役割も果たします。そのため、教育の重要性を理解し、子どもたちに良い影響を与えたいという熱意を持つことが大切です。
子どもが好きであれば、彼らとの接し方にも自然と優しさや思いやりが表れるため、子どもたちの信頼を得やすく、学習意欲を引き出すことができます。
また、教育に興味を持ち、日々の業務の中で子どもの成長を手助けできることは、放課後児童支援員のやりがいの一つです。
子どもたちに学びの楽しさや新しい知識を伝えるために、教育的なアプローチを積極的に取り入れることが求められます。
単に遊んだり宿題を見守るだけでなく、子どもたちが学びの中で成長できるよう、サポートする意欲がある人が向いていると言えるでしょう。
②体力とコミュニケーション力に自信がある人
放課後児童支援員は、児童たちと時間をともにしたり、宿題を手伝ったりと、身体を動かす場面が多いため、一定の体力が必要です。
特に、小学生などのエネルギッシュな子どもたちに対応するため、長時間元気に過ごせる体力や柔軟性が求められます。
体力がなければ、子どもたちと一緒に過ごす時間が長くなると疲れてしまい、質の高いサポートができなくなることもあります。そのため、体力に自信があることは、この仕事を続ける上で非常に大切です。
さらに、放課後児童支援員にとって、コミュニケーション力は欠かせません。子どもたちとの日常的なやり取りに加え、保護者や同僚との連携も重要です。
子どもたちと良好な関係を築くためには、彼らが気持ちを表現できるような雰囲気を作ることが求められます。困った時や嬉しい時に、しっかりとその感情を受け止め、言葉や行動でサポートする力が必要です。
日々の接し方を工夫することで、子どもたちが安心して学び、遊べる環境を提供できます。
③問題解決能力と柔軟性を持つ人
放課後児童支援員は、子どもたちが集団で過ごす中で起こるさまざまな問題に対処しなければなりません。例えば、遊びの中でケンカが起きたり、個々の子どもが学習面で困ったりすることがあります。
こうした問題に対して、放課後児童支援員は素早く冷静に対応する必要があります。感情的にならず、客観的に問題を捉え、適切な対応策を考える力が求められます。
また、放課後の時間帯は、学校から帰ったばかりの子どもたちが疲れやストレスを感じていることもあります。そのため、柔軟な考え方が大切です。
状況に応じて、臨機応変に対応することで、子どもたちのニーズに応え、ストレスを和らげることができます。
例えば、ケンカをしている子どもたちに対して、どちらの立場も理解しながら和解に導く方法を考えるなど、柔軟に対応することが重要です。
④チームワークを大切にする人
この職業の業務は、基本的にチームで行うものです。子どもたちの安全や生活環境を守るためには、同僚や他のスタッフとの協力が不可欠です。
子どもたちの活動を円滑に進めるために、スタッフ間で役割分担をし、意見を交換しながら協力して業務を進めることが求められます。
チームワークを重視することで、子どもたちにとってより良い環境を提供することができます。さらに、放課後児童支援員は、保護者や地域との連携も大切な役割です。
保護者との定期的なコミュニケーションを取り、子どもたちの生活面での相談に応じることが求められます。
そのため、チームとしての協力を大切にし、周囲としっかり連携する意識があることは、この仕事を成功させるために必要な素質です。
⑤責任感が強く自己管理ができる人
放課後児童支援員は、子どもたちの生活や安全を直接的に預かる職業です。子どもたちの行動や健康状態に細心の注意を払い、彼らを守る責任があります。
放課後という時間帯は、学校が終わってから帰宅するまでの時間を過ごす大切な時間です。この時間帯におけるサポートは、子どもたちにとって非常に重要な意味を持ちます。
そのため、放課後児童支援員には、強い責任感が求められます。また、この仕事は自己管理が求められる場面も多くあります。
子どもたちが安全に過ごせるよう、日々のスケジュールや業務をしっかりと管理し、柔軟に対応しながら業務を進める必要があります。
自己管理ができることで、子どもたちに安定した環境を提供でき、信頼される存在となることができるでしょう。
放課後児童支援員として働く将来性

放課後児童支援員は、学童保育を担当する重要な職業であり、その将来性は非常に高いです。特に少子化の影響で、放課後児童支援員の需要は増加傾向にあります。
この職業に従事することで、安定した収入や職場での成長の機会を得ることが可能です。
現在の社会におけるニーズの高まりや、今後予想される社会的背景を踏まえた上で、放課後児童支援員としての将来性について考えてみましょう。ここでは、この仕事で働く将来性について具体的に紹介します。
- 放課後児童支援員のキャリアパス
- 将来の需要と仕事の安定性
- 資格取得後の成長機会
- 他の職業との比較と成長の可能性
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①放課後児童支援員のキャリアパス
放課後児童支援員のキャリアパスは、教育・福祉分野の他の職業と比べても非常に多様です。最初に放課後児童支援員として働き始めた場合、まずは現場で実務経験を積むことが大切です。
この経験を通じて、子どもたちとのコミュニケーション能力や、保護者との連携スキルを向上させることができます。
次に、スキルや知識を深めることで、主任やリーダー職など、より責任ある役職に就くことが可能です。
さらに、資格を取得すると、業務の幅が広がり、教育や福祉の分野でさまざまな職業に挑戦できるようになります。
例えば、児童福祉士や保育士として活躍したり、教育機関での指導職や行政職に進む道も開けます。
これにより、個々のキャリアの方向性に合わせた成長が可能となり、常に新しい挑戦を通じて自己実現を果たすことができるのです。
②将来の需要と仕事の安定性
この職業の仕事は、今後さらに安定することが予想されます。現在、核家族化が進んでおり、共働き家庭が増えているため、学童保育の需要はますます高まっています。
これに伴い、放課後児童支援員の職は欠かせない存在となり、ますます求められるようになるでしょう。また、地域によっては学童保育施設の数が不足しており、新たに施設を設立する動きが加速しています。
今後も地域や社会全体での支援が強化されると考えられ、放課後児童支援員に対する求人は安定して増加するでしょう。
さらに、地域での働き手が不足する中、経験豊富な支援員に対する需要は高まっており、これが安定した雇用機会につながります。
放課後児童支援員として働くことは、社会的にも非常に意義のある仕事であり、仕事に就いた後の安定性が保障されている点が大きな魅力です。
③資格取得後の成長機会
放課後児童支援員として資格を取得した後は、さまざまな成長機会が待っています。資格を取得することで、放課後児童支援員としての専門知識を証明し、より責任のある仕事に挑戦できるようになります。
例えば、現場での実務経験を積んだ後には、指導者としての役割を担うことができ、子どもたちや同僚に対してサポートを行う立場になることもあります。
また、研修や勉強を通じて、児童心理学や教育方法についてさらに深く学ぶことができ、より質の高い支援を提供できるようになります。
資格取得後は、研修制度が整っている施設が多く、定期的にスキルアップの機会が提供されるため、常に自己成長を実感できる点が魅力です。
これらの機会を活かすことで、さらにキャリアアップを目指し、次のステップへの挑戦が可能です。
資格を活かし、より多くの経験を積むことで、専門職としての市場価値を高めることができ、長期的なキャリアを築いていくことができるでしょう。
④他の職業との比較と成長の可能性
放課後児童支援員は、他の教育や福祉関連の職業と比較しても独自の成長機会が豊富です。
例えば、教師や保育士は特定のカリキュラムや子どもの発達に基づいた指導を行いますが、放課後児童支援員は子どもたちと密接に関わりながら、遊びや学びを通じて成長を支援します。
そのため、子どもたち一人ひとりの個性に合わせた支援が求められ、日々の業務で多くの学びがあります。特に放課後児童支援員は、子どもたちとの時間が多いため、直接的な成長を感じやすい点が魅力的です。
また、家庭や地域との連携を強化する役割も担っており、社会的な貢献度が高い仕事です。
これにより、やりがいや充実感を感じながら働くことができ、仕事を通じて自己成長を遂げやすい点も大きなポイントです。
放課後児童支援員は、他の職業と比べて柔軟性があり、さまざまなキャリアパスを選択できるため、将来的にも多くの選択肢が広がる職業であると言えます。
必要な資格について知り、放課後児童支援員を目指そう!

放課後児童支援員として働くためには、必要な資格を取得することが重要です。まず、基本的な資格である「放課後児童支援員資格」を取得することで、専門的な知識とスキルを身につけられます。
さらに、資格取得後も「放課後児童育成支援師」や「放課後児童専門育成支援師」など、上級の資格を取得することで、より専門的な支援ができるようになります。
放課後児童支援員は、子どもたちの成長を支える大切な役割を果たす職業であり、資格を取得することでその責任をしっかりと担えます。
資格取得を通じて、子どもたちの成長に貢献し、自己成長をも実現できる職業です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













