離職率の調べ方を徹底解説|平均値や離職率が高い企業の特徴とは
「離職率ってどうやって調べればいいの?」「数字を見ても意味が分からない…」 就職や転職を考える際に、多くの人が気になるのが企業の離職率です。
働きやすさや定着率を判断するうえで重要な指標ですが、調べ方や平均値の目安、高い企業に共通する特徴などは意外と知られていません。
そこで本記事では、離職率の調べ方を徹底解説し、計算方法や平均値のデータ、さらに離職率が高い企業の傾向について詳しく紹介します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
離職率とは?意味と定義をわかりやすく解説

離職率とは、一定の期間に企業や組織から退職した人の割合を示す数値で、就職先を選ぶときの大切な指標です。就活生にとっては、入社後の働きやすさや職場環境を知るための判断材料となるでしょう。
数値が高ければ「人が定着しにくい職場」、低ければ「働きやすい職場」という印象を持つ人が多いものです。ただし、数字だけを単純に比べるのは危険です。
たとえば成長の速いベンチャー企業では、新しい挑戦を求めて短期間で転職する人が多く、必ずしも「悪い職場環境」だけが理由ではありません。
逆に、離職率が低い企業でも「転職が難しいため仕方なく働き続けている」というケースもあります。大事なのは、離職率の意味を正しく理解し、業界や企業の背景と合わせて考えることです。
この視点を持てば、「こんなはずじゃなかった」という後悔を減らせますよ。
離職率の調べ方|就活生が企業を調べる具体的な方法

就活で企業を選ぶとき、離職率は働きやすさや定着率を知るうえで大切な指標です。しかし、ただ数値を見るだけでは理解が浅くなり、調べ方によって得られる情報の質も変わります。
ここでは、就活生が実際に使える方法を整理しました。
- 就職四季報で調べる
- 有価証券報告書を確認する
- 帝国データバンクを活用する
- ハローワークや求人票で確認する
- 口コミサイトを利用する
- 就活エージェントに相談する
- 企業に直接確認する
- 自分で離職率を計算する
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
① 就職四季報で調べる
就職四季報は就活生にとって最も利用しやすい情報源の1つです。企業ごとの離職率が一覧で確認できるため比較がしやすいですよ。
さらに、掲載されているのは信頼性の高いデータなので参考にしやすいのも強みです。ただし、業界や企業によっては最新情報が反映されていない場合もあるため、過信は禁物です。
四季報を見るときは、他の資料も併せて調べて総合的に判断してください。数値だけでなく、平均勤続年数や新卒3年以内離職率も確認すると実態をつかみやすくなります。
さらに、掲載されている福利厚生や人材育成制度の項目も合わせて読むことで、定着率を左右する背景が見えてきやすいのが特徴です。
書籍版だけでなくオンライン版もあるため、アクセスのしやすさを考えて自分に合った方法で活用して見ましょう。
② 有価証券報告書を確認する
有価証券報告書は上場企業が必ず公開する公式資料で、信頼性が高い点が魅力です。従業員数や平均勤続年数が記載されているため、それを手がかりに離職率を推定できますよ。
特に平均勤続年数が極端に短い場合は注意が必要で、早期退職者が多い可能性があります。しかし、そもそも内容が専門的でわかりづらいですから、なかなか読み解けないこともあるでしょう。
その場合は大学のキャリアセンターや就活エージェントに相談すると理解が進みます。
また、有価証券報告書には企業の事業内容や経営方針、過去の業績の推移も詳細に載っており、会社の安定性を知る手がかりにもなります。
安定性の低い企業は離職率が高い傾向にあるため、経営状態と勤続データを組み合わせて判断することが重要です。
数字を比較しながら、背景を読み解く姿勢を持つことで、表面上は見えないリスクに気づくことができますよ。
③ 帝国データバンクを活用する
帝国データバンクは企業の信用調査を専門に行う機関で、経営情報や従業員データが豊富です。
個人で利用すると費用がかかる場合もありますが、大学や自治体が契約していると学生は無料で閲覧できることもあります。
ここで得られる情報は、離職率に影響する経営の安定性や業績推移を把握するのに役立つでしょう。
ただし、必ずしも離職率そのものが掲載されているわけではないため、他の資料と組み合わせる必要があります。
帝国データバンクのデータには、企業の支払い能力や取引先との関係性も含まれており、これらは働きやすさや雇用の安定性と密接に関わっています。
業績が不安定な企業では人材流出が起きやすいため、経営情報を通じて潜在的な離職リスクを見極められますよ。
利用可能な環境があるなら積極的に確認し、定量的な数字だけでなく経営背景も読み取る姿勢を持つと良いでしょう。
④ ハローワークや求人票で確認する
ハローワークや大学に届く求人票には、企業が提出した離職率の情報が載っている場合があります。特に「新卒採用者の定着率」は参考になりやすい項目です。
実際に入社後すぐに辞める人が多いかどうかを知る手がかりになるでしょう。ただし、記載内容が必ず正確とは限らず、更新頻度にも差があります。
そのため、他の資料や先輩の声とあわせて確認することが大切です。
加えて、求人票には初任給や勤務時間、福利厚生といった項目も記載されており、離職率の背景を読み解くヒントになります。
例えば残業時間が多い企業は定着率が低い可能性が高く、数字以上に重要な判断材料になるでしょう。情報を総合的に捉えることで、求人票を有効な判断基準として活用できます。
⑤ 口コミサイトを利用する
口コミサイトは実際に働いた人の声が集まるため、数字だけでは見えない雰囲気を知る手段となります。離職率の数値がなくても「人間関係」「残業時間」「社風」などから退職理由を推測できるでしょう。
特に人間関係や成長機会に関する投稿は参考になります。ただし、口コミは個人の主観に左右されやすく、極端な意見も少なくありません。1つの投稿にとらわれず複数の声を比較することが欠かせません。
さらに、口コミの投稿時期も重要です。数年前の情報では現在の実態と異なる場合があるため、なるべく直近の投稿を優先して読むと安心でしょう。
公式資料では得られない情報を補い、数字の裏にある現場の空気感を理解する助けとなります。冷静に判断すれば、入社後のギャップを減らす強力な武器になりますよ。
⑥ 就活エージェントに相談する
就活エージェントは企業とのつながりがあるため、一般公開されていない離職率や定着率を知っている場合があります。特に中小企業の情報を得やすいのは大きなメリットです。
採用担当者から直接得た情報を基にアドバイスしてくれることもあるため、信頼性も高いでしょう。
ただし、エージェントによって紹介企業に偏りがあることもあるため、自分に合った企業を見逃す可能性があります。複数のエージェントを利用して情報のバランスを取ることが重要です。
さらに、エージェントは就活全体のスケジュール管理や面接対策のサポートも行ってくれるため、離職率の調査にとどまらず総合的な支援を受けられます。
効率的に情報を収集しながら、自分に合った企業を探すための大きな助けになるでしょう。
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
⑦ 企業に直接確認する
説明会や面接で離職率を質問するのも有効な手段です。直接聞けば最新の情報を得られるだけでなく、企業の姿勢も見えてきます。誠実に答えてくれる企業であれば信頼できるでしょう。
一方で、回答を避けるような企業は注意が必要です。質問の仕方にも工夫が必要で、「新卒の定着率」や「平均勤続年数」といった表現を使うと聞きやすくなります。
さらに、質問したときの担当者の表情や回答の仕方から、企業文化の一端を感じ取れることもあります。数値以上に大切なのは、透明性や誠実さを持っているかどうかです。
面接は自分が評価される場であると同時に、企業を見極めるチャンスでもあります。勇気を持って質問することで、自分に合った環境を選びやすくなるでしょう。
⑧ 自分で離職率を計算する
公開されている従業員数や入退社のデータを使えば、自分で離職率を計算できます。一般的には「一定期間の退職者数÷期初の従業員数×100」という式を用います。
これにより、企業が公表していなくても傾向を把握できるでしょう。ただし、必要な情報が不足すると正確な数値は出せません。
そのため、四季報や有価証券報告書など複数の資料を組み合わせる工夫が必要です。さらに、計算結果を他社や業界平均と比較すると、相対的にその企業の特徴を理解しやすくなります。
少し手間はかかりますが、数値の根拠を理解する力は社会人になってからも大きな武器になります。信頼できる判断軸を持つためにも挑戦してみてください。
日本の離職率の平均と現状

日本の離職率は、業界や年代によって大きく異なります。就活生にとっては「せっかく入社してもすぐ辞めることにならないか」という不安がつきものです。
そのため、全体の平均値だけでなく、新卒3年以内のデータや産業別の傾向まで把握することが大切です。ここでは信頼できる統計をもとに、日本の離職率の実態を解説します。
- 全体の平均離職率
- 新卒入社3年以内の離職率
- 産業別の離職率
- 企業規模別の離職率
- 男女別の離職率
① 全体の平均離職率
離職率の全体平均を知ることは、就活生にとって業界研究の第一歩になります。厚生労働省のデータによると、日本全体の年間平均離職率はおよそ15%前後です。
100人が入社すると、15人ほどが1年以内に会社を去る計算になります。これは「高い」と感じる人もいれば「意外と低い」と思う人もいるでしょう。
重要なのは、この数字を良し悪しで単純に判断しないことです。業界によって差が大きいため、平均だけを基準にしてしまうと実態を見誤る恐れがあります。
さらに離職率の数字には景気動向も反映されるため、好況期と不況期では数値が変動します。
就活では「平均より高いか低いか」を軸にするのではなく、志望する業界と照らし合わせて判断し、加えて景気や雇用の流れを踏まえることで、より現実的な判断ができるでしょう。
② 新卒入社3年以内の離職率
新卒が3年以内に離職する割合は、就活生が特に気になる数字でしょう。厚生労働省の調査では、およそ30%が3年以内に退職しています。つまり3人に1人が早期離職を経験している計算です。
見る人によっては「せっかく就職してもすぐ辞める人が多い」と不安になるかもしれませんが、この数値は長年ほぼ横ばいで、大きな変動は見られません。
また、ここには「ミスマッチによる転職」や「キャリアアップのための前向きな退職」も含まれています。重要なのは、この数字が必ずしもネガティブな意味だけを持つわけではない点です。
例えば近年は働き方や価値観の多様化が進み、最初の会社で経験を積んでから新しいキャリアに挑戦する人も増えています。
就活生は「辞める人が多いから危険」と単純に判断せず、自分が続けやすい環境や成長につながる場をどう選ぶかを考えると安心できるでしょう。
③ 産業別の離職率
産業ごとに見ると、離職率には大きな差があります。宿泊・飲食サービス業では30%を超える一方、金融業や製造業は10%台前半にとどまっています。
背景には、労働環境や給与水準、キャリア形成のしやすさなどが関係しています。注意したいのは、離職率が高い=「悪い会社」とは限らない点です。
たとえば接客業では、人材の流動が活発でスキルを得てから次の職場に移る人も多く見られます。逆に離職率が低い業界は安定していますが、成長のスピードが遅いと感じる場合もあるでしょう。
さらに、同じ業界の中でも企業ごとに差があるため、一括りに判断するのは危険です。就活生は業界全体の数値を参考にしつつ、志望先の企業の取り組みや働き方を具体的に確認することが求められます。
④ 企業規模別の離職率
企業の規模によっても離職率には傾向が見られます。大企業では10%台と比較的低く、中小企業では20%前後とやや高めです。
大企業は福利厚生や教育体制が整っており、長く働きやすい環境といえますが、部署異動が多かったり競争が激しかったりする点が課題になり得ます。
中小企業は裁量が大きく柔軟性もありますが、制度が整っていない場合に負担を感じることも少なくありません。
ただし、離職率が高めであっても、社員が若く転職に前向きであることや、経験を積んで次に進むケースが多いことも影響しています。
規模だけで良し悪しを判断せず、自分が重視するポイントを整理し、具体的な社内制度や働き方を確認すると安心でしょう。
⑤ 男女別の離職率
男女別で見ると、20代から30代にかけては女性の離職率がやや高めです。背景には出産や育児などのライフイベントが関係しており、職場の制度や理解度によって継続のしやすさが変わります。
ただし、近年は育休制度の普及や柔軟な働き方の導入により、女性の離職率は改善傾向を示しています。
男性においても、転職によるキャリアチェンジを積極的に選ぶ人が増えているため、男女間の差は以前ほど大きくありません。
就活生が大切にすべきは、数字そのものよりも「どのような働き方を選んでも続けられる環境が整っているか」という視点です。
制度の有無や取得実績を調べたり、社員の声を確認したりすれば、自分に合う職場を見極めやすくなるでしょう。
引用:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」「雇用動向調査結果」など公表統計データ
離職率の計算方法と基準の見方
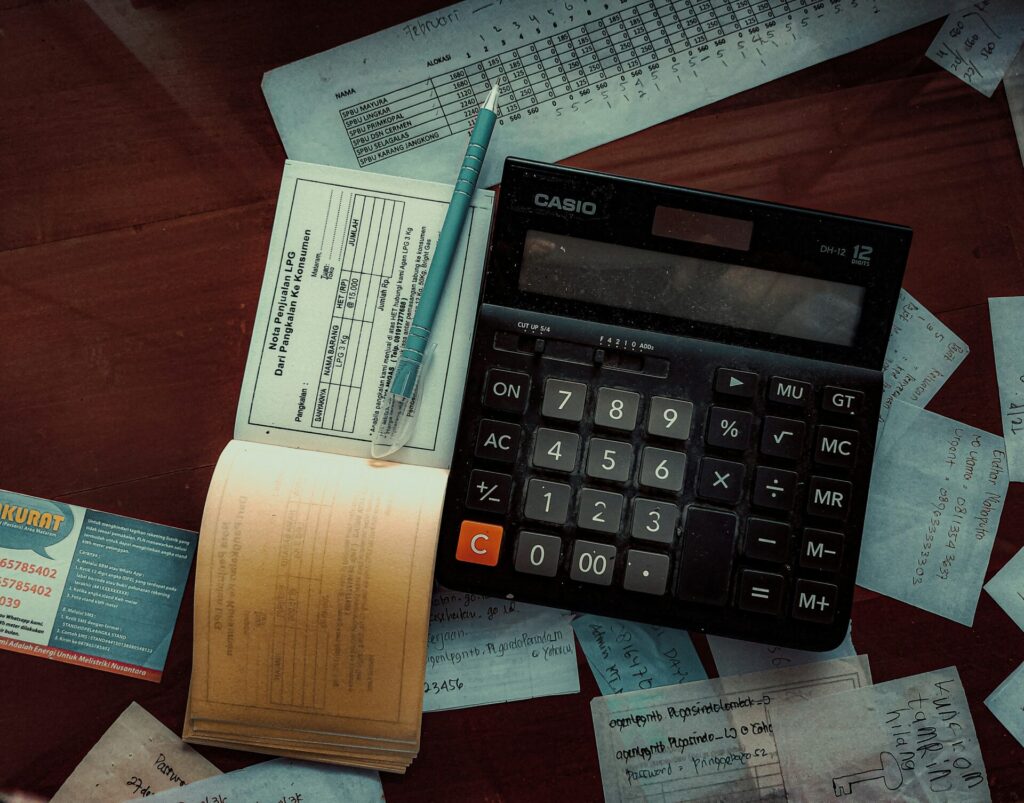
就職活動を進める中で「離職率」という言葉をよく目にしますが、計算方法を理解していないと数値の意味を誤解してしまうかもしれません。
ここでは基本的な計算式から、新卒3年以内離職率、期初・期末を基準にした考え方、中途採用者に関する方法まで順に紹介します。企業を見極めるうえで役立つ知識として押さえておきましょう。
- 基本的な計算式
- 新卒3年以内離職率の計算方法
- 期初・期末を基準にした計算方法
- 中途採用者の離職率の計算方法
① 基本的な計算式
離職率の基本的な出し方は「一定期間に退職した人数を、その期間の在籍社員数で割る」というものです。たとえば、1年間で社員100人の会社から10人が辞めた場合、離職率は10%になります。
数字自体は単純ですが、見方を誤ると実態を正しく把握できません。母数を期初で取るか期末で取るか、または平均人数で取るかによっても大きく変わるからです。
さらに、正社員だけを対象にするのか、契約社員やパートも含めるのかでも結果は違います。実際に企業を調べるときは、どの範囲の人員を基準にしているか確認してください。
単に「離職率が低い=良い会社」と短絡的に考えるのではなく、その背景や算出方法を理解して判断することが安心できる企業選びにつながるでしょう。
② 新卒3年以内離職率の計算方法
「新卒3年以内離職率」は、厚生労働省の調査でも公表される指標であり、就活生にとって特に気になるデータです。
計算方法は、ある年度に入社した新卒社員のうち3年以内に退職した人数を、入社時の人数で割って算出します。たとえば、50人が入社し、そのうち15人が3年以内に辞めたなら離職率は30%です。
数字自体は理解しやすいですが、業界ごとに平均が異なる点に注意しましょう。小売や外食などでは高め、金融や製造では比較的低めになる傾向があります。
つまり、数値だけを見て高低を判断するのではなく、同じ業界の平均と比べることが重要です。
志望先の企業で実際にどのような働き方ができるのかを調べることが、不安を解消する一歩となるでしょう。
③ 期初・期末を基準にした計算方法
離職率を算出する際は「期初の社員数」か「期末の社員数」を母数にするかで結果が変わります。
期初基準は年度の始まりの人数を分母にするため、採用や退職の影響を受けにくく安定的に比較できるのが利点です。
一方で、期末基準は年度末の人数を使うため、採用や増員が多い企業では数値が低めに出やすくなります。
特に成長中の企業では、期末の人数が大幅に増えているケースが多いため、見た目ほど定着率が良いとは限りません。
就活生としては、どの基準で算出されているかを知るだけでなく、採用動向や事業の成長段階を踏まえて数値を解釈することが必要ですよ。
単純に数値だけを信じるのではなく、裏にある状況まで考えてこそ企業理解が深まるでしょう。
④ 中途採用者の離職率の計算方法
中途採用者の離職率も「入社した人数に対して退職した人数を割る」ことで算出しますが、新卒の場合と比べて読み取り方に注意が必要になります。
中途採用は即戦力として採用されるため、仕事内容や責任範囲が明確なケースが多いです。
その一方で、キャリアアップや条件改善を目的に転職する人が一定数いるため、数値が高くても必ずしも悪い環境とは言えません。
むしろ、専門性が高い職種では人材が流動しやすく、それが自然な傾向となっている場合もあります。
離職率を見る際には、どの職種でどのような人材を採用しているか、またその企業がどの段階で人材を必要としているかを考えることが大切です。
数字だけで一喜一憂せず、背景を理解することが就活生にとって安心材料となるはずです。業界特性や職種ごとの傾向を知っておくと、より現実的な判断ができるでしょう。
離職率が高い企業の特徴

就活を進める中で「離職率が高い会社は避けたい」と考える学生は多いですが、その特徴を正しく理解しておくことが大切です。
離職率が高い企業には、働きやすさや将来性に不安を感じさせる共通点があります。ここでは具体的な要因を整理し、就職先を見極める判断材料にしてください。
- サービス残業が多い企業
- 人間関係が悪い企業
- 風通しが悪い企業
- 給与や待遇が低い企業
- 将来性に不安がある企業
- ハラスメントが多い企業
① サービス残業が多い企業
サービス残業が常態化している会社は、離職率が高くなる傾向が強いです。労働時間が長いにもかかわらず正当な報酬が支払われなければ、心身の疲れや不満が積み重なり、働き続ける気持ちを保てません。
たとえば「定時後に残業するのが当然」という空気があり、それが評価や昇進に結びつかない環境では、特に若手社員が早く辞める選択をしがちです。
さらに、サービス残業を見過ごす会社はコンプライアンス意識が低く、他の制度や教育環境も整っていない場合が多いでしょう。
こうした職場を避けるには、説明会や口コミサイトで「残業代がきちんと支払われているか」「勤怠管理の仕組みがあるか」を確認してください。
労働環境が健全であれば、安心感が得られ、長期的にキャリア形成を進めやすくなります。
② 人間関係が悪い企業
人間関係が悪い会社は、離職率が高くなりやすい典型的な特徴を持ちます。
上司との信頼関係が築けない、同僚との協力体制が機能しない職場では、仕事の負担が大きくなるだけでなく精神的ストレスも増加します。
新入社員は特に周囲のサポートを必要としますが、それが得られなければ孤立感を抱き、早期退職を選ぶことも少なくありません。
また、人間関係が悪い環境では情報共有が滞り、誤解や衝突が増えるため、業務効率も下がります。これを見抜くには、口コミやOB訪問で実際の雰囲気を確認するのが効果的です。
さらに、採用面接で「チームで取り組む制度があるか」「社内の交流を促すイベントが行われているか」といった質問をしてみてください。
良好な人間関係が築ける職場であれば、安心して挑戦でき、成長も促されるでしょう。
③ 風通しが悪い企業
風通しが悪い会社とは、社員の意見が上層部に届かず、情報の流れも閉ざされている職場のことです。
改善の提案をしても反映されない、一方的な指示だけが降りてくる環境では、働く意欲が削がれてしまいます。
若手社員は特に、自分の意見を受け止めてもらえるかどうかで成長意欲が変わるため、風通しの悪さは早期離職につながる大きな原因となります。
さらに、このような職場では評価や昇進の基準も不透明で、努力しても報われないと感じやすいですよね。
確認の方法としては、企業インタビューや公開情報から「社員の声をどれだけ施策に取り入れているか」を探ることも有効になります。
風通しの良い職場では、問題点を共有しやすく改善も早いため、安心して長期的に働ける環境である可能性が高いですよ。
④ 給与や待遇が低い企業
給与や待遇が低い企業は、離職率が高くなりがちです。給料は生活の安定を支える重要な要素であり、同業他社と比べて明らかに低い場合は「このままここで働いて良いのか」と不安を抱く原因となります。
特に新卒社員は同世代との比較をしやすく、待遇差が不満につながる傾向が強いです。給与水準だけでなく、昇給の仕組みや賞与、福利厚生といった項目も含めて総合的に判断しなければなりません。
待遇が劣っていると、結婚や住宅購入などライフイベントの際に将来設計を描きにくくなり、転職を考えるきっかけになってしまいます。
応募を検討する際は、厚生労働省や求人票で示される平均データと比較し、納得感を持てる水準かどうか確認してください。
待遇が十分に整った会社なら、働く意欲を維持しやすく長くキャリアを積めるでしょう。
⑤ 将来性に不安がある企業
将来性に疑問がある企業も離職率が高い特徴を持ちます。経営基盤が弱い、業界全体が縮小傾向にある、時代の変化に対応できていないなど、長期的に安定して働ける見込みが薄い場合、社員は安心できません。
若手社員ほどキャリア形成に意欲的であるため、成長が見込めない会社では早めに転職を決断することが多いです。
さらに、経営戦略が曖昧だったり、イノベーションへの投資が不足していたりする企業も注意が必要です。見極めるには、業界の成長性や企業の経営計画、売上の推移を確認することが有効です。
⑥ ハラスメントが多い企業
ハラスメントが横行する企業は、離職率が高いのは当然です。パワハラやセクハラ、モラハラなどが日常的に起きる環境では、社員が安心して働くことはできません。
新入社員は立場が弱く声を上げにくいため、耐えきれず辞めるケースも珍しくないです。
さらに、ハラスメントを放置する会社は法令順守や人材育成への姿勢も甘く、安心して長期的に働ける環境とは言えません。
就活中に完全に見抜くのは難しいものの、企業の口コミや採用広報での取り組みを確認すればある程度判断できます。相談窓口の設置や防止研修を行っているかどうかは重要なチェックポイントです。
健全な会社では社員が互いを尊重し合い、安心して能力を発揮できるため、結果として定着率が高くなります。こうした観点を持つことが、自分に合った職場を見つける近道になるでしょう。
離職率が低い企業の特徴

離職率が低い企業には共通の特徴があります。学生の多くは「入社してすぐに辞めてしまわないか」と不安を抱きますが、実際には環境や制度が整っている会社では長く安心して働けるでしょう。
ここでは就活生が企業研究で注目すべき7つのポイントを整理しました。
- 自己成長の機会を提供する企業
- 福利厚生が充実している企業
- ビジョンを社員に共有する企業
- 柔軟な働き方ができる企業
- 定期的な面談を実施する企業
- 有給取得を推奨する企業
- 女性のキャリアを支援する企業
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
① 自己成長の機会を提供する企業
成長の機会を用意している会社は、社員が長く働きやすい環境を築いています。
人は自分のスキルが伸びていると感じられると自然に仕事へのモチベーションが高まり、将来のキャリアにも自信を持てるようになるからです。
研修制度や資格取得の補助があれば、自分の能力を広げながら実務に活かすことができるでしょう。また、上司や先輩から学べるOJTが整っているかどうかも重要な視点になります。
成長の道筋が明確に描けないと「このままでよいのか」と不安を抱き、転職や離職に至るケースも珍しくありません。
就活の際は、制度の有無だけでなく「どのくらい利用されているのか」「成長を実感している社員がいるか」を確認することが大切です。
こうした仕組みが整った会社は、結果的に社員の定着率を高める力を持っていると言えます。
② 福利厚生が充実している企業
福利厚生は「働きやすさ」を大きく左右する要素です。住宅手当や交通費補助、社員食堂の利用サポートなどがあると、生活費の負担が軽くなり心に余裕を持って働けます。
さらに健康診断や人間ドックの補助、カウンセリング制度などがあると、心身の健康が保たれやすくなりますよね。
福利厚生がしっかり整った会社では、日々の小さな不安や不満が蓄積しにくいため、結果として離職率が下がるのです。一方で「制度はあるが利用されていない」場合もあり得ます。
就活生は会社説明会で直接質問したり、OB訪問や口コミを通じて実際の利用状況を確かめると安心です。
③ ビジョンを社員に共有する企業
企業のビジョンが明確で、社員にしっかり共有されているかどうかは離職率に大きな影響を与えます。社員が自分の業務の意味や会社の目指す方向性を理解できれば、日々の仕事に目的意識を持てますよね。
逆に「何のために働いているのか」が見えにくい職場では、業務が単なる作業に感じられやすく、モチベーションの低下や退職の原因になりかねません。
就活の場では、会社がどのように将来像を語り、それをどう社員と共有しているのかに注目してください。
例えば定期的な全社ミーティングや社内報などを通じて、経営陣の考えを伝える場があるかどうかは大切なポイントです。
ビジョンが浸透している企業では社員同士に一体感が生まれやすく、組織の結束力も強まります。こうした文化を持つ会社は結果的に社員が誇りを持って働き続けやすくなります。
④ 柔軟な働き方ができる企業
柔軟な働き方を認めている会社は、社員のライフスタイルに寄り添っているといえます。
テレワークやフレックスタイム制度を導入している企業では、通勤負担を減らしたり、家族や趣味との時間を大切にしながら働けるため、長期的に働きやすい環境が整います。
特に若い世代はワークライフバランスを重視する傾向が強く、制度の有無は会社選びに直結する大きな要因です。ただし導入していても「形だけ」で利用しづらいケースもあります。
そのため実際の利用状況を確かめることが大切です。例えば社員インタビューや口コミで「どのくらい使われているか」を確認すると実態が見えやすいでしょう。
働き方に柔軟性を持たせる会社は、社員の多様な事情を尊重しているため、結果的に離職率を低く保つことにつながっている傾向にあります。
⑤ 定期的な面談を実施する企業
面談を定期的に行う会社は、社員が抱える悩みや不安を早めに解消しています。小さな問題でも相談する場がなければ、次第に不満が大きくなり退職につながる危険があるからです。
上司と定期的に話せる機会があれば、課題を共有し一緒に解決策を探せるでしょう。
また、キャリアの方向性について相談できる場にもなるため、社員は「自分を大切にしてもらえている」と感じやすくなります。
さらに、面談が制度として定着している会社は社員の声を経営に反映しやすい傾向があります。就活生は企業説明会や面接で「面談の頻度」「キャリア相談の仕組み」について質問してみるとよいでしょう。
こうした仕組みを重視する企業は、社員との信頼関係を築きやすく、結果的に定着率の高さにつながっています。
⑥ 有給取得を推奨する企業
有給休暇を積極的に取れる企業は、社員の心身の健康を大切にしています。休暇をきちんと取れる環境があれば、リフレッシュでき仕事の効率や集中力も上がるでしょう。
一方で「制度はあるが実際には取得しにくい」職場では、不満や疲労が蓄積しやすく、離職の原因になりかねません。就活時には「有給取得率」や「実際の雰囲気」を調べると実態を把握できます。
例えば、取得率が高くても「上司が快く送り出すかどうか」が重要です。社員が安心して休みを取れる職場は、ワークライフバランスを重視する文化が根付いているといえるでしょう。
結果として定着率も上がり、働く人にとって長く安心できる環境になります。
⑦ 女性のキャリアを支援する企業
女性のキャリア支援が整った企業は、性別に関係なく誰もが安心して働けます。
産休や育休制度が充実しており、復帰後の時短勤務や柔軟な働き方が用意されていれば、ライフイベントを迎えてもキャリアを継続できるでしょう。
こうした環境は「働きながら将来を描ける」という安心感につながり、結果的に離職率を下げます。ただし制度があっても実際に使われていなければ意味がありません。
OB訪問や口コミを通じて「どのくらい利用されているか」を調べてください。また、女性管理職の割合やキャリアパスの事例も確認すると、より実態がつかめます。
キャリア支援に積極的な会社は多様性を尊重し、全ての社員にとって働きやすい環境を整えているのです。
離職率が高い業界

就活生にとって「離職率が高い業界」は、入社後のキャリアを左右する大切な判断材料です。数字だけで見るのではなく、その背景や理由を理解することが欠かせません。
ここでは、特に離職率が高いとされる業界の特徴を解説します。
- 宿泊業・飲食サービス業
- 教育・学習支援業
- 生活関連サービス業
- 建設業
- 小売業
① 宿泊業・飲食サービス業
宿泊業や飲食サービス業は、学生から人気がある一方で、離職率が高い業界としてよく名前が挙がります。
接客を中心とした仕事はお客様に喜ばれるやりがいがありますが、勤務時間が不規則になりやすく、夜遅くまで働くことや休日出勤が続くケースも少なくありません。
観光シーズンや繁忙期には残業が増え、体力面や精神面に大きな負担がかかることが離職の要因になっています。
しかし、この業界すべてが同じ環境というわけではなく、働き方改革を進める企業では週休2日制の導入や残業時間の削減に力を入れています。
加えて、外資系ホテルや大手チェーンでは人材育成や研修制度が整っており、キャリア形成につながる学びを得やすい点も魅力です。
離職率の高さを理由に避けるのではなく、企業ごとの取り組みや制度を丁寧に調べ、自分に合った環境を見つけることが大切でしょう。こうした視点を持つことで、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
② 教育・学習支援業
教育・学習支援業は、人の成長を支えるやりがいが大きい業界ですが、離職率が高いという課題を抱えています。
教師や塾講師は、生徒や保護者との関わりが密接で、理想と現実のギャップに直面しやすいのが特徴です。
授業準備や保護者対応に追われ、勤務時間が長くなりやすいため、精神的な負担や体調不良につながることもあります。特に若手のうちは指導経験が少なく、悩みを抱え込みやすいです。
一方で、この業界の多くは「教育を通じて社会に貢献したい」と志望する人が多いため、やりがいが大きな支えになります。
最近では研修やOJT制度を充実させ、フォロー体制を整えて離職率を下げようとする企業も見られるようになりました。
さらに、オンライン教育の拡大によって働き方の幅が広がり、自宅から授業を行えるなど柔軟な働き方も可能になりつつあります。
就活生は離職率という表面的な数字にとらわれず、どんなサポートやキャリアパスを提供しているかを確認すると安心できるでしょう。
③ 生活関連サービス業
生活関連サービス業には、美容院やエステ、冠婚葬祭といった、人々の生活に深く関わる仕事が含まれます。
離職率が高い要因は、顧客の要望に応える接客が中心で、感情労働と呼ばれる精神的な負担が大きいことです。土日や祝日が繁忙期にあたり、友人や家族と過ごす時間が取りにくいのも悩みの一つです。
また、結果が数字や評価としてダイレクトに反映されるため、プレッシャーを感じやすい点もあります。とはいえ、専門技術を高めることで顧客から信頼を得られ、スキルは転職や独立にも活かせます。
美容師やブライダルプランナーなどは資格や経験が強みとなり、自分の手でキャリアを切り開ける魅力があります。近年ではワークライフバランスに配慮したシフト制や福利厚生を整える企業も増えてきました。
就活生は「離職率が高いから大変」という見方だけでなく、得られるスキルやキャリアの広がりにも注目することで、将来を見据えた判断ができますよ。
④ 建設業
建設業はインフラや街づくりを担う重要な業界ですが、離職率が高い点も特徴です。現場仕事では体力的な負担が大きく、夏の猛暑や冬の寒さの中で作業をする必要があります。
さらに、安全管理が厳しく、納期に追われる状況も多いため、勤務時間が長くなりやすい傾向があります。このような労働環境が、早期離職につながる理由のひとつです。
ただし、建設業は経験や技術が評価されやすく、一度身につけたスキルは長期的に活かせる財産となります。
近年ではICTやドローンを活用した施工管理、BIM/CIMといったデジタル技術の導入によって、従来よりも効率的で安全な現場が増えています。
これにより労働環境が改善され、働きやすさを重視する企業も目立つようになりました。
就活生は「大変そう」というイメージだけで判断するのではなく、どんな技術や経験を積めるのか、将来性のある環境なのかを見極めることが重要です。
⑤ 小売業
小売業は消費者と直接関わる仕事であり、接客を通じて成長できる一方で、離職率が高い業界のひとつです。
特に年末年始やセール期間には繁忙を極め、長時間勤務や休日出勤が増えるため、体力的な消耗が大きいです。
さらに、顧客対応によるクレーム処理など精神的な負担もあるため、若手社員の早期退職につながる傾向があります。
しかし、小売業で得られるスキルは汎用性が高く、コミュニケーション能力や販売力は異業種でも通用するものです。
近年では福利厚生の充実や残業時間の削減、ECと店舗を組み合わせた新しいビジネスモデルを導入する企業も増えています。
離職率の高さだけにとらわれず、得られる経験やキャリアパスを考慮しながら業界研究を進めることが、就活生にとって後悔のない選択につながりますよ。
離職率が低い業界

就職活動を進めるとき、働きやすさや将来性を考えるなら「離職率が低い業界」を知ることはとても重要です。
離職率が低いということは、職場環境や待遇への満足度が高く、安心してキャリアを築ける可能性があるといえます。ここでは代表的に離職率が低い業界を紹介します。
- 金融業・保険業
- 複合サービス事業(郵便局・協同組合)
- 情報通信業
- 電気・ガス・水道業
- 製造業
① 金融業・保険業
金融業や保険業は、他業界と比較して離職率が低い傾向にあります。理由の一つは、安定した収益構造と強固な経営基盤です。
特に大手銀行や保険会社は福利厚生が充実しており、健康管理制度や住宅補助、研修制度などを通じて社員を長期的に支える体制を整えています。
業務は数字管理や顧客対応など責任が重く、プレッシャーを感じやすい場面も少なくありません。しかし、それを補うだけの給与水準や明確な評価制度があるため、やりがいを感じやすいのが特徴です。
さらに、専門資格の取得支援やキャリアアップの道筋もはっきりしているため、自分の成長を実感できるでしょう。就活生にとっては安定した雇用とスキル獲得の両立を実現できる魅力的な業界ですよ。
② 複合サービス事業(郵便局・協同組合)
郵便局や協同組合は、地域に密着したサービスを提供することが多く、生活に欠かせない役割を担っています。こうした社会的使命感が、働く人のモチベーションを支え、離職率の低さにもつながっています。
郵便局では郵便や金融、保険など幅広い業務を扱うため、仕事の種類が多く、経験を積みやすい点も特徴です。
協同組合では組合員との信頼関係をベースに運営されるため、人間関係が比較的安定しており、安心して働きやすい環境だといえるでしょう。
大企業ほど高い給与は望めない場合もありますが、その分ワークライフバランスを重視した勤務体制が整っていることが多く、長く働き続けたい人に向いています。
地域で腰を据えて暮らしながら、安定したキャリアを築きたい学生には適した選択肢です。
③ 情報通信業
情報通信業は、デジタル化やインターネットの発展に支えられ、安定した成長を続けています。
その中でも大手通信会社やインフラ事業者は、契約ベースで安定収益を確保しているため、雇用も比較的安定しており、離職率も低めです。
社員に対しては、社内研修や資格支援制度が整備され、専門知識を深めながらキャリアを築ける環境が整っています。
もちろんIT業界全体で見ると、開発業務やプロジェクト進行で労働時間が長引くこともありますが、通信インフラを担う企業は業務の安定性と社会的意義の高さから社員の定着率が高いのです。
また、テレワーク制度の導入など柔軟な働き方を取り入れている企業も多く、自分のライフスタイルに合わせて働ける点も魅力といえるでしょう。
技術力を磨きながら安心して働きたい学生にはうってつけの業界です。
④ 電気・ガス・水道業
電気・ガス・水道業は、生活に不可欠なライフラインを扱うため、景気に左右されにくく離職率が低い業界の代表です。
公共性が高い事業であることから雇用の安定性が際立ち、安心して長期的に働ける環境が整っています。給与水準は比較的高く、福利厚生も手厚いことが多いため、経済的な安定を得やすいのが特徴です。
現場業務では体力や夜間対応が求められる場合もありますが、リスクを補うための安全対策や手当制度が整っていることが多く、安心材料となっています。
さらに、インフラを支える使命感は大きなやりがいにつながり、地域社会への貢献を実感できるでしょう。
今後もエネルギーや水資源の安定供給は欠かせないため、長期的な需要が見込まれ、就活生にとって安定性の高い選択肢となります。
⑤ 製造業
製造業は自動車、化学、精密機器など幅広い分野があり、特に大手メーカーは離職率が低いことで知られています。
技術力を基盤に長期的な事業展開を行う企業が多く、社員は専門スキルを習得しながら安定して働けることが大きな特徴です。
大手メーカーは給与や福利厚生が手厚く、研修制度も整っており、キャリアアップを図りやすい点が魅力です。国際競争力を持つ企業ではグローバルに活躍できる可能性もあり、挑戦の場が広がっています。
一方で、中小規模の製造業は労働環境や待遇にばらつきがあるため、就活時には企業の規模や業績を確認することが欠かせません。
安定性と成長性を兼ね備えた大手製造業は、専門技術を磨きながら安心してキャリアを築きたい学生にとって非常に有力な選択肢です。
離職率を改善するための方法と企業の取り組み

離職率は企業の健全性を測る重要な指標であり、就活生にとっても将来の働きやすさを考えるうえで欠かせません。ここでは、企業が実際に行っている改善策を紹介します。
取り組みを理解することで、企業研究の際に注目すべき点が明確になり、不安の解消につながるでしょう。
- 社内アンケートやヒアリングを実施する
- 労働条件や給与制度を見直す
- 多様な働き方に対応できる環境を整備する
- 人事評価制度を透明化する
- 外部のサポートを活用する
- コミュニケーションを活性化し面談を実施する
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
① 社内アンケートやヒアリングを実施する
従業員の本音を把握することは、離職率を下げるための第一歩です。定期的なアンケートやヒアリングを行えば、働きにくさや改善点を発見できます。
この方法が効果的なのは、課題を可視化できるだけでなく、従業員が「声を聞いてもらえている」と実感できるからです。
さらにアンケート結果をもとに改善策を実行すれば、企業に対する信頼感が高まり、安心して働ける環境が築かれますよね。
また、ヒアリングを通じて一人ひとりの背景を理解できるため、個別の悩みにもきめ細やかに対応できます。就活生は説明会やOB訪問で「社員の声をどう反映しているか」を確認みましょう。
社員の声を放置する会社か、行動に移す会社かで、働きやすさには大きな差が生まれますよ。
② 労働条件や給与制度を見直す
離職の大きな原因の1つが待遇面です。労働時間が長すぎる、給与が仕事内容に合わないといった状況では、モチベーションが下がってしまいます。
そのため企業は残業削減や給与テーブルの適正化に力を入れています。こうした取り組みにより、社員が安心して長く働ける環境が整い、キャリア形成の基盤が固まるからです。
加えて福利厚生の充実や休日制度の見直しも、離職率低下につながります。休暇を取得しやすい環境があれば、心身ともに健康を保ちながら働けますよね。
就活生は求人票や企業HPにある数値だけでなく、実際に社員がどのように制度を利用しているかを意識して調べてください。
平均残業時間や昇給・賞与の実績、さらに育休や時短勤務の利用率まで確認できれば、定着率の高い職場を見極めやすくなります。
③ 多様な働き方に対応できる環境を整備する
現代では、リモートワークやフレックス制など柔軟な働き方が求められています。
こうした制度を導入している企業は、社員のライフスタイルに合った働き方を提供できるため、結果として離職率の低下につながっています。
さらに、子育てや介護との両立を支援する制度があれば、ライフイベントの変化にも対応できますよね。
就活生が見るべきは制度の存在だけではありません。実際にどの程度活用されているか、社員が不利益を被らず利用できているかを調べることが大切です。
説明会で「制度の利用率」や「実際の運用事例」を聞いてみてください。制度が形だけでなく実際に機能している企業は、長期的に働きやすい職場である可能性が高いでしょう。
④ 人事評価制度を透明化する
不透明な評価制度は社員の不満を生みやすく、離職につながります。
例えば、上司と社員が目標を共有し、成果だけでなくプロセスも評価に加える仕組みが導入されています。こうすることで「努力が無駄になる」という不公平感を防ぎ、社員のやる気を維持できますよね。
さらに評価制度が明確であれば、社員がキャリアをどう積み重ねればよいかを理解でき、将来像を描きやすくなります。就活生は、企業がどのような評価制度を採用しているのかに注目しましょう。
面接で「評価や昇進はどのように決まりますか」と聞くことで、実際の透明性を見極められます。評価基準がオープンになっている企業は、安心して挑戦できる環境を提供してくれるはずです。
⑤ 外部のサポートを活用する
企業が離職率を改善する際に有効なのが、外部の専門家や機関を取り入れることです。産業医やカウンセラーによるメンタルヘルス支援、研修会社によるスキルアップ研修などが代表的な例です。
社内だけで解決できない問題を外部の専門知識で補うことで、社員の不安や不満を解消しやすくなります。
特にメンタル面のケアは、職場で相談しにくい内容であっても外部のプロなら安心して打ち明けられるでしょう。
さらに研修の機会を通じて成長できる環境は、社員に「自分を大切にしてもらえている」という実感を与え、会社への定着意識を高めます。就活生は企業が外部の支援を導入しているかを必ず確認してください。
説明会や企業HPに記載されている場合は、その活用度合いにも注目すると良いでしょう。
⑥ コミュニケーションを活性化し面談を実施する
職場で孤立感を覚えることは、離職の大きな要因です。そこで企業は定期的な1on1面談や交流の場を設け、上司と部下のコミュニケーションを深めています。
こうした取り組みによって、悩みを早い段階で共有でき、問題を抱え込まずに解決できる環境が整います。
また、同僚との交流を通じて信頼関係が強まれば、職場への帰属意識が高まり、安心感も生まれるでしょう。さらに、気軽に意見を言える社風やオープンな相談窓口があれば、社員は働きやすさを実感できます。
就活生は、企業の面談制度や社内イベントの頻度を確認してください。制度が形式だけで終わらず実際に機能している企業は、社員が孤立せずに長く働ける環境を整えているといえるでしょう。
職場の人間関係やコミュニケーションの活性度合いは、離職率に直結する重要な要素です。
離職率を調べる際の注意点

就活生が企業研究を進めるとき、「離職率」は働きやすさを測る大切な指標のひとつです。ただし、数字の裏側には見えにくい事情があり、数値だけで判断すると誤解を招くことも少なくありません。
ここでは、離職率を理解するうえで気をつけたいポイントを解説します。
- 社員数が少ない場合の参考性を考慮する
- 企業が数字を操作している可能性を意識する
- 単年度データに依存しないで判断する
- 業種ごとの離職率の違いを理解する
- 離職率だけに偏らず情報収集する
① 社員数が少ない場合の参考性を考慮する
少人数の企業では、数人の退職で離職率が大きく変動します。たとえば、従業員10人の会社で2人辞めれば20%になりますが、大規模な企業で同じ割合が出ることはめったにありません。
この数字だけを見て「働きにくい」と判断するのは早計でしょう。小規模な組織では、事業内容の変化や経営者の方針転換など、外的要因で人が動くことも多くあります。
さらに、ベンチャー企業では挑戦的な環境を求めて入社した人が短期間でキャリアチェンジするケースも少なくありません。そのため、規模やフェーズを無視して単純に比較するのは正確ではないのです。
就活生にとって重要なのは、企業が今どんな成長段階にあり、自分にどのような経験をもたらすのかを見極めることです。
離職率はあくまで参考の一部としてとらえ、社員数や経営状況とあわせて総合的に判断することが、納得できる企業選びにつながります。
② 企業が数字を操作している可能性を意識する
離職率は客観的な数字に見えますが、計算方法の設定次第で大きく変わる場合があります。
例えば、試用期間中の退職を含めない、契約社員を母数から外すなどの工夫によって、見かけ上の数字を下げることができてしまいます。
こうした数字の扱い方は外部から確認しにくいため、公式発表の数値だけに頼るのは危険でしょう。また、離職率の公開自体を行わない企業もあり、その場合は積極的に情報を隠している可能性も考えられます。
真実に近づくためには、口コミサイトでの現場の声やOB・OG訪問での体験談を照らし合わせることが大切です。
さらに、企業説明会で「人材の定着率」や「平均勤続年数」など関連データを質問することで、見えにくい部分を補うこともできます。
1つの数値をうのみにするのではなく、背景や文脈を意識して読み解くことが、安心してキャリア選択を進めるための土台になるでしょう。
③ 単年度データに依存しないで判断する
離職率を確認するとき、1年分のデータに頼るのは非常に危険です。
その年だけ経済の停滞や景気の過熱によって転職市場が活発になったり、制度変更や人事異動が多発したりすることで、例年に比べて数値が上下することはよくあります。
つまり、単年度の数字は偶然や一時的な要因に大きく左右されるため、企業の実態を映すとは限りません。
正しい見極めには3年から5年ほどの推移を確認し、離職率の動きに一貫した傾向があるかどうかを見てください。
もし毎年高い数字が続いているなら慢性的な問題がある可能性が高く、逆に一時的な増加であれば心配しすぎる必要はありません。
さらに、過去の動向とあわせて企業がどのような改善策を打ち出しているかを調べると、今後の働きやすさを予測する手がかりになります。
複数年を見て長期的に判断する姿勢が、ミスマッチを防ぐために欠かせないでしょう。
④ 業種ごとの離職率の違いを理解する
離職率は業界によって大きな差があり、同じ数字でも意味が変わります。たとえば、飲食業や小売業は人の入れ替わりが多く、30%を超えることも珍しくありません。
これは業務特性としてシフト制や体力的な負担が大きいこと、また学生や若手の短期就労が多いことが背景にあります。
一方で、電力や金融などの安定したインフラ業界は、10%以下で推移することも多く見られます。こうした傾向を知らずに単純比較すると、「高いから悪い」「低いから良い」と早合点してしまいがちです。
正しい理解のためには、業界ごとの平均値や特徴を把握し、そのうえで対象企業が平均より高いのか低いのかを判断してください。
また、同じ業界でも職種によって働き方は異なるため、部署や役割ごとの違いに目を向けることも大切です。業種の性質を前提に考えることで、より精度の高い企業分析ができるでしょう。
⑤ 離職率だけに偏らず情報収集する
離職率は働きやすさのひとつの指標にすぎません。実際の職場環境を理解するには、社風、福利厚生、教育制度、ワークライフバランスなど多面的な視点が欠かせません。
たとえば、離職率が高くても、挑戦的なプロジェクトに積極的に関われる環境であれば、短期間で大きく成長できるチャンスになります。
反対に、離職率が低い企業であっても、変化が少なく新しい経験を積みにくい環境であれば、自分のキャリア形成にとっては物足りなく感じるかもしれません。
重要なのは、数字の高低ではなく「自分に合った環境かどうか」を基準に考えることです。
そのためには、社員インタビューや説明会での雰囲気、実際に働いている人の声など、多方面からの情報を組み合わせて判断してください。
数値に偏らない情報収集こそが、後悔のない企業選びにつながるのです。
離職率を理解し企業選びや改善に活かそう!

離職率は、企業の働きやすさや将来性を判断する重要な指標です。
就職四季報や有価証券報告書、口コミサイトなど複数の方法で調べられ、日本全体の平均値や業界別の傾向と合わせて比較することで、より正確な理解が可能になります。
また、離職率が高い企業には労働環境や人間関係の課題が見られる一方、低い企業は福利厚生や働き方の柔軟性が充実している点が特徴です。
数字の背景を正しく読み取り、他の情報と組み合わせて判断することが、就活や転職活動において失敗を避けるカギとなります。
さらに企業側も、労働条件の見直しやコミュニケーションの改善などの取り組みを進めることで、離職率低下と組織の安定化につなげることができます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














