就活のWebテスト種類を網羅!目的・方式・見分け方・対策まで
「就活のWebテストって種類が多すぎて、正直どれがどんな内容なのか分からない…」
エントリーが本格化すると、SPIや玉手箱などさまざまなテストを受ける機会が一気に増えます。出題形式や受験方法も企業によって異なるため、対策の方向性を誤ると合格ラインに届かないことも少なくありません。
そこで本記事では、Webテストの目的や方式、見分け方、主要テストごとの特徴や対策ポイントまでを徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
WEBテストとは?

WEBテストとは、企業が就活生の基礎学力や適性を客観的に判断するために導入しているオンライン試験です。パソコンやスマートフォンを使い、自宅や会場から受験できる点が特徴でしょう。
効率的に多くの応募者を比較するために使われており、今や就職活動に欠かせない仕組みです。出題範囲は国語や数学といった基礎問題に加え、論理的思考力や性格特性を測る設問まで多岐にわたります。
そのため、単なる学力確認にとどまらず、企業が自社に合う人物かどうかを見極める重要な手段となっています。想像以上に選考への影響が大きく、結果によっては面接に進めないことも珍しくありません。
同じエントリーシートを提出しても、テストの点数で評価が分かれるケースは多いものです。つまり、WEBテストは形式的な通過点ではなく、就活における本格的な関門と理解する必要があります。
早めに準備を進めることが、合格への大きな一歩になるはずです。
企業がWEBテストを実施する目的

企業がWEBテストを導入する背景には、採用活動の効率化や人材のミスマッチ防止といった理由があります。
「なぜ受けなければならないのか」を理解することで、単なるハードルではなく選考の一環として前向きに取り組めるようになるでしょう。
ここでは、WEBテストの主な目的について整理し、分かりやすく紹介していきます。
- 応募者の絞り込み
- 自社適合人材の判定
- 面接・選考プロセス効率化
- 早期離職リスク低減
- 配属・配置最適化
①応募者の絞り込み
企業がWEBテストを導入する大きな理由の1つは、多数の応募者の中から効率的に候補者を選び出すことです。
書類選考だけでは学力や論理性を把握するのが難しく、すべての学生を面接に呼ぶのも現実的ではありません。そこで基礎学力や論理的思考力を数値化し、一定の基準に満たない応募者をふるいにかけています。
学生にとっては「なぜ落ちたのか分からない」という不安につながりやすいですが、過去問や模試形式の問題を繰り返し解いておけば、対策をした人とそうでない人の差が明確になります。
多くの学生が軽視しやすい領域だからこそ、準備を重ねることで他の候補者との差を広げられるでしょう。基礎力を整えることこそが、選考突破の最初の扉を開くカギなのです。
②自社適合人材の判定
企業は採用後に長期的に活躍してくれる人材を求めており、社風や仕事の進め方に合うかどうかを重要視しているため、WEBテストを価値観の一致度を確認する仕組みとしても利用しています。
たとえば協調性を重んじる企業ではチーム志向が評価され、挑戦を重視する社風であればリスクを恐れない姿勢が見られます。
就活生にとっては「性格をテストで判断されるのは不安」と感じるかもしれませんが、実際には自分に合った企業を知る機会でもあります。
合わない企業に入社すると大きなストレスや早期離職につながるため、むしろ素直に回答することが自分を守ることになるでしょう。
WEBテストの結果は、企業に評価されるだけでなく、自分のキャリアを考える手掛かりにもなるのです。
③面接・選考プロセス効率化
応募者数が年々増えている現状では、面接官が一人ひとりに十分な時間を割くのは困難です。
そのためWEBテストは「事前の整理フィルター」として機能し、企業は本当に会いたい学生に面接の時間を集中させます。結果として面接の質が高まり、学生も自分を深く伝えるチャンスを得やすくなるのです。
一方で、テストで落ちると「能力を見てもらえなかった」と感じることもあるでしょう。しかし、WEBテストを通過した時点で企業が関心を持っている証拠だと考えることができます。
ここを突破すれば面接での評価も高まりやすく、選考全体を有利に進められるのです。効率化は企業だけの利点ではなく、学生にとっても選考期間の短縮や不安の軽減といったメリットがあります。
④早期離職リスク低減
企業がWEBテストを重視する背景には、採用した人材の早期離職を防ぐ狙いがあります。採用活動には大きなコストがかかるため、入社してすぐに辞められてしまうことは大きな損失です。
そこでテストを通じてストレス耐性や価値観、組織との相性を多角的に測り、長く働けるかどうかを確認しています。
学生の中には「正直に答えると不利になるのでは」と不安に思う人もいますが、むしろ素直に答えた方が将来のためになります。なぜなら、自分に合わない企業を避けることができるからです。
たとえその企業に受からなくても、他の環境で活躍できる可能性が高まります。WEBテストは不合格を決める道具ではなく、「自分に合った職場を見つける指標」と捉えるのが賢明でしょう。
⑤配属・配置最適化
WEBテストは採用段階だけでなく、入社後の配属や配置決定にも活かされています。学生の多くは「配属は運次第」と考えがちですが、実際には客観的データを踏まえて判断されるケースが少なくありません。
たとえば、論理的思考力が高い学生は企画や分析系の職種に、対人スキルが優れている学生は営業や人事に、といったように適性を見極める基準となります。
これにより社員が得意分野を活かせる部署に配置され、結果的に組織全体の力が高まります。
そのため、「自分の強みがどう評価されるか」を意識してテストに臨むことで、希望に近いキャリアを歩める可能性が広がるでしょう。
WEBテストは選考通過のためだけでなく、入社後の働きやすさやキャリア形成にも影響を与える重要な要素なのです。
WEBテストの主な受検方法

就活におけるWEBテストは、企業が効率的に応募者を評価するための大切な手段です。受検方法にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や注意点があります。
ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
- テストセンター
- Webテスティング(自宅受検)
- インハウスCBT(企業内PC)
- ペーパーテスティング
①テストセンター
テストセンター方式は、専用会場に設置されたパソコンを利用して受検する方法です。多くの大手企業で導入されており、会場の環境は統一されているため公平性が高いのが特徴です。
- 会場受検のため時間と場所の制約がある
- 企業ごとに再受検の必要がある場合もある
- 周囲の環境が一定で集中しやすい
テストセンター受検は公平性が保たれる一方で、移動や予約の手間が負担になることもあります。特に就活が本格化する時期は予約が埋まりやすく、思うように日程調整できない場合もあるでしょう。
ただし、会場は静かな環境と安定した通信設備が整っているため、集中して受けやすい利点もあります。
さらに、企業によっては同じスコアを複数社で利用できることもあるため、効率的に活用できる場合もあります。
つまり、テストセンターは「安心して力を発揮できる場」として受検者にメリットがある方式といえるでしょう。
②Webテスティング(自宅受検)
自宅で受けられるWebテスティング方式は、受検者にとって利便性が高い一方で、注意点も存在します。
- インターネット環境の安定が必須
- カンニング対策として制約が多い場合もある
- 時間制限や監視システムに注意が必要
最大の利点は移動せずに好きな場所で受けられることです。特に地方学生にとっては時間や費用の節約につながるでしょう。
ただし、通信が不安定だと途中で接続が切れるリスクがあり、再受検できない場合もあります。さらに、不正防止のためカメラで監視されたり、画面操作が制限されたりすることも少なくありません。
安心して受けるには、事前にネット環境を確認し、静かな場所を整えて試験に臨む必要があります。準備次第で大きな不安を解消できるでしょう。
③インハウスCBT(企業内PC)
企業内のパソコンを利用して受けるインハウスCBTは、独自の環境で実施されるケースが多い方式です。
- 企業内会場で直接受検する
- 採用プロセスの一環として行われる
- 他方式に比べて導入企業は少ない
この方式は企業が自社でテストを行うため、採用活動との結びつきが強い点が特徴です。
学生にとっては実際の企業の雰囲気を感じられる機会になりますが、他の受検者と同じ空間で行うため緊張感が高まりやすいでしょう。
さらに、面接と同日に実施される場合もあり、柔軟な対応が必要になることもあります。導入している企業は限られていますが、その分独自の評価基準として活用されるのです。
十分な準備をして臨めば印象も良くなるでしょう。
④ペーパーテスティング
紙を使った試験方式は近年減少していますが、一部の企業では今も利用されています。ペーパーテスティングは昔ながらの方法で、パソコン操作に不安を感じる学生には安心感があります。
ただし、採点に時間がかかるため結果が出るまでに遅れが生じ、効率性ではデジタル方式に劣ります。それでも、対面実施により受検中の姿勢や集中力を観察できるというメリットがあります。
特に中小企業や独自の採用文化を持つ組織では依然として行われることがあるため注意が必要です。マークシートや記述問題に対応する練習をしておけば、不意の場面でも落ち着いて取り組めるでしょう。
WEBテストの見分け方

就活生が最も不安に感じやすいのは「受けるテストがどの種類なのか事前にわからない」という点です。テストの形式を事前に見分けられれば、効率的に対策でき、合格の可能性も高まるでしょう。
ここでは、実際に確認できる「見分け方のポイント」を紹介します。
- URLからの判別ポイント
- 出題形式からの判別ポイント
- 科目構成からの判別ポイント
- 制限時間・解答方式の判別ポイント
- 案内文・受検要項からの判別ポイント
①URLからの判別ポイント
案内メールやログインページに記載されているURLは、テストの種類を判断する手がかりになります。
多くのテストは提供会社ごとに固有のドメインを使用しており、「〇〇test.jp」や「cub〇〇.com」などの文字列から推測できることが多いです。
代表的なSPIや玉手箱はURLの特徴が知られており、検索すると過去受験者の情報を見つけやすいでしょう。事前に調べておけば教材を誤って選ぶリスクを避けられます。
確認を怠ると間違った学習に時間を費やし、本番での得点が伸びない原因になりかねません。案内が届いた段階でURLを確認し、出題形式を推測する習慣をつけてください。
| テスト種類 | 代表的なURL / ドメイン例 |
|---|---|
| SPI | arorua.net / www3.arorua.net |
| 玉手箱 | web1.e-exams.jp / web2.e-exams.jp / web3.e-exams.jp / nsvs / tsvs |
| GAB / Web-GAB / C-GAB | (玉手箱と同系) e-exams.jp系 / nsvs / tsvs |
| CAB / Web-CAB | (同上) e-exams.jp系 / nsvs / tsvs |
| TG-WEB | e-assessment.jp / assessment.c-personal.com / assessment.e-gitest.com / tg-web.net |
| CUBIC | web-cubic.jp / assessment.cservice.jp |
| SCOA | apps.ibt-cloud.com |
| TAL | tal-sa.jp/talsqi/ |
※年度や導入形態によってURLは変わる場合があります。必ず案内メールのURLと運営会社名を確認してください。
②出題形式からの判別ポイント
問題の形式を見るだけでも、どのテストかを推測できます。長文読解や表の空欄補充が多い場合は玉手箱型である可能性が高く、短文の言語や非言語問題が続くならSPI型と判断できるでしょう。
さらに、計数問題が図やグラフの読み取り中心か、数列や推論中心かでも種類を見分けられます。解き始めてから気づくこともありますが、制限時間が進んでいる状況では対応が難しくなります。
模試や過去問を幅広く確認しておけば、初見の問題でも形式から素早く判断できる力を養えるはずです。形式を見抜けるかどうかが、解答の切り替えの速さや選考での差に直結します。
③科目構成からの判別ポイント
出題科目の組み合わせも、テストを見分ける有力な材料です。言語・非言語に加えて性格検査があればSPI型の可能性が高く、英語や図表問題が含まれていれば玉手箱やTG-WEBである可能性が大きいでしょう。
見落とされがちなのは英語の有無です。外資系や大手企業では英語が課されることが多く、準備不足が露呈すると通過率が下がってしまいます。
案内に記載された科目を必ず確認し、苦手分野を重点的に補強してください。科目構成を理解するだけで、効率的な学習計画につながります。
④制限時間・解答方式の判別ポイント
制限時間や解答方式にも違いがあります。SPIは1問ごとの制限時間が短く、スピードが求められるテストです。対して玉手箱は科目ごとに時間が設定されており、全体の配分が重要になります。
さらに、SPIは選択肢形式が多いのに対し、TG-WEBは記述式を含む場合もあり、本番で初めて方式に気づくと戸惑い、時間を無駄にするかもしれません。
案内や模擬問題で事前に確認し、操作に慣れておくと安心できるでしょう。制限時間や方式を理解することは、実力を発揮するための土台になります。
⑤案内文・受検要項からの判別ポイント
企業から届く案内や要項の記載も見逃せません。「所要時間◯分」「自宅受験可」「カメラ監視あり」といった文言は、使用されるシステムの特徴を表しています。
特に監視システムが導入されている場合は、受検環境が限定されることが多いため注意が必要です。細かい記載を流し読みすると、大事なヒントを見逃す可能性があります。
事前に熟読しておけば、準備や環境設定が整い、当日のトラブルを避けられるでしょう。要項をしっかり確認する姿勢が、他の受験者との差を生む大切な要素になります。
主要なWEBテストの種類一覧
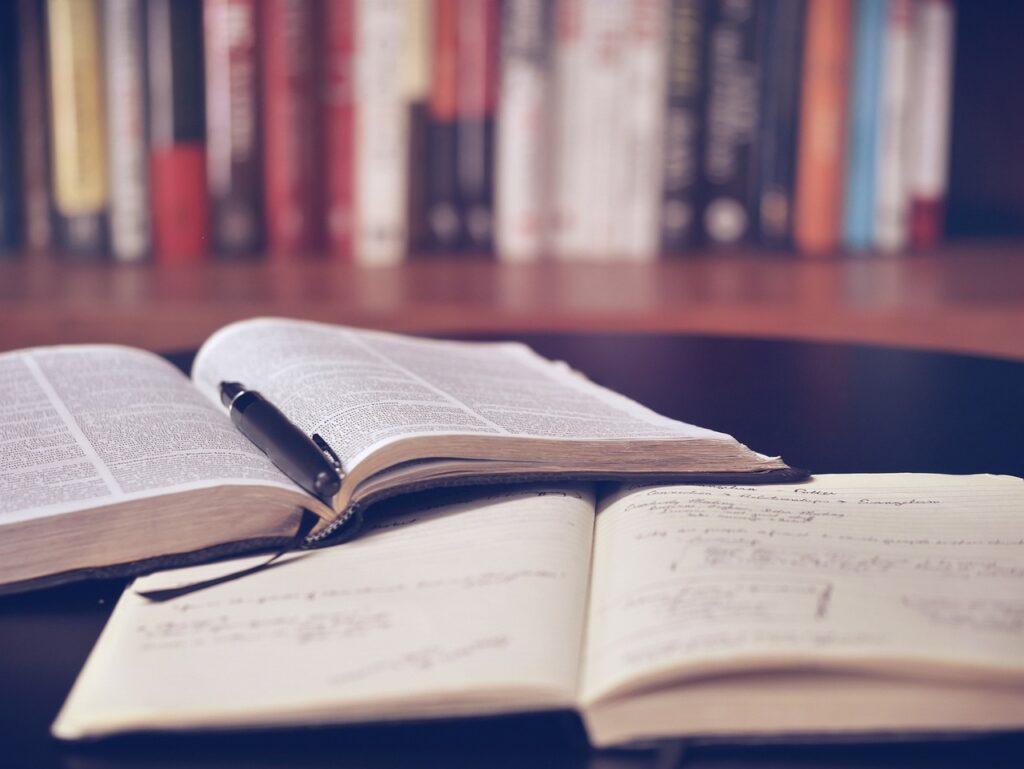
就職活動における企業選考では、多くの学生が最初に直面するのがWEBテストです。WEBテストには種類や特徴がさまざまあり、事前に理解していないと企業ごとの選考にうまく対応できません。
ここでは、代表的なWEBテストの種類を整理し、それぞれの特徴や出題傾向を解説します。自分に合った準備を進める第一歩にしてください。
- SPI
- 玉手箱
- TG-WEB
- GAB
- CAB
- ENG(SPI英語)
- CUBIC
- SCOA
- TAP
- IMAGES(イメジス)
- TAL
- 内田クレペリン検査
- デザイン思考テスト
①SPI
SPIは最も広く利用されているWEBテストで、大手企業を中心に多くの選考で導入されています。出題は「言語」「非言語」「性格」の3領域に分かれ、知識量よりも基礎的な読解力や計算力を重視するのが特徴です。
特に非言語分野では典型的なパターン問題が多く、素早い判断が必要になります。全体として制限時間が短く、解答スピードと正確さの両立が求められるでしょう。
②玉手箱
玉手箱は金融や商社をはじめとする業界で多く導入されており、出題領域は「言語」「計数」「英語」が中心で、特に表やグラフを読み取る形式が目立ちます。
計数問題は複雑な資料を扱うため、正確さとスピードの両方が求められるのです。会場受験と自宅受験の両方があり、形式の違いによって出題傾向が変化することもあります。
総じて「情報処理力」を測るテストといえるでしょう。
③TG-WEB
TG-WEBは難易度が高いとされるWEBテストで、ベンチャーから大手企業まで幅広く導入されており、出題内容は一般常識や思考力を問う独自の形式が多いです。特に数的処理や図形問題に特徴があります。
問題数が多い一方で制限時間が短いため、全問解答は現実的ではありません。取捨選択を意識し、柔軟な思考力や問題解決力が試されます。
④GAB
GABは外資系コンサルティングや金融業界で広く利用されるテストです。特徴は論理的思考力や英語力を重視する点にあり、長文読解や計数処理問題の難易度が高い傾向にあります。
特に英語問題では速読力と要点把握力が必要で、短時間で精度の高い処理を求められます。全体的に「量と精度の両立」を評価する試験といえるでしょう。
⑤CAB
CABはIT業界を中心に導入されており、プログラミング的な思考力や論理力を評価する形式が特徴です。図形問題や命令処理を扱う問題が多く、単純な数学知識だけでは対応が難しいものとなっています。
効率的に処理手順を見抜く力が求められ、論理的かつ実務的な思考を測るテストです。
⑥ENG(SPI英語)
ENGはSPIの英語版で、外資系企業やグローバル企業の選考でよく用いられます。出題は「文法」「語彙」「読解」と幅広く、TOEICやTOEFLに近い形式です。
ただし制限時間が短いため、英語力だけでなく時間内に処理する力が問われます。語学力とスピードを同時に測るテストといえるでしょう。
⑦CUBIC
CUBICは知識や学力ではなく、性格や行動特性を把握するための適性検査です。回答の一貫性や自然さが評価の鍵となり、受験者の性格や企業文化との適合性を確認する目的で利用されます。
採点基準は単純な正誤ではなく、受験者の人となりを明らかにすることを重視しています。
⑧SCOA
SCOAは「国語」「数学」「理科」「社会」「英語」といった幅広い基礎学力を測定するテストです。出題内容は中学〜高校レベルに相当し、特に理科や社会では知識差が出やすい傾向があります。
幅広い分野を網羅するため、知識のバランスや基礎学力を確認する目的で利用されます。
⑨TAP
TAPは限られた企業で採用されているWEBテストで、知識問題ではなく思考力や判断力を測る形式が特徴です。
出題は仕事上のケーススタディに近い内容が多く、状況をどう分析するかが評価の中心となります。実務的な視点を重視する試験といえるでしょう。
⑩IMAGES(イメジス)
IMAGESは空間把握力や図形認識力を測る珍しいタイプのテストです。展開図や立体を扱う問題が中心で、直感的な思考や空間的イメージ力が評価されます。
数式や文章ではなく、ビジュアル的な認識能力を問う点が特徴です。
⑪TAL
TALは論理的思考力や推論力を問うテストで、難解な文章や数列のパターンを題材とする出題が多いのが特徴です。
解答選択肢が一見するとどれも正しそうに見えるため、慎重に論理を追う力が求められます。短い制限時間の中で、柔軟かつ効率的に推論する力を試されます。
⑫内田クレペリン検査
内田クレペリン検査は単純な計算を長時間繰り返すことで、集中力や持続力、取り組み姿勢を測る心理検査です。
計算能力そのものではなく、作業のリズムや変化、安定性といった側面が評価されます。心理学的要素が強く、性格診断的な位置づけで利用されています。
⑬デザイン思考テスト
デザイン思考テストは比較的新しい形式のテストで、課題解決に向けた発想力や論理的な説明力を測ります。
正解が1つに定まらないケースが多く、柔軟な思考の広がりと、それを筋道立てて表現する力が重視されるのです。特に企画職や新規事業を志望する学生を対象に導入される傾向が見られるでしょう。
テスト別の対策ポイントまとめ【主要5テスト】
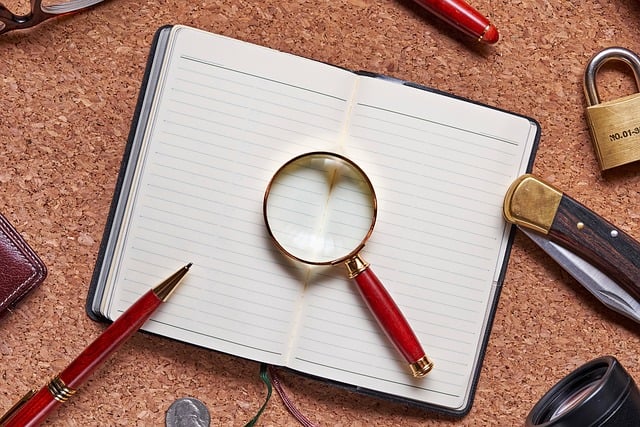
就活における適性検査は、多くの企業が導入している重要なステップです。しかし同じ「Webテスト」といっても形式や特徴は大きく異なり、準備方法を誤ると実力を出せないことがあります。
ここでは、代表的な5つのテストについて、それぞれの対策ポイントを整理します。
- SPIの対策ポイント
- 玉手箱の対策ポイント
- TG-WEBの対策ポイント
- GABの対策ポイント
- CABの対策ポイント
①SPIの対策ポイント
SPIは最も多くの企業で採用されている適性検査で、言語・非言語・性格の3領域から成り立っています。特に非言語問題は計算スピードが問われるため、公式の理解と繰り返し演習が欠かせません。
速さや比率の問題は公式暗記だけでは対応できないため、解き方を定着させる必要があります。また性格検査では回答の一貫性が重視されるため、良く見せようと操作すると矛盾が生まれやすいです。
事前に自己分析を深め、自分の価値観に沿った回答を意識すると安定した評価につながるでしょう。SPIでは基礎学力のトレーニングと自己理解の両方が合格の近道になります。
②玉手箱の対策ポイント
玉手箱は外資系や大手企業で多く導入され、言語・計数・英語の3分野に加えて性格検査を含む場合があります。特徴は制限時間が厳しく、情報処理の速さが合否を左右する点です。
長文読解は速読力が求められるため、普段から記事やレポートを素早く読み要点をつかむ練習が効果的でしょう。
計数問題では表やグラフから必要な数値を素早く抜き出す力が必要で、実践形式での練習が欠かせません。英語問題はビジネス文書が中心なので、TOEIC対策と並行して進めると効率的です。
玉手箱は「知識量よりも処理スピード」が重要なテストといえます。
③TG-WEBの対策ポイント
TG-WEBは難易度が高く、受験者の思考力を深く見る傾向があります。言語問題は抽象的な内容が多く、論理構造を把握して因果関係や前提条件を整理する習慣が大切です。
非言語問題は一見複雑でもパターンをつかめば効率的に解けるため、過去問演習を通じて解法の流れを身につけてください。時間制限は比較的緩やかですが、その分じっくり考える力が問われます。
焦らず丁寧に思考する姿勢が結果につながるでしょう。TG-WEBは公式暗記だけでは対応できない、「思考の深さ」を試すテストです。
④GABの対策ポイント
GABは外資系金融やコンサルティング業界でよく用いられるテストで、言語理解と計量処理が中心です。
計量処理は大量の数値を短時間で扱う必要があるため、数字に苦手意識を持つ学生には大きな壁となりやすいでしょう。
ただし無理に全問解こうとして精度を落とすより、得意分野を見極めて確実に得点する方が有効です。
特にGABは全体の正答率よりも処理スピードを重視する傾向があるため、制限時間を意識した演習が欠かせません。正確さとスピード、この2つを両立させることが合格の鍵となります。
⑤CABの対策ポイント
CABは主にIT企業で使われることが多く、暗算力や論理的思考力を問う独自形式のテストです。
暗算問題や命令処理問題など、他の適性検査では見られない形式が特徴であり、準備不足だと戸惑いやすいでしょう。対策としてはCAB専用の問題集を繰り返し解き、形式そのものに慣れることが第一歩です。
さらにIT業界志望者にとっては、CABの得点が論理思考力の証明となるため、しっかり準備しておく価値があります。特殊形式だからこそ、「慣れ」と「訓練」が合否を分けるテストです。
WEBテストを受検する際の注意点(自宅受検の環境・不正防止・禁止事項)
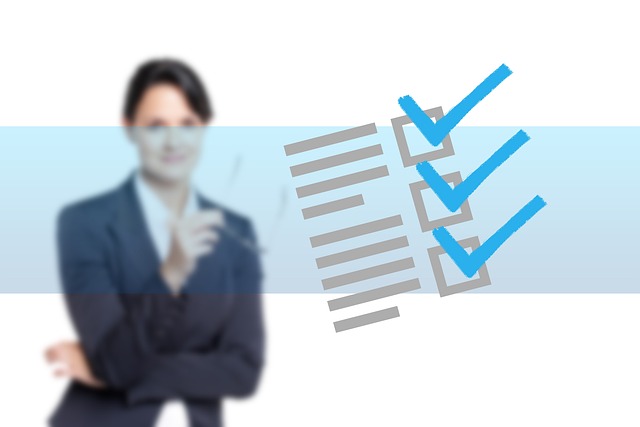
就活においてWEBテストは避けて通れないプロセスですが、意外と「受け方」そのものに不安を持つ学生は多いでしょう。
特に自宅での受検が一般的になった今、環境や禁止事項を理解していないと、実力を発揮できないどころか選考に不利になる場合もあります。
ここでは、受検前に必ず確認しておきたい注意点を解説します。
- 受検環境を整える
- 通信・機材トラブル対策を行う
- 時間配分を決める
- 締切・再受検ルールを遵守する
①受検環境を整える
WEBテストを受ける際にまず意識すべきなのは、集中できる環境をつくることです。理由は明確で、雑音や人の出入りがあると集中が途切れ、ミスにつながってしまいます。
静かなカフェや図書館を利用する学生もいますが、通信環境が安定せず途中で受検できなくなることも少なくありません。そのため最適な場所は自宅の個室や安定した回線のある空間です。
机の上を片付け、スマートフォンの通知を切るなど細部まで配慮してください。環境づくりを怠ると、外部要因で実力を出し切れないこともあるでしょう。
②通信・機材トラブル対策を行う
WEBテストでは通信や機材のトラブルが意外と起こりやすいものです。特にオンライン形式では回線切断やシステムエラーが生じると、そのまま再受検できないケースもあります。
こうした事態を避けるには、事前にネット速度を確認し、可能であれば有線LANを利用するのがおすすめです。パソコンのブラウザを最新版に更新し、不要なアプリを閉じておくのも有効でしょう。
スマートフォンでも受検できますが、画面が小さく操作ミスの原因となるためPCを優先してください。準備を整えておけば、不測のトラブルによる不利を防げます。
③時間配分を決める
WEBテストには制限時間が設定されていることが多く、時間配分が合否に直結します。焦るとケアレスミスが増えますし、逆に1問に時間をかけすぎると最後まで解き切れません。
効果的なのは、全体を見渡してから得意分野から解答する方法です。難問に固執せず後回しにする判断も重要でしょう。
また、残り時間を確認できるシステムが多いため、定期的に残り時間を意識してください。
時間配分を考えずに臨むと、解けるはずの問題を落としてしまう恐れがあるため、事前にシミュレーションしておくと安心です。
④締切・再受検ルールを遵守する
WEBテストには提出期限が設けられており、締切を過ぎると受験資格を失う場合があります。再受検を認める企業もありますが、多くは認められません。
同時期に複数社から案内が届くと日程管理を誤って受験機会を逃す学生もいるため注意が必要です。対策としては、スケジュールアプリに期限を記録し、余裕を持って受検すると良いでしょう。
アクセス集中でログインできないこともあるため、前日までにログイン確認をしておくのも安心です。規定を守る姿勢は信頼にもつながるので、必ず意識してください。
主な出題企業例【テスト別】

就活で受験するWebテストは種類が多く、企業によって出題傾向も大きく異なります。代表的なテストごとに導入の意図や採用する企業を知っておくことで、効率的な対策につながるでしょう。
ここでは、代表的なテストごとの出題企業例を紹介します。
- SPIの出題企業例
- 玉手箱の出題企業例
- TG-WEBの出題企業例
- GABの出題企業例
- CABの出題企業例
- ENG(SPI英語)の出題企業例
- CUBICの出題企業例
- SCOAの出題企業例
- TAPの出題企業例
- IMAGES(イメジス)の出題企業例
- TALの出題企業例
- 内田クレペリン検査の出題企業例
- デザイン思考テストの出題企業例
①SPIの出題企業例
SPIは国内で最も利用されている適性検査のひとつで、大手から中堅まで幅広い企業が採用しています。
具体的には三菱UFJ銀行や三井住友銀行などの金融機関、トヨタ自動車や日立製作所といった製造業、リクルートやNTTグループなどサービス業まで多岐にわたります。
SPIが多くの企業で導入される理由は、基礎的な能力や性格傾向を効率的に測れるからです。受験者は数的処理や言語問題の演習に加え、性格検査の理解を深めることが欠かせません。
特に注意すべき点は、SPIにはWeb版とテストセンター版があるため、準備を取り違えると効果が半減してしまうことです。志望先がどちらを採用しているかを事前に確認してください。
- トヨタ自動車
- 日立製作所
- ソニーグループ
- パナソニック
- NTTグループ
- JR東日本
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほフィナンシャルグループ
- リクルート
②玉手箱の出題企業例
玉手箱は外資系や大手総合商社などでよく採用され、英文読解や計数処理が特徴です。
三菱商事や伊藤忠商事などの商社、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーといった外資系金融機関、さらにP&Gやユニリーバなどの消費財メーカーも代表例です。
特徴は出題時間が短く、正確さとスピードの両立が求められる点にあります。油断すると時間切れになることが多く、焦って実力を出せない場合も少なくありません。
そのため、問題形式に慣れるための過去問演習が有効です。また、外資系志望者は英語問題が必須となるため、リーディング力の強化も大切でしょう。
- 三菱商事
- 三井物産
- 伊藤忠商事
- 住友商事
- 丸紅
- ゴールドマン・サックス
- J.P.モルガン
- モルガン・スタンレー
- P&G
- ユニリーバ
③TG-WEBの出題企業例
TG-WEBはIT企業や広告代理店などで導入されることが多いテストです。代表例はサイバーエージェントや電通、博報堂などの広告業界、楽天やソフトバンクといったIT関連企業です。
特徴は推論力や論理的思考を問う問題が多く、SPIや玉手箱とは形式が異なります。特に図形や論理パズルの問題は慣れていないと時間を大幅に消費してしまうでしょう。
注意点は、難易度が高くても全問正解を前提としていないことです。
解ける問題を見極め、効率的に解答する力が評価されます。演習では問題選別の練習を取り入れると、本番でも安定した得点につながります。
- サイバーエージェント
- 楽天グループ
- ソフトバンク
- LINEヤフー
- ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 電通
- 博報堂DYグループ
- カヤック
- サイボウズ
- ミクシィ
④GABの出題企業例
GABは外資系コンサルや金融の採用で多く使われ、論理的に情報を整理する力を重視します。英語長文や数表を素早く処理し、要点を的確に選ぶ力が問われるためです。
受験者は「英語が難しいから全部できない」と考えがちですが、これは誤解で、実際には時間配分を工夫し、解く問題を選ぶ姿勢が大切になります。
過去問形式に慣れて処理の順番を型化すると、冷静に対応できるでしょう。論理推論は短時間で結論を導く訓練を積むことが効果的です。
- マッキンゼー・アンド・カンパニー
- ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)
- ベイン・アンド・カンパニー
- ゴールドマン・サックス
- J.P.モルガン
- モルガン・スタンレー
- バークレイズ
- シティグループ
- アマゾンジャパン
- マイクロソフト日本法人
⑤CABの出題企業例
CABはシステム開発やエンジニア採用に使われ、論理思考と情報処理のスピードを測るテストです。IT業界志望の学生にとっては重要な検査といえるでしょう。
論理的にフローチャートや表を解析する力は、プログラミングや設計業務に直結します。陥りやすいのは時間内に全問解こうとする焦りです。
スピードと正確性の両立が求められるため、完答を狙うより確実な問題から積み重ねることが効果的です。過去問や類題を解くことで、処理パターンを定着させてください。
- NTTデータ
- 富士通
- NEC
- 日立ソリューションズ
- 野村総合研究所(NRI)
- 大和総研
- NTTコムウェア
- オービック
- 楽天グループ(技術職)
- ソニーグループ(IT部門)
⑥ENG(SPI英語)の出題企業例
ENGはグローバル展開する企業で重視される検査です。海外取引や英語での情報処理が日常的に必要な職場では、読解力と語彙力が採用基準となります。
見落としやすいのは文法よりも読解問題の比重が大きい点です。速読と要約が鍵となるため、英語記事を読み短時間で要点をつかむ練習を積むとよいでしょう。
リスニングは課されませんが、英語での判断力が見られます。試験勉強にとどめず、英語ニュースを活用すると実戦的な力が養われます。
- 楽天グループ
- ソニーグループ
- 三菱商事
- 伊藤忠商事
- ユニリーバ
- P&G
- アクセンチュア
- デロイトトーマツ
- アマゾンジャパン
- マイクロソフト
⑦CUBICの出題企業例
CUBICは性格検査の要素が強く、企業文化との適合性を測るために導入されます。能力の高さだけでなく、組織との相性を見たい企業に多いです。
受験者が誤解しやすいのは「無難な答えでよい」と思い込むことです。矛盾した回答をすると一貫性が欠けていると判断されかねません。
自分の強みや価値観を整理し、回答の軸をぶらさないようにしてください。正解があるわけではないため、自然体で一貫した回答が評価されます。
- 三井住友銀行
- 東京海上日動火災保険
- 大和証券
- りそな銀行
- 第一生命保険
- 日本生命保険
- みずほフィナンシャルグループ
- NTTコミュニケーションズ
- ANA(全日本空輸)
- JAL(日本航空)
⑧SCOAの出題企業例
SCOAは総合適性検査として幅広い能力を多面的に測るのが特徴です。中堅から大手まで幅広い業種で採用され、汎用性の高いテストといえます。
言語・数理・論理・英語・性格と多岐にわたる領域を評価できます。受験者が気づかない点は、得意不得意の差が大きいと全体評価が下がることです。
弱点分野を補強し、バランスを意識して学習を進めてください。幅広く知識に触れることが定着と応用力の強化につながります。
- JR東日本
- 東急不動産
- セガサミーホールディングス
- 大和ハウス工業
- ヤマトホールディングス
- サントリーホールディングス
- 日本郵政グループ
- みずほ信託銀行
- 明治安田生命
- 損害保険ジャパン
⑨TAPの出題企業例
TAPは専門的な適性を測る目的で導入され、大手メーカーや商社などで見られます。基礎学力に加え、論理的な読解や数理処理を重視します。問題数が多く、集中力を長時間維持することが必要です。
準備不足だと途中で失速しやすいため、本番を想定した模試や演習で慣れてください。基礎力の徹底と時間配分の工夫が合否を分けます。
- 三井物産
- 住友商事
- 丸紅
- 日本製鉄
- 川崎重工業
- 日産自動車
- 東芝
- 京セラ
- 清水建設
- 鹿島建設
⑩IMAGES(イメジス)の出題企業例
IMAGESはデザイン感覚や空間認識を問う検査で、クリエイティブ系や建築系の採用で使われ、視覚情報を素早く処理する力が評価されます。注意したいのは「直感で解ける」と思い込むことです。
実際には視覚情報を言葉に置き換える練習が効果的です。図形パズルや空間把握問題を繰り返し、思考パターンを固めてください。
- 大日本印刷(DNP)
- 凸版印刷
- 電通
- 博報堂
- 乃村工藝社
- 竹中工務店
- 大成建設
- 清水建設
- コクヨ
- サンゲツ
⑪TALの出題企業例
TALは語学力と論理力を同時に測るテストで、外資系企業や国際志向の強い企業で導入されていますが、語学試験と同じと思うと誤解を招きます。
実際には論理推論と組み合わせて出題されるため、英語理解と論理力の両立が必要です。英語長文を要約し、論理的に説明する練習が効果的でしょう。
- アクセンチュア
- PwCコンサルティング
- デロイトトーマツコンサルティング
- KPMGコンサルティング
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング
- アマゾンジャパン
- グーグル日本法人
- マイクロソフト
- シスコシステムズ
- 日本IBM
⑫内田クレペリン検査の出題企業例
内田クレペリン検査は性格や作業能率を測定する心理検査として有名です。集中力や安定性を評価したい企業で広く導入されています。単純な計算だから準備不要と思うのは誤りです。
時間ごとの作業曲線が分析されるため、途中で大きな波が出ると評価が下がります。一定のリズムで作業できるように練習を重ねてください。
- 警視庁
- 地方公務員(市役所・県庁)
- 自衛隊
- JR東日本
- ANA(全日本空輸)
- JAL(日本航空)
- トヨタ
WEBテストに関するよくある質問(Q&A)

就活において避けて通れないのがWEBテストです。
ここでは、よくある質問を取り上げ、不安を解消できるように解説します。
- WEBテストの合格ラインは?
- WEBテストの結果って使い回せる?
- WEBテストはいつ・何回くらい実施される?
- WEBテストで時間が足りないときはどうすればいい?
- WEBテストの練習サイトや模試はある?
- WEBテストでウィンドウ監視ってバレる?
- 不正検知はされる?
①WEBテストの合格ラインは?
WEBテストの合格ラインは企業や選考の段階によって変わります。一般的には上位3〜4割に入る点数が目安とされるでしょう。
なぜなら、多くの応募者を効率的にふるいにかけるために足切りが行われるからです。SPIや玉手箱などでは6割前後を合格基準とする企業が多いですが、難易度や応募者数によって基準が上がることもあります。
逆に応募者を広く集めたい企業では基準が低めになる場合もあります。大切なのは点数そのものではなく、安定して基準以上を取れる力を持つことです。
過去問や模試を繰り返し、7割程度を確実に取れるように練習しておけば安心でしょう。
②WEBテストの結果って使い回せる?
WEBテストの結果は基本的に使い回せません。企業ごとに採用プロセスや利用目的が違うためです。多くの企業は専用のシステムで結果を管理しており、他社のスコアを流用することはできないでしょう。
外部のテストセンターを利用する場合でも、年度や受験日によって再受験が必要なことが多いです。使い回せると誤解して準備を怠ると、予想外の失敗につながる危険があります。
そのため、毎回の受験で力を出し切れるよう、基礎力を日頃から鍛えておくことが重要です。結果が共有されない前提で臨むことが、就活全体を有利に進める秘訣といえます。
③WEBテストはいつ・何回くらい実施される?
WEBテストはエントリー直後から面接前までの間に複数回実施される可能性があります。就活全体で10回以上受ける学生も珍しくありません。
企業によっては書類選考後すぐに課す場合もあれば、面接前に確認として行うケースもあります。特に大手企業では母集団を絞るために初期段階で用いられることが多いです。
想定よりも受験回数が増えるため、短期的な暗記ではなく繰り返し練習で基礎を固める必要があります。また、複数社から同時に案内が届くこともあるため、スケジュール管理も欠かせません。
受験回数を見込んで計画的に準備することが成功の鍵です。
④WEBテストで時間が足りないときはどうすればいい?
WEBテストでは制限時間が厳しく設定されているため、時間が足りないと感じる人は多いでしょう。大切なのは解ける問題から優先的に進めることです。
難しい問題にこだわると時間を浪費し、解ける問題まで落とす恐れがあります。たとえば計数や読解問題では、形式に慣れていないと戸惑いやすいため、すぐに切り替える判断が必要です。
普段からタイマーを使って練習すれば、時間感覚を養うことができます。さらに暗算力や読解速度を鍛えることで処理力も上がります。
焦りは誰にでも起こりますが、日頃の工夫で本番の不安を小さくできるでしょう。
⑤WEBテストの練習サイトや模試はある?
WEBテスト対策には練習サイトや模試が役立ちます。無料と有料の両方があり、目的に合わせて選ぶことができるのです。無料サイトでは基本的な形式を体験でき、有料模試では本番に近い環境で実力を試せます。
形式に慣れるかどうかで得点に差が出るため、模試で繰り返し練習することは効果的です。特にSPIや玉手箱は問題のパターンが決まっているため、模試を通じて解答スピードを高められます。
模試のフィードバックを活用すれば弱点も明確になります。効率よく対策を進めたい学生にとって、模試の利用は大きな助けとなるでしょう。
⑥WEBテストでウィンドウ監視ってバレる?
WEBテスト中に別のウィンドウを開くと、不正とみなされる可能性が高いです。監視システムは画面の動きを記録しているため、バレないと考えるのは危険でしょう。
企業は公平性を保つため監視機能を導入しており、不自然な操作があれば結果が無効化されることもあります。「少しくらい大丈夫」と思うのは誤解です。
不正が判明すれば選考から外されるだけでなく、信頼も失ってしまいます。正攻法で実力をつけることこそが、最も安全で確実な対策です。
模試や演習で力を積み上げておけば、監視を気にせず堂々と受験できるでしょう。
⑦不正検知はされる?
WEBテストでは不正検知システムが導入されており、不正は高確率で見抜かれます。カンニングや代理受験は必ずリスクが伴い、避けるべきです。
検知方法には解答時間の不自然さやIPアドレスの異常、場合によってはカメラ映像の分析もあります。一見バレないように思える行為でも、データから不自然さが浮かび上がります。
不正が確認されれば即時に不合格となり、他社に情報が共有される可能性もあります。つまり不正は就活全体を危うくする行為です。正しい方法で努力すれば誠実さが評価されることもあります。
地道な準備こそが成功への近道でしょう。
就活でのテストを攻略するために

就活においてWEBテストは、多くの企業が応募者を評価・選抜する重要なプロセスとして位置づけられています。
企業はSPIや玉手箱、TG-WEBなど複数種類のテストを導入し、応募者の適性や基礎能力を客観的に判断しています。
そのため、受検方法やテストの見分け方を理解し、主要テストごとの対策を行うことが、内定獲得に直結するのです。
実際、WEBテストの結果が合否や配属に大きく影響するケースも多いため、事前準備を怠ると不利になります。逆に、特性を押さえた練習と環境整備を徹底すれば、安定した得点力を発揮できます。
就活生は「どの企業で、どの種類のテストが出題されるのか」を把握したうえで、自分に合った学習法を取り入れることが成功のカギです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










