エントリーシートは何文字書くべき?8割原則と文字数別ES例文で完全理解
「エントリーシートの文字数って、どのくらい書けばいいの?」 就活を始めた学生が必ず直面する疑問のひとつです。文字数制限がある場合もない場合もあり、何割まで埋めるのが正解なのか迷う方も多いでしょう。
この記事では、8割原則の理由や文字数超過・不足時の対処法、さらに文字数別の例文まで徹底解説します。これを読めば、どんなESでも自信を持って書けるようになります。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
エントリーシートとは?

エントリーシートとは、就職活動で企業に自分を知ってもらうための最初の関門です。履歴書と似ていますが、より詳細に学生生活での経験や強みを文章で伝えることが求められます。
単なる事実の羅列ではなく、自分の考えや行動の背景を表現することが評価につながるでしょう。企業はエントリーシートを通して、応募者の思考力や表現力、人柄を読み取ろうとしています。
さらに、エントリーシートは限られた文字数の中で自分を的確に表現する力が求められるため、冗長な言葉を避けつつ要点を整理して書くことが重要になります。
採用担当者は多くの応募書類を短時間で確認しているため、伝えたい内容が簡潔でわかりやすいかどうかが評価を左右するのです。
文字数を意識した書き方を身につければ、読み手にわかりやすく誠実さを感じさせることができ、結果として採用担当者に強い好印象を残すことにつながるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
エントリーシートで文字数の8割以上を埋めるべき理由

エントリーシートは単なる自己紹介ではなく、企業に自分の意欲や能力を伝える大切な書類です。そのため「文字数をどの程度埋めるべきか」と悩む学生は多いでしょう。
結論から言えば、8割以上を埋めることが望ましく、採用担当者からの印象にも直結します。ここをおろそかにすると熱意が伝わらず、せっかくの努力が評価につながらない恐れもあります。
ここでは、その理由を5つの観点から具体的に解説します。
- 応募者の熱意を判断するため
- 思考力や表現力を測定するため
- 公平な評価基準を守るため
- 他の応募者との差を見極めるため
- 読み手に十分な情報を伝えるため
①応募者の熱意を判断するため
エントリーシートをきちんと埋めることは、応募への熱意を示す重要なサインになります。文章が短すぎると「本当に志望しているのか」「やる気があるのか」と疑念を持たれてしまうでしょう。
逆に、文字数を満たしつつ自身の経験や思いを丁寧に表現すれば、誠実さや主体的な姿勢を伝えられます。
例えば部活動やアルバイトで努力した経験を具体的に書けば、表面的な志望理由よりもはるかに説得力が増します。ただし、無理に水増しすると逆効果になるので注意が必要です。
枠を有効に使い、熱意と具体性を両立させることが合格への近道になるでしょう。
②思考力や表現力を測定するため
企業はエントリーシートを通じて、学生が考えを整理して分かりやすく伝える力を確認しています。単に字数が多ければよいわけではなく、限られた枠内で自分の強みを的確に表現できるかが評価されます。
文字数が極端に少ないと、論理展開や文章の構成力を測る材料が不足し、評価につながりません。
一方、与えられた枠をきちんと使って「結論→理由→具体例→まとめ」という流れで書けば、論理的思考力や表現力を自然に示せます。
就活においては知識だけでなく、相手に伝える力も大切です。エントリーシートでこの力を見せることができれば、面接にもつながる大きな強みとなるでしょう。
③公平な評価基準を守るため
エントリーシートの文字数は、全ての応募者を公平に評価するための基準として機能しています。
もし字数が極端に少なければ、他の学生と比べて情報量に差が出てしまい、採用担当者も比較が難しくなります。
多くの企業は短時間で数百枚のESを確認するため、ある程度統一された条件で判断できることが重要です。文字数を守らないと、その時点で「評価の対象外」とみなされる危険すらあります。
学生側としても、公平に見てもらうためにしっかり枠を埋める姿勢が必要です。採用担当者に「読みやすい」「比較しやすい」と感じてもらうことで、選考をスムーズに進めてもらえる可能性が高まるでしょう。
④他の応募者との差を見極めるため
同じ設問に答える場合でも、文字数をしっかり活用して具体的に書く学生と、空白が目立つ学生とでは伝わる印象が大きく異なります。
採用担当者はその差を基準にして、どれだけ真剣に考え、準備をしてきたかを見極めています。
たとえば「チームワークを大切にした」とだけ書くよりも、「アルバイトで意見の衝突があった際に〇〇の工夫をして改善した」と具体的に説明したほうが、実際の行動力が伝わります。
8割以上を埋める意識は、単に形式を整えるだけでなく、他の応募者との差別化につながります。結果として自分の強みや人柄をより鮮明に示すことができるでしょう。
⑤読み手に十分な情報を伝えるため
エントリーシートは、面接前に学生の人物像を把握するための資料です。文字数が少なければ経験や学びが十分に伝わらず、面接官も掘り下げた質問ができません。
逆に、枠を埋めて具体的なエピソードを盛り込めば、面接官が関心を持ちやすくなり、面接の会話も深まります。
たとえば「サークル活動を通してリーダーシップを発揮した」と書いた後に「その結果、チームの成果が向上した」という具体例を加えるだけで、印象は大きく変わります。
エントリーシートは面接の土台となるものなので、十分な情報を伝えることで自分の魅力をさらに引き出すきっかけを作れるのです。
エントリーシートで文字数制限がない場合の書き方
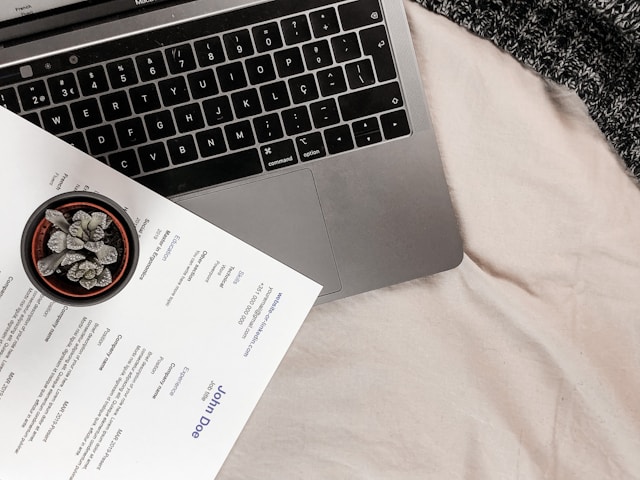
就活でエントリーシートに文字数制限がないと、どれくらい書けばよいのか迷う学生は多いでしょう。採用担当者は読みやすさと内容の濃さを重視するため、適切な分量を知っておくことが重要です。
特に本番の選考では、文字数の感覚ひとつで評価が変わることもあるため、事前に基準を持っておくことが安心につながります。ここでは、文字数制限がないときに意識すべきポイントを整理しました。
- 目安となる文字数を決める
- 300〜400字でまとめる構成を意識する
- 記入スペースの8割以上を埋める
- 簡潔さと具体性を両立させる
- 冗長さを避けて内容を整理する
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
①目安となる文字数を決める
文字数制限がない場合でも、あらかじめ自分なりの基準を設けることが大切です。なぜなら、短すぎると意欲が伝わらず、逆に長すぎると冗長になって要点がぼやけるからです。
目安として300〜400字程度を設定しておくと、採用担当者が読みやすい長さに収まりつつ、経験や学びを十分に盛り込めます。
就活生は「どの程度書けば伝わるのか」という感覚をつかみにくいものですが、300〜400字を意識すると、情報不足や書きすぎを防げます。
基準を持つことで安心して文章を組み立てられ、結果として一貫性と説得力を兼ね備えたエントリーシートになるでしょう。
②300〜400字でまとめる構成を意識する
300〜400字を目安にしたときは、その中で「結論→具体例→学び→志望理由」の流れを意識すると効果的です。
例えば冒頭の2〜3行で自分の強みや結論を述べ、その後の200字前後で具体的なエピソードを説明し、最後に学んだことや志望動機につなげると、自然に400字程度に収まります。
こうした構成を意識すれば、だらだらと書き連ねることを避けつつ、必要な情報を過不足なく盛り込めます。
就活生にありがちな「体験談だけで終わってしまう」「結論が曖昧なまま締める」といった失敗も防げるでしょう。限られた字数に沿って論理的に配置することで、読み手に伝わる文章へと仕上げられます。
③記入スペースの8割以上を埋める
記入欄が広い場合は、スペースの8割以上を埋めることを意識してください。空白が多いと「準備不足なのでは」と思われ、熱意が伝わらない恐れがあります。
一方で、8割程度を埋めれば誠実さや積極性を示せます。無理に字数を稼ぐ必要はなく、エピソードに具体的な数字や行動を入れることで自然と分量は増えていきます。
例えば「アルバイトで接客を担当した」と書くだけでは短いですが、「1日平均50人以上の来客対応を通じて、臨機応変に行動する力を養った」と書けば説得力も増します。
分量を意識することは、評価されやすいエントリーシートを作るうえでの重要な姿勢です。
④簡潔さと具体性を両立させる
伝わりやすい文章に仕上げるには、簡潔さと具体性を同時に意識する必要があります。抽象的な言葉だけでは弱く、細かすぎる説明は冗長になりがちです。
例えば「リーダーシップを発揮した」とだけ書くと曖昧ですが、「ゼミで20人のメンバーをまとめ、期限内に研究発表を成功させた」と具体的に書けば強みが鮮明になります。
就活生は「採用担当者は自分の背景を知らない」という前提を持ち、分かりやすく伝える意識を忘れないことが大切です。
要点を整理しながら事実を盛り込むことで、担当者の印象に残る文章を作成できるでしょう。
⑤冗長さを避けて内容を整理する
文字数制限がないと、多くの情報を詰め込みたくなるものです。しかし情報過多は主張をぼやけさせ、結果として評価を下げかねません。
大切なのは「伝えたい軸を1つに絞る」ことです。強みや経験を明確にし、それを裏付けるエピソードを1つ中心に据えましょう。
同じ内容を言い換えて繰り返すのは避け、経験から得た学びを志望理由や今後の目標へつなげる形でまとめると、簡潔ながらも説得力ある文章になります。
情報を整理して書くことで、エントリーシート全体がすっきりと読みやすくなり、採用担当者に強い印象を残すことができるでしょう。
エントリーシートの文字数が超過するときの対処法

就活でエントリーシートを書くとき、熱意を込めるあまり文字数がオーバーしてしまうことがあります。限られた枠に自分の経験や強みを詰め込もうとすると、どうしても文章が長くなりがちです。
しかし企業は短時間で多くの応募書類を確認するため、簡潔さや読みやすさが評価に直結します。
したがって、文字数を超えてしまった場合は「どの情報を残し、どこを削るか」を考えることが欠かせません。ここでは、文字数オーバー時に役立つ具体的な方法を学生目線で解説します。
- 冗長表現や重複内容を削除する
- 接続詞や言い回しを見直す
- 伝える内容を絞り込む
- 簡潔に言い換える
- 下書きを活用して調整する
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①冗長表現や重複内容を削除する
文章が長くなる大きな原因は、同じ意味を異なる言い方で繰り返してしまう点にあります。例えば「積極的に行動しました」と「自ら率先して動きました」は、どちらも同じ意図を伝えています。
両方を残すと冗長になり、読み手に負担を与えてしまうでしょう。エントリーシートでは、新しい情報を端的に示すことが重要です。重複を削れば内容は引き締まり、印象もすっきりとします。
特に就活生は、自分の強みをアピールしたい気持ちが強いため同じ表現を何度も使いがちですが、削る勇気を持つことが評価につながります。
文字数を整理する過程で、自分が一番伝えたい核が明確になり、文章全体の完成度も高まるでしょう。
②接続詞や言い回しを見直す
文字数を整える際に効果的なのが、接続詞や長すぎる表現を削る工夫です。「そして」「また」といった接続詞を頻繁に使うと字数が増えるだけでなく、文章が単調に見えてしまいます。
文を区切って短く表現すれば、論理は十分伝わります。また「〜することによって」は「〜して」に置き換えられるように、簡潔な言い回しに変えることも有効です。
こうした調整により、不要な字数を減らしながらも流れを崩さずにまとめられます。結果として採用担当者は内容を短時間で理解でき、あなたが伝えたいポイントに集中してくれるはずです。
就活生にとっては細かい表現を直す作業が面倒に思えるかもしれませんが、小さな改善の積み重ねが、評価されやすいエントリーシートを形づくります。
③伝える内容を絞り込む
文字数オーバーは、多くの情報を詰め込みすぎることで起こるケースが大半です。エピソードの背景や状況説明を長く書きすぎると、肝心の成果や学びが埋もれてしまいます。
企業が本当に知りたいのは「どのように行動し、何を学び、どう成長したのか」です。したがって、細かい描写よりも成果や学びに焦点を当てることが大切でしょう。
情報を取捨選択することで文章はより明確になり、印象的な内容に仕上がります。就活生は「これも伝えたい」と思う気持ちから説明を増やしてしまいがちですが、あえて削る勇気を持つことが効果的です。
読み手にとって理解しやすい文章は、あなたの成長や適性を鮮明に伝える力を持ち、結果として合格につながりやすくなります。
④簡潔に言い換える
表現の仕方を工夫することで、短くしながらも十分に意図を伝えることが可能です。例えば「積極的に挑戦する姿勢を持ち続けました」という文章は「積極的に挑戦しました」と言い換えられます。
余分な副詞や助詞を省けば、文章はすっきりし説得力も高まります。また、端的な表現は読み手の集中を途切れさせず、内容をダイレクトに伝えられる点も魅力です。
就活生にとっては「表現が簡単すぎるのでは」と不安に感じることもあるかもしれませんが、採用担当者にとっては読みやすさが最優先です。
回りくどい言葉よりも、短く分かりやすい表現こそが、あなたの熱意や姿勢をしっかりと伝えてくれるでしょう。
⑤下書きを活用して調整する
文字数オーバーを防ぐためには、一度で完璧な文章を書こうとせず、下書きを作って調整する習慣をつけることが大切です。まずは思いのままに書き、その後で削ったり言い換えたりして整えましょう。
こうしたプロセスを踏むと、内容の厚みを残しながら自然に文字数を調整できます。さらに繰り返すうちに、自分の冗長になりやすい癖や、余分な表現を見つけやすくなるはずです。
就活生にとって下書きは「手間がかかる作業」に思えるかもしれませんが、時間をかけて調整した文章は説得力や完成度が格段に上がります。
準備段階で十分に練り直せば、本番で焦ることなく、堂々と提出できるエントリーシートに仕上がるでしょう。
エントリーシートの文字数が足りないときの対処法

エントリーシートを書いていると、指定された文字数に届かず困る学生も多いでしょう。特に初めての就活であれば、何を書けばよいか迷ってしまい、気づけば文章が短くまとまってしまうこともあります。
文字数不足は内容が浅いと判断される要因になりかねません。ここでは、自然に文章を充実させるための工夫を解説します。
- 必要要素を網羅する
- 抽象的表現を具体化する
- 経験やエピソードを掘り下げる
- 成果や周囲の反応を盛り込む
- PREP法を使って厚みを出す
①必要要素を網羅する
文字数が足りないときは、まず設問で求められている要素をすべて書き出しているかを確認してください。志望動機なら「志望理由」「根拠となる経験」「将来の目標」の3点は欠かせません。
これらの観点を押さえるだけで、書くべき内容が増えます。例えば志望理由だけに終始してしまうと短い文章になりますが、過去の経験や将来像を結び付ければ、文字数を埋めつつ内容も深まるでしょう。
端的すぎる回答では熱意が伝わりにくいため、要素を丁寧に盛り込むことが大切です。読み手が「この学生はしっかり考えている」と思えるようにする工夫が必要です。
②抽象的表現を具体化する
「努力した」「成長した」といった表現は便利ですが、そのままでは説得力に欠けます。具体的な行動や成果を添えることで文字数も自然に増え、読み手に伝わる文章に変わります。
例えば「部活動で努力した」では印象が弱いですが、「毎日練習後に自主的に30分の振り返りを半年間継続した」と書けば臨場感が生まれます。数値や期間を盛り込むと、さらにリアリティが増すでしょう。
就活生は自分の取り組みを数値や具体的な行動に置き換えることを意識すると、文字数不足の悩みを解決しやすくなります。
③経験やエピソードを掘り下げる
短い文章にとどまる最大の原因は、経験を表面的に語ってしまうことです。「アルバイトで接客を経験した」とだけ書けば数行で終わってしまいます。
しかし「クレーム対応で相手の要望を正確に聞き取る重要性を学び、その後の業務で改善を意識した」と展開すれば、文字数は自然に増えます。
さらに「その経験を通じて、自分は課題を冷静に整理して行動できる強みがある」とまとめれば、文章全体が厚みを増すでしょう。
就活生にとって大切なのは、単なる出来事ではなく、その中で得た気づきや成長まで掘り下げて書く姿勢です。
④成果や周囲の反応を盛り込む
取り組みの成果に加えて、周囲の反応を交えると文章はより豊かになります。
「売上を伸ばした」だけでは簡潔すぎますが、「新人研修で提案した接客改善が採用され、結果的に売上が前年比で15%伸び、上司からも評価を得た」と書けば、文字数も増え、説得力も格段に高まります。
成果と反応を併せて書くことで、自分の行動が組織にどう影響を与えたかまで伝えられるのです。就活生にとっては、自分の成長だけでなく、周囲からどう評価されたかを書くことが差別化につながるでしょう。
⑤PREP法を使って厚みを出す
文章の構成を工夫することも有効です。結論(Point)から始め、理由(Reason)を説明し、具体例(Example)を加え、最後に再び結論(Point)で締めるPREP法を使えば、自然に400字前後の分量になります。
例えば「私は粘り強さが強みです」と述べた後、その理由を示し、具体的な経験を紹介すれば、文字数が安定します。
最後に「以上の経験から、困難に直面しても最後まで取り組む力があります」と結ぶと、一貫性のある文章になるでしょう。
文字数不足を感じたときこそ、PREP法を活用して論理的で読みやすい文章を組み立ててください。
エントリーシートで重点的に書くべき項目

就活のエントリーシートでは、すべての欄を均等に埋めれば良いわけではなく、企業が重視するポイントに的を絞って内容を充実させることが重要です。
とくに自己PRや学生時代の経験、志望動機の深掘りなどは、選考で差をつける決め手になるでしょう。漠然と文章を埋めるのではなく、採用担当者が知りたい情報を意識して書く姿勢が求められます。
ここでは重点的に書くべき5つの項目を整理しました。
- 自己PRの内容
- 学生時代に力を入れた経験
- 志望動機の展開
- 学びや成果の具体例
- 企業が重視する評価ポイント
①自己PRの内容
自己PRは、自分の強みを企業に最も直接的に伝える大切な場面です。結論としては、強みを端的に示し、その裏付けとなる具体的なエピソードを添えると効果的でしょう。
抽象的な表現だけでは説得力が弱く、採用担当者の印象にも残りにくいからです。
例えば「責任感が強い」と述べるなら、ゼミ活動で役割を最後までやり抜いた経験や、アルバイトで困難を引き受けて成果を上げた経験を具体的に書くと良いでしょう。
そのうえで「その強みを入社後にどう活かすか」まで触れると、単なる自己紹介にとどまらず将来の働きぶりをイメージさせられます。
「強み→根拠→活かし方」の流れを意識すると、読み手に理解されやすく評価につながりやすいです。結果として、自己PRはエントリーシート全体の軸となる部分になるはずです。
②学生時代に力を入れた経験
学生時代に力を入れた経験は、応募者の人柄や価値観を具体的に伝える手段になります。単なる活動の羅列ではなく「課題と取り組み」「工夫と成果」を明確に書くことが必要です。
企業はその経験を通じて「主体性」や「課題解決力」を判断しているからです。
例えば、部活動で大会を目指す過程で練習メニューを改善したり、アルバイトで売上向上の施策を提案して実行したりした経験は説得力を持ちます。
さらに「困難をどう乗り越えたか」「そこから何を学んだか」を加えると、努力の質や成長がより伝わります。失敗から得た教訓を含めれば、人間性や学びを深く表現できるでしょう。
こうした経験は社会人として困難に直面した際の対応力を示す材料にもなります。自分の成長物語として描くことを意識すれば、読み手の印象にも強く残るはずです。
③志望動機の展開
志望動機は、企業への熱意を伝える最も重要な部分です。結論として「企業への共感→自分の経験との接点→将来のビジョン」という流れで展開すると説得力が増します。
単なる「御社で働きたい」という表現では差別化が難しいからです。例えば、企業理念やサービスに共感した理由を自分の活動や経験と結びつけると、説得力が高まります。
さらに、その企業だからこそ実現できる目標を語り、入社後に具体的にどう貢献したいかを伝えると効果的です。
採用担当者にとっては「この学生が自社で活躍する姿」が鮮明にイメージできるかどうかが重要になります。
ありきたりな志望動機ではなく、自分の経験や価値観と企業の特徴を組み合わせて展開することで、他の応募者との差をつけられるでしょう。結果的に、志望動機は企業との相性を示す決め手となります。
④学びや成果の具体例
学びや成果を具体的に示すことは、単なる努力ではなく「結果を出す力」を伝えるために欠かせません。数字や比較を用いて成果を客観的に表現することが効果的です。
「努力した」だけでは評価が曖昧になり、採用担当者にインパクトを与えにくいからです。
例えば「売上を10%改善した」「イベント参加率を2倍にした」など具体的な数字を入れると、自分の取り組みが実際に価値を生んだと示せます。
また、その成果に至るまでの工夫や行動を簡潔に添えることで、行動力や発想力も伝わるでしょう。さらに、成果だけでなく「その経験から得た学び」を加えると、成長意欲や今後の可能性を示せます。
読み手は成果そのものよりも、そこからどんな力を伸ばしてきたかに注目するものです。この項目を工夫して書くことで、即戦力としての期待を持たれる可能性が高まります。
⑤企業が重視する評価ポイント
企業がエントリーシートで重視するのは、知識やスキルそのものよりも「人柄」「成長意欲」「協調性」といった評価ポイントです。これらを意識的に盛り込むと、書類全体の完成度が高まります。
採用担当者は「一緒に働きたい人物かどうか」を最終的な基準にしています。例えば、強みを語る際にチームへの貢献や周囲への影響を加えれば、協調性やリーダーシップを感じさせられるでしょう。
挑戦を通じて学んだことを強調すれば、成長意欲も自然に伝わります。さらに、相手の意見を尊重したり課題に前向きに取り組んだ姿勢を描いたりすると、組織適応力の高さも示せます。
読み手の視点に立って整理することで「この学生なら安心して任せられる」と思わせることができるのです。結果として、選考を突破する可能性を高める要素になります。
読みやすいエントリーシート作成のコツ

エントリーシートは内容の良し悪しだけでなく、読みやすさも合否に直結します。採用担当者は短時間で多くの書類を確認するため、伝えたいことが整理されているかどうかが重要です。
特に就活生にとっては、せっかくの努力が「読みにくい」という理由で評価されないのは避けたいでしょう。ここでは、読みやすさを高めるための実践的な工夫を紹介します。
- 一文を短くする
- 段落を分ける
- 数字や具体例を活用する
- 誤字脱字を確認する
- 読み手を意識して書く
①一文を短くする
一文を短くすることで内容がすぐに理解でき、読み手に余計な負担をかけません。長い文は主語と述語の関係が不明確になりやすく、結果として「何を伝えたいのか」がぼやけてしまいます。
例えば「私は部活動でキャプテンを務め、練習の効率化やメンバーとの信頼関係を築き、最終的に大会で優勝しました」と一気に書くよりも、「私は部活動でキャプテンを務めました。
練習の効率化を進め、メンバーとの信頼を築きました。その結果、大会で優勝を果たしました」と分けた方が理解しやすいのです。
普段から日記やレポートを書く際に一文を短くする意識を持っておくと、本番でも自然と読みやすい文章が書けるようになります。
②段落を分ける
段落を分けることは、読みやすさを大きく向上させる工夫です。話題が変わる場面で改行を入れることで、文章に自然なリズムが生まれます。
特に自己PRや志望動機では「経験」「学んだこと」「応募先での活かし方」といった流れごとに段落を変えると、全体像が整理されて伝わりやすくなります。
改行がない文章は読み手に負担をかけ、内容が頭に入りにくくなるでしょう。一方で適切に段落を区切れば要点を素早く理解してもらえ、読み手の集中力も持続します。
就活生の多くは「どのくらいの分量で改行すればよいか」と迷うことがありますが、2~3文を目安にするとバランスが良くなります。段落分けは、読む人に寄り添った思いやりの表現方法といえるでしょう。
③数字や具体例を活用する
抽象的な言葉よりも数字や具体例を使うことで、文章は一気に説得力を持ちます。
「努力して成果を出した」では曖昧ですが、「週5日の練習を継続し、参加率を90%以上に保ち、最終的に大会でベスト4に入賞した」と書けば、努力の規模や成果が明確に伝わります。
数字は客観的な根拠となり、読み手の信頼を得やすいのです。また具体例を交えることで文章に厚みが増し、他の応募者との差別化にもつながります。
例えばアルバイト経験を書く際も「接客を頑張った」ではなく「1日200人以上のお客様に対応し、常連客のリピート率を20%高めた」と表現すれば効果的です。
採用担当者は「具体的な行動や結果」を知りたいと考えているため、数字や実例を取り入れる姿勢は高評価につながるでしょう。
④誤字脱字を確認する
誤字脱字は小さなミスに見えても、注意力や誠実さに欠ける印象を与えかねません。せっかく良い内容を書いても、細部の誤りで評価を落とすのは非常にもったいないことです。
提出前には声に出して読み返す、第三者に確認してもらうといった工夫が効果的です。
特にパソコンで入力した場合は変換ミスが多いため、自動チェック機能だけに頼らず、自分の目で丁寧に見直してください。
例えば「貴社」を誤って「貴者」と書いてしまうと、それだけで真剣さを疑われることもあります。
誤字脱字の有無は採用担当者にとって大きな判断材料となるため、最後の見直しを怠らないようにしてください。
⑤読み手を意識して書く
最も大切なのは「誰に読まれるか」を常に意識することです。採用担当者は限られた時間の中で多くのエントリーシートを読み、数分で判断を下す場合もあります。
したがって、専門用語や説明不足な表現は避け、初めて読む人にも伝わるように工夫する必要があります。
さらに志望先の企業が重視する価値観やスキルを理解し、それを文章に反映させれば「この学生は自社に合っている」と感じてもらいやすいでしょう。
例えば「協調性」を重んじる企業に対しては、チームで成果を出した経験を具体的に書くと効果的です。就活生にとって、読み手を意識する姿勢こそが評価を高める重要な一歩になるはずです。
手書きでエントリーシートを書くときの注意点

手書きでエントリーシートを提出する場合、文字の丁寧さや全体の仕上がりは企業に与える印象を大きく左右します。
デジタル入力とは異なり、修正や清潔感の管理に工夫が必要となるため、細部への配慮が欠かせません。さらに、文字の見やすさや余白のバランス、修正跡の有無などは読み手の心理に強く影響します。
ここでは就活生が失敗しやすいポイントと、その改善方法を5つの観点から整理しました。
- 文字の丁寧さに注意する
- スペース配分に注意する
- 修正方法に注意する
- 清潔感に注意する
- 仕上がり確認に注意する
①文字の丁寧さに注意する
手書きのエントリーシートでは、文字の丁寧さが読み手の第一印象を決める大きな要素です。字が雑だと、どれほど内容が優れていても「誠実さが足りない」と判断される危険があります。
反対に一字一字をていねいに書くことで、自然と「真剣に取り組んでいる学生だ」と伝わるでしょう。特に、漢字とひらがなの大きさや形をそろえると見た目が整い、文章全体が読みやすくなります。
また、筆圧の強弱やペンの持ち方によっても印象は変わるため、練習段階から意識することが大切です。急いで仕上げると文字が崩れやすいので、余裕を持って取りかかってください。
ていねいな文字は自己PRの一部となり、内容を引き立てる効果を持ちます。
②スペース配分に注意する
手書きのエントリーシートは、文字だけでなく行間や余白の使い方で完成度が大きく変わります。字を詰め込みすぎると窮屈に見え、逆に余白が広すぎると中身が薄いと誤解される恐れがあります。
適度な大きさの文字を心がけ、行の始まりと終わりをそろえることで、見た目が整い落ち着いた印象を与えられるでしょう。
さらに、文章の要点を行頭に配置したり、段落の区切りを意識して余白を活用したりすると、読み手が内容を追いやすくなります。
文字だけでなくレイアウトを工夫することは、採用担当者に「論理的に文章を構成できる学生だ」と思わせる効果もあります。見やすさを意識した配分は、内容以上に信頼感を高める要素になるはずです。
③修正方法に注意する
手書きのエントリーシートは、一度書いた文字を完全に消すことが難しいため、修正方法に細心の注意が必要です。
修正液や修正テープを多用すると清潔感を欠き、「準備不足なのでは」と不安を与える可能性があります。そのため、事前に下書きを作成して誤字脱字を減らす工夫をしましょう。
どうしても修正が必要な場合は、二重線で訂正し、横に正しい文字を添える方法が最も無難です。インクのにじみや消し跡が残ると、全体の完成度が下がるため、筆記具や紙質も意識するべきです。
さらに、1枚目から清書するのではなく、練習用に複数のシートを用意すると安心です。計画的に準備をすれば、修正跡のないエントリーシートを仕上げられ、誠実さと信頼性を伝えることができます。
④清潔感に注意する
手書きのエントリーシートでは、紙の状態そのものが清潔感を伝える要素となります。折れやシワ、インクのにじみ、手汗による汚れなどがあると、内容以前に「雑な扱いをしている」と見られてしまいます。
提出までの管理方法も重要で、クリアファイルに入れて保管すれば、折れや汚れを防ぐことができます。また、インクがにじまないペンや速乾性のあるボールペンを選ぶと仕上がりが美しくなります。
書き始める前に手を清潔に保つことも忘れないでください。細部にこだわる姿勢は、採用担当者に「業務でもきめ細やかな配慮ができる人材だ」と印象づける効果があります。
⑤仕上がり確認に注意する
最後に欠かせないのが仕上がりの確認です。誤字脱字や表現の誤りが残っていないかを確認するのは当然ですが、全体のレイアウトや見やすさまで点検することが大切です。
自分では気づけない部分を把握するために、第三者に読んでもらうのも有効でしょう。また、自然光や明るい照明の下で全体を眺めると、文字の濃さや行のそろい具合もチェックしやすくなります。
複数回の確認を重ねることで、完成度の高い仕上がりを実現できます。提出前に時間を割いて見直す習慣を持てば、「最後まで手を抜かない学生だ」と信頼を得られるはずです。
仕上げの確認は単なるチェック作業ではなく、自分をより良く見せるための最終ステップだと意識してください。
文字数別エントリーシート例文

エントリーシートは文字数の指定によって求められる表現力や情報量が変わるため、実際の例文を確認することは大きな参考になります。
ここでは、100字から1000字までのパターンごとに具体的な例文を紹介し、それぞれの文字数における工夫や伝え方の違いを理解できるようにまとめています。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①100字のエントリーシート例文
100字のエントリーシートは、限られたスペースで自分を的確に表現する必要があります。短い文章の中で「何を伝えたいのか」を明確にしなければならず、構成力や要点をまとめる力が特に重要です。
就活生にとっては難しく感じるかもしれませんが、工夫次第で十分に自分の強みを伝えることができます。ここでは、大学生活での経験をもとにした例文を紹介します。
《例文》
| 私はサークル活動でイベント運営を担当し、参加者200名を取りまとめました。限られた時間で計画を練り直すこともありましたが、チームと協力して最後までやり抜く力を身につけました。 この経験から、困難な状況でも冷静に判断し、周囲と力を合わせて成果を出す姿勢を大切にしています。 |
《解説》
短文でも「経験→学び→強み」の流れを意識すると内容が伝わりやすくなります。具体的な人数や状況を入れると説得力が増し、採用担当者の目に留まりやすい文章になります。
また、100字の場合は余分な表現を削り、結論を先に示すことが効果的です。限られた枠内で端的にまとめる練習をすると、他の文字数指定にも応用しやすくなります。
②200字のエントリーシート例文
200字程度のエントリーシートでは、限られた文字数の中で自分の強みを端的に伝える必要があります。短い文字数だからこそ、要点を整理し、読み手が理解しやすい構成を意識することが重要です。
伝える内容を詰め込みすぎず、一番伝えたいエピソードに集中することで、読み手に印象を残すことができます。ここでは、大学生活での経験をもとにした一般的な例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学でのアルバイト経験を通じて、責任感と協調性を身につけました。飲食店で働いていた際には、ピーク時の混雑に対応するために、スタッフ同士で声を掛け合い効率的に業務を進めました。 また、新人スタッフが困っている場面では自らサポートし、全体の流れを滞らせないよう努めました。その結果、店長から「安心して任せられる」と評価をいただきました。 今後も周囲と連携しながら主体的に行動することで、御社に貢献したいと考えています。 |
《解説》
200字のエントリーシートでは、エピソードを1つに絞り、行動と成果を簡潔にまとめることが効果的です。
「どんな場面で」「どのように動いたか」「結果どうなったか」を押さえると、説得力のある文章になります。また、最後に自分の強みを今後どう活かしたいかを一言添えると、前向きな印象を与えやすくなります。
③300字のエントリーシート例文
エントリーシートを書く際に、300字程度は最も多くの企業で課される文字数の一つです。長すぎず短すぎない分量だからこそ、限られた文字数の中で自分の強みを端的に表現する工夫が求められます。
内容が薄いと印象に残りませんが、情報を詰め込みすぎても読みにくくなるため、適度なバランス感覚が大切です。
ここでは、大学生活でのアルバイト経験を題材にした、実際に使えるイメージの例文を紹介します。身近な体験をもとに「学び」や「成長」をどう整理するかの参考にしてください。
《例文》
| 私は飲食店でのアルバイトを通じて、チームで協力しながら目標を達成する力を培いました。 忙しい時間帯には一人で対応できない場面も多く、スタッフ同士が声を掛け合い、役割分担を工夫することが必要でした。 特に新人が加わった際には、業務を教えながら全体の流れを維持することに力を注ぎました。その結果、ピーク時の混乱を減らし、売上の向上にもつながりました。 この経験から、状況に応じて柔軟に行動し、周囲と連携して課題を解決する大切さを学びました。今後も積極的に周囲と協力し、組織全体の成果に貢献したいと考えています。 |
《解説》
この例文は、アルバイト経験を通じて「協調性」と「柔軟性」を示しています。同じテーマで書く際は、身近な出来事でも「行動」と「結果」を具体的に書き分けると、読み手に強い印象を残せます。
また、300字程度では一つの経験に絞り込む方が文章にまとまりが出やすくなります。経験の幅広さよりも、深掘りした一例を丁寧に書く意識を持つと評価されやすいでしょう。
④400字のエントリーシート例文
エントリーシートでは、制限文字数の中で自分の経験をわかりやすく伝えることが重要です。特に400字程度の設問は、多くの企業が志望動機や自己PRで用いる定番の分量となっています。
そのため、エピソードの背景から成果までをバランスよく盛り込み、読み手が納得できる構成にする必要があります。ここでは、大学生活でのサークル活動を題材にした具体的な400字例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学で所属しているテニスサークルにおいて、幹部として活動を円滑に進める役割を担いました。サークルは部員数が多く、練習や大会の日程調整が難しくなることがありました。 私はそこで、メンバーが参加しやすい環境を整えるために、スケジュールを見える化する仕組みを導入しました。 具体的には、オンライン上で誰でも確認できるカレンダーを作成し、参加希望や練習内容を共有できるようにしました。その結果、出席率が向上し、練習の質も高まりました。 また、意見交換の場を設けることで部員同士の関係もより良くなり、全体としてサークルの雰囲気が活発になりました。 この経験を通じて、私は課題を整理し、解決策を実行に移す行動力を培いました。今後はこの力を活かし、周囲と協力しながら成果を生み出せる社会人を目指していきたいと考えています。 |
《解説》
400字程度では経験の背景や具体的な工夫、成果までをしっかり盛り込めるため、成長の過程を明確に描くことが可能です。
同じテーマで書く場合は「課題→工夫→成果→学び」の流れを意識すると、読み手に伝わりやすい文章になります。
さらに、数字や改善前後の変化を示すと、取り組みの効果が具体的に伝わりやすくなり、採用担当者に強い印象を残すことができます。
⑤600字のエントリーシート例文
600字程度のエントリーシートは、最も一般的な分量の一つであり、具体的なエピソードを丁寧に描写しつつ、自分の強みや学びをしっかりと伝える必要があります。
分量があるからこそ話が広がりやすい一方で、内容が散漫になると読み手に伝わりにくくなります。そのため、課題→行動→結果→学びの流れを意識しながら、端的かつ具体的にまとめることが重要です。
ここでは、部活動での取り組みを題材にした例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学4年間、テニスサークルで活動し、主に大会運営と練習環境の改善に力を注ぎました。入学当初は人数が多いものの参加率が低く、活気に欠ける状況でした。 そこで、私はまずメンバーの意見を集め、全員が楽しめる練習メニューを考案しました。また、大会参加を目標に掲げ、週ごとに達成度を確認する仕組みを導入しました。 その結果、練習参加率は大幅に上がり、チームとして初めて地方大会でベスト8に進出できました。この経験を通じて、仲間の声を反映させながら目標を具体化し、実行に移す力を身につけました。 貴社でも同じように周囲と協力しながら課題を見極め、改善策を実行することで成果を出していきたいと考えています。 |
《解説》
600字では、エピソードを複数盛り込みながら一貫性を保つことがポイントです。数字や成果を入れると具体性が増し、採用担当者にあなたの努力や成長がより鮮明に伝わります。
また、最後の結びでは企業で活かせる力にしっかりとつなげることで、自己PRと志望動機を兼ね備えた完成度の高い文章になります。
⑥1000字のエントリーシート例文
1000字程度のエントリーシートは、学生時代の経験をより深く掘り下げ、課題に直面した状況や具体的な行動、成果、学びを丁寧に表現することが求められます。
長文だからこそ「ストーリー性」と「論理性」の両方を意識することで、読み手に強い説得力を与えることができます。ここでは「学生時代に力を入れた経験」を題材とした例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学のサッカーサークルで副キャプテンを務め、チームの目標達成に向けて主体的に行動しました。 私たちのサークルは全国大会出場を目指していましたが、当初は練習への参加率が低く、組織としてまとまりに欠けていました。 私はまずメンバーの意識を高めることが必要だと考え、全員が参加しやすい練習環境を整えることから始めました。 授業やアルバイトの都合で参加できない人が多かったため、練習日程をオンライン上で共有し、意見を取り入れて柔軟に調整しました。 また、練習メニューについても上級生と下級生が共に取り組める内容に工夫し、全員が役割を持てるようにしました。 その結果、練習参加率は大幅に向上し、チーム全体の雰囲気も改善しました。最終的には全国大会への出場は叶いませんでしたが、地方大会で過去最高成績を収めることができました。 この経験から、目標に向かってチームをまとめるためには、一人ひとりの状況を理解し、全体最適を意識して行動することが大切だと学びました。 私はこの学びを社会に出てからも活かし、組織の成果に貢献していきたいと考えています。 |
《解説》
この例文では「課題→工夫→成果→学び」という流れで記述しており、1000字でも一貫性が保たれています。
文字数が多い場合は、経験の背景や工夫の詳細を厚く描写しつつ、最後は社会でどう活かすかまで触れると、説得力が高まります。
また、途中で数値や具体的な変化(参加率の向上や大会成績など)を示すことで、文章に具体性と信頼性が加わります。長文執筆では「抽象」と「具体」のバランスを意識することが重要です。
エントリーシートの文字数対策を実践に活かす

エントリーシートの文字数は、単なる形式的な条件ではなく、応募者の熱意や思考力を示す重要な要素です。実際に、文字数の8割以上を埋めることは採用担当者への誠実さのアピールにつながります。
また、制限がない場合でも300〜400字を目安に構成し、内容の濃さと簡潔さを両立させることが評価につながります。
一方で文字数が超過する場合は冗長な表現を削除し、逆に不足する場合は具体的なエピソードや成果を掘り下げることで厚みを加えることが効果的です。
さらに、自己PRや志望動機など企業が重視する項目に重点を置き、読みやすさや誤字脱字の確認を怠らないことも不可欠です。
こうした工夫を積み重ねることで、文字数を適切に管理しつつ自分の強みを最大限に伝えるエントリーシートを作成できます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













