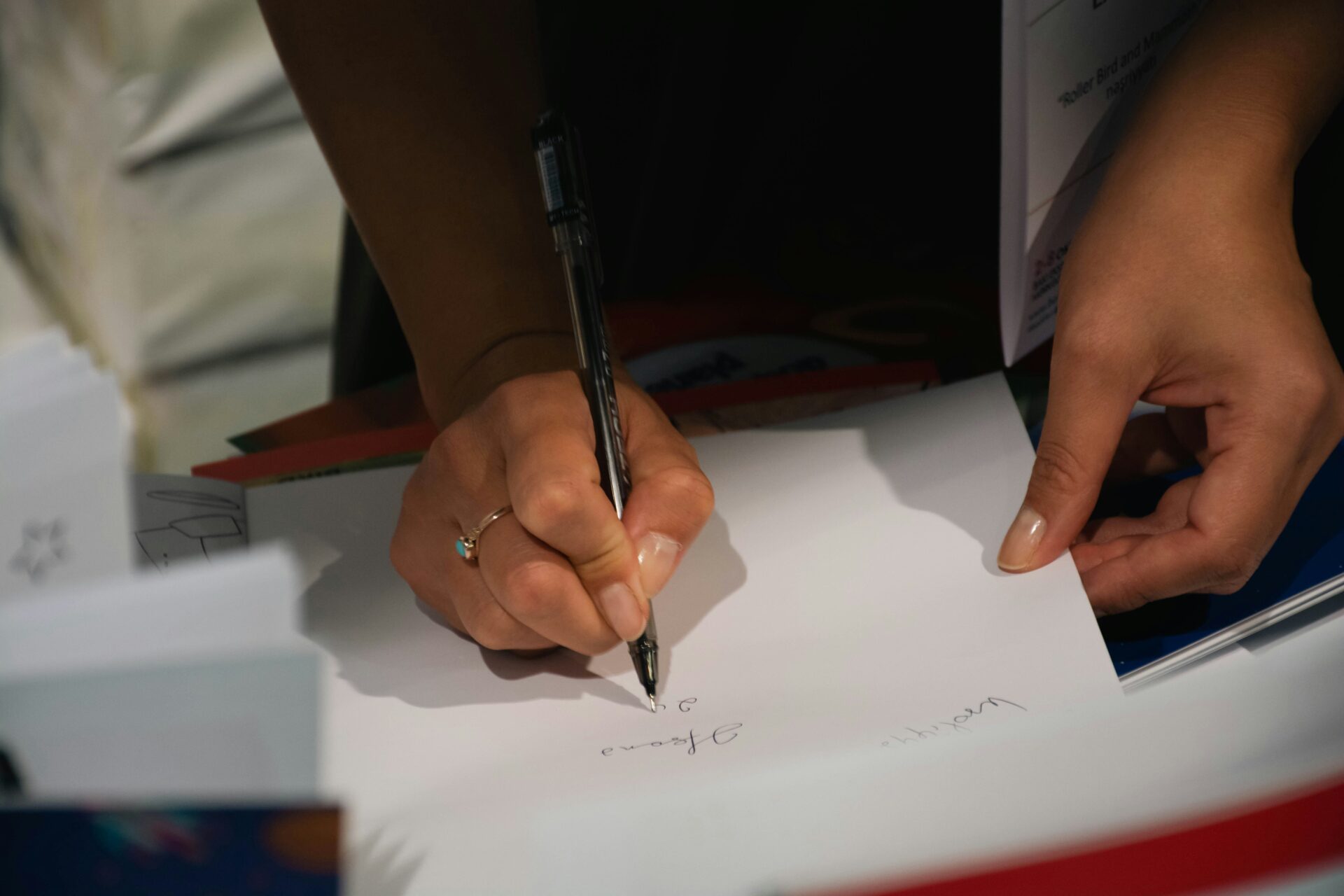ライターに向いている人の特徴10選|適性と成功の秘訣を徹底解説
ライターという職業に興味がある方は多いですが、実際に向いているかどうかは人それぞれ。ライターとして活躍するためには、必要なスキルや特徴を理解しておくことが重要です。
本記事では、ライターに向いている人の特徴を中心に、未経験からライターになるためのステップや、ライターとして働く際のメリット・デメリットについても詳しく紹介します。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
ライターに向いている人の特徴

ライターを目指す就活生にとって、自分がこの仕事に向いているかどうかは気になるところです。ここでは、ライターとして活躍しやすい人の特徴を具体的に紹介します。
それぞれの資質がなぜ大切かをわかりやすく解説するので、進路選択の参考にしてください。
- 文章を書くことが好きな人
- 情報収集やリサーチが得意な人
- 論理的に物事を考えられる人
- 継続力や自己管理能力がある人
- 相手の立場を想像できる人
- 細かい作業が苦にならない人
- 向上心を持ち学び続けられる人
- インターネットやデジタルツールに抵抗がない人
- 柔軟に考え方を変えられる人
- 自己主張よりも客観性を重視できる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①文章を書くことが好きな人
文章を書くことが好きであることは、ライターにとって基本であり大きな強みです。表現すること自体に喜びや達成感を感じられることが、仕事を続ける上で欠かせません。
日々の業務は執筆が中心のため、「書くのが好き」と思える人は作業そのものを楽しめるでしょう。好きだからこそ探究心が芽生え、表現を工夫する姿勢も自然に身についていきます。
こうした意欲はスキル向上につながり、他のライターとの差別化にも有効です。逆に、苦手意識がある場合は執筆が負担となり、成果が安定しにくくなります。
「好き」という感情は仕事を長く続けるためのエネルギー源です。好きなことを仕事にできる喜びは、技術以上にやりがいを生み出し、文章を通して情熱を伝えられるでしょう。
②情報収集やリサーチが得意な人
ライターの仕事は、文章を書くことだけではありません。実際には、書き始める前の「調べる力」が記事の質を大きく左右します。
テーマに沿って信頼できる情報を探し、要点を的確に整理する力のないライターは、内容が浅く、読者にとって価値の低い記事を作りかねません。
優れたリサーチ力を持つ人は、ネット上のの信頼できる情報を選び取るだけでなく、書籍や論文、一次情報まで丁寧に確認できるものです。
さらに背景や文脈を理解できれば、事実の羅列ではなく深みのある文章になります。興味を持って調べ、新しい知識を得る喜びを感じられる人には、特に向いた職業です。
③論理的に物事を考えられる人
読者に伝わる文章を書くには、感情や雰囲気だけでなく、筋道立てて話を展開する論理的思考力が欠かせません。文章の構造が明確であるほど、読み手は安心して読み進められます。
情報を整理し、適切な順序で提示する力が求められるのです。論理的に考えられる人は、主張と根拠のバランスを保ちながら、説得力のある記事を構成できるでしょう。
複雑な情報や難しいテーマでも、論理の流れに沿ってわかりやすく説明できれば、読みやすく信頼される文章になります。これにより、読者の満足度も高まるでしょう。
論理的思考は文章だけでなく、仕事全体の進め方にも役立つスキルです。構成や因果関係を意識できる人は、書くほどに信頼を積み重ねられるでしょう。
④継続力や自己管理能力がある人
ライターの仕事は、外から見ると自由な働き方に見えるかもしれませんが、実際は地道さと根気が必要です。案件ごとに締切があり、自己管理を怠ると信頼を損ねる恐れもあります。
継続力のある人は、一時的なやる気に頼らず、習慣としてコツコツ作業を進められるものです。自己管理ができれば、タスクを細かく分け、優先順位をつけて計画的に進められます。
さらに、集中力が落ちる時間帯を避けるなど、自分なりの工夫で成果を出すことが可能です。体調や気分に左右されずに進められる姿勢は、信頼構築にも直結します。
地道な作業を日々積み重ねられることは、派手さはなくても確実な武器になるものです。継続と信頼こそ、ライターとして長く活躍するための土台といえるでしょう。
⑤相手の立場を想像できる人
ライターにとって文章力と同じくらい重要なのが、「読者目線」です。読者が何を期待して記事を読むのか、どんな言い回しや構成なら理解しやすいかを想像できる力は、文章の質に大きく影響します。
一方的な発信ではなく、読み手との対話のつもりで文章を書くことが、読者にとって「読みやすい」「わかりやすい」と感じてもらえるポイントになります。
例えば、専門的な用語を使う場合でも、読者の知識レベルに応じた解説を入れたり、例え話を交えたりする工夫ができれば、読み手の理解度が格段に上がります。
相手を思いやる気持ちがある人は、自然と文章にもその姿勢が表れるものです。読者の反応を想像しながら書ける人ほど、共感や信頼を得やすくなるでしょう。
情報を一方的に伝えるだけではなく、「誰かのために書く」ことを楽しめる人には、ライターの適性があります。
⑥細かい作業が苦にならない人
ライターの仕事には、文章を書く以外にも多くの細かい作業があります。誤字脱字の確認や文体やトーンの整合性、句読点のバランス、SEOキーワードの埋め込み、リンクチェックなども重要です。
こうした確認作業を面倒に感じず、「文章の完成度を高めるための最後の磨き」として楽しめる人は、質の高い記事を継続的に生み出せるでしょう。見えない部分での努力が読みやすさを支えます。
少しの違和感や読点の打ち方に敏感であれば、読み手のストレスを減らし、伝えたい内容をより自然に届けられるものです。細部への意識は信頼にも直結するでしょう。
逆に全体の流ればかりを重視し、細部をおろそかにすると評価は下がります。文章の微調整をいとわない姿勢こそ、ライターとしての武器になるでしょう。几帳面さや完璧主義が良い方向に働く仕事でもあります。
⑦向上心を持ち学び続けられる人
ライターは学びの連続です。文章力だけでなく、読者ニーズや検索エンジンの仕様、媒体ごとの書き方、専門分野の知識など、必要なスキルは多岐にわたります。
常にアンテナを張り、新しい知識を吸収する姿勢がなければ、業界で長く活躍することは難しいでしょう。変化に対応する柔軟さも欠かせません。
向上心がある人は、他のライターの文章を分析したり、自分の過去記事を読み返して改善点を探したりするものです。学びを継続することで、専門性の高い分野にも挑戦しやすくなるでしょう。
現状に満足すると文章の質が停滞し、読者に飽きられる恐れがあります。継続的に学び、進化を楽しめる人に向いている職業でしょう。
⑧インターネットやデジタルツールに抵抗がない人
現代のライター業務は、ほぼすべてがデジタル環境で行われます。情報収集はWeb検索、原稿作成はWordやGoogleドキュメント、納品はクラウド、やり取りはチャットツールを活用するのが一般的です。
これらのツールに苦手意識があると、作業効率が落ちてしまい、結果的に仕事の質にも影響します。一方で、これらを使いこなせる人は多くの場面で優位に立てるでしょう。
スケジュール管理やファイル整理、リサーチ速度の面でもアドバンテージを得られます。特に在宅ワークでは、デジタルリテラシーが成果に直結するでしょう。
AIツールや支援サービスなど、新技術は次々登場しています。変化を楽しみながら試せる人ほど、業務のスピードやクオリティをさらに高められるでしょう。
⑨柔軟に考え方を変えられる人
ライターは、自分の考えや意見だけを押し通す職業ではありません。記事の目的や読者層、クライアントの意向に応じて、文体や主張の強さ、切り口を調整する必要があります。
思い込みに固執せず、状況に応じて考え方を切り替えられる柔軟さが求められるのです。修正依頼を受けた際に理由を分析できる人は、改善の機会だと捉えて成長できます。
読者の反応を見て「この表現は伝わりにくかった」と分析できれば、次回以降に反映できるでしょう。こうした姿勢は、文章の質を高める循環を生み出します。
反対に、自分の書き方にこだわりすぎるとニーズとズレが生じるでしょう。環境の変化や新しい要望に柔軟に対応できる力は、長く活躍するための大きな武器です。
⑩自己主張よりも客観性を重視できる人
ライターは、自分の意見や感情よりも、読者が必要とする情報を正確かつ冷静に伝えることが重要です。多くの案件では、主観よりも客観的な情報提供が求められます。
客観性を持てる人は、信頼性のあるデータや第三者の視点をうまく引用し、安心して読める文章を書けるでしょう。公平な視点で構成された文章は、幅広い層の読者に届きやすくなります。
もちろん、自分の考えを持つことは大切です。しかし、それを適切に整理し、情報の一部として冷静に提示できる人こそ、プロフェッショナルといえるでしょう。
感情に流されず、事実に基づいたライティングを意識できる人は、ジャンルを問わず信頼を得られます。これは長く活動するうえで欠かせない資質です。
ライターに向いていない人の特徴

ライターという仕事は、一見自由でクリエイティブに思えるかもしれませんが、実際には多くの適性が求められます。
ここでは、ライターとして活動していくうえで、向いていないとされる人の特徴を紹介します。
- すぐに結果を求める人
- 注意力が散漫な人
- 人とのコミュニケーションが苦手な人
- 一人での作業が苦手な人
- 自己表現が強すぎる人
- スケジュール管理ができない人
- 読者目線を意識できない人
- 学ぶ姿勢がない人
- フィードバックを受け入れられない人
①すぐに結果を求める人
ライターは、即効性のある結果を求める人にはもどかしさを感じやすい職業です。記事を書いても、すぐに多くの人に読まれるとは限らず、検索順位が上がるまで時間がかかります。
特にSEO記事は、成果が数字に表れるまで時間差があるでしょう。短期間での反応を期待すると挫折しやすく、継続的な学習や実践を通して成長する姿勢が必要です。
文章力の向上や構成力の習得、読者ニーズの理解といったスキルは一朝一夕には身につきません。地道な積み重ねが信頼や評価につながることを理解する必要があります。
結果を急ぎすぎると自己流に走ったり、実力が伸びる前に辞めたりしてしまう恐れがあるのです。努力のプロセスを楽しみ、少しずつでも前進できる人こそが、この仕事に向いています。
②注意力が散漫な人
文章作成で重要なのは、ただ言葉を並べることだけではありません。文法の正しさ、語句の使い分け、読者への思いやり、誤字脱字のチェックなど、細部の積み重ねが高品質な文章を生みます。
注意力が散漫な人は、こうした細部への意識が弱く、読み手に不親切な文章を書いてしまいがちです。特にWebライティングでは、小さな誤りが離脱につながります。
数字の表記ゆれ、漢字とひらがなの使い分け、改行位置など気を配る点は多くあるのです。これらを無視すると、どれだけ内容が良くても伝わらない文章になってしまいます。
校正作業もライターの重要な仕事です。丁寧に言葉を扱い、細かい部分まで気を配れる人が、読者に信頼される文章を書けます。
③人とのコミュニケーションが苦手な人
ライターは一人で作業する印象がありますが、実際には他者とのやり取りが欠かせません。クライアントとの要件確認や編集者との打ち合わせなど、多くの場面で円滑なコミュニケーションが必要です。
コミュニケーションを拒んでしまうと、案件の理解不足や認識のズレが生じ、記事の方向性が大きく外れる恐れがあります。確認を怠れば誤解が発生しやすくなるでしょう。
その結果、修正の手間が増えたり、信頼を失ったりすることもあります。文章力以上に「伝える力」や「聞く力」が評価される場面も少なくありません。
また、メールやチャットなどのやり取りも丁寧さが求められます。相手に失礼のない言葉遣いやわかりやすい表現ができなければ、依頼が減る可能性があるでしょう。人と関わることに前向きであることも、立派なスキルの一つです。
④一人での作業が苦手な人
ライターの仕事は基本的に一人で進める場面が多く、自らスケジュールを立てて作業する必要があります。自由度が高い反面、常に自分を律する姿勢が求められるのです。
誰かに指示されないと動けないタイプの人には、負担が大きく感じられるでしょう。納期が迫っているのに作業が進まず焦ったり、作業に集中できず他のことに気を取られたりすることもあるものです。
ライターは、ネタ探しから情報収集、文章構成、執筆、校正までを一人でこなす場面が多く、孤独やプレッシャーと向き合う必要があります。頼れる人がいない状況も少なくありません。
一方で、一人の作業時間を自分のペースで使いこなせる人には適した環境です。自己管理力が高く、集中力を維持できる人ほど、着実に成果を出しやすい職業といえます。
⑤自己表現が強すぎる人
ライターに必要なのは、自分の考えを押し通す力ではなく、読者やクライアントの意図に寄り添った「伝える力」です。独自の視点や個性は重要ですが、それらが強すぎると文章が独りよがりになってしまいます。
文章はあくまでコミュニケーションの手段であり、自己満足の場ではありません。商業ライティングでは「誰に」「どんな情報を」「どう届けるか」が最優先されます。
たとえば、自分の経験談を長く語っても、読者にとって有益でなければ、記事から離脱されるでしょう。記事の意図や目的に沿わない自己主張は、記事全体の品質を下げる原因にもなります。
成果を出すには、相手の目的をくみ取り柔軟に対応することが不可欠です。必要な場面で適切に主張できる人こそ、プロとして信頼されるライターになれます。
⑥スケジュール管理ができない人
ライターの仕事では、納期を守ることが信頼の基本です。文章力があっても締切を守れなければ、継続的な依頼は期待できません。
複数の案件を同時に抱える場合、進捗の管理や作業時間の見積もりが甘いと遅れやミスにつながります。締め切り当日に焦って仕上げると、クオリティが低下してしまうでしょう。
体調不良や急用などの予測不能な事態に備え、余裕を持った計画を立てる意識も必要です。ギリギリの計画では、わずかなトラブルで全体が崩れてしまいます。
ライターにとって、スケジュール管理は「能力」ではなく「信用」です。工程を事前に組み、優先順位を決めて取り組める人が、安定した働き方と継続的な依頼を得られます。
⑦読者目線を意識できない人
文章は「自分のため」ではなく「誰かに読んでもらうため」に書くものです。読者目線が欠けると、情報が整理されず、自己中心的で伝わりにくい文章になってしまいます。
たとえば、初心者向けの記事なら、専門用語に説明を加える必要があります。疑問解消できなければ、読者が離脱する原因となり、記事の価値も下がるでしょう。
また、構成が複雑すぎたり、一文が長すぎたりする文章も理解を妨げます。読者目線とは、情報の順序や適切なトーンなどを設計する意識を持つことです。
これができる人は、読み手との距離を縮められます。読者の理解や感情に寄り添うことが、読みやすさと共感を生む鍵となるものです。
⑧学ぶ姿勢がない人
ライターは、常に変化する情報や環境に対応する必要があります。検索エンジンの仕様やSNSのトレンド、読者の関心は日々移り変わっているものです。
古い知識のままでは評価を得られません。数年前のSEO対策が今では逆効果になることもあり、新しい情報を学び直す姿勢が欠かせないでしょう。
過去の記事を見直して改善点に気づける人は成長できます。反対に、学ぶ気持ちがなければ、同じ失敗を繰り返し伸び悩むでしょう。
新しいテーマに挑戦し、他分野の文章を読む習慣を持つことで表現力は広がります。変化をチャンスと捉え、常にアップデートできる人が価値を高めるでしょう。
⑨フィードバックを受け入れられない人
ライターの仕事は、納品して終わりではありません。クライアントや編集者からの指摘を反映し、記事をより良く仕上げる過程が欠かせないものです。
指摘を素直に受け入れられない姿勢では、スキル向上も信頼の構築も難しくなります。聞き入れようとしない態度は関係の悪化を招き、依頼が減る原因にもなるでしょう。
フィードバックは欠点を突かれるだけでなく、改善の機会でもあります。他人の視点を取り入れれば、自分では気づけない弱点を補えるでしょう。
感情的にならず、迅速かつ丁寧に対応できる人は信頼を得やすく、案件の継続にもつながります。冷静に受け止め改善できる力が長期的な活躍を支えるでしょう。
ライターの主な仕事の種類

ライターと一口に言っても、その仕事内容はさまざまです。就活生の中には「書く仕事」とひとくくりに考えている方もいるかもしれません。
しかし、実際には媒体や目的によって求められるスキルや文体が異なるものです。ここでは、ライターの代表的な仕事の種類を紹介し、それぞれの特徴ややりがいを分かりやすく解説していきます。
- Web記事のライティング
- 取材・インタビュー記事の作成
- セールスライティング
- SEOライティング
- SNSや広報系コンテンツの執筆
- シナリオ・脚本のライティング
①Web記事のライティング
Web記事のライティングは、ライター業務の中でも最も一般的な仕事です。企業ブログや情報メディア、就活サイト、コラムなど幅広い分野でニーズがあります。
テーマに沿って読者が求める情報を分かりやすくまとめる力が求められるでしょう。基本的な文章力に加え、リサーチ力や構成力も欠かせません。
記事のボリュームや納期が明確な場合が多いため、スケジュール管理や安定した執筆力があると重宝されるでしょう。冒頭で惹きつけ、最後まで読ませる構成も重要です。
読み飛ばされやすいネット環境では、見出しや改行の工夫が結果に影響します。引用元や一次情報を正しく扱う意識を持てば、初心者にも実績作りの場として適した分野です。
②取材・インタビュー記事の作成
取材やインタビュー記事は、対象となる人物や企業に直接アプローチし、リアルなエピソードや本音をもとに魅力的な記事へ仕上げる仕事です。文章力に加え、対話力や柔軟性も求められます。
準備段階では、相手の経歴や実績を徹底的に調査するものです。質問は単なる事実確認にとどめず、相手の考えや価値観を引き出す工夫が必要となります。
本番では想定外の展開も起こるため、その場で判断できる柔軟さが不可欠です。記事に仕上げる際は、話した内容を書き起こすだけでは不十分で、構成や表現を整える編集力も重要な要素といえます。
人とのつながりを築きながら、言葉で魅力を引き出す喜びを感じられる人にとって、大きなやりがいを得られる分野といえるでしょう。
③セールスライティング
セールスライティングは、商品やサービスの魅力を最大限に伝え、読み手の購買行動を促す文章を作成する仕事です。特徴説明だけでなく、悩みや欲求、理想に寄り添う姿勢が求められます。
感情に訴える技術やマーケティング視点を持つ人にとっては、非常に相性の良い分野でしょう。活用場面はランディングページやセールスレター、広告コピー、ECサイトの商品説明など多岐にわたります。
何が読み手の「刺さる言葉」になるかを分析し、訴求力の高い構成を練る必要があるでしょう。「いますぐ申し込みたい」と感じさせる導線設計も重要な要素です。
誇張しすぎた表現や実態と異なる情報は逆効果になるため、誠実さとのバランスが欠かせません。成果が売上という数字で示されるため、実績が評価や報酬に直結しやすい分野です。人の心を動かす表現力を磨きたい人におすすめです。
④SEOライティング
SEOライティングは、検索エンジン上での記事順位を上げることを目的とした文章作成の仕事です。単にキーワードを盛り込むだけでは不十分で、読者の求める情報に的確に応える必要があります。
検索意図を読み取り、的確な情報を自然な文脈に組み込みながら提供する技術が求められるでしょう。見出し構成や内部リンク、メタディスクリプションなどの知識もあると有利です。
SEOはアルゴリズムの変化に左右されるため、常に最新情報をチェックする姿勢が重要でしょう。成果は順位やアクセス数、クリック率など数値で明確に把握できます。
記事公開後のデータを分析し改善を重ねる運用スキルも必要です。戦略的に情報を届けたい人やWebライターとしてのスキルの幅を広げたい人にとって実践的で価値ある分野といえます。
⑤SNSや広報系コンテンツの執筆
SNSや広報系の文章作成では、端的かつ魅力的な表現でメッセージを届ける力が必要です。特にSNSは一文一文が短くなりやすく、限られた文字数でどう伝えるかが勝負になります。
プラットフォームごとに好まれる文体や表現は異なりるものです。Instagramではビジュアルを意識したコピー、X(旧Twitter)では速報性や話題性が重視される傾向があります。
投稿のタイミングや流行語の選び方にも注意が必要です。広報分野では企業イメージを守るための慎重な言葉選びと、それと同時に印象に残るための工夫が求められます。
事実の提示だけでなく共感やストーリー性を加えることで、多くの人に届くコンテンツとなるでしょう。タイムリーな情報発信が得意な人、トレンドをつかむのが好きな人には、大きなチャンスがある分野です。
⑥シナリオ・脚本のライティング
シナリオや脚本のライティングは、物語を構成し、登場人物やストーリーを生み出す創作性の高い仕事です。映像作品やゲーム、WebCM、アニメなど対象は幅広くあります。
文章力だけでなく、演出や映像演技の流れを意識して構成する総合力が求められるでしょう。自然な会話に聞こえるセリフの技術や、ストーリーに起伏を与える構成力、視聴者を引き込む展開づくりなど、捜索に対するこだわりも重要です。
特にゲームやドラマでは複数パターンを同時に用意することもあり、柔軟な発想と粘り強さが必要になります。多くの場合、チームでの制作となるのも特徴です。
自分の意見だけを押し通さず、他者と意見をすり合わせて完成させる協調性も欠かせません。完成作品が多くの人に届く瞬間は大きな達成感が得られます。「自分の発想をかたちにする」というやりがいのある分野といえるでしょう。
未経験からライターになるには?

未経験からライターを目指す就活生にとって、「何から始めればいいのか」「本当に自分にできるのか」といった不安はつきものでしょう。
しかし、正しいステップを踏めば、経験がなくてもライターとしての一歩を踏み出すことは十分可能です。ここでは、必要な準備や具体的な行動について段階的に解説していきます。
- 基本的なライティングスキルを学ぶ
- ポートフォリオを作成する
- クラウドソーシングで案件を獲得する
- ブログなどで実績を積む
- 出版社や編集部に企画を持ち込む
- ライター向け講座やセミナーを受講する
- SNSやnoteを活用して発信する
- メンターや先輩ライターに相談する
①基本的なライティングスキルを学ぶ
ライターを目指すなら、まず必要なのは「読み手に伝わる文章力」です。ただ長く書くだけでなく、情報を整理し、わかりやすく説得力ある形で届けるスキルが求められます。
PREP法(結論→理由→具体例→結論)や5W1H、SEOの基礎など、文章の型を知るだけでも読みやすさは大きく向上するでしょう。文章を書くことに慣れていても、ライティングの目的を意識することが重要になります。
自分が書きたいことではなく、相手が求めている内容にフォーカスする姿勢が大切です。学び方は、ライティング関連の書籍やWeb教材、講義動画など多様な方法があります。
文章添削サービスを使い客観的なフィードバックを受けるのも有効です。自己流に頼らず、正しい知識を取り入れつつ実践を重ねれば、成長が早まります。読みやすく、伝わる文章を少しずつ書けるようになることを意識して取り組んでみてください。
②ポートフォリオを作成する
未経験から仕事を得るには、自分の「書ける力」を可視化することが欠かせません。その方法として最も効果的なのが、ポートフォリオの作成です。
ポートフォリオとは、自分が書いた記事をまとめた実績集であり、クライアントに自分のスキルを伝えるツールです。実績がないうちは、架空のテーマで記事を用意しても構いません。
たとえば「大学生の時間管理術」や「おすすめのカフェ5選」など、自分が詳しい分野を選べば取り組みやすくなります。文章の構成や見出しの使い方、情報の整理を意識すると完成度が高まるでしょう。
記事はWordやGoogleドキュメントでまとめてPDF化し、ブログやnoteに掲載すればオンライン公開も可能です。ジャンルを分けておけば、対応の幅広さもアピールできます。自分の文章を形にして公開する経験自体が大きな成長になります。
③クラウドソーシングで案件を獲得する
未経験からでも挑戦しやすい方法のひとつが、クラウドソーシングの活用です。ランサーズやクラウドワークスなどには、初心者歓迎の案件が多く掲載されています。
実績がない状態でも応募でき、報酬を得ながら経験を積める貴重な機会となるのです。まずはプロフィールを作り込み、自己紹介や志望動機、得意分野、ライティングへの意欲を明確に示しましょう。
ポートフォリオを添えると信頼度が高まります。応募時には定型文ではなく、募集内容に沿った提案文を作成することが重要です。具体的な経験や切り口を提示すると効果的です。
納期やマナーを守る姿勢も評価されます。単価が低くても丁寧に対応すれば高評価がつき、次の案件につながるでしょう。実績を重ねながら仕事の流れを体得することが成長の近道です。
④ブログなどで実績を積む
自分のペースで発信できるブログやnoteは、ライター志望者にとって絶好の練習場です。実際に記事を書く機会がなくても、自由にテーマを選び、文章を継続的に書くことで実践力を鍛えられます。
書く内容は特別なものでなくても構いません。大学生活の工夫や就活の体験談、趣味に関するレビューなど、身近なテーマから始めましょう。
読み手の目線を意識し、共感や学びにつながる文章を目指すことがポイントです。ブログを続ける中で、自分にとって書きやすいジャンルや構成が見えてくるでしょう。
記事のPV数やSNSの反応を通じて、読者の関心がわかり、読者ニーズを意識したライティングの訓練にもつながります。noteはSNSとの連携がしやすく、拡散も得やすいため初心者にもおすすめです。実績作りとスキル向上を両立できる手段を活用しましょう。
⑤出版社や編集部に企画を持ち込む
ライターとして活動する方法の一つに、出版社やWebメディアの編集部に自分の企画を提案する道があります。実績がなくても挑戦できるチャンスであり、自分の視点やアイデアが評価される場です。
単に「書きたい」だけではなく、「読者にとって価値のある提案」を形にすることが重要になります。企画書には、記事タイトル案や本文の構成、対象読者、提供する価値を明記にするとよいでしょう。
まずは、応募するメディアが対象とする読者層や記事のトーン、扱うジャンルを把握することが企画作りの第一歩です。企画書では、なぜそのテーマを選んだのか、自分がどんな視点や経験を持っているかも伝えると信頼性が増すでしょう。
たとえば、「大学生向けの節約術」や「就活と副業の両立法」など、自身のリアルな体験を基にした企画は説得力があります。仮に不採用となっても、提案する行動力そのものが、今後のライター人生の大きな糧となるでしょう。
⑥ライター向け講座やセミナーを受講する
効率よく基礎を習得したい人には、ライター向けの講座やセミナーの受講が非常に効果的です。独学では気づきにくいクセや間違いを、講師からのフィードバックで修正できます。
特に初心者の場合、文章構成やリズム、表現の引き出しに限界を感じることが多いため、体系的に学ぶことで成長が加速するでしょう。オンライン形式や対面形式など、自分に合った学習スタイルを選べるのも魅力です。
受講することで、スキルだけでなく、講師や受講生とのネットワークも得られます。仕事の紹介や情報交換など、つながりから広がる可能性も多くあるでしょう。
費用面が不安なら、無料体験や一部公開の講座で試してみるのも良い方法です。実際の授業の雰囲気を知ることで、自分に合っているか判断しやすくなります。プロの目で見てもらうことで自信と確実な成長が得られます。
⑦SNSやnoteを活用して発信する
現代のライターにとって、SNSやnoteを使った発信力は大きな武器となります。特に未経験者の場合、過去の実績が少ない分、日々のアウトプットで存在感を示すことが重要です。
SNSでの投稿がきっかけとなり、ライターとしての仕事を依頼されることも少なくありません。たとえば、X(旧Twitter)で記事リンクを投稿し、気づきや意見を加えることで、関心を持った人が記事を読むようになります。
また、noteは記事を公開できるプラットフォームとして、ブログ感覚で気軽に始められるでしょう。ただ書くだけでなく、「誰のために」「何を届けるのか」を意識することが大切です。
読者の共感を得る工夫をすることで、文章力は確実に伸びていきます。テーマやタイトル選び一つで読まれる確率が大きく変わるため、試行錯誤を重ねることが必要です。情報発信の積み重ねが信頼や仕事へとつながります。
⑧メンターや先輩ライターに相談する
未経験からライターを目指す際、最も頼りになるのが、すでに現場で活躍している先輩ライターです。実際に仕事をしている人から話を聞くことで、ネットではわからないリアルな情報を得られるでしょう。
相談相手を見つける方法はさまざまで、大学のOB・OGを調べたり、SNSでライター活動をしている人にメッセージを送ったり、オンラインコミュニティに参加したりするといった方法があります。
最初は少し勇気がいるかもしれませんが、「話を聞きたい」という姿勢で丁寧に連絡すれば、意外と応じてくれる人も多いものです。実際に話を聞くことで、今後直面するかもしれない課題への対処法がわかります。
信頼関係が築ければ、仕事を紹介してもらえることもありますが、最初からそれを期待せず学ぶ姿勢が大切です。メンター的な存在との出会いが、あなたのライター人生を大きく後押ししてくれるかもしれません。
ライターの働き方

ライターの働き方にはいくつかのパターンがあり、それぞれに向き不向きがあります。安定を重視する人もいれば、自由を求める人もいます。ここでは代表的な3つの働き方を紹介します。
- 企業の正社員として働く
- 副業としてライティングを行う
- フリーランスとして独立する
①企業の正社員として働く
企業の正社員としてライターを務める場合、安定性や福利厚生といった安心感が得られます。特に新卒や未経験者にとって、編集体制が整った環境で仕事を始められる点が魅力です。
企業によっては、研修やOJT制度が充実しているため、ライティングの基礎に加え、SEOや編集技術、コンテンツマーケティングなどの幅広い知識が身につきます。
社内でのやりとりや取材、他職種との連携を通じて、ビジネスマナーやスケジュール管理能力も自然に鍛えられるものです。これらのスキルは将来、フリーランスや別業種への転職の際にも役立つでしょう。
一方、担当ジャンルやプロジェクトは会社の方針に左右されます。自分の興味や専門分野と異なる内容を扱う場合もありますが、安定した仕事が得られる点では長期的なキャリアを積みたい人に向いているでしょう。
②副業としてライティングを行う
副業ライターは年々増加しています。学生や会社員が空き時間を活用して文章を書き、報酬を得るスタイルは、スキルアップと収入確保の両面でメリットが大きいです。
クラウドソーシングサービスやSNS経由で案件を見つけやすくなり、ライティングの敷居が下がっています。副業ライターの魅力は、本業のリスクを負わずに始められる点と、複数ジャンルに挑戦できる点です。
エンタメ系、ビジネス系、教育系など、それぞれの分野で求められる知識や書き方が異なりますが、トライアンドエラーを繰り返しながら自分に合うテーマや文体を見つけられます。
しかし、納期のプレッシャーや疲労の蓄積に悩むこともあります。仕事や学業との両立には、時間管理や優先順位づけが欠かせません。副業として始めることは、ライターの仕事を体験する手段となります。
③フリーランスとして独立する
フリーランスライターとして独立する最大の利点は、時間やテーマを自分で自由に選べることです。好きなジャンルに特化すれば、専門性を高めつつ自分らしいスタイルを築けます。
実績が増えると、単価が上がったり、継続案件の依頼が来たりと、収入面でも成長を感じやすくなるでしょう。しかしその反面、フリーランスには大きな責任も伴います。
営業やスケジュール管理、納品、請求など、すべての業務を一人でこなすため、会社員時代には感じなかったプレッシャーが生まれるかもしれません。
収入が月ごとに変動することもあり、金銭面で不安を感じやすい点もデメリットです。将来的に独立を目指すなら、副業や正社員としてスキルを磨いたうえで段階的にステップアップするのが現実的といえます。
ライターの年収
ライターの年収は、働き方や経験、スキルによって大きく変わります。
就職活動中の学生にとっては、ライターという職業が現実的な選択肢なのか、将来的に安定した収入を得られるのかが気になるポイントでしょう。
ここでは、初心者からプロまで、それぞれの働き方による年収の目安とその違いについて分かりやすく紹介します。
- 会社員ライターの年収
- フリーライターの年収
①会社員ライターの年収

会社員ライターの年収は、所属する企業の業界や規模、勤務地によって大きく異なります。新卒で出版社や編集プロダクション、Webメディアに就職した場合、最初の年収は250万円から350万円が一般的です。
これは他の業種と比較しても決して高くはありませんが、編集や企画などの業務経験を積むことで年収は徐々に上がります。大手メディア企業や広告代理店では、30代で年収500万円を超えるケースもあるのです。
特に、SEOやマーケティングの知識を持ち、記事の効果を意識して執筆できるようになると、社内でも重宝され昇進や昇給の機会が増えます。会社員として働くことの利点は、収入が安定していることや社会保険、福利厚生が充実している点です。
副業が許可されている企業も増えているため、本業で安定した収入を得ながら、副業ライターとして経験を広げる道もあります。文章を書くことが好きで、着実にスキルを磨きながら安定した生活を送りたい人には魅力的な選択肢です。
②フリーライターの年収
フリーランスとして活動する場合、収入は完全に自分の実力に依存します。特定の企業に雇用されているわけではないため、案件の獲得数や執筆の効率が年収を大きく左右するのです。
駆け出しのフリーライターは月収5万円〜10万円といった低収入で悩むことが多く、生活が不安定な期間が続くこともあります。しかし、実績を積み、得意なジャンルを確立できれば、年収は急増するでしょう。
中には、1記事あたり5万円以上の高単価案件をこなし、年収1,000万円を超える人もいます。特に専門性が高い分野(医療、法律、ITなど)は単価が高くなりやすいです。
収入が高いフリーライターほど、営業やスケジュール管理、経理などの裏方業務に多くの時間を割いています。自己管理能力や備えが必要となるでしょう。リスクや現実も理解したうえで、準備を整えてから一歩踏み出すことが大切です。
ライターに必要なスキル

ライターとして活躍するには、文章力だけでなく、読者のニーズを読み取り、的確に伝えるための総合的なスキルが求められます。
ここでは、ライターにとって重要なスキルを具体的に紹介していきます。
- 情報収集力とリサーチ力
- 分かりやすい文章力
- SEOやマーケティングの知識
- ビジネスコミュニケーションスキル
- 読者目線で構成を組み立てる力
- 継続して学び続ける力
- 納期を守るためのスケジュール管理能力
①情報収集力とリサーチ力
インターネットが普及し、情報があふれる現代では、ライターには質の高い情報を選別する力が求められます。
検索結果の上位に表示される情報が正しいとは限りません。信頼できるソースを見極める力が必要で、特に就活や業界解説などのテーマでは注意が必要です。
信頼できる情報源には、企業の公式サイトや政府の統計、専門家のインタビューなどがあります。これらを基に、自分なりに再構成する力が重要です。
さらに、複数の資料を見比べて情報の裏取りを行うことも大切でしょう。一次情報をうまく取り入れることで、記事に深みが加わり、差別化されたコンテンツが生まれます。
②分かりやすい文章力
読み手に伝わる文章を書くには、ただ言葉を並べるだけでは不十分です。文章にはリズムや構造があり、適切な順序や表現が必要になります。特にWeb記事では簡潔さが重要です。
複雑な言い回しや長すぎる文は避け、1文を短くすることを心がけましょう。1文が30文字を超えると読みづらさを感じやすくなるため、文章を短く区切ることが基本です。
接続語を適切に使うことで、文と文のつながりが自然になります。簡単な表現への言いかえも心掛けるべきです。また、語尾や文末表現のバリエーションを意識しましょう。
読者に寄り添った言葉づかいや表現を心がけることで、最後まで読んでもらえる文章に近づきます。
③SEOやマーケティングの知識
SEOの知識は、Webライターとして活躍するための必須スキルです。検索結果の上位に表示されるためには、キーワード選定や記事構成、見出しの使い方に工夫が必要でしょう。
例えば、「ライターに向いている人」というキーワードを狙う場合、そのキーワードをタイトルや見出し、導入文に自然に盛り込むことが重要です。これで検索エンジンが記事内容を認識しやすくなるでしょう。
ただし、キーワードを無理に詰め込みすぎると、読者が離脱してしまう可能性があります。SEOの目的はあくまで「検索から多くの読者に届くこと」であり、「読者にとって有益な内容であること」が前提です。
マーケティング観点で「誰がこの記事を読むのか」「どんな悩みを持っているのか」を考えることも重要です。SEOとマーケティングの知識を組み合わせることで、より効果的で価値ある記事を作ることができます。
④ビジネスコミュニケーションスキル
ライターの仕事は、文章を書くことが中心ですが、実は人とのやり取りも非常に重要です。クライアントや編集者との関係は、仕事の継続に大きく影響します。
依頼されたテーマの意図を正確に理解し、内容に反映させるには事前の確認や質問が欠かせません。「よくわからないけれど、書く」といった姿勢は、信頼を失う原因になります。
また、連絡のスピードや言葉遣いも大切です。ビジネスメールでは、簡潔で礼儀正しい文面を心がけ、「お世話になっております」「ご確認よろしくお願いいたします」などの基本表現を覚えておきましょう。
意思疎通がスムーズにできれば、仕事も円滑に進みます。コミュニケーションに不安がある場合は、まずはチャットやメールでのやり取りに慣れることから始めましょう。
⑤読者目線で構成を組み立てる力
良い記事とは、読者がストレスなく読み進められる記事です。そのためには、情報の順序や見せ方に対する工夫や、構成力が必要になります。特にWeb記事では最初の数秒で「読むかやめるか」を判断されることが多いため、結論を早めに提示しましょう。
PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を使うことで、論理の流れが明確になり、読者が内容を把握しやすくなります。しかし、毎回同じ構成では単調になってしまうため、箇条書きや図解を使うと、さらに読みやすくなります。
読者目線で記事を組み立てることは、単に「わかりやすく書く」ことではありません。読者が「どんな状態でこの記事を読んでいるか」を想像し、そのニーズに合わせて内容を整理することが大切です。
読者に寄り添いながら試行錯誤を続けることが、質の高い記事を書くための基盤となります。
⑥継続して学び続ける力
ライターとして成長し続けるためには、「常に学び続ける姿勢」が重要です。Web業界のトレンドや検索アルゴリズムは変化し続けており、数カ月前の書き方が評価されなくなることもあります。
例えば、Googleの検索評価基準のアップデートにより、「読者ファースト」のコンテンツがより高く評価されるようになりました。そのため、情報の網羅性だけでなく、読みやすさやオリジナリティも重視されるようになっています。
最新情報をキャッチし、取り入れる習慣が求められるでしょう。例えば、SEO関連の信頼できるブログをチェックしたり、専門家をフォローしたりすることが有効です。
また、他のライターの記事を分析して、その構成や内容がなぜ読まれるのかを考えることも効果的でしょう。さらに、自分の記事を振り返り、改善点を見つけて次に活かすことが大切です。
⑦納期を守るためのスケジュール管理能力
どれだけ良い記事を書いても、納期を守れなければライターとしての信頼は得られません。納期は単なる締切ではなく、ライターの「信用の証」です。特にフリーランスでは、納期を守れるかどうかが次回の依頼の有無に直結します。
スケジュール管理が苦手な人は、まず「自分の作業時間を可視化すること」から始めると効果的です。例えば、1,500字の記事を書くのに何時間かかるかを把握すれば、納期までに必要な余裕も見えてきます。
Googleカレンダーやタスク管理アプリを活用して、事前に「いつ何をするか」を決めておくと、管理がしやすくなるのです。複数の案件がある場合は、締切日から逆算してスケジュールを組みましょう。
また、突発的な予定やトラブルに備え、余裕を持ったスケジューリングも重要です。例えば、「納期の前日に提出することを目標にする」といった工夫で、多少のずれにも対応できます。
ライターとして働くメリット

ライターという仕事には、特定の場所に縛られずに働ける自由さや、自分の得意を活かせる楽しさがあります。未経験でも始めやすく、スキル次第で収入やキャリアの幅も広がっていく点が大きな特徴です。
ここでは、ライターとして働くうえで得られる代表的なメリットを紹介します。
- 場所を選ばずに働くことができる
- 自分の興味や得意を活かすことができる
- スキル次第で収入を増やすことができる
- 幅広いキャリアパスを築くことができる
- 未経験からでも挑戦することができる
- 自分に合った働き方を選ぶことができる
- 知識や経験を将来の資産にすることができる
①場所を選ばずに働くことができる
ライターの大きな魅力は、どこでも仕事ができることです。パソコンとネット環境があれば、自宅はもちろん、カフェや旅行先、地方にいても仕事に支障は出ません。
従来の働き方では考えられないほど自由度が高く、自分のペースで働けるのが特長です。通勤にかかる時間やストレスがなくなれば、その分だけ執筆や休息に時間を使えるようになります。
人によっては、家族の事情や体調の問題でオフィス勤務が難しいこともあるでしょう。そうした事情を抱える人にとっても、柔軟に働けるライターという職業は大きな選択肢になります。
今後ますます多様な働き方が広がる中で、場所に縛られない働き方を実現できる職業として、ライターは今後さらに注目されていくでしょう。
②自分の興味や得意を活かすことができる
ライターは、自分の得意なジャンルや興味のあるテーマを活かせる仕事です。自分が詳しい分野の知識がそのまま記事に反映されます。
自分が好きなことに関われるのは、大きなモチベーションにつながるでしょう。与えられたテーマを書くのではなく、興味を持って調べ、掘り下げることで記事の質も高まります。
読者に響く記事は、その分野に熱意を持ったライターが書いたものが多いです。得意なテーマで記事を続けることで、「その分野に強いライター」と認識されます。
こうした認知は、継続的な依頼や安定した収入、キャリア形成にも寄与するでしょう。
③スキル次第で収入を増やすことができる
ライターは、成果がそのまま報酬に反映されやすい職種です。ライティングに必要なスキルを磨けば、報酬単価が上がります。
初心者は最初、数百円の単価でスタートすることが多いですが、経験を積めば1万円以上の案件や連載の仕事を受けることも可能です。実績が認められれば、企業との契約も増えます。
さらに、ライターは副業としても始めやすく、学生や社会人にとっても魅力的な選択肢です。成果が出れば、その分収入に結びつきやすい仕事といえるでしょう。
努力が報われるシンプルな仕組みであるため、着実に収入を増やすことができます。
④幅広いキャリアパスを築くことができる
ライターとしての経験は、その後のキャリアにも幅広く応用が利きます。
たとえば編集者やコンテンツディレクター、Webマーケター、SNS運用など、情報発信に関わるあらゆる職種でライティングのスキルは重宝されるのです。
実際に、ライターとして数年経験を積んだ後、企業の広報担当や出版社の編集部に転職する人もいます。また、Web業界ではライター出身のマーケターやSEOコンサルタントも多く活躍。
文章を書く力だけでなく、読者の心をつかむ視点、構成を考える力、情報をわかりやすく整理する力などが、幅広い職種に転用できるのです。
さらに、執筆した実績が増えることで信頼性が高まり、出版や講演などの仕事につながることもあります。書く仕事は、それ自体がキャリアの軸になり得る可能性を秘めているのです。
⑤未経験からでも挑戦することができる
ライターは、専門資格や経験がなくてもスタートできる数少ない職種のひとつです。実際に、まったくの未経験から始めて実績を積み、プロライターとして活動している人も大勢います。
インターネットの普及により、クラウドソーシングやライター募集サイトを使って誰でも案件に応募できる環境が整いました。
初めは簡単な記事や体験談などから始められるため、ハードルは決して高くありません。重要なのは、「文章を書くことが好き」「学びながら成長したい」という気持ちを持ち続けることです。
また、大学で得た知識や自分の趣味、日常の経験など、身の回りのことすべてが記事のネタになるため、未経験でも始めやすく、努力次第で十分にプロの域に達することができるでしょう。
⑥自分に合った働き方を選ぶことができる
ライターは、自分のライフスタイルやスケジュールに合わせて働き方を選べます。たとえば、1日8時間がっつり執筆する人もいれば、学業やアルバイトの合間に数時間だけ取り組む人もいるでしょう。
フリーランスとして独立する道もあれば、企業内ライターとしてチームで働く道もあります。
このように、柔軟に働き方を調整できるため、家庭の事情や体調、人生のフェーズに合わせて無理なく仕事を続けられるでしょう。
就活生であれば、まず副業として少しずつ始めて、将来の選択肢として広げていくのもひとつの方法です。
将来的に子育てや介護との両立が必要になったときにも、時間と場所を自由にコントロールできる点は安心材料になります。自由度の高い働き方は、自分らしい人生設計に大きく貢献してくれるでしょう。
⑦知識や経験を将来の資産にすることができる
ライターとして書き続けることで、自然と知識や経験が蓄積されていきます。リサーチや取材を通じて得た情報、文章を構成するスキル、読者に伝える表現力など、すべてが自分の財産となるでしょう。
書いた記事はポートフォリオとして保存でき、次の仕事につながる実績にもなります。
クライアントに提示できる成果物があることで、信頼を得やすくなり、継続案件や高単価案件の獲得にもつながりやすくなるでしょう。
また、身につけた文章力は、他の職種や生活の中でも役立ちます。たとえば就活でのエントリーシート作成、SNSでの発信、資料作成などにも応用できるでしょう。
こうしてライターとして得た知識やスキルは、将来にわたって価値を持ち続ける無形の資産になっていくのです。
ライターとして働くデメリット

ライターという仕事は自由度が高く、魅力的に感じるかもしれませんが、実際には見落とされがちな大変さも多くあります。
ここでは、ライターとして働く際に感じやすいデメリットを具体的な視点から紹介します。
- 締切や修正対応に追われることがある
- 収入が安定しづらい場合がある
- 書きたい内容と求められる内容のギャップがある
- 自己管理力が求められる
- 孤独を感じやすい働き方である
- フィードバックが厳しいことがある
- キャリアアップの道筋が見えにくい場合がある
①締切や修正対応に追われることがある
ライターの仕事で最も大きなプレッシャーの一つは、「締切の管理」です。創造的な作業は思うように進まないこともありますが、納期は常に決まっており、延長は基本的に認められません。
例えば、複数の案件を同時に受けると、1日のスケジュールが分刻みになることもあります。時間的な余裕がなくなることが多く、効率的なスケジューリングが求められるのです。
さらに、納品後の修正対応も軽視できません。表現の微調整や構成の変更をクライアントから求められることが多く、修正が続く場合もあります。これにより、次の案件にも影響が出ることがあるでしょう。
安定して活動するためには、納期を守る計画性と、修正リクエストに迅速かつ柔軟に対応する姿勢が求められます。最初から完璧を目指すより、改善を積み重ねて精度を上げていく意識が大切です。
②収入が安定しづらい場合がある
ライターの収入は、月ごとに大きく変動する可能性があります。特にフリーランスで活動している場合、安定した仕事量が確保できなければ、収入が大幅に落ち込むことも。
駆け出しの時期は、低単価の案件が多くなりがちで、努力の割に報酬が見合わないと感じることもあります。また、原稿料は納品後に支払われることが多く、すぐに振り込まれるわけではありません。
支払い遅延や不払いのトラブルも発生することがあるため、取引先を慎重に選ぶことが大切です。ライターの報酬は「文章量」や「質」によって変動するため、自分の作業スピードも収入に影響します。
安定志向の人にとっては、このような環境が大きなハードルになるかもしれません。
③書きたい内容と求められる内容のギャップがある
ライターに憧れる人の中には、「好きなことを書いて生活したい」と考える人も多いです。しかし、実際の業務では、個人の表現や興味よりも、クライアントや読者のニーズが優先されます。
特にWebライティングでは、SEOを意識した構成やキーワードの使用が求められ、自由な創作とはかけ離れた作業になることもあるのです。自分が書きたいテーマと求められるテーマが一致しないことがよくあります。
例えば、旅行やグルメに興味があっても、健康食品や金融サービスなど専門性の高い分野を担当することも。言葉選びや文章のトーンもターゲット層に合わせる必要があります。
創作的な要素よりも論理的な構成や分かりやすさが重視されるため、柔軟性や分析力が求められるでしょう。このギャップをどう受け止めるかが、ライターとして成長する鍵になります。
④自己管理力が求められる
ライターの多くは、会社に出社することなく自宅やカフェで働いています。一見自由に見えますが、すべてを自分で管理しなければならないという難しさも。
勤務時間や業務の優先順位、休憩のタイミングを自己判断で決める必要があり、計画性と継続力が求められます。特に就活生や社会人経験のない人にとって、生活リズムを整え、モチベーションを維持することが難しいかもしれません。
タスクをリストアップしたり、作業時間を区切ったりする方法が効果的です。ポモドーロ・テクニックなどの効率化ツールも活用し、安定した作業リズムを築くことが重要といえます。
自由と引き換えに、強い自制心が求められる仕事であることを理解しましょう。
⑤孤独を感じやすい働き方である
ライターの仕事は、基本的に一人で完結するため、孤独を感じやすい傾向があります。職場に出勤せず、ほとんどのやり取りがオンラインで完結するため、誰かと直接会話する機会が少なくなりがちでしょう。
作業中は静かな環境で、相談相手もいないまま淡々と文章を仕上げていく日々が続くことが多いです。特に人との関わりを大切にする人にとって、この働き方がストレスになることがあります。
仕事に関する悩みを共有できる仲間や、成果を褒めてくれる上司がいないことなど、社会的なつながりの欠如を感じることも多いです。また、評価が数字や修正依頼として返ってくるだけで、温かみを感じにくいのも特徴の一つ。
孤独に強いかどうかは、ライターに向いているかを見極める一つのポイントといえるでしょう。
⑥フィードバックが厳しいことがある
ライターとして仕事をしていくと、納品した文章に対するフィードバックを受けることになります。その内容が予想以上に厳しいと、落ち込んでしまうことも。
特にWebメディアや企業案件では、文章の読みやすさ、構成、SEO対策まで細かくチェックされ、赤字修正が大量に戻ってくることも珍しくありません。厳しいフィードバックに不安を感じることもあります。
しかし、このフィードバックこそがライターとして成長するための大切なステップです。指摘されたポイントを次回に活かすことで、着実にスキルアップできます。
フィードバックを「否定」と捉えるのではなく、「改善のヒント」と捉えることが大切です。文章力だけでなく、心の持ちようもライターとして生き抜くための大切な要素でしょう。
⑦キャリアアップの道筋が見えにくい場合がある
ライターは、一般的な会社員のような昇進や役職といった明確なキャリアパスが存在しないケースが多いです。経験を積んでも、次に何を目指せばよいのかが分かりづらく、成長を実感しにくいことも。
特にフリーランスの場合、自分でキャリアの方向性を定めなければ、ただ案件をこなすだけになりがちです。ライターとしての実績を活かし、編集者やディレクターを目指す道もありますが、企画構成やチーム管理のスキルが求められます。
ブランディングを意識して専門分野を絞ることで、講師やコンサルタントへの道も開けるでしょう。一方で、ただ「とりあえず書く」ことだけを続けると、数年後も変化がない可能性があります。
キャリアを前に進めるには、学びを止めず、スキルアップや新しい挑戦を自分で見つける姿勢が重要です。
ライターに向いている人とはどんな人かを知っておこう!

ライターという職業は、単に文章を書くスキルだけではなく、多面的な能力が求められます。文章を書くのが好きだったり、情報収集やリサーチが得意だったりすることは大きな強みです。
また、論理的思考力や継続力、相手の立場を想像できる共感力なども欠かせません。反対に、すぐに結果を求めたり、自己主張が強すぎたりする人は向いていない傾向があります。
ライターには多様な働き方があり、正社員・副業・フリーランスなど自分に合ったスタイルを選べるのです。年収や仕事内容もさまざまで、SEOライティングや取材記事など幅広い分野で活躍できます。
未経験でも学ぶ意欲と行動力があればスタート可能です。つまり、ライターに向いている人とは、読者視点を大切にしながら、常に学び続ける姿勢を持った人だと言えるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。