イラストレーターの年収相場と収入アップ術を徹底解説!
イラストレーターとしてのキャリアを考えたとき、収入面は一番気になるポイントですよね。そこで本記事では、イラストレーターの年収相場を業種別や年代別に徹底解説します。
さらに、収入アップのために必要なスキルやキャリアアップ術についても解説しますので、これからイラストレーターを目指す方や、収入を増やしたい方は参考にしてみてください。
イラストレーターとは?
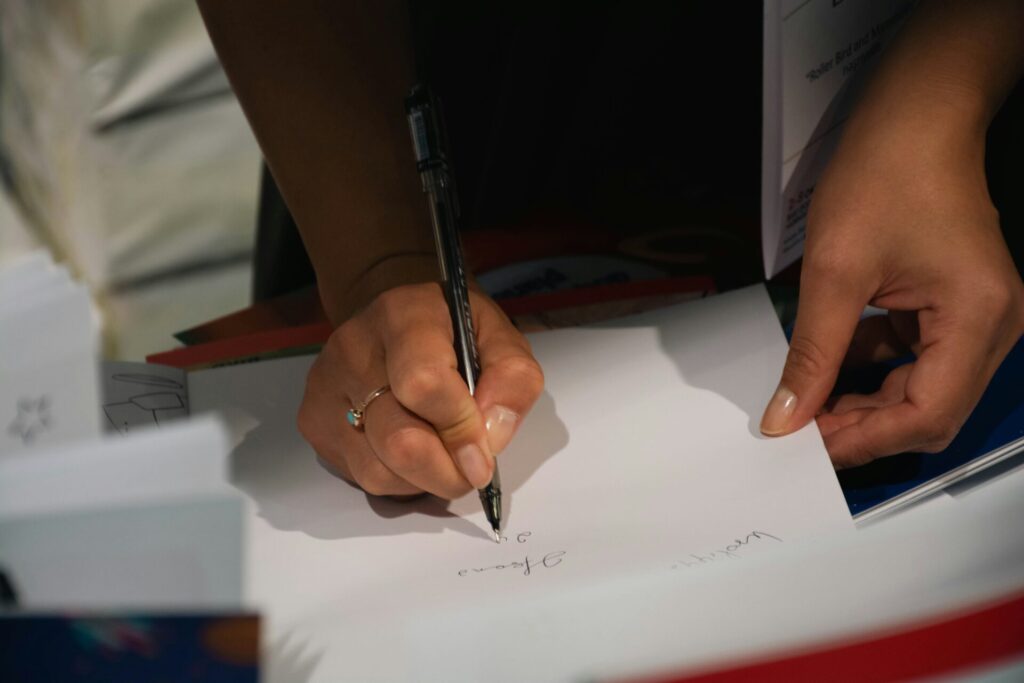
イラストレーターとは、広告や出版物、Webメディア、ゲーム、アニメなど、さまざまな媒体で使われるイラストを制作する仕事です。
視覚的に魅力あるビジュアルを生み出すために、表現力とデザインに対する理解が求められます。イラストレーターは、ただ絵が上手な人というわけではありません。
加えて、Webデザインや動画編集など関連分野のスキルがあると、より幅広い仕事を獲得しやすくなるでしょう。
「絵が好き」という気持ちだけで進むと、現実とのギャップに苦しむかもしれません。将来を見据え、仕事内容をしっかり理解した上で進路を選ぶことが大切です。
イラストレーターの平均年収

イラストレーターを目指す就活生にとって、収入の相場を知ることは重要です。働き方や業種、年代によって年収には大きな差があります。
ここでは、正社員、フリーランス、業種別、年代別に分けて、イラストレーターの平均年収について詳しく紹介します。
- 正社員イラストレーターの平均年収
- フリーランスイラストレーターの平均年収
- 業種別の平均年収
- 年代別の平均年収
①正社員イラストレーターの平均年収
企業に所属する正社員のイラストレーターは、収入の安定性が魅力ですが、自由に働ける範囲や報酬の伸びには限界がある場合が多いです。
平均年収は約300万円から400万円ほどで、特に業界未経験や新卒の場合はスタートラインが低くなることも少なくありません。
それでも、大手企業や人気の高い分野に配属されれば、実務経験を積むことで昇給やボーナスを期待できるでしょう。
正社員としての立場は福利厚生や社会保障が整っている点もメリットであり、収入の面での安心感が強いです。ただし、給与の上昇スピードが緩やかであることも理解しておく必要があります。
②フリーランスイラストレーターの平均年収
フリーランスで活動するイラストレーターの年収は、スキルや営業力に大きく左右されるため幅が非常に広いのが特徴です。
一般的な平均は年間250万円から500万円ですが、実績を積み、知名度が上がれば1000万円以上稼ぐ人も珍しくありません。
自分のペースで好きな案件を選べる自由さが魅力的ですが、収入の波が大きく、安定を得るには工夫と努力が必要です。
また、クライアントとの交渉や契約管理、請求業務なども自身でこなさなければならず、時間や労力の自己管理能力が問われます。
自由度が高い反面、責任も大きいため、しっかりとした計画と継続的なスキルアップが求められる働き方と言えるでしょう。
③業種別の平均年収
イラストレーターの年収は、所属する業界や担当する仕事の種類によって大きく異なります。
例えばゲーム業界や広告業界では、クリエイティブな要求が高いため報酬も高めで、平均年収は400万円から500万円程度となっています。
一方、出版系の仕事は書籍や雑誌の挿絵が中心で単価が比較的低いため、平均年収は300万円前後で推移します。近年はWeb業界が伸びており、オンラインコンテンツや広告のイラスト需要が増加中です。
Web分野ではスピード感と多様な表現力が求められ、高単価の仕事を得るチャンスも増えているため、自分の得意分野に合わせて業界を選ぶことが収入のカギになるでしょう。
④年代別の平均年収
イラストレーターの年収は、年齢が上がるにつれて基本的には上昇傾向にあります。
20代の平均は250万円から300万円とまだ低い水準ですが、実務経験や技術の習得とともに、30代では350万円から450万円まで伸びることが多いです。
30代はキャリアの基盤を築く時期であり、担当する案件の幅や責任も増えていくため、収入アップにつながります。
40代以降は、実績や人脈の広がりによって年収500万円以上を稼ぐイラストレーターも多くなりますが、必ずしも自動的に昇給するわけではありません。
長く活躍し続けるためには、若いうちからスキルを積み重ね、業界での信頼を築くことが重要といえるでしょう。
フリーランスイラストレーターの単価相場

フリーランスのイラストレーターが得られる収入は、仕事の受け方やスキルによって大きく変わります。
特に、どのルートで仕事を受けるかによって単価の目安が変わるため、収入を左右する重要なポイントです。ここでは代表的な4つの受注ルートの単価相場について説明します。
- クラウドソーシングサイトの単価相場
- スキルマーケットの単価相場
- フリーランスエージェントの単価相場
- 直接契約の単価相場
①クラウドソーシングサイトの単価相場
クラウドソーシングは初心者でも気軽に仕事を始められるため、多くのフリーランスが最初に利用する方法です。
ただし、単価は比較的低く設定されていることが多く、1枚あたりの報酬は2,000円〜5,000円程度であることが一般的です。これは経験やスキルが浅い人が多く参入するため、価格競争が激しいためでしょう。
また、低価格帯の案件が多いため、労力に対して十分な報酬が得られない場合もあります。それでも、初めての仕事を獲得しやすく、実績や評価を積み上げることができるのは大きなメリットです。
ただし、安価な案件が多い環境では、収入の安定性に不安を感じることもあるでしょう。安定した収入を目指すなら、クラウドソーシングを足がかりにしつつ、他の受注ルートの開拓も考えるべきです。
②スキルマーケットの単価相場
スキルマーケットは、自分のサービスに対して自由に価格設定できる点が特徴です。SNSアイコンや似顔絵の販売が多く、単価は3,000円〜10,000円程度が一般的といえます。
自分の得意なジャンルや作風に合ったターゲットを見つけられれば、高単価での受注も可能です。ただし、売れるまでは時間や工夫が必要です。特に新規出品の場合は、知名度が低いため集客に苦労します。
また、高すぎる価格設定は購入の妨げになるため、慎重な価格設定が求められます。そのため、まずは手頃な価格で多くの評価を集め、信頼を築いてから段階的に値上げするのが現実的な戦略です。
③フリーランスエージェントの単価相場
フリーランスエージェントは、企業とイラストレーターの間をつなぐ仲介役で、案件の質や単価の面で優れていることが多いです。
案件単価は数万円から10万円以上が目安となり、クラウドソーシングやスキルマーケットに比べて高単価な傾向にあります。
エージェントを利用すると、安定した仕事が得やすく、契約や条件交渉もサポートしてもらえるため、営業に時間をかけずに済むのが魅力です。
中級者以上のスキルを持つ人に向いていますが、登録時にはポートフォリオ提出が必須で、一定の実績や技術が求められる点には注意が必要です。
実績を積みながらエージェントと良好な関係を築くことが、収入アップにつながります。
④直接契約の単価相場
直接契約はクライアントと直接交渉するため、報酬の自由度が最も高い受注方法です。単価は1点あたり1万円〜数十万円まで幅広く、内容や規模に応じて高額報酬も狙えます。
ただし、営業活動や契約交渉、納品後のフォローまで自分で対応する必要があり、単にイラストの技術だけでなくビジネススキルも必要とされます。
クライアントとの信頼関係を築ければ、継続案件や高額案件を獲得しやすくなるため、長期的な収入の安定につながります。
SNSの活用や展示会での発信など、自分を積極的に売り込む努力が重要です。直接契約で成果を出すには、実績の蓄積と自己プロモーションの両方をバランスよく進めることが成功の秘訣でしょう。
イラストレーターの年収アップを目指す方法
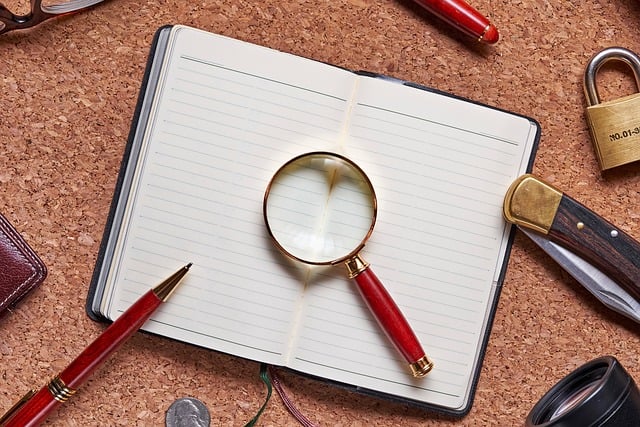
イラストレーターとして収入を安定させたり、さらに高めたりしたい就活生に向けて、年収アップの具体的な方法を紹介します。すぐに効果が出る方法から、将来を見据えた手法まで幅広く知ることが大切です。
ここでは、イラストレーターとして働き、年収アップを成功させるための方法について具体的に紹介します。
- ポートフォリオの充実
- オリジナリティの追求
- 作業スピードの向上
- 副業や兼業の活用
- 専門ジャンルへの特化
- デザインやビジネススキルの習得
- SNSやWebでの発信強化
- 転職・キャリアアップの検討
- アートディレクターなど他職種への転向
①ポートフォリオの充実
ポートフォリオは、自分のスキルや作風を示す重要なツールです。年収を上げたいなら、まず質の高いポートフォリオ作成を優先すべきでしょう。
クライアントや企業は、履歴書よりも作品を重視しますから、得意分野を明確にしつつ、多様な表現を取り入れて印象に残る内容にすることが必要です。
ただ作品数を増やすだけではなく、見やすさや構成にも配慮してください。例えばテーマ別に整理したり、代表作を目立たせたりする工夫が効果的です。
質の高いポートフォリオは、より高単価の案件や大手企業からのオファーを引き寄せる強力な武器となり、結果的に収入アップにつながります。
②オリジナリティの追求
イラストレーターとして他者と差別化するには、独自のスタイルや世界観を持つことが不可欠です。多くのイラストが似た傾向にある現状では、唯一無二の作風がなければ埋もれてしまうことも多いです。
基礎を模写でしっかり身につけたあと、自分だけの表現方法を探求しましょう。流行を追いすぎず、自分の個性をしっかり打ち出すことが大切です。
オリジナリティが高まると、ファンやクライアントの信頼を得やすくなり、継続依頼や単価アップの機会も増えます。自分のブランドを作るイメージで挑戦してください。
③作業スピードの向上
収入を増やすには、作業の効率化も見逃せません。単価が高くても作業が遅ければ、収入は限られてしまいます。
逆に、一定の品質を保ちながら速く仕上げられれば、1日にこなせる案件数が増え、結果的に収入が増えます。効率化のためには、自分の制作工程を見直して無駄を省くことが基本です。
例えば、作業手順の統一や使用ツールのショートカットを覚えると大きな時間短縮につながります。また、描き慣れたジャンルやテクニックを増やして、迷う時間を減らすことも効果的です。
ただし、クオリティを犠牲にしないことが前提です。高品質かつ迅速に仕事をこなせる人材は、信頼を得て収入アップにつながるでしょう。
④副業や兼業の活用
イラストレーターの収入は不安定になりがちなので、副業や兼業を活用することは非常に現実的な手段です。
特に就活中やキャリア初期は収入が安定しにくいため、クラウドソーシングやSNS経由の短期案件を活用すれば収入の底上げになります。また、副業は新しいスキルや人脈を広げる機会にもなります。
イラスト関連だけでなく、デザインやライティングなどの周辺分野に挑戦すれば、将来的に本業の幅も広がるでしょう。
ただし、学業や本業とのバランスは重要なので、無理のない範囲で取り組むことをおすすめします。計画的に副業を行うことで、安定した収入と経験が同時に得られます。
⑤専門ジャンルへの特化
イラストレーターとして長く安定した収入を得るには、得意分野を明確にすることが効果的です。
広く浅く描くよりも、特定のジャンルに特化したほうが、クライアントからの信頼を得やすく、高単価案件も受注しやすくなります。
例えばゲームイラストや医療系、広告用イラストなど、需要のあるニッチな分野に絞ると専門性が高まり、リピート依頼や固定クライアントが増えやすいです。
特化することで自分の市場価値が上がり、安定した収入源につながります。深く掘り下げる努力が将来的に大きな成果をもたらすでしょう。
⑥デザインやビジネススキルの習得
イラストのスキルだけでなく、デザインやビジネススキルを身につけることも年収アップのカギです。
例えばグラフィックデザインやUI/UXの基礎を学べば、イラスト以外の案件もこなせるようになり、仕事の幅が広がります。
さらに、見積もりの作り方や契約交渉などビジネス面の知識があると、単価を下げずに継続案件を獲得しやすくなります。
スキルの幅を広げることで「イラストだけできる人」から「価値の高いクリエイター」へと成長でき、報酬も自然と上がるでしょう。
⑦SNSやWebでの発信強化
どんなに優れた作品も、見てもらわなければ仕事につながりません。現代ではSNSやWebでの発信力が仕事獲得に直結します。
TwitterやInstagram、ポートフォリオサイトを活用し、定期的に作品を発信することが重要です。
ハッシュタグの使い方や投稿時間の工夫で、露出度は大きく変わります。フォロワーが増えれば、広告やタイアップの依頼も期待できるでしょう。
発信を続けることで信頼や認知度が高まり、仕事の幅が広がります。地道な努力が結果を生むので、継続して情報発信を続けてください。
⑧転職・キャリアアップの検討
現在の職場で年収に限界を感じるなら、転職やキャリアアップを積極的に考えることも大切です。
特に企業に所属するイラストレーターは評価や給与体系に左右されやすいため、努力だけでは収入が伸びにくい場合があります。
定期的に自分のスキルや実績を見直し、他社での市場価値を確認しましょう。転職エージェントを利用すれば、非公開求人やより条件の良い案件に出会うチャンスが増えます。
環境を変えることで新しい挑戦ができ、年収アップの道が開けるでしょう。
⑨アートディレクターなど他職種への転向
イラストレーターの経験を活かし、アートディレクターやコンセプトデザイナーなど上流工程の職種へ転向することも年収を大幅に増やす方法です。
これらの職種は制作だけでなく企画やマネジメントも担当するため、責任は増えますが報酬も高くなります。早めに方向転換すると、長期的なキャリア形成に役立ちます。
指導的な立場になることで仕事の幅が広がり、独立や経営の道も開けるでしょう。単なる作業者から企画者へと変わることで、収入だけでなくやりがいも大きく変化します。
イラストレーターの仕事内容

イラストレーターの仕事は非常に幅広く、分野ごとに求められるスキルや働き方が大きく異なります。自分の適性や将来の目標に合わせて、どの分野で活躍したいかをしっかりと見極めることが重要でしょう。
ここでは、代表的な分野を詳しく紹介し、それぞれの特徴や求められる力について解説します。
- 映像・ゲーム分野でのイラスト制作
- 出版物や広告でのイラスト制作
- グッズ・キャラクターデザインの制作
- アバター・LINEスタンプなどデジタルコンテンツ制作
- 展示会や個展での作品販売
①映像・ゲーム分野でのイラスト制作
映像やゲームのイラストレーターは、キャラクターや背景、アイテムといった様々なビジュアル素材を制作します。
この分野では絵の技術だけでなく、ゲームのストーリーやシステムの構造を把握する力も重要です。アートディレクションや仕様を正しく理解し、チームと連携しながら制作を進める能力も求められます。
多くの場合、初心者は下請け案件からスタートしますが、実績を重ねることで大手タイトルやオリジナル作品の制作に参加できるチャンスも増えるでしょう。
また、最新のツールやソフトに対応できるスキルも必要で、技術の進歩に合わせて常に学び続ける姿勢が欠かせません。ゲーム業界は変化が激しいため、柔軟な対応力がある人に向いているでしょう。
②出版物や広告でのイラスト制作
書籍や雑誌、広告ポスターなどの紙媒体で使われるイラストは、媒体の読者層やテーマに応じた表現力が重要です。広告の場合は特に、消費者の注意を引きつけ、記憶に残るインパクトが求められます。
この分野では、アート性と商業性のバランスを取る必要があり、自分の個性を出しつつもクライアントの意図やマーケティング戦略をしっかり理解しなければなりません。
デジタルと紙の両方の制作に対応できる柔軟性も求められます。また、期限が厳しい案件も多く、スケジュール管理や効率的な制作方法も重要です。
多様なジャンルの案件に携わることで幅広い経験が積めるため、キャリアの幅を広げたい人におすすめの分野です。
③グッズ・キャラクターデザインの制作
グッズやキャラクター制作では、かわいさやユニークさといった「売れるデザイン」を追求します。
企業やブランドのマスコットやキャラクターは、商品やサービスの顔となるため、一目で覚えてもらえるデザインが求められます。
特にサンリオやアニメ関連のキャラクター制作は、マーケティングやプロモーション戦略とも密接に関わるため、企画段階からの参加や提案力も重要です。
クライアントと密にコミュニケーションを取りながら、コンセプトを具体化していく過程が多いのも特徴でしょう。
長期的にファンを獲得し、ブランド価値を高める役割も担うため、クリエイターとしての成長にもつながります。
④アバター・LINEスタンプなどデジタルコンテンツ制作
スマートフォンやSNSの普及に伴い、アバターやLINEスタンプなどのデジタルコンテンツの需要が急増しています。
これらはユーザーの日常生活に溶け込みやすく、親しみやすいデザインや使いやすさが特に求められます。
自作のスタンプやアバターをオンラインで販売できるプラットフォームも整っているため、フリーランスや副業として始めやすい環境が整っています。
ただし競合が多く目立つため、流行をつかむセンスや他とは違う独自性が重要になるでしょう。
また流行の移り変わりが激しい分野なので、常にトレンドをリサーチし、ユーザーが欲しがるデザインを提供し続けられることが成功のポイントです。
⑤展示会や個展での作品販売
展示会や個展で自分の作品を販売するスタイルは、商業案件とは違い、アーティストとしての自由な表現ができる場です。自分の世界観やメッセージを直接伝えられるため、創作意欲を高める機会にもなります。
一方で集客や販売戦略は自分で考えなければならず、SNSやクラウドファンディングなどのツールを活用して告知活動を行うことが欠かせません。
単に絵を描くだけでなく、ブランディングやマーケティングの知識も求められます。
こうした活動を通じてファンを増やし、継続的な支持を得られれば、将来的に安定した収入や幅広いキャリア展開も可能になります。自身の名前をブランド化したい人に向いている方法といえるでしょう。
イラストレーターになるには?

イラストレーターを目指すなら、絵が上手いだけでは十分とはいえません。今のイラスト業界では、デジタルツールを使いこなしたり、スキルを常に磨いたり、自分の作品を発信する力も必要になります。
ここではイラストレーターを目指す学生に向けて、重要なポイントと注意すべきことをわかりやすく説明します。
- 必要な道具を準備する
- スキルを継続的に習得する
- 作品を公開してポートフォリオを作成する
- 専門学校や大学で学習する
①必要な道具を準備する
イラストレーターとして活動を始めるには、まず基本の道具をそろえることが欠かせません。
現在はデジタル制作が主流なので、パソコンや液晶ペンタブレット、さらにイラスト制作ソフトを用意する必要があります。
Adobe PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTは、プロの現場でも多く使われているため、これらを扱えるようになると仕事の幅が広がります。
道具の性能や使い勝手は、作品の仕上がりや制作時間に大きく影響しますので、選ぶ際は機能面とコストのバランスをよく考えましょう。
②スキルを継続的に習得する
イラストの世界はトレンドや技術が常に変化しているため、最初に身につけたスキルで満足してしまうのは危険です。
新しい表現方法やツールの使い方を学び続けることで、より幅広いジャンルに対応できる力がつきます。自己流だけで続けると、独りよがりな表現に偏ってしまい、仕事の依頼が減ることもあります。
定期的に講座やセミナーを受講し、他のクリエイターの作品や意見に触れることで、自分の弱点に気づきやすくなります。さらに、実践的な練習やフィードバックを得ることで、作品の質を高められます。
変化の速い業界だからこそ、学び続ける姿勢がプロとしての信頼を築く鍵になるでしょう。
③作品を公開してポートフォリオを作成する
仕事を得るためには、自分の作品を多くの人に見てもらい、魅力を伝えることが必要です。SNSやポートフォリオサイトは、気軽に作品を発信できる場として非常に役立ちます。
公開を続けることで、フォロワーやファンを増やすことができ、そこから仕事の依頼が来ることも珍しくありません。
作品が増えたら、テーマやジャンル別に整理して見やすいポートフォリオを作成しましょう。単に絵の上手さを並べるだけでなく、自分の得意分野や個性をはっきりとアピールできる構成が大切です。
こうした努力は、プロとしての信頼獲得や、依頼につながる大きな武器となるため、手を抜かず丁寧に仕上げてください。
④専門学校や大学で学習する
独学に限界を感じたり、基礎から体系的に学びたい場合は、専門学校や大学での学習が効果的です。
カリキュラムに沿って段階的に技術や知識を習得でき、プロの講師から直接指導を受けられるのは大きなメリットです。
また、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨することで刺激を受け、創作意欲が高まることも多いでしょう。
ただし、授業に出席するだけでなく、自主制作や課題に積極的に取り組む姿勢が欠かせません。環境を活かし、自分から成長の機会を掴むことが、将来の選択肢を広げるために重要だといえます。
イラストレーターになるために必要な資格
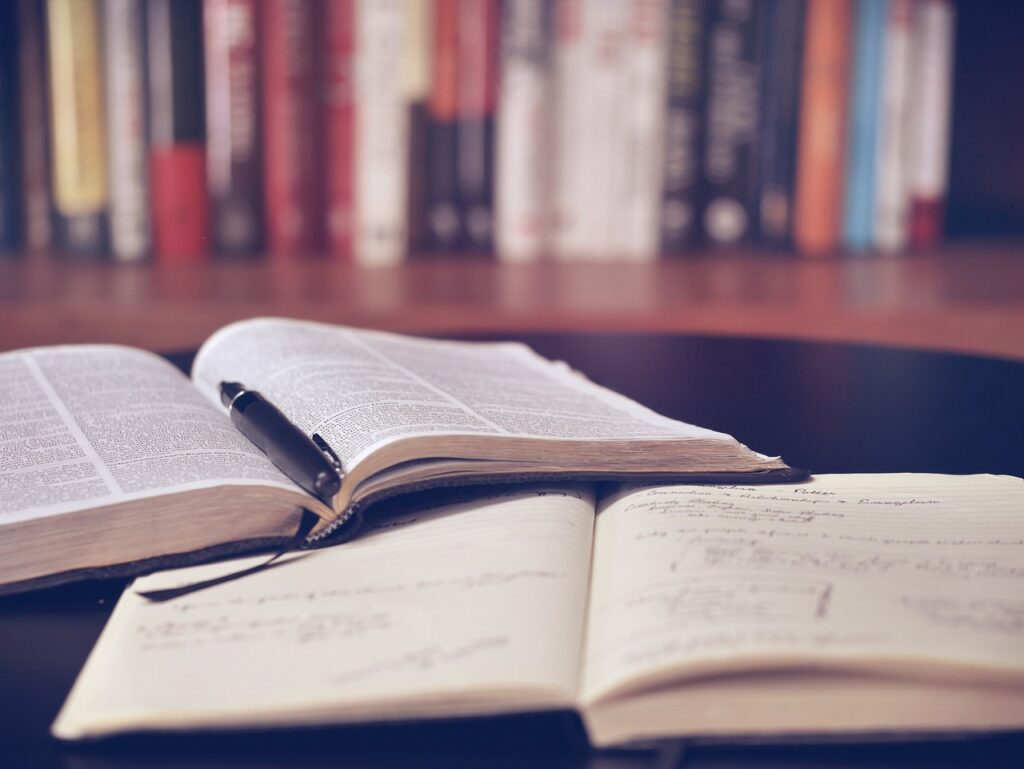
イラストレーターを目指す学生にとって、資格はスキルの証明だけでなく、仕事の幅を広げる大きな武器になるでしょう。
資格が必ずしも必要とは限りませんが、競争が激しい業界では、実力の裏付けとして有利に働く場面が多いです。
ここではイラストレーターに関連する資格を6つ紹介します。それぞれの内容を理解して、自分に必要な資格を見極めてください。
- CGクリエイター検定
- Photoshop®クリエイター能力認定試験
- アドビ認定プロフェッショナル
- 色彩検定
- Webデザイン技能検定
- デジタル画像処理エンジニア認定試験
①CGクリエイター検定
CGクリエイター検定は、コンピューターグラフィックスの基本知識と制作技術を問う資格です。イラストの分野でもCG技術の需要が増えており、特にアニメやゲーム業界を目指す方には重要な資格でしょう。
資格取得を通じて、視覚表現の基礎や制作の流れを理解できます。これにより、現場で即戦力として働けることを示せるため、アピールポイントにもなります。
さらに、CG制作の知識はデジタルイラストだけでなく、3Dモデリングやアニメーションの基礎理解にもつながります。
こうした幅広い技術を身につけることで、多様な表現に挑戦できるようになるでしょう。
②Photoshop®クリエイター能力認定試験
Photoshop®クリエイター能力認定試験は、画像編集ソフト「Photoshop」の実務スキルを測る試験です。イラスト制作では、描くだけでなく色の調整や加工などの作業も必要になります。
試験対策を通じて、操作の基本から応用まで幅広く学べるので、未経験者でも取り組みやすいでしょう。
Photoshopのスキルが高まると、単にイラストの修正だけでなく、広告用のバナー制作やSNS用の画像作成にも対応できるようになります。
さらに、Photoshopの知識は他のAdobe製品の理解にも役立つため、クリエイターとしての総合力が向上します。
③アドビ認定プロフェッショナル
アドビ認定プロフェッショナルは、Adobe社公認のソフトウェア操作スキルを証明する資格です。
PhotoshopやIllustratorなど、業界でよく使われるソフトを対象としており、企業や制作会社で高く評価されます。
独立を目指す人はもちろん、就職活動中の方も、この資格を持っていると即戦力として見られやすいです。
加えて、資格取得の過程で最新のソフトウェア機能を学べるため、技術のトレンドに遅れずについていけます。これが結果としてクライアントからの信頼につながり、仕事の受注にも好影響を与えるでしょう。
④色彩検定
色彩検定は、色の理論や配色技術を体系的に学ぶ資格です。イラストにおいて色は作品の印象を左右する重要な要素ですが、感覚だけに頼るとイメージを正確に伝えにくくなることがあります。
色彩検定では、色の仕組みや心理効果、配色のルールを学べるため、理論に基づいた色選びが可能になります。ポートフォリオやSNSでの発信では、魅力的なビジュアルを作る力が差を生みます。
この資格を持っていると、ほかの人と差別化できるでしょう。また、色彩検定の知識は印刷物の色管理やデジタルメディアでの色表現の理解にも役立つため、幅広い分野での活躍が期待できます。
さらに、色彩心理学を学ぶことで、見る人の感情に訴える作品作りができるようになります。
⑤Webデザイン技能検定
Webデザイン技能検定は、Webコンテンツ制作に必要な知識と技術を問う国家資格です。最近ではイラストレーターにもWebデザインの知識が求められる場面が増えています。
自分の作品をWeb上で紹介したり、SNSやWeb広告のビジュアルを作成したりする際に、HTMLやCSSの基礎がわかっていると強みになるでしょう。
さらに、Webデザイン技能検定の知識があれば、クライアントからの要望に柔軟に応えられ、より高品質な作品の提供が可能です。
これにより、信頼関係を築きやすくなり、仕事の継続や新規案件獲得につながりやすくなります。
⑥デジタル画像処理エンジニア認定試験
デジタル画像処理エンジニア認定試験は、画像の処理や解析に関する専門的な知識を問う資格です。一見すると理系の内容に思えますが、イラスト制作の現場でもAIや画像解析技術との連携が進んでいます。
ゲームや映像業界では、画質の最適化や処理の効率化が求められるため、この資格は技術力の裏付けとして有効です。難易度は高めですが、他の人と差をつけたい上級者にはおすすめの資格といえます。
さらに、この資格で学ぶ技術は、今後のデジタルコンテンツ制作においてますます重要になるため、将来性も高いです。
画像処理の知識があれば、新しい表現技術の開発や改善にも貢献でき、クリエイターとしての価値が大きく高まるでしょう。
イラストレーターに向いている人の特徴
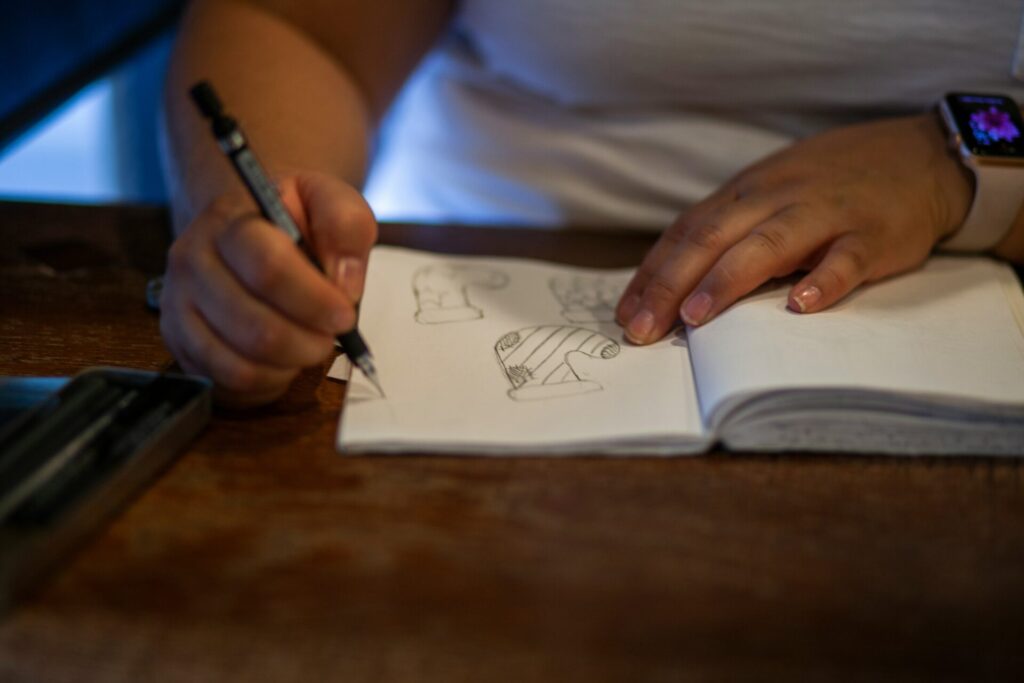
イラストレーターは技術だけでなく、向いている性格や考え方も重要です。自分に合うかどうか知るには、いくつかの特徴を理解しておく必要があります。
ここでは、イラストレーターに求められる性質を具体的に紹介します。
- プレッシャーに強い人
- 流行や市場の動向に敏感な人
- 人の意見を柔軟に取り入れられる人
- 独自性や個性を大切にする人
- 継続的に努力を続けられる人
- 一人でも集中して作業に取り組める人
- 細部まで丁寧に仕上げることができる人
①プレッシャーに強い人
イラストレーターの仕事は、締め切りやクライアントの要望に応える必要があり、常にプレッシャーがつきまといます。こうした環境の中で、冷静に質の高い作品を提供し続けるには、強い精神力が不可欠です。
プレッシャーに負けてしまうと、作業の効率が落ちたり、クオリティが下がったりするリスクがあります。だからこそ、ストレスをコントロールしながら安定して作業できる人が向いているでしょう。
②流行や市場の動向に敏感な人
イラストレーターの世界は流行の移り変わりが早く、常に最新のトレンドを理解している必要があります。人気の絵柄や色使い、表現方法が変化し続けるため、流行に敏感であることは大きな武器です。
これを意識しないと、せっかくの技術も時代遅れになりやすく、仕事の機会を逃すこともあります。
また、流行を追うだけでなく、それをどう自分のスタイルに取り入れて作品に反映させるかが腕の見せどころです。普段からアニメやゲーム、SNSのトレンドをチェックし、時代の空気を読み取る力が求められます。
こうした敏感さが長期的な活躍につながるため、アンテナを高く張っておくことが大切です。
③人の意見を柔軟に取り入れられる人
イラストレーターの仕事は、クライアントや編集者からの要望に応じて修正を重ねながら完成させることが多いため、他人の意見を受け入れる柔軟さが欠かせません。
自分の絵に強いこだわりを持つことは良いことですが、時には妥協や調整が必要になるため、意見を素直に聞き入れる姿勢が求められます。
特に商業イラストの場合、クライアントの期待に応えることが最優先なので、自分の理想だけを押し通すことは難しいでしょう。
反発するよりも、アドバイスを成長のチャンスと捉え、より良い作品づくりにつなげる姿勢が重要です。こうした対応力が、信頼関係を築き、次の仕事につながることも多いです。
④独自性や個性を大切にする人
イラストレーターの世界は競争が激しく、たくさんのクリエイターがいます。その中で目立つには、「この人らしさ」が伝わる独自性が必要です。
個性的な絵柄や表現は、ファンやクライアントの心をつかみやすく、長く支持されるための大きな要素となります。しかし、ただ奇抜なだけでは逆効果になることもあります。
魅力的で分かりやすい個性を持ち、それを作品の中で洗練させていくことが重要です。自分のスタイルを見つけるためには、模倣や試行錯誤を繰り返す必要がありますが、続けるうちに「らしさ」が形作られます。
個性は一朝一夕で身につくものではありませんが、それを大切にしながら磨き続ける姿勢が、将来の成功につながります。
⑤継続的に努力を続けられる人
イラストの技術は一朝一夕で身につくものではなく、日々の地道な努力が上達のカギとなります。プロのイラストレーターも、デビュー後に新しい技術や表現を学び続けています。
努力を怠らず、常に自分のスキルを向上させようとする姿勢が求められるでしょう。また、練習だけでなく、SNSでの発信やポートフォリオの更新なども継続的に行うことが大切です。
これらは仕事を得るうえで重要な活動であり、地道に積み重ねていくことでチャンスが広がります。途中で諦めてしまうと、せっかくの才能も埋もれてしまうため、粘り強く続けることが成功への道といえます。
⑥一人でも集中して作業に取り組める人
イラストの制作は基本的に一人で行う時間が長いため、一人でも集中して作業を続けられる能力が重要です。
長時間パソコンやタブレットの画面に向かうことになるので、孤独を苦にしない人ほど向いているでしょう。
逆に、誰かと話しながら作業するほうが集中できる人や、一人でいることがストレスになる人にとっては、孤独感が負担になる可能性があります。
一人の環境でも没頭できることは、クオリティの高い作品を作るうえで大きな強みとなります。作業中の集中力を保つ工夫ができる人は、より効率よく仕事を進められます。
⑦細部まで丁寧に仕上げることができる人
イラストは細かな部分までこだわることで作品全体の魅力が大きく変わります。影の入れ方や線の太さ、色のグラデーションなど、細部に気を配ることができる人は完成度の高いイラストを生み出せます。
反対に、作業を急ぎすぎると雑な印象になりやすく、見る人の評価も下がってしまいます。
細かい部分を丁寧に仕上げることは時間もかかりますが、その分作品の質が格段に上がるため、プロとして求められる大切な要素です。繊細な作業を楽しみながら取り組める人は、強みを持つでしょう。
イラストレーターの将来性

イラストレーターは「趣味の延長」と思われがちですが、最近では働き方や活躍の場が大きく変わっています。
デジタル化の進展やグローバル展開、NFT市場の誕生などによって、イラストレーターの将来性は多様な可能性を持つようになりました。ここでは、イラストレーターの今後の展望を多角的に説明します。
- デジタル需要の増加と新領域の広がり
- AI技術との共存と新たな表現の可能性
- 市場競争と自己ブランディングの重要性
- グローバル市場への展開可能性
- 複業・副業としての柔軟な働き方の広がり
- NFTやメタバース分野での新たな収益モデル
①デジタル需要の増加と新領域の広がり
スマートフォンやSNSの普及により、イラストの需要は紙媒体からデジタル領域へ大きく移っています。
企業の広告、ゲーム、Webコンテンツで求められるビジュアルはより魅力的で多様化しており、それに伴いイラストレーターの役割も広がっています。
特に、WebデザインやUIデザイン、動画用のモーションアートなど、これまでになかった新たな分野が増えているのです。
こうした変化に対応するためには、単に絵が上手いだけではなく、デジタルツールの操作や多様な表現方法を身につけることが必要です。
②AI技術との共存と新たな表現の可能性
近年AIによる画像生成技術が急速に発展し、イラストレーターの仕事が奪われるのではと懸念する人もいます。
しかしAIはあくまでツールであり、クリエイターの創造力や感性を完全に代替できるわけではありません。
むしろ、AIをうまく活用することで、作業効率が格段に上がり、より高度な表現に挑戦できるようになるでしょう。
AIは繰り返し作業やアイデア出しの補助に最適で、クリエイターが本来の創作活動に集中できる環境を作れます。重要なのは、AIを恐れず、積極的に使いこなす姿勢を持つことです。
③市場競争と自己ブランディングの重要性
イラストレーター志望者が増加する中で、ただ絵を描けるだけでは仕事を得にくくなっています。多くのライバルがいるため、自分だけの強みや作風を明確にし、発信することが不可欠です。
SNSやWebサイトを使って自分の世界観を発信すれば、ファンやクライアントの獲得につながります。また、自己ブランディングは単価の上昇にも直結します。
レスポンスの速さや誠実な対応、納期の厳守などプロとしての態度が評価され、安定した収入を確保できます。競争が激しい市場だからこそ、技術だけでなく人間力も磨いていく必要があるでしょう。
④グローバル市場への展開可能性
インターネットの普及で、イラストレーターは国内だけでなく海外のクライアントとも簡単に取引できる時代になりました。
特に日本のアニメやマンガのスタイルは世界的に高い人気を誇り、日本人イラストレーターは独自の強みを持っています。
海外市場へ進出することで、より多くのチャンスや高い単価の仕事を得る可能性が広がります。ただし、海外展開には語学力や時差対応、文化の違いを理解する努力が必要です。
とはいえ、翻訳ツールの進化により、言葉の壁は以前よりずっと低くなっています。グローバルな視点で活動することで、多様な案件に挑戦でき、自己成長にもつながるでしょう。
⑤複業・副業としての柔軟な働き方の広がり
イラストレーターはフリーランスとしてだけでなく、副業としても注目されています。
SNSやクラウドソーシングサービスの発展で、本業を続けながらイラストの仕事をすることが以前よりも現実的になりました。自宅でできるため、時間や場所の制約が少ないのも大きな魅力です。
このような働き方は収入源の多様化につながり、経済的なリスクヘッジにもなります。副業から始めることでスキルを磨き、ゆくゆくは本業にするケースも増えてきました。
イラストレーターとしてのキャリアを築くために、まずは小さな仕事からチャレンジしてみるのもよいでしょう。働き方の自由度が高い分、自分で計画的に動くことが成功の鍵です。
⑥NFTやメタバース分野での新たな収益モデル
NFT(非代替性トークン)やメタバースは、イラストの価値を従来とは異なる形で高めています。
作品をNFTとして販売すれば、二次流通で収益を得ることも可能ですし、メタバース空間内のアイテムやアバターのデザインに携わることもできます。
これらは「作品自体が資産」として機能する、新しい収益モデルです。まだ発展途上の分野なので、リスクや不確実性もありますが、先行者利益を得やすいチャンスともいえます。
新しい技術やトレンドに敏感であれば、他にない独自の価値を生み出せる可能性が高いです。NFTやメタバースの知識を積極的に学び、早めに挑戦することで、新たな収入の柱を築けるでしょう。
イラストレーターの収入実態を知ろう!

イラストレーターの年収は、働き方や経験、業種によって大きく異なります。正社員とフリーランスでは収入構造が違い、クラウドソーシングや直接契約といった単価相場も多様です。
年齢や専門ジャンル、スキルアップやポートフォリオの充実によって年収アップが可能であり、SNSや転職などキャリア戦略も重要です。
イラストレーターの仕事内容や必要な資格、向いている人の特徴を理解し、将来の市場動向やデジタル技術の進展も踏まえることで、より具体的に収入向上の道が見えてきます。
つまり、多角的な視点から自分の強みを伸ばし、環境に合わせた戦略を立てることが年収アップの鍵です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














