公認会計士就職の特徴とキャリアステップ|マネージャーCFO独立の道
「公認会計士の就職って、実際どんなキャリアが描けるの?」
難関試験を突破した後の進路は、監査法人での勤務をはじめ、事業会社やコンサルティングファーム、さらには独立開業まで幅広く存在します。
特に、将来的にマネージャーやCFOといったポジションを目指す人にとって、最初の就職先の選択は大きな分岐点になります。
そこで本記事では、試験合格後の流れから最新の就職市場動向、監査法人の種類や就職先ごとの特徴、さらにキャリアステップまで詳しく解説します。
これを読めば、公認会計士としてのキャリア設計を具体的にイメージでき、将来の選択肢を広げるためのヒントが得られるはずですよ。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
公認会計士の就職について
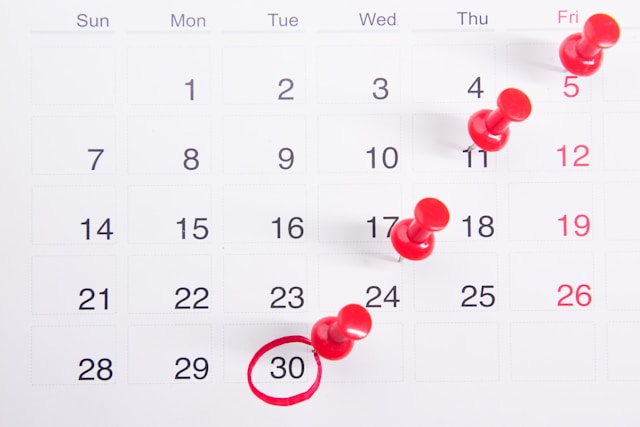
公認会計士の就職活動は、試験合格の発表時期とほぼ同時に始まるため、一般的な新卒採用と比べてスケジュールが大きく異なります。
公認会計士の就職活動は、例年11月中旬〜下旬に行われる論文式試験の合格発表後、すぐに本格化します。
多くの監査法人や事業会社は合格発表の直後からエントリー受付を開始し、12月上旬には説明会や面接が集中し、12月中旬〜下旬には内定が決まるケースが一般的です。
つまり、わずか3〜4週間の間に志望先選び・面接・内定という一連の流れが進む超短期決戦となります。
そのため、合格発表前の10月〜11月に自己分析や法人研究、志望動機の整理、履歴書準備などを済ませておくことが、スムーズに内定を得るための最大のポイントでしょう。
公認会計士試験合格後の流れ

公認会計士試験に合格したあとは、就職活動から業務補助、実務補習、修了考査までのプロセスを経て正式に登録できます。
ここでは、合格後にどのように動けばよいかを具体的に示し、就活生が安心してキャリア形成を進められるようポイントを整理しました。
- 就職活動
- 業務補助
- 実務補習
- 修了考査
①就職活動
公認会計士試験合格後、最初に取り組むのが就職活動です。例年11月中旬〜下旬に合格発表があり、その直後から監査法人や事業会社、コンサルティングファームなど多様な就職先での募集が始まります。
短期間での選考が多く、12月中旬には内定が決まるケースも多いでしょう。事前に自己分析や志望動機の整理、履歴書準備を10月〜11月に進めておくことで、短期決戦でも落ち着いて臨めます。
さらに、複数の就職先を比較して将来像に合う選択肢を選ぶことが、長期的な満足度を高めるコツです。
②業務補助
就職先が決まると、実際の業務補助に携わります。業務補助は、先輩会計士や上司の指導のもとで監査や会計業務をサポートし、実務経験を積むプロセスです。
ここで得る経験やスキルは、その後のキャリア形成に大きく役立ちます。新人のうちは単純な作業が多いかもしれませんが、幅広い業務に挑戦することで知識の定着や人脈形成につながるでしょう。
業務補助の期間に積極的な姿勢で学び取ることが、将来の成長を左右します。
③実務補習
業務補助と並行して実務補習も始まります。これは公認会計士協会が主催する研修で、合格者が3年間にわたり実務に必要な知識や倫理観を体系的に学ぶものです。
週末や業務の合間に受講するためスケジュール管理が重要で、日々の仕事との両立に苦労する人もいます。
しかし、講義やグループ演習を通じて同世代の受講者とつながる機会が多く、刺激を受けながら成長できる環境です。
早めに課題や復習を進める習慣を身につけることで、負担を軽くしつつ修了を目指してください。
④修了考査
最後のステップが修了考査です。これは実務補習の集大成として行われる試験で、職業倫理・監査・会計など多岐にわたる知識を問われます。
合格することで、正式に公認会計士として登録する資格を得られるでしょう。試験範囲が広いため、業務や実務補習で学んだ内容を日々整理し、計画的に学習を進めることが必要です。
過去問演習や勉強会への参加を取り入れると、効率的に準備が進められます。修了考査を乗り越えることで、公認会計士として本格的なキャリアが始まります。
公認会計士就職市場の最新動向(2025年版)

2025年の公認会計士就職市場は、慢性的な人手不足が続く一方で、採用基準の厳格化も進んでいます。
ここでは、就活生が知っておくべき2つの動向を取り上げ、これからの就職活動を有利に進めるためのポイントを整理しました。
- 売り手市場継続
- 採用基準の厳格化
①売り手市場継続
2025年も公認会計士の就職市場は売り手市場が続いています。背景には監査法人や事業会社での人材不足があり、特に若手会計士へのニーズは高いままです。
そのため、以前より多くの求人や多様な就職先が用意され、自分に合う環境を選びやすくなっているでしょう。
ただし、売り手市場だからといって油断はできません。志望先ごとの業務内容や社風を調べ、早めに準備を整えてください。
複数の企業を比較し、将来像に合った選択をすることが長期的なキャリア形成に役立ちます。
②採用基準の厳格化
一方で、採用基準の厳格化が進んでいる点にも注意が必要です。売り手市場でも、企業は求める人物像をより明確にし、志望動機や適性を細かく見極める傾向が強まっています。
特にコミュニケーション力やチームでの協働姿勢など、専門知識以外の要素も重視されるようになりました。
こうした変化に対応するには、事前に自己分析を深め、志望先に合わせた自己PRを準備することが大切です。面接練習やOB・OG訪問で現場の声を知ることが、選考突破の確率を高める近道となるでしょう。
監査法人の種類と選び方

監査法人は大きく分けてBig4監査法人、準大手監査法人、中小監査法人の3つに分類されます。それぞれ規模や得意分野、働き方が異なり、就職先としての特徴や選び方のポイントも変わります。
ここでは各監査法人の違いを整理し、自分に合ったキャリアを築くためのヒントをまとめました。
- Big4監査法人の特徴と選び方
- 準大手監査法人の特徴と選び方
- 中小監査法人の魅力と選び方
①Big4監査法人の特徴と選び方
Big4監査法人はEY新日本、あずさ、PwC、トーマツの4法人を指し、規模や案件数、国際ネットワークの広さが特徴です。
上場企業やグローバル案件に多く携わることができ、短期間で幅広い知識や経験を積めるでしょう。ただし、業務量が多くスピード感も求められるため、体力や柔軟性が必要です。
選ぶ際には、各法人の専門分野や社風、研修制度の違いを比較し、自分が成長したい分野と合っているかを見極めてください。OB・OG訪問や説明会で実際の雰囲気を知ることも有効です。
②準大手監査法人の特徴と選び方
準大手監査法人は、Big4ほどの規模ではないものの、全国展開や専門分野に強みを持つ法人が多くあります。
中堅・中小企業や特定業種に特化した案件を担当することも多く、幅広い業務に携われる環境が整っているでしょう。
大手に比べて一人ひとりの裁量が大きく、早い段階から責任ある仕事を任されることも少なくありません。
選ぶときは、自分が希望する地域や業種に強みを持つ法人かどうかを確認し、将来のキャリアパスと照らし合わせてください。
待遇面だけでなく、教育制度やワークライフバランスにも注目することが大切です。
③中小監査法人の魅力と選び方
中小監査法人は、地域密着型や特定分野に特化した案件を多く扱い、少人数でアットホームな環境が魅力です。
監査以外にもコンサルティングや税務など幅広い実務に触れられるため、総合的なスキルを身につけやすいでしょう。
一方で、法人によっては研修制度が限定的な場合もあるため、自己学習や積極的な質問が欠かせません。
選ぶ際には、どの業種やクライアント層を対象にしているか、将来的に独立や転職を考えたときにどの程度経験が活かせるかを確認してください。
規模や知名度にこだわらず、自分の働き方や価値観に合う環境を選ぶことが重要です。
公認会計士の主な就職先と特徴

公認会計士は、資格取得後に選べる就職先が幅広いことが魅力です。
監査法人から事業会社、コンサルティングファーム、金融機関、ベンチャー企業、公的機関や独立開業まで、多彩なキャリアを築けます。
ここでは、それぞれの就職先の特徴を整理し、自分に合った進路選びのヒントを紹介します。
- 監査法人
- 一般事業会社
- コンサルティングファーム
- 金融機関
- ベンチャー企業
- 税理士法人
- 公的機関・教育機関
- 独立開業
①監査法人
監査法人は、公認会計士の就職先として最も多い選択肢です。上場企業や大手クライアントを対象に監査業務を行い、専門知識を深めながら多くの経験を積めます。
大規模な法人では国際案件や高度な監査に携われる一方、業務量が多くスピード感も必要でしょう。希望する業種やプロジェクトに強い法人を選ぶことが、キャリア形成の近道になります。
②一般事業会社
一般事業会社では、経理や財務部門に所属し、企業の内部から会計・財務管理を担当します。
公認会計士の知識を活かして企業の成長を支えることができ、将来的にCFOや経営企画など管理職への道も開けるでしょう。
ただし、監査法人に比べると専門性を深めるよりも、幅広い業務に携わる傾向が強いので、自分のキャリア目標に合うか慎重に判断してください。
③コンサルティングファーム
コンサルティングファームでは、M&A、事業再生、会計アドバイザリーなど多様な業務に携われます。
公認会計士としての知識を活かし、企業の経営改善や成長戦略の策定をサポートすることが可能です。
業務の幅が広いため、短期間で高いスキルを身につけたい人や挑戦的な環境を求める人に向いています。ただし、成果が強く求められるため、常に成長意識を持つことが必要です。
④金融機関
金融機関では、銀行や証券会社などで監査・リスク管理・投資関連業務を担当します。
企業の財務状況を分析し、融資や投資判断のサポートをするなど、公認会計士ならではの視点を活かせる場面が多いでしょう。
金融の知識やスキルを深めることで、将来的にファンドや投資銀行へのキャリアアップも見込めます。
⑤ベンチャー企業
ベンチャー企業では、急成長中の会社で経理・財務・経営企画などを幅広く担当することが多く、スピード感のある環境で実力を磨けます。
大企業と違い一人ひとりの裁量が大きく、意思決定に直接関わる機会が多いのが特徴です。ただし、安定性より挑戦を重視する環境であるため、柔軟性とチャレンジ精神が求められます。
⑥税理士法人
税理士法人では、税務や会計に特化した専門サービスを提供します。公認会計士資格を持つことで、高度な税務アドバイスやコンサルティング業務に携われる機会が増えるでしょう。
監査法人とは違い、顧客との長期的な信頼関係を築きやすく、税務分野に強みを持ちたい人に適しています。
⑦公的機関・教育機関
公的機関や教育機関では、政策立案、監査業務、会計教育など幅広い分野で活躍できます。社会的貢献度が高く、安定した環境で専門知識を活かせることが魅力でしょう。
ただし、民間企業に比べると報酬や昇進のスピードが緩やかな場合もあるため、将来像を明確にして選ぶことが大切です。
⑧独立開業
独立開業は、公認会計士が自身の専門分野を生かして自由な働き方を目指す選択肢です。クライアントを選び、自分の裁量で業務を進められる反面、営業力や経営力が求められます。
開業前には十分な実務経験と顧客基盤の構築が必要であり、慎重な計画を立てて準備することが成功の鍵です。
就職先ごとのキャリアステップと将来の展望

公認会計士のキャリアは、就職先によって進む道や成長スピードが大きく変わります。
監査法人、事業会社、コンサルティングファーム、そして独立開業と、それぞれに求められるスキルや役割が異なります。
ここでは、将来のキャリアパスをイメージしやすくするために、代表的な4つの進路を解説します。
- 監査法人でのキャリアパス
- 事業会社でのキャリアパス
- コンサルティングファームでのキャリアパス
- 独立開業後のキャリアパス
①監査法人でのキャリアパス
監査法人では、入所後にスタッフとして現場業務を担当し、その後シニアスタッフ、マネージャー、パートナーと段階的に昇進していきます。
大規模法人では上場企業や国際案件に携わる機会が多く、幅広い経験を積みながら専門性を高められるでしょう。
一方、早い段階から管理職を目指すには、業務の正確さだけでなくチームのマネジメント力や顧客対応力が重要です。
多忙な環境でも主体的に学び、成長のチャンスを逃さないことが将来の飛躍につながります。
②事業会社でのキャリアパス
事業会社では、経理や財務部門に所属し、決算や資金調達、経営計画の策定など幅広い業務を経験します。数年後には経営企画やCFOなど管理職へ昇進する道も見えてくるでしょう。
監査法人と比べると専門領域は狭まることがありますが、企業の内部から経営に深く関われる点が魅力です。
社内で信頼を築き、リーダーシップを発揮することで、より早くキャリアを広げられます。
③コンサルティングファームでのキャリアパス
コンサルティングファームでは、入社後すぐにプロジェクト単位で仕事を任されることが多く、短期間で実践力を養えます。
シニアコンサルタント、マネージャー、ディレクター、パートナーと昇進の道が明確で、高い成果を出せば若いうちから大きな裁量を持つことも可能です。
公認会計士としての知識を武器に、M&Aや事業再生、会計アドバイザリーなど専門性を深めることで市場価値が高まります。成果主義の環境に対応し、挑戦を恐れずに取り組む姿勢が求められるでしょう。
④独立開業後のキャリアパス
独立開業は、公認会計士として培った専門性と人脈を活かし、自ら顧客を持ってサービスを提供する道です。
開業後は税務、会計、コンサルティングなど幅広い業務に対応しながら、自分の強みを発揮できます。
自由度が高い反面、営業力や経営力が求められるため、開業前に十分な実務経験と顧客基盤を築いておくことが重要です。
独立後は規模を拡大し事務所経営にシフトする、専門分野に特化して高付加価値サービスを提供するなど、多様な成長の道が開けるでしょう。
就職活動に失敗した場合の対策と代替キャリアパス

近年のデータでは、公認会計士試験合格者のうちおよそ1~2割が就活で第一志望から内定を得られず、進路変更を迫られているといわれます。
就職活動で思うような結果が出なかった場合でも、公認会計士として活躍できる道は複数あります。
ここでは、会計事務所や税理士法人への就職、一般企業の経理・財務職、独立開業やフリーランスなど、将来の可能性を広げるための選択肢を紹介します。
- 会計事務所・税理士法人に就職する
- 一般企業の経理・財務専門職に就職する
- 独立開業やフリーランスとして活動する
①会計事務所・税理士法人に就職する
会計事務所や税理士法人は、公認会計士の基礎力を活かしやすい職場です。
税務申告や財務コンサルティング、経営支援など、実務を通じて専門性を深められます。大手法人では教育体制が整っていることも多く、将来の独立にも役立つ経験を積めるでしょう。
監査法人とは異なる顧客層や業務に触れることで、スキルの幅を広げることが可能です。
②一般企業の経理・財務専門職に就職する
一般企業の経理や財務専門職は、企業内部から経営を支える立場として活躍できます。決算や予算策定、資金管理など幅広い業務を経験し、将来的にはCFOや経営企画職への道も見えてくるでしょう。
監査法人のような監査業務ではなく、経営視点を持った財務管理に携わるため、社内での信頼構築や幅広い知識が求められます。
③独立開業やフリーランスとして活動する
独立開業やフリーランスとして活動する道もあります。クライアントを持ち、税務や会計コンサルティング、経営支援など幅広いサービスを提供できるのが強みです。
自由度が高い反面、営業力や顧客開拓力が欠かせません。開業前に実務経験や人脈をしっかり築いておくと、安定した事業基盤をつくりやすくなります。
公認会計士就職の最終ポイント

公認会計士の就職は、試験合格後の流れや市場動向、監査法人や事業会社など多彩な就職先を理解することが成功の鍵です。
まず、就職活動や実務補習などのプロセスを把握し、売り手市場や採用基準の変化に対応する準備が必要です。
次に、Big4監査法人から中小監査法人、コンサルティングファーム、金融機関、さらには独立開業まで、自分に合うキャリアパスを具体的に描くことが重要です。
最後に、就職活動に失敗しても会計事務所や税理士法人、一般企業など代替キャリアの選択肢があるため、柔軟な戦略で挑む姿勢が将来のキャリア形成を強く支えますよ。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














