「どこでもいい」就活はやめよう!後悔しないための対策とは?
「どこでもいいから内定がほしい」と思っていませんか?就活がうまくいかないと、「とにかく受かればいい」と考えてしまいがちですよね。
しかし、そのまま適当に会社を選んでしまうと、入社後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性が高くなります。せっかく就職するなら納得のいく選択をしたいですよね。
本記事では、「どこでもいい就活」を避けて後悔しないための対策を紹介します。ぜひ最後まで読んで、自分に合った企業を見つける方法を学んでください。
「どこでもいい」就活はやめよう

実際、なんとなくで就職した人は、職場の雰囲気や業務内容が合わずに短期間で退職してしまうことが多くあります。せっかく就職したのに、すぐに転職活動をするのは大きな負担になりますよね。
だからこそ、「どこでもいい」ではなく、自分に合った企業を見極めることが大切になります。
「どこでもいい」就活が失敗してしまう理由

ここでは、「どこでもいい」就活が失敗しやすい理由を解説します。就職活動がうまくいかないと、「とにかく内定がほしい」「どこでもいいから就職したい」と思ってしまうこともあるでしょう。
しかし、そうした考えで就活を進めると採用担当者に自分の熱意や資質が伝わらないため、結果的に就職活動が長引き、苦しむことになりかねません。
①熱意が足りないことが採用担当者に伝わるから
就活を「どこでもいい」と思って進めていると、熱意が足りないことが採用担当者に伝わってしまうためおすすめしません。
採用担当者は「仕事に対して情熱を持っているか」を重視しているため、面接やエントリーシートを通して、熱意が不足していることを簡単に見抜いてしまうのです。
「仕事に対しての情熱が足りないのではないか」と疑問を抱かれることは、選考過程で評価を下げることにつながります。
②ありがちな志望動機しか作れないから
「就職できればどこでもいい」という考えでは、ありがちな志望動機しか作れずに、就活で不利となってしまいます。
明確な志望理由がないため、誰にでも当てはまるテンプレート的な志望動機になってしまうのです。
その結果、他の就活生と差別化できずに採用担当者の印象に残りにくくなるデメリットがあります。
③自分の資質が企業の期待するものと異なるから
「就職先はどこでもいい」と思って入社すると、自分の資質が企業の期待するものと合致しないことが多くあります。
企業ごとに求める人物像やスキルは異なるため、投げやりになって応募すると自分の強みや価値観と合わない企業を選んでしまうこともあるでしょう。
その結果、企業側に「この人は本当にうちで活躍できるのか?」と疑問を持たれて不採用となってしまう可能性が高まります。
「就職先はどこでもいい」で就活すると後悔する理由
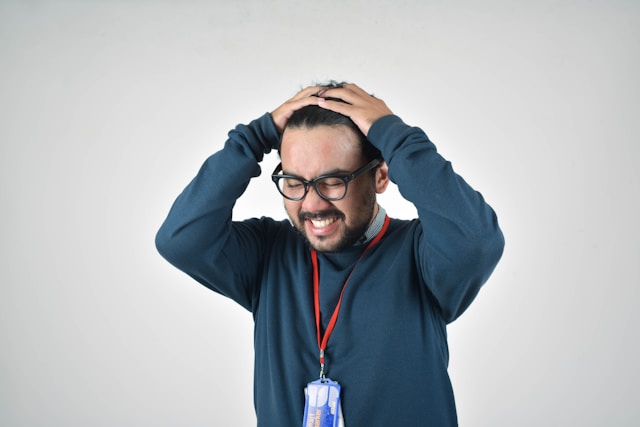
ここでは、「就職先なんてどこでもいい」と投げやりな就活をして後悔する理由を紹介します。
「どこでもいい」と思って入社した企業では、自分に合わない仕事や環境に苦しみ、長期的なキャリアに悪影響を及ぼすリスクがあることを知っておきましょう。
①労働環境の悪い企業に入社してしまうから
「どこでもいい」と思って企業を選ぶと、労働環境が悪い企業に入社してしまうことがあります。
例えば、過度な残業が常態化している、パワハラが横行している、休暇が取りづらいといった問題がある企業に入社してしまうと、自分の生活や健康を害してしまいかねません。
企業の労働環境を知る方法としては、企業の口コミサイトを確認する、実際に働いている社員の声を聞く、説明会や面接で職場の雰囲気について質問するなどがあります。
②就職しても自分に合わずにすぐ辞めてしまうから
「どこでもいい」と考えて就職した場合、すぐに辞めてしまうことも少なくありません。入社後に、仕事内容や職場の雰囲気が自分には合わないことに気付くからです。
特に、仕事にやりがいを感じられないとモチベーションを保てないため、働き続けるのが難しくなってしまうでしょう。
短期間で退職を繰り返すと、履歴書にも傷がついてしまいます。自己分析をしっかり行い、自分がどんな働き方をしたいのかを明確にした上で、企業選びを進めることが大切です。
③希望していた勤務地で働けない場合があるから
「どこでもいい」と考えて就職した企業では、希望していた勤務地で働けない場合があることを覚えておきましょう。
例えば、転勤が多い企業や勤務地を自由に選べない企業に入社すると、予期せぬ場所で働くことを命じられるかもしれません。
家族や友人と離れて慣れない土地で暮らすことは、想像以上に大きなストレスとなります。そのため、就職活動では勤務地の条件や転勤の有無をしっかり確認することが重要です。
④モチベーションが上がらずキャリアの成長が見込めないから
「どこでもいい」という気持ちで就職先を決めると、仕事に対するモチベーションが上がらないためキャリアの成長は見込めないでしょう。
自分が興味を持てない仕事を続けることは、長期的に見ると精神的な疲れやストレスの原因となり、キャリアアップのために必要なスキルや経験を積むことも難しくなるからです。
これを避けるためにも、自己分析を通じて「どんな仕事なら前向きに取り組めるか」を明確にした上で、企業を選ぶようにしましょう。
「どこでもいい」就活に逃げてしまう理由

ここでは、「就職できればどこでもいい」と逃げてしまう理由を紹介します。就職活動は人生における大きな転機となるため、慎重に進めるべきです。
しかし、思うようにいかない時期が続くと、周囲のプレッシャーや自分自身の不安から安易な選択に流されてしまうことも少なくありません。
- 不採用が続いてやる気を失ってしまうから
- 学歴に自信がなくネガティブになってしまうから
- 焦りから早く就職できる企業を選んでしまうから
- 就活を進めることを面倒に感じてしまうから
- 高い給与を貰えればどこでもいいと考えてしまうから
①不採用が続いてやる気を失ってしまうから
「どこでもいい」就活に逃げる理由に、不採用が続いてやる気を失ってしまうことがあります。
就職活動がうまくいかずに何度も選考に落ちてしまうと、「もうどこでもいいから内定が欲しい」という投げやりな気持ちになってしまうのです。
しかし、この状態では自分に合った企業を見つけられず、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
就職活動はメンタルの維持が重要です。長期戦になることを想定しながら無理のないペースで活動を続け、自分が納得できる企業を見つけましょう。
②学歴に自信がなくネガティブになってしまうから
学歴に自信がなくネガティブになることも、「どこでもいい」と思ってしまう原因になります。「自分に大手企業や憧れている業界で働くチャンスはない」と思い込んで就職先に妥協してしまうからです。
しかし、最初から諦めてしまうのはもったいないことです。実際に、多くの企業では学歴だけでなく「どのような経験をしてきたか」「どんな能力を持っているか」を重視する傾向が強まっています。
たとえ学歴に自信がなくても、アルバイトやインターンでの経験、資格取得、自己学習などをアピールすることで、自分の価値を伝えられることを覚えておきましょう。
③焦りから早く就職できる企業を選んでしまうから
焦ることも「どこでもいい」と考えてしまう理由になります。周囲が次々と内定をもらっていく中で自分だけが内定をもらえない焦りから、「どこでもいいから早く就職したい」と考えてしまうのです。
しかし、焦っていると労働環境や仕事内容をよく確認せずに決めてしまい、入社後に後悔することになります。
大切なのは内定のスピードではなく、「自分が納得できる企業かどうか」です。周囲と比べて焦るのではなく、自分のペースで企業選びを進めましょう。
④就活を進めることを面倒に感じてしまうから
就活を面倒に感じることも、「どこでもいい」就活に逃げてしまう理由です。書類選考や面接、自己分析など、やることが多すぎて疲れてしまうと、「もうどこでもいい」と考えてしまうのです。
しかし、面倒だからと適当に就職先を決めてしまうと、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔し、結局また転職活動をすることになるかもしれません。
就職先を選ぶというのは、将来の生活やキャリアに大きな影響を与える重要な決断です。だからこそ、面倒に感じても妥協せずに納得のいく選択をすることが大切です。
⑤高い給与を貰えればどこでもいいと考えてしまうから
高い給与を貰えればどこでもいいと考えてしまうことも、「どこでもいい」就活をしてしまう理由です。
もちろん、高い給与は魅力的な要素の1つです。しかし、給与だけを基準に就職先を選んでしまうと、仕事内容や職場環境が自分に合わずに長く続けられない可能性があります。
例えば、激務すぎてプライベートの時間が取れない、職場の人間関係が悪くストレスが溜まる、仕事にやりがいを感じられない、といった問題が発生することもあるでしょう。
そのため、やりがいを感じられる仕事、無理なく続けられる職場、人間関係の良い環境など、総合的に判断することが大切です。
「どこでもいい」就活から抜け出す方法
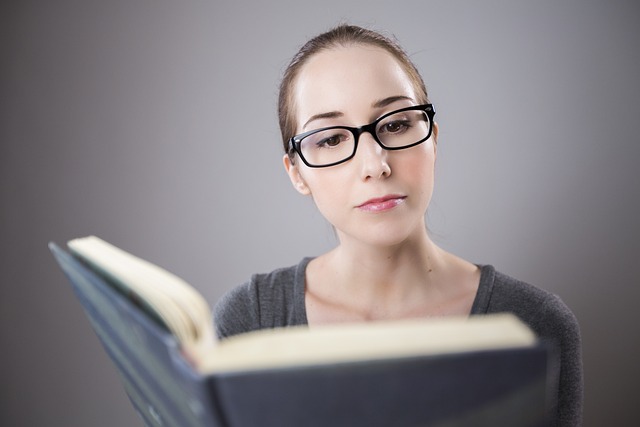
ここでは、「どこでもいい」就活から抜け出す方法を紹介します。
後悔しない就活を進めていくために、今すぐできる対策を一緒に見ていきましょう。
①焦る気持ちを落ち着ける
まずは、焦る気持ちを落ち着けましょう。就職活動の途中で、「早く内定が欲しい」「卒業前に決めないと不安」と焦りを感じることは誰にでもあります。
しかし、焦って無理に決めるのは逆効果です。まずは深呼吸をして、一度冷静になりましょう。「自分はなぜ焦っているのか?」と客観的に考えてみるのも有効です。
例えば、「周りがどんどん内定をもらっているから」焦っているのであれば、「早く内定を得るよりも自分に合った企業を見つけることが最優先」と意識を切り替えてみましょう。
②これまでの就活の改善点を見い出す
これまでの就活の改善点を見い出しましょう。自己分析をして、自分がどこでつまずいたのかを見極めることは大切です。
例えば、面接で緊張してしまった、エントリーシートがうまく書けなかった、企業の選定基準が曖昧だったなど、改善できる点はたくさんあります。
改善点を次のステップに活かすことで、前向きな気持ちで就活に臨めるようになります。これまでの経験を無駄にしないことが、ポジティブな気持ちで次のステップに進むためのコツです。
③自分自身の強みや能力を見直す
自己分析を行い、自分の強みや能力を見直すことも大切です。過去を振り返り、自分が他の人とどう差別化できるかを考えましょう。
良い結果を出したプロジェクトや学んできた専門知識、人間関係を築いた経験など、自分がどんな場面で強みを発揮してきたのかを振り返ることは効果的です。
自分の強みを再認識し、それを基に企業選びをすることで、より自分に合った企業を見つけるチャンスが広がります。
④就活で自分が大切にする軸を決める
自分が就活で大切にする軸を決めましょう。給料、福利厚生、働きやすさ、キャリアパスなど、自分が最も重視する点を整理してみてください。
例えば、給料や福利厚生を重視するなら、生活基盤をしっかり支えるために給与水準や福利厚生の充実度を軸に企業を選ぶことができます。
自分の価値観やライフスタイルに合った軸を決めることで企業選びが具体的になり、漠然とした「どこでもいい」気持ちはなくなります。
⑤業界・企業について研究する
自分が興味を持つ業界や企業について積極的に調べてみましょう。業界や企業について十分に理解していないと、「どこでもいい」と思ってしまいがちです。
まず、業界の動向を把握します。業界全体のトレンドや課題、成長の可能性について調べて今後の展望を理解することで、将来的に自分がどのような役割を果たせるかをイメージしやすくなるでしょう。
その後、企業ごとの特徴や企業文化を調べれば、自分がどのような環境で働きたいのか、どんな価値観の企業と合うのかが見えてきます。
業界や企業を深く理解することで、「どこでもいい」就活から脱却して自信を持って企業選びを進められるようになるのです。
⑥業界地図に目を通して選択肢を広げる
業界の動向を把握するために、業界地図に目を通してみましょう。業界地図は、各業界の主要企業やその規模、位置づけが一目で分かる資料です。
これを読むことで、自分が知らなかった企業や業界に気づけます。例えば、IT業界だけに目を向けていた場合、製造業や医療業界にも興味が湧くかもしれません。
自分の可能性を広げて就職活動に対するアプローチをより具体的にするために、業界地図は有効なツールとなります。
「どこでもいい」をやめて就活を成功させるコツ

ここでは、就活で「どこでもいい」をやめて内定を獲得するためのコツを解説します。
これらを実践することで、投げやりな気持ちを解消し、自分に合った企業を効率的に見つけられるでしょう。
①内定に有利に働くインターンに参加する
就活を成功させるために、インターンシップに参加することをおすすめします。実際に企業で働いて企業文化を知ることは、「どこでもいい」気持ちの解消につながるからです。
また、インターンシップでは企業の社員とも交流するため、面接だけでは伝えきれない自分の強みや人間性をアピールできます。
このような機会は、選考において大きなアドバンテージとなることは言うまでもありません。選考で有利となり気持ちに余裕が生まれれば、就活を前向きに進められます。
②就活エージェントを利用する
就活エージェントを活用することも、就活を成功させる大きなコツです。エージェントは、あなたの状況や希望に合わせて企業選びから面接対策まで幅広くサポートしてくれます。
専門的なアドバイスを受ければ、「どこでもいい」気持ちから脱却して自分に合った企業を絞りやすくなるでしょう。
また、エージェントは業界や企業についての深い知識を持っているため、自己分析や企業研究だけでは見落としてしまうような企業の特徴や魅力を教えてくれることがあります。
履歴書や面接の対策についても細かく指導してくれるため、自己PRの方法や面接時の対応に自信が持てるようになるでしょう。
③就職を目指しやすい業界に注目する
「どこでもいい」就活をやめて就活を成功させるためには、目指しやすい業界に絞ることも1つの方法です。
成長している業界や求人が増えている業界を選べば、就職の成功確率が高まります。その結果、気持ちに余裕が生まれ、就活のモチベーションも維持しやすくなるでしょう。
以下は、人手が不足しやすく未経験からでも活躍しやすい業界です。
| 販売・ サービス | 求人数が多く未経験でも採用されやすい。 接客経験があるとさらに有利。 |
| 営業職 | 営業スキルが身につけやすく、 未経験者向けの求人も豊富。 年齢や学歴不問の求人が多い。 |
| 事務職 | 比較的安定した職種で、求人も多い。 未経験者でも基本的なPCスキルさえあれば応募可能。 |
| IT系 | ITスキルが求められるものの エンジニアやプログラマーは人手不足で求人が多く 未経験からでも挑戦しやすい。 |
| カスタマー サポート | 顧客対応の経験が少なくても応募可能。 求人も多く、コミュニケーション能力を活かせる。 |
④大企業だけでなく中小企業にも注目する
大企業だけでなく中小企業に注目することも、就活成功のカギです。もしも、あなたが「大企業であればどこでもいい」と思っているのなら、中小企業にも目を向けてみましょう。
中小企業には、大企業にはない魅力がたくさんあります。企業の規模が小さいため社員1人ひとりの役割が大きく、自分の成長を実感しやすいことも中小企業ならではと言えるでしょう。
中小企業への就職も視野に入れることで選択肢が大幅に広がり、自分がより興味を持つ企業を見つけられる可能性が高まります。
⑤多くの企業に応募して選考の感覚をつかむ
就活を成功させるためには、多くの企業に応募して選考の感覚をつかむことが大切です。応募先を増やせば、面接やグループディスカッションの流れに慣れ、選考の対策も練りやすくなります。
「失敗を恐れず挑戦する」姿勢を身につけるためにも、一度の失敗に固執することなく、気持ちを切り替えて複数の企業に応募してみましょう。
挑戦を重ねることで改善点が見つかり、就活を進める中で成長できるため、結果的に内定獲得のチャンスが広がるのです。多くの企業に積極的に応募して経験を積むことが、就活成功の鍵となるでしょう。
どうしても就活がうまくいかない時に実施すること

ここでは、どうしても就活がうまくいかない時に実施したいことを紹介します。
就活を成功させるためには、選考ごとの対策を徹底することが重要です。
①説得力のある志望動機を盛り込んだ履歴書を作成する
説得力のある志望動機を盛り込んだ履歴書を作成しましょう。履歴書は基本情報や学歴が中心のため、限られたスペースで自分をアピールすることは難しいかもしれません。
しかし、志望動機で「なぜその企業なのか」「自分がその企業でどのように貢献できるか」を明確に伝えられなければ企業の目には留まりません。
企業が求める人材像と自分のスキルや経験のマッチングを強調することで、他の応募者との差別化ができ、書類選考を通過する可能性が高まるでしょう。
②企業の求める人物像に沿ったエントリーシートを作成する
企業の求める人物像に沿ったエントリーシートを作成することも大切です。そのために、まずは企業のウェブサイトや採用情報、社内の雰囲気やメッセージをチェックしましょう。
その企業が大切にしている価値観や目指している方向性を把握することで、自分の強みや経験が企業にどう役立つのかをエントリーシートに記載しやすくなります。
採用担当者に「この人は自社に適した人材だ」と感じてもらえれば、選考を有利に進められるでしょう。
③企業の適性検査に向けた対策を行う
企業の適性検査に向けた対策も行いましょう。特に、SPIや玉手箱といった適性検査は多くの企業が選考の重要なステップとして位置づけているため、事前にしっかり準備しておくことが大切です。
まず、適性検査の形式や内容を把握して問題集や過去問を繰り返し解くことで、試験の傾向や出題形式に慣れましょう。適性検査には時間制限がある場合が多いため、時間配分を意識しながら解く練習をすることも大切です。
適性検査の準備をしっかり行うことで、選考の際に焦らず落ち着いて取り組むことができ、より有利な立場で就活を進められます。
④グループディスカッションの練習をする
グループディスカッションの練習も欠かせません。グループディスカッションでは、単に自分の意見を述べるだけでなく、他のメンバーとの意見交換を円滑に進めることが求められます。
そのため、事前に友人や仲間と練習を重ねることで、議論が滞った際に進行役として立ち回れるようになったり、他のメンバーの意見を引き出すスムーズな発言ができるようになったりします。
グループディスカッションで協調性やリーダーシップ、積極性などを発揮できれば、企業から高く評価されて選考通過に大きなプラスとなるでしょう。
⑤面接の対策を徹底する
面接の対策も徹底しましょう。面接では、自己紹介や志望動機をしっかりと伝えることはもちろん、相手に良い印象を与えるために言葉遣いや身だしなみ、表情にも注意を払う必要があります。
事前に模擬面接を行うことで、実際の面接の流れを把握し、どんな質問が来ても冷静に対応できるようになります。
自信をもってリラックスして自分をアピールできれば、採用担当者に自分の魅力が伝わり、内定に大きく近づけるでしょう。
就職活動は「どこでもいい」ではなく自分で選ぼう
就職活動は人生における大きな転機であり、軽い気持ちで臨むべきではありません。
「どこでもいい」と考えるのではなく、自分が本当にやりたいことや成し遂げたい目標をしっかりと見つめ直すことが大切です。
自分の成長ややりがいを感じられる職場を選べれば、就職後も充実した日々を送れるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










