医師の平均年収を徹底解説!年代・診療科・勤務先別の最新データ
医師は社会的地位の高い職業として知られていますが、実際の年収は年代・診療科・勤務先などによって大きく異なります。
この記事では、最新データをもとに医師の平均年収を徹底解説し、年代別・診療科別・勤務先別の詳細から、キャリア戦略、手当や福利厚生の実態、医師の“リアルな収入事情”をわかりやすく紹介します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
医師の平均年収はどれくらい?

医師の平均年収は、おおよそ1,200~1,300万円程度とされており、日本の全職種の中でも非常に高い水準にあります。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和6年)」によると、医師の平均年収は約1,338万円で、月額給与およそ90万円、年間賞与が約255万円です。
この数字は全産業平均(約530万円)の約2.5倍にあたります。専門知識の習得に長い年月を要し、診療や判断に高い責任が伴うことが高収入の背景にあるといえるでしょう。
勤務医の場合、所属する病院の規模や所在地、勤務体系によって年収は変わります。大学病院では研究や教育の比重が高く、給与が抑えられる傾向にあります。
また、開業医の場合はクリニックの経営状況によって収入が大きく異なります。いずれの形態であっても、医師という職業は経済的な安定性が高く、長期的なキャリア形成がしやすい職種といえるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」
- 厚生労働省「医療経済実態調査」
- OpenWork 年収事例:東京女子医科大学病院で医師3年目に年収1,300万円
- OpenWork 年収事例:医療法人徳洲会で研修医1年目550万円、10年目1,200万円程度
年代別に見る医師の平均年収

医師の平均年収は年代や経験、勤務形態によって大きく変わります。就活生にとって医師は「高収入」という印象が強いですが、実際には立場や環境で収入に差があります。
ここでは、厚生労働省などの公的統計や信頼できる情報をもとに、医師の年収の実態をわかりやすく解説します。
| 年代 | 平均年収(目安) |
|---|---|
| 20代 | 500万円前後 |
| 30代 | 1,000万円前後 |
| 40代 | 1,350万円前後 |
| 50代 | 1,600万円前後 |
| 60代 | 1,500万円前後 |
勤務医の平均年収はおよそ1,300万円前後とされています。これは公的な賃金統計をもとにした数値で、給与と賞与を合わせた金額です。
大学病院では年収が低くなる傾向がありますが、地方病院や夜勤の多い職場では高くなる場合もあります。
20代では研修医として400〜600万円台、30代で1,000万円前後、40〜50代で1,500万円を超えるケースも多く、経験を積むほど収入が上がる傾向です。
外科系が高く、内科や小児科はやや低めという傾向があります。勤務地による差も大きく、都市部より地方病院のほうが待遇が良い場合も見られます。
自分がどんな働き方やライフスタイルを望むかを考えたうえで、口コミや求人情報を確認しておくことが現実的です。
引用:
診療科別で見る医師の平均年収

医師の平均年収は診療科によって大きく異なります。厚生労働省などの統計によると、全体平均は約1,300万円前後ですが、診療科によっては2,000万円を超える場合もあります。
この差は、勤務形態や夜間当直の有無、自由診療の割合、地域の医師需要などが影響しており、開業医か勤務医かによっても収入構造が大きく変わります。
外科や整形外科などの外科系は、手術や緊急対応の手当がつきやすく、高収入を得やすい分野です。
一方で内科系は安定した勤務環境を選びやすく、働き方改革の影響でワークライフバランスを重視する医師が増えています。
皮膚科や眼科などは、自由診療を取り入れることで収入を大きく伸ばせます。美容医療やレーシックを扱う開業医は、年収2,000万円を超えることもありますが、競争が激しく経営力も求められます。
麻酔科や放射線科、救急科は専門性が高く、安定した高収入を得やすい診療科です。AI診断や在宅読影など新しい働き方も広がっており、今後も需要が高まる分野といえるでしょう。
- 外科:1,503.1万円
- 整形外科:1,548.7万円
- 脳神経外科:1,488.7万円
- 心臓血管外科:1,412.8万円
- 内科:1,469.8万円
- 消化器内科:1,446.3万円
- 循環器内科:1,461.2万円
- 呼吸器内科:1,408.2万円
- 小児科:1,366.3万円
- 産婦人科:1,526.8万円
- 精神科:1,481.9万円
- 皮膚科:1,399.2万円
- 眼科:1,410.1万円
- 耳鼻咽喉科:1,514.1万円
- 泌尿器科:1,481.9万円
- 放射線科:1,333.3万円
- 麻酔科:1,406.4万円
- 救急科:1,354.1万円(※救命救急科の数値)
- 診療科による年収差の要因:勤務形態、当直回数、自由診療比率、地域の医師需給、開業の有無、求人数の多さなどが影響します。
このように、医師の年収は診療科によって構造的に差が生まれます。手術を伴う外科系や高い専門性が求められる分野ほど収入が高くなりますが、身体的負担も増す傾向があります。
年収だけでなく、働き方の自由度やキャリアの継続性を見据えた診療科選びが、将来の満足度を左右するといえるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「勤務医・開業医の給与・収支差額データ」
- 厚生労働省「臨床研修医の処遇(年収レンジ)」
- 民間医局コネクト「診療科別の年収ランキング(10,233件の募集データに基づく)」
- 第23回医療経済実態調査(勤務医・診療所データ)
勤務先・勤務地別で変わる医師の平均年収

医師の年収は、勤務先や勤務地によって大きく異なります。特に大学病院や民間病院、クリニックなどでは、給与体系や仕事内容に差が出やすいです。
ここでは、それぞれの勤務先ごとの特徴や年収の違いを、信頼できるデータに基づいて解説します。
- 大学病院
- 国公立病院
- 民間病院
- クリニック
- 診療所
①大学病院
大学病院で働く医師の年収は、卒後年次や役職によって大きく変わります。初期研修医では約400万円前後、助教や講師クラスになると700〜900万円程度が一般的です。
大学病院では研究や教育の比重が高く、診療による収入が直接反映されにくい傾向があります。
一方で、大学病院勤務は専門医資格の取得や研究実績の蓄積、人脈構築など、長期的なキャリア形成において大きな強みがあります。
短期的な収入よりも医師としての成長を重視する人にとって、大学病院は魅力的な職場といえるでしょう。
②国公立病院
国公立病院の医師は、公務員的な待遇と昇給制度による安定性が特徴です。平均年収は900〜1,200万円ほどで、福利厚生も手厚く、住宅手当や家族手当、退職金などが整っています。
ただし、給与の上限が決まっている場合も多く、大きな年収アップは見込みにくい傾向があります。安定を求める医師には適していますが、収入を最優先に考える人には物足りなさを感じる場面もあるでしょう。
③民間病院
民間病院は、経営方針や診療科によって年収の差が最も大きい勤務先です。平均年収はおおよそ1,200〜1,800万円ほどで、成果に応じた報酬制度を採用している病院も多くあります。
特に地方の中核病院では、医師確保のために高い給与が提示されるケースも見られます。その一方で、労働時間が長くなりやすく、負担が大きくなることもあります。
自分の価値観や働き方に合った職場を選ぶことが、収入と生活のバランスを取るうえで重要です。
④クリニック
クリニック勤務医の年収は、診療科や地域、患者数によって変動します。平均年収は1,000〜1,500万円前後が一般的で、夜勤や当直が少なく勤務時間が安定している点が魅力です。
また、将来開業を目指す医師にとっては、経営ノウハウを学べる貴重な場でもあります。ただし、患者数や診療報酬の変動が収入に直結するため、安定して稼ぐには患者との信頼関係づくりが欠かせません。
柔軟な働き方を求める医師に人気の勤務先といえるでしょう。
⑤診療所
診療所は地域医療を支える重要な存在であり、勤務医の平均年収はおよそ1,000万円前後です。小規模経営のため、診療科や地域によって収入差が生じやすい傾向があります。
勤務医として働く場合は、院長の方針や経営状況が給与に直結するため、事前に労働条件を確認することが大切です。
一方で、開業医となれば年収2,000万円を超えることもあり、独立を視野に入れる医師にとって診療所勤務は貴重な経験の場となります。
引用:
- 厚生労働省「臨床研修医の処遇」
- 厚生労働省「第23回医療経済実態調査」
- OpenWork「医療法人鉄蕉会」医師の平均年収データ
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」医師の年収データ
- PHCホールディングス:開業医と勤務医の年収比較
医師が年収を上げるための方法・キャリア戦略
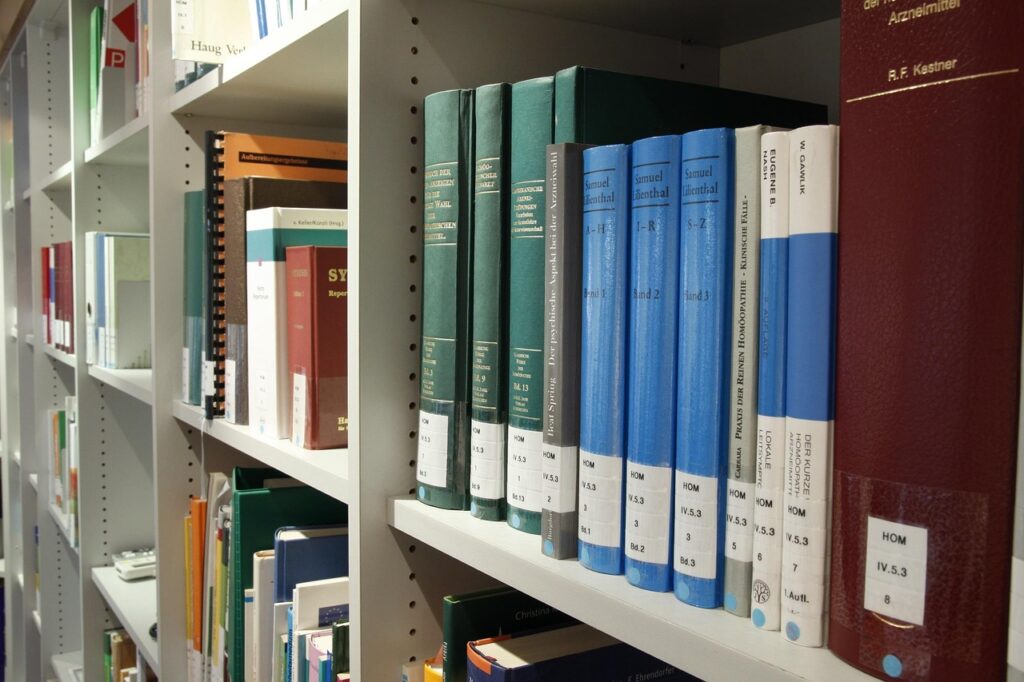
医師として働くうえで、年収の差は勤務先やキャリアの方向性によって大きく変わります。ここでは、転職・資格取得・副業など、収入を上げるための現実的な方法を紹介します。
あなたの将来設計に合わせて、最適なキャリア戦略を見つけてください。
- 高収入につながる転職・勤務先の選び方
- 専門医資格・スキルアップによる収入向上
- 役職・管理職への昇進による年収アップ
- アルバイト・非常勤勤務の活用方法
- フリーランス医師として働く選択肢
- 資産運用・副業による収入の多角化
①高収入につながる転職・勤務先の選び方
医師が年収を上げたいと考えるとき、もっとも効果的なのが転職です。勤務医の給与は、大学病院よりも民間病院のほうが高く、さらに都市部より地方の医療機関のほうが報酬が高い傾向があります。
地方では医師不足が深刻なため、給与が2倍近くになることもあります。条件交渉や福利厚生も、転職先によって大きく変わる点です。
一方で、給与だけを基準に選ぶと、労働時間や人間関係のストレスが増え、長期的なキャリアに悪影響を及ぼすこともあります。
そこで、転職エージェントを活用し、給与以外に勤務体制やキャリア支援制度を比較検討することが重要です。自分の将来像と一致する職場を選べば、収入だけでなく、医師としての成長も実現できるでしょう。
②専門医資格・スキルアップによる収入向上
医師の収入を決定づける要素のひとつが専門性です。麻酔科、形成外科、放射線科などの専門医は、一般診療科に比べて高収入を得やすい傾向があります。
専門医資格の取得には数年間の研修や試験を経る必要がありますが、資格を持つことで転職市場での評価が上がり、年収アップにつながります。
また、近年では語学力を生かして海外医療や国際医療協力に携わる医師も増えています。英語論文の執筆や国際学会への参加は、専門性の証明となり、キャリアの幅を広げる強力な武器になります。
さらに、AI医療や遠隔診療といった新領域のスキルを学ぶことも将来的に高収入へとつながるでしょう。学びを継続する意識こそが、安定したキャリアを築く鍵です。
③役職・管理職への昇進による年収アップ
医師としてのキャリアを積み重ねる中で、管理職や部長職への昇進は年収を上げる確実な手段です。大規模病院や医療法人では、経営に携わるポジションになると手当や賞与が増え、総収入が大きく伸びます。
また、診療方針の決定や若手医師の育成など、裁量を持って働けるのも魅力です。
ただし、昇進には医療技術だけでなく、リーダーシップや経営感覚が求められます。チーム運営や組織マネジメントのスキルを磨くために、MBA取得や医療経営セミナーに参加する医師もいます。
目の前の診療に加え、経営的視点を持つことが、年収と信頼の両方を高める近道になります。
④アルバイト・非常勤勤務の活用方法
常勤医として勤務しながら、アルバイトや非常勤を組み合わせることで、効率的に年収を増やせます。
健診や産業医、当直勤務、ワクチン接種など、短時間で高報酬の案件は多く、自由な働き方が実現しやすいです。特に専門資格を持つ医師は、限られた時間でも高い時給で働けるチャンスがあります。
ただし、過度な労働は疲労や本業への悪影響を招くおそれがあります。そのため、働く目的を明確にし、体調とスケジュールのバランスを意識してください。
近年では医師専用の求人サイトで、条件に合った勤務先を柔軟に選べるようになっています。空き時間を上手に使いながら、無理のない範囲で収入を増やすことが、長期的なキャリア形成につながるでしょう。
⑤フリーランス医師として働く選択肢
フリーランス医師は、近年注目を集める働き方です。常勤契約に縛られず、複数の病院やクリニックでスポット勤務を行い、自分のペースで報酬をコントロールできます。
週に数日働くだけでも、一般的な常勤医に匹敵する収入を得るケースもあります。
一方で、安定収入や福利厚生が得にくい点はリスクです。税金・保険・契約の手続きなど、自己管理が求められます。独立前に税理士や労務の専門家へ相談し、準備を整えておくと安心です。
また、自身の専門分野を明確に打ち出すことで、医療機関からの信頼を得やすくなります。自由度を重視し、自らの裁量で働きたい医師には、フリーランスという選択肢が最適でしょう。
⑥資産運用・副業による収入の多角化
医師は安定した職業といわれますが、将来の変化に備えるためにも、資産運用や副業で収入を多角化することが重要です。株式・投資信託・不動産などの運用は、長期的に資産を育てる手段として効果的です。
余裕資金を活用し、リスクを分散しながら安定したリターンを狙いましょう。
また、医師の専門知識を生かした副業も増えています。オンライン講座の講師、医療記事の監修、製薬会社のアドバイザーなど、知識を収入に変える機会は多岐にわたります。
ただし、投資や副業はリスクもあるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めてください。複数の収入源を持つことで、経済的な安心感を得ながら、医師としての可能性を広げられるでしょう。
開業医と勤務医の違い

医師としての働き方には「開業医」と「勤務医」があります。それぞれに収入の構造や働き方、責任の重さが異なり、将来のキャリア形成にも大きく関わります。
ここでは、就活生が医療業界をより深く理解できるよう、両者の違いをさまざまな視点から整理して解説します。
- 年収・収入構造の違い
- 勤務形態・労働時間の違い
- 業務内容・責任範囲の違い
- 経営リスク・安定性の違い
- キャリアパス・将来性の違い
- ワークライフバランスの違い
- 必要なスキル・資質の違い
①年収・収入構造の違い
医師の年収は、勤務形態によって大きく異なります。勤務医は病院や大学などの医療機関に所属し、給与と賞与が安定しています。
昇給や福利厚生も制度として整っており、生活の見通しが立てやすい働き方です。一方、開業医は自らのクリニックを経営し、収入が自分の努力と戦略によって大きく変動します。
経営が成功すれば勤務医を大きく上回る年収を得られますが、患者数の減少や設備投資の負担によって赤字になるリスクも存在します。
自分の性格や目指す生活スタイルに合わせて、どちらの仕組みが合うかを見極めることが大切です。
②勤務形態・労働時間の違い
勤務医はシフト制で勤務することが多く、夜勤や当直があるなど、勤務時間が不規則になりがちです。特に大学病院や救急病院では緊急対応が求められる場面が多く、体力面での負担が大きい傾向があります。
一方、開業医は診療時間を自ら設定できるため、生活リズムを整えやすい面があります。
ただし、表向きの診療時間が短く見えても、実際には事務処理やスタッフ管理、会計業務などに追われることが少なくありません。
勤務医は医療行為に集中できる環境が整っており、研究や専門性の向上に時間を使える点がメリットです。対して開業医は、自分の裁量で時間を使える反面、経営者としての責任も背負います。
③業務内容・責任範囲の違い
勤務医の主な業務は、診療や手術などの医療行為に集中することです。病院組織の一員としてチーム医療を行い、上司の指示や病院方針に従いながら患者を治療します。
開業医は診療だけでなく、経営全般にも関わります。クリニックの方針決定、人事採用、宣伝、経理など、経営者としての判断が日常的に求められます。
そのため、医療知識だけでなく、経営センスやマネジメント力も必要になります。一方で、開業医は自分の理想とする医療を実現しやすいという魅力もあります。
責任の重さと自由度の高さが共存しているのが開業医の特徴であり、この両立を楽しめる人に向いているでしょう。
④経営リスク・安定性の違い
勤務医は病院に雇用されているため、給与は毎月一定で、経営状況に直接影響されることは少ないです。勤務先が安定している限り、生活の基盤も安定しやすい働き方といえます。
対して開業医は、クリニックの経営成績がそのまま収入に直結します。地域の需要や競合状況、患者層、医療制度の変更など、外部要因に大きく左右される点が特徴です。
特に診療報酬制度の改定や医療機器の更新コストは経営を圧迫する要因になりやすく、経営者としての判断が欠かせません。
つまり、勤務医は「守りの安定型」、開業医は「攻めの自立型」という特徴を持つ働き方です。どちらを選ぶかは、自分の性格や将来のリスク許容度によって異なるでしょう。
⑤キャリアパス・将来性の違い
勤務医のキャリアは、経験年数や実績に応じて階段を上るように進んでいきます。専門医資格を取得したり、研究成果を発表したりすることで、教授や部長、病院幹部などへの道が開けます。
一方で、組織の中では人事評価や昇進のスピードに限界があることも事実です。開業医は、自らのビジョンを基に独自の医療を展開できる点で自由度が高く、努力次第で事業を拡大することも可能です。
成功すれば複数のクリニックを経営する医師も珍しくありません。また、地域社会に貢献しながら長く働けることも魅力です。
医師としてどんな貢献をしたいのか、どんな環境で成長したいのかを明確にすることで、自分に最も適したキャリアパスを描くことができるでしょう。
⑥ワークライフバランスの違い
勤務医は病院の勤務体制に従うため、勤務時間や休日の融通が利きにくい場合があります。特に救急や外科などでは当直や緊急対応が多く、プライベートの時間を確保するのが難しいこともあります。
開業医は診療時間を自由に設定できるため、家庭や趣味との両立がしやすい点が魅力です。
しかし、実際には経営上の雑務や人事対応などに時間を取られることもあり、完全にオフを取るのは簡単ではありません。
勤務医は「制度に守られた働き方」、開業医は「裁量を持つ働き方」といえます。どちらを選んでも、無理のない働き方を見つけることが、長く医療に携わるうえでの鍵になるでしょう。
⑦必要なスキル・資質の違い
勤務医に求められるのは、専門知識の深さとチーム医療における協調性です。上司や同僚との連携、患者や家族への丁寧な説明など、医療現場では人間関係の構築が欠かせません。
開業医はそれに加えて、経営力・判断力・リーダーシップが求められます。医療の質を維持しつつ経営を安定させるには、数字を読む力や地域との信頼づくりが重要です。
勤務医は組織の一員として協調的に動くスキルを磨くことが求められ、開業医は自らの理念を形にするための発信力と経営感覚を養う必要があります。
どちらも「患者の信頼を得る力」が基盤であり、医師としての本質を忘れずに成長を続ける姿勢が大切です。
医師の月給・賞与(ボーナス)の実態

医師の収入は高額という印象がありますが、支給の仕組みや手当の内容まで把握している人は多くありません。勤務先や診療科、役職によって月給や賞与が大きく変わるからです。
ここでは、医師の平均月収やボーナスの実態、報酬体系の種類、公務員医師との差など、就活生が押さえておきたい点を具体的に説明します。
- 医師の平均月収と支給形態
- 賞与・ボーナスの相場と算出基準
- 年俸制・出来高制の報酬体系
- 公務員医師の給与・ボーナスの特徴
①医師の平均月収と支給形態
医師の平均月給は約100万円前後とされており、勤務先や役職、診療科によって差があります。一般的には大学病院よりも民間病院の方が給与水準が高く、夜勤や当直の回数が多いほど収入が増える傾向です。
支給形態は基本給に加え、時間外手当や当直手当、住宅手当などが加算される場合が多く、固定給の安定と手当の柔軟さが特徴といえます。
また、臨床研修医の給与は年額300万円台から700万円台までと幅があり、経験や勤務先によって大きく異なります。
就活生は求人票の「月給額」だけでなく、手当の有無や支給条件をしっかり確認しておくことが大切です。支給形態を理解しておくことで、就職後の収入ギャップを防ぎやすくなります。
②賞与・ボーナスの相場と算出基準
医師の賞与は年2回支給されることが多く、年収の15~25%ほどを占めるケースが一般的です。賞与額は勤務実績や評価制度、勤続年数、診療への貢献度などを基に算出されます。
公立病院では基準が明確で安定している一方、民間病院では経営状況によって変動する場合があります。賞与は単なるボーナスではなく、医師としての努力や成果が正当に評価される重要な指標です。
就活生は「固定給が高いか」「賞与で調整されるか」を見極めることで、自分に合った職場を選びやすくなるでしょう。
③年俸制・出来高制の報酬体系
医師の報酬体系には主に「年俸制」と「出来高制」があります。年俸制は年間で定めた金額を月割りで支給する仕組みで、収入の安定性が高い点がメリットです。
勤務医の多くはこの方式を採用しています。一方、出来高制は診療件数や成果に応じて報酬が変動し、努力次第で高収入を目指せる点が魅力といえるでしょう。
特に美容外科や自由診療を扱うクリニックでは出来高制の割合が高く、スキルや集患力が評価に直結します。安定を求めるなら年俸制、成果重視なら出来高制が向いています。
④公務員医師の給与・ボーナスの特徴
公務員医師は地方自治体や国立病院などに勤務し、公務員として給与が支給されます。給与体系は職務等級と勤続年数に基づき、安定した収入が得られる点が特徴です。
ボーナスも年2回支給され、景気の影響を受けにくいのも利点です。
ただし、昇給ペースは緩やかで、当直手当などの加算が少なめな傾向があります。
収入よりも安定性や福利厚生、働きやすさを重視する人には適した働き方といえるでしょう。地域医療への貢献や家庭との両立を望む医師にも向いています。
引用:
医師の手当・福利厚生の内容

医師の収入を考えるうえで、基本給に加えて支給される「手当」や「福利厚生」は欠かせない要素です。勤務形態や病院の方針によって内容が異なり、年収に大きな影響を与えることもあります。
ここでは、代表的な手当の種類や医療機関ごとの福利厚生、住宅手当や研修支援制度などについて詳しく紹介します。
- 代表的な手当の種類(当直・時間外・資格手当など)
- 医療機関ごとの福利厚生制度
- 住宅手当・学会参加補助・研修費支援の有無
- ワークライフバランスを支える支援制度
①代表的な手当の種類(当直・時間外・資格手当など)
医師の給与には、基本給のほかに多くの手当が含まれています。中でも当直手当や時間外手当は、勤務時間の不規則さを反映した重要な要素です。
当直は1回あたり数万円支給されることが多く、勤務頻度によって月収が大きく変わります。
また、専門医や指導医といった資格を持つ医師には「資格手当」が上乗せされる場合もあり、スキルや経験が収入に直結します。
単に「年収〇〇万円」と記載されていても、手当の有無で生活水準は変わるため、見逃さないよう注意してください。
②医療機関ごとの福利厚生制度
勤務する医療機関によって、福利厚生の内容は大きく異なります。大学病院では研究支援や研修制度が整っている一方、地方の中小病院では住宅補助や通勤手当が手厚い傾向があります。
国公立病院では公務員に近い待遇で、休暇制度や退職金が安定している点が魅力です。民間病院では成果に応じたインセンティブや自由度の高い働き方が選べる場合も多いでしょう。
こうした違いを理解せずに就職先を選ぶと、「思っていた環境と違う」と感じてしまうこともあります。福利厚生は単なる付加要素ではなく、長期的に働くうえでの安心を支える重要な仕組みだといえます。
③住宅手当・学会参加補助・研修費支援の有無
医師の仕事は専門性が高く、常に学び続ける姿勢が求められます。そのため、多くの医療機関では学会や研修への参加を支援しています。
交通費や宿泊費、参加費の一部を補助してくれる場合もあり、自己負担を抑えながらスキルアップを目指せます。さらに、都市部の高い家賃をカバーする住宅手当も重要な福利厚生のひとつです。
こうした支援制度は、経済的な負担を軽くしながら医師の成長を後押しします。就職活動の際には、給与額だけでなく、これらの制度が整っているかどうかを確認しておくと安心でしょう。
④ワークライフバランスを支える支援制度
医師の仕事は長時間労働になりやすく、私生活との両立が課題となることも少なくありません。
最近では、産休・育休の整備や短時間勤務制度の導入など、ワークライフバランスを重視する医療機関が増えています。
特に女性医師の復職支援や、院内保育所の設置なども進んでおり、安心して働ける環境づくりが広がっています。
また、メンタルヘルスのサポート体制や相談窓口を設ける病院もあります。働きやすさは給与だけでは測れません。こうした制度の充実度を知ることで、自分に合った働き方を選びやすくなるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「共済のしおり」 — 医師手当・時間外手当・宿日直手当など
- 天竜病院公式サイト — 医師手当・手当構成など具体例
- OpenWork — 医療法人の福利厚生に関するクチコミ
- 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」制度解説 — 医療機関にも適用可能性
医師のやりがいと魅力

医師という職業は「高収入」という印象が強いですが、実際にはお金以外にも多くの魅力があります。
ここでは、医師として働くうえで感じる精神的な満足や社会的な意義、そしてキャリアとしての安定性について詳しく見ていきましょう。
- 患者との信頼関係と社会的貢献
- 医療技術の進歩と専門性の発揮
- 高収入以外のキャリア的価値
- 生涯働ける専門職としての安定性
①患者との信頼関係と社会的貢献
医師のやりがいの大きな部分は、患者との信頼関係を築きながら社会に貢献できる点にあります。命を預かる仕事であるため責任は非常に重いですが、その分だけ人の人生を支え、希望を与えることができます。
診察や治療を通じて患者の不安を軽くし、回復を見届ける瞬間には言葉では表せない達成感があるでしょう。
特に地域医療や家庭医療では、患者や家族と長い時間をかけて関係を築き、人生の節目にも寄り添うことが求められます。
こうした関係性は単なる医師と患者の枠を超え、人として深く信頼される喜びをもたらします。医師という仕事は、人との絆を通じて社会に確かな貢献を果たせる尊い職業なのです。
②医療技術の進歩と専門性の発揮
医療の現場は日々進歩しており、医師は常に最先端の知識と技術を学び続ける必要があります。AIによる診断支援、遠隔医療、ロボット手術など、医療技術はかつてないスピードで進化しています。
こうした環境では、努力次第で自分の専門性を高め、より多くの命を救うことが可能です。新しい知識を吸収して臨床に応用する過程で、自身の成長を日々実感できるのも医師の魅力といえるでしょう。
さらに、専門分野を深めることでチーム医療の中心的存在となり、後輩医師の指導や研究への参加など、さまざまな形で貢献できます。
最新医療に携わることで、自分の知識が社会に還元されるという喜びを得られるのです。医師という職業は、学びと挑戦を繰り返すことで、常に新しい自分に出会える職種といえるでしょう。
③高収入以外のキャリア的価値
医師は高収入という側面が注目されがちですが、それ以上にキャリアの選択肢が広い職業です。
臨床現場で患者と向き合う以外にも、大学や研究機関での教育・研究、行政や医療政策への関与、医療ベンチャーへの参画など、多彩な道が開けています。
近年では、企業の産業医として従業員の健康管理に携わる医師や、海外で国際医療支援を行う医師も増えています。
こうした多様な進路は、医師として培った専門知識や判断力が社会のあらゆる場で求められている証拠です。収入だけでは測れない「生涯を通じた成長と社会的価値」を実感できる職業といえるでしょう。
④生涯働ける専門職としての安定性
医師の魅力の一つは、景気や時代の変化に左右されにくい安定性です。どんなに社会が変化しても医療ニーズはなくならず、全国どこでも医師の需要があります。
これは他の職種にはない強みといえるでしょう。勤務医として病院で働き続ける道だけでなく、開業医として独立する選択肢もあります。自分のペースで働き方をコントロールできる点も大きな利点です。
さらに、定年後も非常勤や地域医療、産業医として活躍するケースも多く、生涯現役でいられる職業でもあります。
医師という資格は、安定と自由を両立できる「人生の資産」として、将来を見据える就活生にとっても大きな魅力になるはずです。
医師の仕事の大変さ

医師という職業は高収入で安定した印象を持たれやすいですが、その裏には多くの苦労があります。
特に長時間労働や精神的な負担、家庭との両立の難しさなど、学生の段階では見えにくい現実も少なくありません。ここでは医師の仕事の厳しさを4つの側面からわかりやすく紹介します。
- 長時間労働と当直勤務の実態
- 責任の重さと精神的プレッシャー
- ワークライフバランスの課題
- キャリア継続における健康管理とメンタルケア
①長時間労働と当直勤務の実態
医師の働き方で最も過酷といわれるのが、長時間労働と当直勤務です。勤務医の多くは1日10時間を超える勤務を続けており、手術や救急対応が立て込むと休憩を取れないまま朝を迎えることもあります。
こうした勤務環境は、医療現場の人手不足や緊急性の高い業務が要因で、特に地方病院では医師1人あたりの負担がさらに大きくなりがちです。
当直明けにそのまま外来診療を行うケースも珍しくなく、慢性的な睡眠不足に陥ることも少なくありません。
最近では、働き方改革の一環として、医師の勤務時間に上限を設ける動きも始まりました。しかし、現場では人員が足りず、理想どおりに運用できていない病院も多いのが実情です。
医師を目指すなら、このような現場の現実を理解し、自身の体調管理と働く環境への意識を高めておくことが大切でしょう。
②責任の重さと精神的プレッシャー
医師は人の命を預かる立場であり、どんな場面でも正確で迅速な判断が求められます。たとえ小さな判断でも結果が患者の人生を左右する可能性があり、その重責は計り知れません。
特に若手医師は経験が浅く、常に緊張感の中で判断を迫られます。自分の診断に自信を持てず、ミスを恐れて眠れなくなる人もいます。
患者や家族への説明も重要で、誤解を避けるために言葉を選ぶ慎重さも求められます。こうした日々のプレッシャーが積み重なり、燃え尽き症候群やメンタル不調に陥ることもあります。
精神的な負担を和らげるためには、周囲との信頼関係を築き、悩みを共有できる環境を整えることが重要です。責任感は大切ですが、1人で抱え込みすぎない姿勢が長く働く秘訣といえるでしょう。
③ワークライフバランスの課題
医師の働き方改革が進んでいるとはいえ、ワークライフバランスの実現は依然として難しい課題です。特に若手医師や研修医の間は、休みが少なく、生活の大半を病院で過ごすケースが一般的です。
緊急対応の多い診療科では、プライベートの予定を立てにくいこともあります。
一方で、近年は医療現場の意識も変化しつつあり、柔軟な働き方を取り入れる病院が増えています。
時短勤務や当直免除制度、在宅診療などを組み合わせることで、子育てや介護と両立しながら働く医師も少なくありません。さらに、AIや電子カルテの活用により、業務の効率化も進んでいます。
理想のライフスタイルを実現するためには、就職前に病院の働き方や勤務体制をしっかり調べておくことが欠かせません。自分に合った環境を選ぶ意識が、キャリアを長く続ける鍵となるでしょう。
④キャリア継続における健康管理とメンタルケア
医師は人の健康を守る仕事ですが、自身の健康管理をおろそかにしてしまうことが少なくありません。多忙なスケジュールや不規則な生活、緊張の連続によって、心身の疲労が蓄積しやすい職業です。
体調不良を放置したまま働き続けると、集中力が落ち、医療ミスのリスクも高まります。そのため、医師自身が「自分を守る意識」を持つことが非常に大切です。
最近では、医療機関内にカウンセリングルームやストレスチェック制度を導入する動きも増えています。
医師は強い使命感を持つ職業ですが、同時に「自分の健康があってこそ患者を支えられる」という意識を忘れないでください。
医師の年収を最大化するために知っておこう

医師の平均年収は勤務先や診療科、年代によって大きく異なります。特に大学病院や国公立病院では安定性が高い一方、民間病院やクリニックでは成果やスキル次第で高収入を得られる傾向があります。
結論として、医師が年収を上げるには、自身のキャリア戦略を明確にすることが重要です。
専門医資格の取得や転職、非常勤勤務・フリーランスなど多様な働き方を組み合わせることで収入の最大化が可能になります。また、開業医か勤務医かという選択も将来の収入構造を左右します。
医師の平均年収を正しく理解し、自分に合った働き方やスキルアップを計画的に進めることで、経済的にもキャリア的にも充実した医師人生を実現できるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














