内定者面談とは?質問例やお礼メールの書き方も紹介
「内定者面談って、何を話すの?」「準備ってどこまで必要?」
内定が決まった後に行われる面談は、入社前の大事なコミュニケーションの場です。企業によって目的や進め方は異なりますが、入社意思の最終確認や配属先決定、不安解消など重要な役割を担っています。
そこで本記事では、内定者面談の目的や流れ、事前準備のポイントから服装・持ち物、お礼メールの書き方まで、例文を交えて詳しく解説します。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
内定者面談には準備を整えて挑もう

内定者面談は、学生と企業の信頼関係を築く大切な場です。カジュアルな雰囲気に見えても、企業側はしっかりと学生の姿勢や意欲を見ています。
そのため、しっかりと準備をしておくことが安心して臨むポイントになるでしょう。内定者面談に参加する際、「気楽に行けばいい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、準備をせずに臨むと、企業に対して意欲や誠実さが伝わらず、不安を与えてしまうこともあるでしょう。逆に、企業研究や逆質問の準備をしておけば、自信を持って受け答えでき、好印象を残せます。
また、服装や持ち物、身だしなみも見られているポイントです。気が緩みがちな時期ではありますが、基本的なマナーを守れているかは、社会人としての自覚を示す上でも重要。
準備とは特別なことをするのではなく、当然のことを丁寧に行うこと。落ち着いて面談に臨むためにも、事前の準備を怠らないようにしてください。
内定者面談とは

内定者面談とは、企業が内定を出した学生に対して行う面談のことで、選考とは異なり、情報共有やフォローを目的としています。就活生にとっては、実際に働くイメージを深めたり、不安を解消したりする良い機会でしょう。
「内定が出たのに、また面談があるのはなぜ?」と不安に感じるかもしれませんが、多くの企業では、評価や再選考の場ではなく、むしろ内定辞退を防ぐためのサポートの場として行っています。
内定者の疑問や不安を聞き取ってくれるため、気になることは遠慮せず相談してみてください。また、若手社員や内定者の先輩が同席することも多く、実際の仕事内容や職場の雰囲気をリアルに知ることができます。
内定者面談は単なる形式的な手続きではありません。企業とお互いの理解を深めるための大切な機会です。
不安な気持ちを抱えたまま参加するのではなく、自分の意思で積極的に活用することが、納得のいくキャリア選択につながります。
企業が内定者面談を実施する目的

内定者面談は、企業が学生と向き合いながら信頼関係を築く大切な機会。 形式はカジュアルでも、その目的は明確で、配属や不安解消、離職防止など多くの意味があるのです。
ここでは、企業が内定者面談を実施する主な理由を紹介します。
- 入社意思の最終確認をするため
- 配属先の決定材料を得るため
- 内定者の不安を解消するため
- 入社後のミスマッチを防ぐため
- 早期離職を防止するため
①入社意思の最終確認をするため
企業が内定者面談を行う理由の一つは、学生の入社意思を見極めることです。形式は柔らかくても、熱意や覚悟があるかどうかを会話の中で確認しています。
志望動機やキャリアの考え方を聞かれることも多く、言葉に詰まると不安を持たれるかもしれません。「入社したい」という気持ちがあるなら、その理由やエピソードを交えて話すと説得力が増します。
事前に自分の志望理由や目指す姿を整理しておけば、自然な受け答えがしやすくなるでしょう。面談では正直さと前向きな姿勢が伝わることが大切です。
②配属先の決定材料を得るため
内定者面談では、興味のある仕事や働き方について聞かれることがよくあります。これは、配属先や担当業務を決めるうえでの判断材料として使われるためです。
企業としても、適性や希望を理解したうえでミスマッチのない配属を目指しています。「どこでも大丈夫」と答えると、逆に判断が難しくなってしまうのです。
自分の強みや関心を具体的に伝えることで、企業側もよりよい判断ができるでしょう。希望を伝えることはわがままではなく、適切な配属を実現するために欠かせない要素です。
③内定者の不安を解消するため
入社前は誰しもが不安を感じるものです。仕事内容が合うか、職場になじめるか、社会人としてやっていけるかなど、疑問や不安は尽きません。
企業はその気持ちに寄り添い、面談を通じてサポートしようとしています。面談では、制度や社内の雰囲気、入社までの流れなどを詳しく説明してくれる場合が多いです。
わからないことや気になる点は、遠慮せずに相談するのがおすすめ。不安を解消しておくことで、安心して入社準備に取り組めるようになるでしょう。
④入社後のミスマッチを防ぐため
企業は、学生が入社後に「思っていたのと違った」と感じないようにしたいと考えています。そのため、内定者面談では、会社の実情や業務内容について率直に伝える姿勢を持っているのです。
学生側も、自分の価値観や希望と企業の実態にずれがないかを確認するチャンス。話を聞くだけでなく、自分の考えを伝えながらイメージのすり合わせをしておくことが大切です。
お互いの理解が深まれば、入社後のギャップも少なくなり、安心して働き始められるでしょう。
⑤早期離職を防止するため
企業にとって、早期離職は大きな損失につながります。採用にかけた時間やコストが無駄になるだけでなく、チームへの影響も少なくありません。
内定者面談では、不安や悩みを早めに把握し、必要があれば先輩との面談や個別フォローを行う企業もあります。これは、長く働いてもらうための土台作りの一環です。
学生側も、自分の気持ちを率直に伝えることで、企業のサポートを受けやすくなります。内定者面談はただの儀礼ではなく、安心して社会人生活をスタートするための大切な一歩です。
内定者面談に参加する学生側のメリット

内定者面談には、学生にとって多くのメリットがあります。企業側の意図を理解するだけでなく、面談に参加することで得られる実質的な利点を知ると、より前向きな気持ちで活用できるでしょう。
- 選考で聞けなかったことを直接質問できる
- 配属部署や業務内容の具体像がわかる
- 企業理解が深まり入社意欲を高められる
- 同期や社員と話せて社風が感じられる
- 不安を解消し安心して入社準備ができる
①選考で聞けなかったことを直接質問できる
選考中は時間が限られていたり、評価されていると感じて質問を控えたりすることもあったのではないでしょうか。
内定者面談では、選考はすでに終わっているため、立場を気にせず率直な疑問を伝えることが可能です。
たとえば、「配属後の一日の流れ」や「新人の成長支援体制」など、より現実的で個人的な内容についても気軽に聞けます。
入社後にギャップを感じないためにも、このタイミングでしっかり確認しておくと安心です。
また、自分から質問する姿勢は企業側からも好印象を持たれやすいため、消極的にならず積極的に関わってみてください。
②配属部署や業務内容の具体像がわかる
内定者面談では、配属予定の部署や業務の実態について具体的な情報を得られることがあります。
求人票や説明会ではわからなかった日々の仕事の流れや、使うツール、職場の雰囲気などが明確になることも少なくありません。
実際に働く社員から直接話を聞ければ、表面的な情報だけでは見えてこなかった部分も見えてくるでしょう。このような情報は、自分が本当にやりたいことと照らし合わせるうえでとても大切です。
不安を減らし納得した状態で入社するには、事前の理解が欠かせません。興味のあることは遠慮なく質問して、具体的なイメージをつかんでおきましょう。
③企業理解が深まり入社意欲を高められる
企業の理念や将来の展望などに触れられるのも、内定者面談の魅力です。
選考中にはあまり語られなかった経営層の考え方や、若手社員のリアルな声にふれることで、その企業が目指す方向性を深く理解できます。
たとえば、自分が共感できるビジョンや、興味のあるプロジェクトの詳細を知れたときには、入社後のやる気にもつながるはずです。
また、企業の方針を知ることは、自分のキャリアとの相性を考えるうえでも役立ちます。入社に対する迷いが減り、前向きな気持ちで準備を進められるようになるでしょう。
④同期や社員と話せて社風が感じられる
内定者面談では、同期の内定者や若手社員との交流ができることもあります。そうした場を通じて、説明会では見えにくかった社風や人間関係の雰囲気を体感できるのが大きな魅力です。
たとえば、社員同士の会話のテンポや内定者への接し方を観察するだけでも、「この会社はフラットな文化なのか」「上下関係がしっかりしているのか」といった印象を持つことができるでしょう。
自分に合った雰囲気かどうかを知るには、実際に人と接してみるのがいちばんです。少しでも不安があれば、その場で感じ取って判断するきっかけにしてください。
⑤不安を解消し安心して入社準備ができる
内定をもらったあとも、「この選択でよかったのか」「入社後うまくやっていけるのか」など、漠然とした不安を抱える人は少なくありません。内定者面談は、そんな不安をやわらげる機会になります。
たとえば、配属後の研修制度や、働き方に関する柔軟な取り組みについて説明を受けられることがあるものです。そうした情報を知るだけで、入社後の自分をより具体的に想像でき、不安が薄れていくでしょう。
納得して入社準備を進めるためにも、疑問はそのままにせず、面談の中で少しずつ解消していってください。
内定者面談の流れ

内定者面談はカジュアルに見えても、実際にはある程度の流れが決まっています。事前に把握しておくことで、当日あわてず落ち着いて受け答えできるでしょう。
ここでは、一般的な面談の流れを5つのステップに分けて紹介します。
- 日程調整と面談形式の案内を受ける
- 企業側からの質問に答える
- 逆質問や不明点を確認する
- 入社意思の表明や調整事項を話す
- 今後のスケジュールや手続きを確認する
①日程調整と面談形式の案内を受ける
内定者面談の第一歩は、企業との日程調整です。メールや電話で連絡が入り、候補日や希望時間を確認されることが多いでしょう。
対応が遅れたり、返信が不適切だったりすると、社会人としての印象に影響するおそれもあります。特にビジネスメールの書き方や敬語の使い方には注意が必要です。
企業によっては、面談の形式が対面かオンラインかもこの時点で伝えられます。オンラインであれば、使用ツールや当日の接続方法の案内も含まれていることがあるので、見落とさずにチェックしてください。
返信内容の確認やスケジュールの調整には、慎重さとスピードの両方が求められます。スムーズなやりとりは、誠実さやコミュニケーション力のアピールにもつながりるでしょう。
②企業側からの質問に答える
面談当日は、企業からさまざまな質問を受けることになります。
形式は比較的柔らかくても、質問内容は「学生時代に力を入れたこと」「自社への志望理由」「働く上で大切にしたいこと」など、面接に近いものも少なくありません。
特に、志望度の高さや企業理解の深さを確認されるような問いかけが多くなる傾向があります。事前に「よくある質問」をリストアップし、自分なりの回答を準備しておくと安心です。
ただし、丸暗記のような受け答えではなく、自分の言葉で伝えることが大切。また、想定外の質問が来ても焦らないためには、自分の経験や価値観を整理しておくことが有効です。
企業側は、学生の人柄や考え方を知ろうとしていますので、誠実に答える姿勢が何よりも評価されるでしょう。
③逆質問や不明点を確認する
面談の後半には、「何か質問はありますか?」と逆質問の時間が設けられるのが一般的です。この時間を活用することで、自分の興味・関心を示せるだけでなく、企業への理解を深めることもできます。
ただし、聞く内容をその場で考えようとすると、焦って的外れな質問になる可能性もあるため、事前に質問を3つほど準備しておくと安心です。
たとえば、「入社後の研修制度について」「配属先はどのように決まるのか」「1年目社員の業務内容は?」など、具体的な視点を持つことで、面談の質も上がります。
また、「特にありません」は避けるのが無難です。質問を通じて、仕事への意欲や自分らしい視点を伝えることができれば、企業側に強く印象づけられるはず。
④入社意思の表明や調整事項を話す
企業によっては、面談の終盤で入社の意思について尋ねられることがあります。「御社に入社する気持ちは固まっていますか?」と直接的に聞かれることもあるでしょう。
このとき、まだ迷っている場合は「前向きに検討しており、近日中に決断します」など、正直に答えるのがベストです。無理に答えを出す必要はありませんが、誠実な姿勢を見せることが大切。
また、勤務地や配属部署、働き方の希望がある場合も、このタイミングで相談できます。具体的な希望があるときは理由を添えて伝えると、企業側も前向きに受け止めてくれる可能性が高まるでしょう。
一方で、希望がない場合も「柔軟に対応します」と伝えておくとスムーズです。意思表示と調整の場として、事前に自分の考えをまとめておくことが望ましいでしょう。
⑤今後のスケジュールや手続きを確認する
面談の最後には、今後の流れや必要な準備について説明されることが多くあるでしょう。
たとえば「内定承諾書の提出期限」「健康診断の日程」「入社前研修の有無」「住居手配に関する案内」などが挙げられます。
説明が多くなる分、うっかり聞き逃してしまうこともあるため、メモを取りながら確認してください。不明点が残っている場合は、その場で質問して解消することが重要です。
「こんなこと聞いてもいいのかな」とためらわず、疑問は早めにクリアにしておきましょう。
面談後にメールでフォローが入ることもありますが、当日のやり取りで基本的な内容を押さえておくと安心です。丁寧な姿勢で面談を締めくくることが、今後の信頼関係にもつながります。
内定者面談に向けた事前準備のポイント

内定者面談は選考とは異なり、企業とより良い関係を築くための大切な場です。準備をきちんとしておけば、不安を減らし、より有意義な面談につなげられるでしょう。
以下のポイントを参考に、当日に向けて備えてください。
- 面談の目的を明確にしておく
- 自身の入社意思や希望を整理する
- 企業から想定される質問に備える
- 逆質問の内容を事前に考える
- 服装や持ち物の準備を確認する
①面談の目的を明確にしておく
内定者面談は企業側が学生の不安や疑問に向き合うための場であり、ただ話を聞くだけの時間ではありません。自分にとっての目的をはっきりさせておくことで、面談の内容が深まります。
たとえば、「配属の話を聞きたい」「働く環境を具体的に知りたい」など、面談で得たい情報を事前に整理しておくと安心です。
そうすることで、会話の主導権を自分が握れるようになり、後悔のない時間にできるでしょう。目的を持たずに参加すると、何となく終わってしまう可能性があります。
自分の意図を持って積極的に臨んでください。
②自身の入社意思や希望を整理する
面談では「入社の意思は固まっていますか?」と聞かれることがあります。その際、自分の考えをうまく言葉にできるようにしておきたいところです。
たとえば、「勤務地の希望」「やってみたい業務内容」「不安に感じていること」など、現時点での思いや考えを整理しておくと、面談中も落ち着いて話せます。
入社を迷っている場合でも、素直に伝えて問題ありません。大事なのは、自分の考えを正直に話す姿勢です。企業との信頼関係を築く第一歩として、自分の気持ちを整理して臨みましょう。
③企業から想定される質問に備える
面談では選考のような厳しい質問はされませんが、企業側からいくつか質問されることがあります。「キャリアについてどう考えているか」「入社後に不安はあるか」などが代表的です。
こうした問いかけに対して、自分の意見や気持ちをしっかり話せるよう準備してください。あらかじめノートに簡単なキーワードを書き出しておくのも効果的でしょう。
受け答えの中で一番大切なのは、正直さと誠実さです。飾らず、自分の言葉で伝えることを意識してください。
④逆質問の内容を事前に考える
面談の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれることが多くあります。そのときに何も浮かばないと、やる気がないと思われてしまうかもしれません。
たとえば、「新人研修の期間や内容」「部署間の連携の様子」「評価の仕組み」など、入社後の働き方に関する質問を用意しておくとよいでしょう。
ただし、調べればわかることや待遇に関する質問は、タイミングや言い方に気をつけてください。質問は、企業への関心を示すチャンスでもあります。
あらかじめ複数の質問を考えておくと、柔軟に対応できるでしょう。
⑤服装や持ち物の準備を確認する
面談当日の第一印象を決めるのが服装や持ち物です。特に指定がない場合でも、基本はリクルートスーツが無難。清潔感のある身だしなみを意識しましょう。
オンライン面談であっても、カメラに映る範囲は整えておくべきです。また、対面であれば筆記用具やメモ帳、スケジュール帳、A4サイズの資料が入るカバンなど、必要な持ち物を前日に準備してください。
服装や持ち物は社会人としての基本です。小さなことと思わず、丁寧に準備しておきましょう。
内定者面談でおすすめの逆質問

内定者面談では、企業からの質問に答えるだけでなく、自分から質問をする「逆質問」も非常に重要です。
逆質問の内容によって、あなたの関心や入社意欲が伝わるため、準備しておくことが面談成功のカギになるでしょう。ここでは、おすすめの逆質問例を5つ紹介します。
- 配属部署や仕事内容について
- 入社後の研修や育成体制について
- 先輩社員のキャリアパスについて
- 年間スケジュールや繁忙期について
- 評価・昇進の仕組みについて
①配属部署や仕事内容について
配属される部署や担当する業務内容は、入社後の働きがいや成長スピードに直結する重要な要素です。
逆質問として「配属先はどのように決まるのか」「希望はどの程度考慮されるのか」「実際に任される業務の一例を教えてください」といった具体的な内容を尋ねることで、自分の働くイメージを明確にできるでしょう。
もし業務内容が合わないと感じた場合でも、事前に気づければミスマッチを防げます。また、業務内容を把握しておくことで、入社前の準備や必要なスキルの確認にもつながるでしょう。
配属や職種に関する質問は、志望度が高いからこそ出るものと受け取られやすいため、好印象を残せる可能性も高いです。
②入社後の研修や育成体制について
「入社してからついていけるか」「スキル不足をどう補えばいいか」といった不安を感じている方にとって、育成体制の確認は非常に有効です。
たとえば、「入社後の初期研修は何日間行われるのか」「OJT以外にフォロー体制はあるか」「自己学習用のツールや制度は用意されているか」などを具体的に聞いてみてください。
企業によっては、eラーニングや社外研修、メンター制度など、手厚いサポートを用意している場合もあります。
こうした制度の有無を事前に知ることで、安心して入社準備ができるだけでなく、自分がどう成長していくかの道筋も見えてくるものです。
不安を前向きな質問に変えることで、意欲の高さを自然に伝えられるでしょう。
③先輩社員のキャリアパスについて
入社後の将来像を描くには、実際に働いている先輩たちのキャリアパスを知ることが一番の参考になります。
「3年後・5年後にどんな仕事をしているのか」「異動や昇進のタイミングはどのように決まるのか」「役職を持つ社員はどんな経験を積んできたのか」といった質問を投げかけると、よりリアルな情報が得られるでしょう。
また、「自分と同じようなバックグラウンドの人がどのような成長をしているか」と尋ねるのも効果的です。
企業によってはキャリアの幅が広いケースもあり、自分が思っていた以上の働き方に気づけるかもしれません。未来を見据えた質問をすることで、企業との長期的な関係を意識している姿勢も示せます。
④年間スケジュールや繁忙期について
働き方やプライベートとのバランスを考える上で、業務の年間スケジュールや繁忙期の情報はとても大切です。
「年間で最も忙しい時期はいつか」「部署によって繁忙期は異なるのか」「休暇の取得状況や有給の取りやすさはどうか」などを聞くことで、より現実的な働き方のイメージがつかめます。
実際、入社後に「思っていたより忙しい」「休みが取りづらい」とギャップを感じてしまうケースも少なくありません。
あらかじめ情報を得ておけば、自分の生活スタイルとのすり合わせができ、入社後のミスマッチも防ぎやすくなります。
業務内容だけでなく、その“濃度”や“波”を知ることも、逆質問の大事な視点といえるでしょう。
⑤評価・昇進の仕組みについて
「頑張ればどのように評価されるのか」「昇進の基準は明確に示されているのか」といった質問は、働く上でのモチベーション維持に関わる重要なテーマです。
企業によって評価制度の透明度や基準は異なり、曖昧な仕組みのまま働き続けると不満の原因になることもあります。
たとえば、「定量的な目標は設定されるのか」「定期的な面談で評価のフィードバックがあるか」「昇進にはどのような経験やスキルが必要なのか」といった視点で質問してみてください。
成長意欲がある学生ほど、このような質問を通じて“自分がどうなりたいか”を考える傾向があります。目標を明確にして働きたいという意思を伝えられれば、企業からの評価も高まりやすいでしょう。
内定者面談の服装マナー

内定者面談は選考ではありませんが、学生としての第一印象が企業に伝わる大切な場です。服装のマナーを押さえておけば、不安なく自信を持って臨めるでしょう。以下のポイントを意識して準備してください。
- リクルートスーツを着用する
- 服装指定がない場合はオフィスカジュアルにする
- 清潔感を意識した髪型・身だしなみにする
- 華美にならないアクセサリーや腕時計を選ぶ
- オンライン面談でも上半身だけでなく下半身の服装も整える
①リクルートスーツを着用する
企業から服装の指定がない場合は、リクルートスーツを選ぶのが基本です。内定者面談はカジュアルな場と思われがちですが、社会人としての意識が見られる場でもあります。
とくに対面面談では、第一印象を左右する大事な要素です。黒や紺、グレーなど落ち着いた色のスーツに、白や淡い色のシャツを合わせると良いでしょう。派手な柄や個性的なデザインは避けてください。
「選考ではないから自由でいいだろう」と思って油断すると、思わぬマイナス評価につながることもあります。不安な場合は、リクルートスーツで行くのが最も無難です。
②服装指定がない場合はオフィスカジュアルにする
「服装自由」と案内された場合、どうすればよいか迷うこともあるでしょう。そんなときは、オフィスカジュアルを意識した服装が適しています。
オフィスカジュアルとは、ビジネスの場にふさわしい清潔感のあるスタイルです。たとえば、襟付きのシャツやブラウスに、ジャケットとスラックスまたは膝丈のスカートを合わせたコーディネートが基本。
色は白・ベージュ・ネイビーなど、落ち着いたトーンがおすすめです。私服感が強すぎる服装は避けましょう。迷ったときは、少しフォーマル寄りに整えておくと安心です。
③清潔感を意識した髪型・身だしなみにする
服装と同じくらい重要なのが、髪型や身だしなみです。たとえば、髪が乱れていたり、爪が伸びっぱなしだったりすると、全体の印象が悪くなってしまいます。
髪型は派手すぎず、顔まわりがすっきり見えるように整えておきましょう。色もナチュラルなトーンが安心です。また、寝ぐせやフケがないか鏡でチェックしておくことも忘れないでください。
靴やカバンも意外と見られています。くたびれた印象を与えないよう、清潔な状態を保ちましょう。
④華美にならないアクセサリーや腕時計を選ぶ
アクセサリーや腕時計は、あくまで控えめなものを選ぶことが大切です。面談では自分をアピールする場であると同時に、相手に配慮した装いが求められます。
たとえば、シンプルなピアスや小ぶりな腕時計など、目立ちすぎないものなら問題ありません。反対に、大きなアクセサリーやキラキラした装飾は避けたほうがよいでしょう。
装いの細部にも気を配れるかどうかは、社会人としての意識の現れと受け取られることもあります。選ぶ際は、TPOに合っているかを意識してください。
⑤オンライン面談でも上半身だけでなく下半身の服装も整える
オンライン面談だからといって、下半身をラフな服装のままにしてしまうのは危険です。突然立ち上がる場面があるかもしれませんし、カメラの角度によって意外と見えてしまうこともあります。
上半身だけ整えて満足せず、全身をきちんとした服装にしておきましょう。また、背景や部屋の明るさも面談の印象に関わります。生活感が出すぎないよう、背景にも配慮してください。
オンラインであっても、姿勢や身だしなみの丁寧さが伝わります。油断せず、万全の状態で臨んでください。
内定者面談に必要な持ち物リスト

内定者面談では、必要な持ち物をあらかじめ確認しておくことが大切です。忘れ物があると、面談に集中できなかったり、印象が悪くなったりするおそれもあるでしょう。
ここでは、面談当日に持っておくべき基本的なアイテムを5つ紹介します。
- 筆記用具とメモ帳
- 企業から指定された書類
- 身分証明書や学生証
- 交通費精算がある場合は印鑑や領収書
- オンラインの場合はネット環境と端末
①筆記用具とメモ帳
面談中には、会社の説明や今後のスケジュール、配属に関する話など、重要な情報が多く共有されます。
その場で覚えておくのは難しいこともあるため、筆記用具とメモ帳を持参し、必要な内容はメモを取りながら聞くようにしましょう。
また、話の内容にしっかり向き合う姿勢としても、メモを取る行動はポジティブな印象を与えます。
さらに、ペンが書けなくなった場合に備えて、予備のボールペンやシャープペンシルを1本用意しておくと安心です。メモ帳はできるだけシンプルでビジネスシーンに適したものを選んでください。
派手なデザインやキャラクターものは避けたほうが無難です。
②企業から指定された書類
内定者面談では、企業側からあらかじめ提出を求められている書類がある場合があります。たとえば、履歴書や成績証明書、誓約書、健康診断書などです。
これらの書類は、面談前に送られてくるメールや案内文書で明示されるので、内容を見落とさず、漏れなく準備しましょう。
提出書類は、折れたり汚れたりしないようにクリアファイルに入れておくのが基本です。さらに、予備のコピーを1部持っていくと、不測の事態に備えられます。
持参する書類に不備があると信頼感に影響することもあるため、チェックリストを作成しておくとよいでしょう。
③身分証明書や学生証
本人確認が必要な場面は、意外と多いものです。特に、オフィスビルの入館手続きや受付時には、学生証や運転免許証などの提示を求められるケースがあります。
また、企業によっては、セキュリティ対策の一環として本人確認を徹底していることもあり、提示を求められた際に持っていないと入館できない可能性もあるため要注意です。
さらに、オンライン面談でも本人確認を行う企業もあります。
カメラ越しに学生証を画面に映して提示するケースもあるため、オンラインだからといって油断せず、すぐに取り出せる場所に準備しておいてください。
④交通費精算がある場合は印鑑や領収書
一部の企業では、面談にかかった交通費を支給してくれる場合があります。その際には、移動にかかった実費を証明するために、領収書の提出が求められることも珍しくありません。
また、交通費の精算書に捺印が必要なケースもあるため、印鑑も一緒に持参しておくと安心です。
特に、交通費支給の有無や手続き方法は事前に案内されている場合が多いので、企業からのメールや書面をしっかり確認しておきましょう。
うっかり忘れるとその場で申請ができなかったり、後日手続きが面倒になったりするおそれがあります。
領収書は財布やバッグの中で折れ曲がらないように、こちらもクリアファイルなどで丁寧に保管しておくと良いでしょう。
⑤オンラインの場合はネット環境と端末
オンラインでの内定者面談が増えている現在では、ネット環境とデバイスの準備も重要なポイントです。
まず、使用するパソコンやスマートフォン、タブレットのカメラとマイクが正常に動作するかを事前に確認しておきましょう。
面談用のツール(Zoom、Google Meet、Teamsなど)が指定されている場合は、アプリのインストールやアカウント作成も忘れずに。
さらに、ネット接続が不安定だと、会話が途中で切れてしまったり、相手の声が聞こえなかったりするなどトラブルが発生しやすくなります。
そのため、できるだけWi-Fi環境が安定している場所を選び、可能であれば有線接続にしておくとより安心。バックアップとしてスマホのテザリングを準備しておくのもひとつの手です。
内定者面談後に送るお礼メールの例文
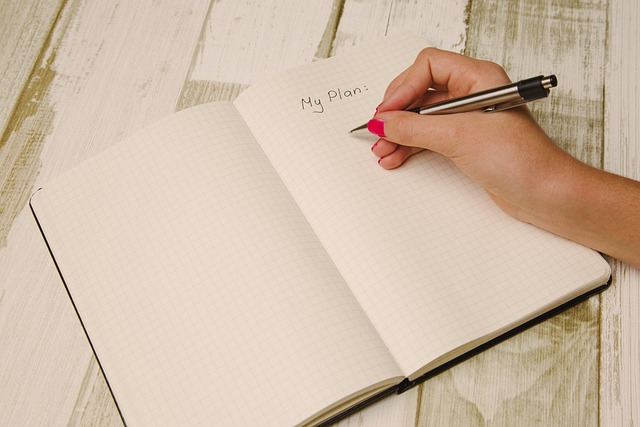
面談が終わったあと、どのようなお礼メールを送ればよいか悩んでいませんか?印象を損ねないように言葉を選ぶのは難しいものです。
ここでは、内定者面談後の状況別に、適切なお礼メールの文例を紹介します。内容に迷う場面でも参考にできるよう、複数のケースを具体的にまとめました。
- 基本的なお礼メールの例文
- 内定承諾の意志を伝えるお礼メール例文
- 内定を保留したい場合のお礼メール例文
- 内定辞退を決めた場合のお礼メール例文
- 面談での質問回答に感謝するお礼メール例文
- メールで追加の質問をする際のお礼メール例文
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
基本的なお礼メールの例文
内定者面談後には、感謝の気持ちを簡潔に伝えるお礼メールを送るのが基本です。ここでは、一般的な面談後に送るスタンダードなお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:本日の面談のお礼(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 本日はお忙しい中、内定者面談の機会をいただき、誠にありがとうございました。 実際に働く環境や業務内容について詳しくお話を伺えたことで、入社後のイメージがより明確になりました。 特に、若手社員の方の働き方や成長のサポート体制についてのお話が印象に残っており、貴社で自分も成長していきたいという思いが一層強まっております。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
内定者面談後のお礼メールは、シンプルかつ丁寧にまとめるのがポイントです。印象に残った話題に触れることで、面談への関心と感謝が伝わりやすくなります。
内定承諾の意志を伝えるお礼メール例文
内定者面談を経て「この会社に入社したい」と強く思ったなら、面談後のメールでその意思を丁寧に伝えましょう。ここでは、内定承諾の意志を明確に伝えるお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:内定者面談のお礼(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 社員の方々の働き方やキャリアの進め方を直接伺うことで、貴社で働くイメージがより明確になっています。 学生時代に学んだプロジェクト活動でのチーム協働の経験を活かし、貴社の一員として貢献したいという思いが一層強まりました。 つきましては、改めて内定をありがたくお受けさせていただきたく存じます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
内定承諾のメールでは、入社の意思をはっきり伝えることが大切です。印象に残った面談の内容と、自分の気持ちをセットで伝えると説得力が増します。
内定を保留したい場合のお礼メール例文
内定者面談を経て、入社に前向きな気持ちがありつつも、もう少し慎重に判断したいと感じることもあるでしょう。ここでは、失礼にならずに内定の保留を伝えるお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:面談のお礼と今後のご相談(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 本日は内定者面談の貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 社員の皆さまのリアルな声を伺い、貴社の風通しの良さや働きやすい雰囲気に大変魅力を感じました。 一方で、自分のキャリアプランをより明確にしてから判断したく、内定について少しお時間をいただければ幸いです。 ご迷惑をおかけし恐縮ですが、改めてご連絡差し上げますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
内定の保留を伝える際は、企業への敬意と感謝を忘れずに書くのがポイントです。ネガティブな印象を与えず、前向きな姿勢を添えて伝えるよう心がけましょう。
内定辞退を決めた場合のお礼メール例文
他社との比較や将来の目標を再確認した結果、やむを得ず内定を辞退する決断をする場合があるでしょう。ここでは、誠意を持って辞退を伝えるお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:内定辞退のご連絡(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 先日は内定者面談のお時間をいただき、誠にありがとうございました。 社員の方々のお話を伺い、貴社の魅力を改めて感じる貴重な機会となりました。 しかしながら、今後の進路について熟考を重ねた結果、自分のやりたいことや将来像と照らし合わせた際、別の道に進む決断をいたしました。 ご期待に沿えず心苦しい限りですが、貴重な機会をいただいたことに深く感謝しております。 貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
辞退の連絡は早めに行い、感謝の気持ちと丁寧な言葉で締めくくることが大切です。一方的にならないよう、面談で得た学びにも軽く触れておくと好印象につながります。
面談での質問回答に感謝するお礼メール例文
面談中に自分の質問へ丁寧な回答をもらえた場合は、感謝の気持ちをメールで伝えると印象がより良くなるでしょう。
ここでは、質問に答えてもらったことへの感謝をしっかり伝えるお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:面談のお礼とご回答への感謝(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 内定者面談の中で、私が質問させていただいた「1年目の業務内容やサポート体制」について、非常にわかりやすく丁寧にご説明いただき、安心感を持つことができました。 学生時代に参加した地域プロジェクトでチームでの課題解決を経験しており、入社後も主体的に学びながら貢献していきたいと強く感じています。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
質問に対する回答へのお礼を具体的に伝えると、感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。質問の内容に触れつつ、自分の意欲にもつなげるのが効果的です。
メールで追加の質問をする際のお礼メール例文
内定者面談後に「聞きそびれてしまったこと」や「面談を振り返って新たに浮かんだ疑問」が出てくることは珍しくありません。
ここでは、追加の質問を丁寧に伝えつつ、失礼にならないお礼メールの例文をご紹介します。
《例文》
| 件名:面談のお礼と追加のご質問(○○大学・氏名) ○○株式会社 人事部 ○○様 先日は内定者面談の機会をいただき、誠にありがとうございました。 貴社の社風や業務内容について詳しく知ることができ、大変有意義な時間となりました。 面談を終えてから、研修制度についてもう少し詳しくお伺いしたい点ございます。 具体的には、新入社員向けの研修がどのくらいの期間で行われるのか、また、配属後のフォロー体制についてもご教示いただけますでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますと幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。 ○○大学 ○○学部 ○○学科 氏名(ふりがな) 電話番号/メールアドレス |
《解説》
追加質問のメールでは、お礼と前向きな姿勢をしっかり伝えることが大切です。質問は簡潔かつ具体的に書き、相手の負担にならないよう配慮しましょう。
内定者面談を成功させるために意識したいこと

内定者面談は、企業と学生が相互理解を深め、入社への最終確認を行う大切な機会です。事前準備を怠ると、逆に不安やミスマッチの原因にもなりかねません。
だからこそ、面談の流れや企業の意図、服装・持ち物・逆質問のポイントなどをしっかり押さえておくことが重要です。
準備を整えて臨むことで、面談から得られる情報が増え、入社後のイメージも明確になります。内定者面談を就職活動の集大成として活用し、納得のいく社会人スタートを切りましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









