公務員の勤務時間は何時から?残業や休日も徹底解説
「公務員って定時で帰れるって聞くけど、実際の勤務時間はどうなんだろう?」そんな疑問を持つ就活生や転職希望者の方も多いかもしれません。
実際には職種や配属先によって勤務時間や残業の実態はさまざまです。
この記事では、公務員の基本的な勤務時間から、職種別の違い・残業や休日の実態まで詳しく解説します。
公務員の働き方を具体的に知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
公務員の勤務時間は何時から何時まで?

公務員の勤務時間は原則「午前8時30分から午後5時15分まで」で、実働時間は7時間45分です。
国家公務員法や関連法律により標準化されており、地方公務員も各自治体の条例でほぼ同様の時間帯となっています。
配属先によって多少の違いはありますが、基本的な勤務時間帯が明確に定まっている点が公務員の特徴です。
民間企業と公務員の勤務時間を比較

公務員は「1日7時間45分、週38時間45分」と法律で定められ、民間企業の「1日8時間、週40時間」よりわずかに短く設計されています。
制度によって時間が明確に管理されているため安定感があり、生活の見通しも立てやすいのが特徴です。
一方、民間企業は会社ごとに管理が異なり、業種や部門によって労働時間に大きな差が出る傾向があります。
ただし配属部署によっては公務員も多忙になることがあるため、制度と現実のバランスを理解することが重要です。
勤務時間が長い公務員の職種とは?

公務員の仕事は安定しているという印象がありますが、すべての職種が定時で帰れるわけではありません。実際には、民間企業と比較しても長時間労働が求められる公務員も存在します。
ここでは勤務時間が長くなりがちな公務員の職種を取り上げ、それぞれの特徴と理由を分かりやすく解説します。
- 教員
- 警察官
- 消防官
- 国税専門官
- 労働基準監督官
- 入国審査官
① 教員
教員の勤務時間が長くなる理由は授業以外の業務が非常に多いことにあるでしょう。
授業準備・成績処理・校内会議に加え、保護者対応や進路指導など多岐にわたるタスクに追われます。
部活動指導は平日・土日問わず時間を取られ、朝練や大会引率で早朝・夜間・休日勤務が常態化するケースも。
多くの教員が教材づくりや採点を自宅に持ち帰り、勤務管理が不十分で時間外労働がカウントされないことも多く、入職後にギャップを感じる可能性が高いでしょう。
② 警察官
警察官は夜勤や24時間勤務も組み込まれたシフト制で、交番勤務では「24時間勤務・48時間休み」が基本。
その間は昼夜問わず出動対応に追われ、事件・事故・緊急通報に即応する必要があるため予定通り退勤できることは少ないのが現状です。
交通取り締まりや地域パトロール、選挙警備など臨時業務も多く、時期によっては連続勤務や深夜勤務が続きます。
犯罪被害者対応では精神的ストレスも大きく、業務外でも心身の疲労が残りやすい職種といえるでしょう。
③ 消防官
消防官は人命救助が主任務で常に非常時に対応できる体制が求められます。
「24時間勤務・48時間休み」が一般的ですが、火災・交通事故・災害・急病人救助などあらゆる緊急事案に出動する必要があります。
都市部では出動件数が多く仮眠や食事時間も確保できないほど忙しく、出動の合間にも訓練・機材点検・報告書作成・防災指導など業務は多岐にわたります。
大規模災害時は数日間現場に入りっぱなしとなることもあり、体力と精神力を高いレベルで維持する必要がある職種です。
④ 国税専門官
国税専門官は国民や企業の税金に関わる業務を担当する専門職で、税務調査・指導・滞納整理などを行います。
確定申告や決算期は業務量が増加し時間外勤務が常態化しやすく、訪問スケジュールは先方の都合に合わせるため夕方以降の対応も珍しくありません。
1件の調査に数日かける場合もあり、法令解釈や証拠精査に多くの時間を要します。
税務訴訟などイレギュラー対応による残業も発生しやすく、数字や法律に関心がある人にはやりがいがある一方で、勤務時間に関しては柔軟な対応力が求められるでしょう。
⑤ 労働基準監督官
労働基準監督官は企業の労働法遵守を調査・指導する役割で、現場への立ち入りや聴取、行政指導を行います。
ブラック企業への監督は入念な準備と長時間対応が必要で、突然訪問が基本のため時間が読めない業務が多くなりがちです。
労働者からの相談・申告による突発的案件や労災発生時の詳細な事情聴取、報告書・指導文書作成などデスクワークも多く、労働者を守る使命感がある一方で人手不足により残業や休日出勤も避けられない場面が増えています。
⑥ 入国審査官
入国審査官は空港や港で外国人の出入国を審査・管理する重要な役割を担っています。
空港のフライトスケジュールに合わせたシフト制で早朝・深夜・祝日の不規則勤務が当たり前です。
大型連休や観光シーズンは業務量が膨らみ、審査業務では書類確認・面接対応・不審者特定などミスが許されない作業で精神的プレッシャーも大きくなります。
国際情勢や感染症流行時は審査強化でさらに過密になり、外国語対応や文化的配慮も必要で、勤務時間の厳しさは覚悟しておくべきです。
公務員の1日のスケジュール例
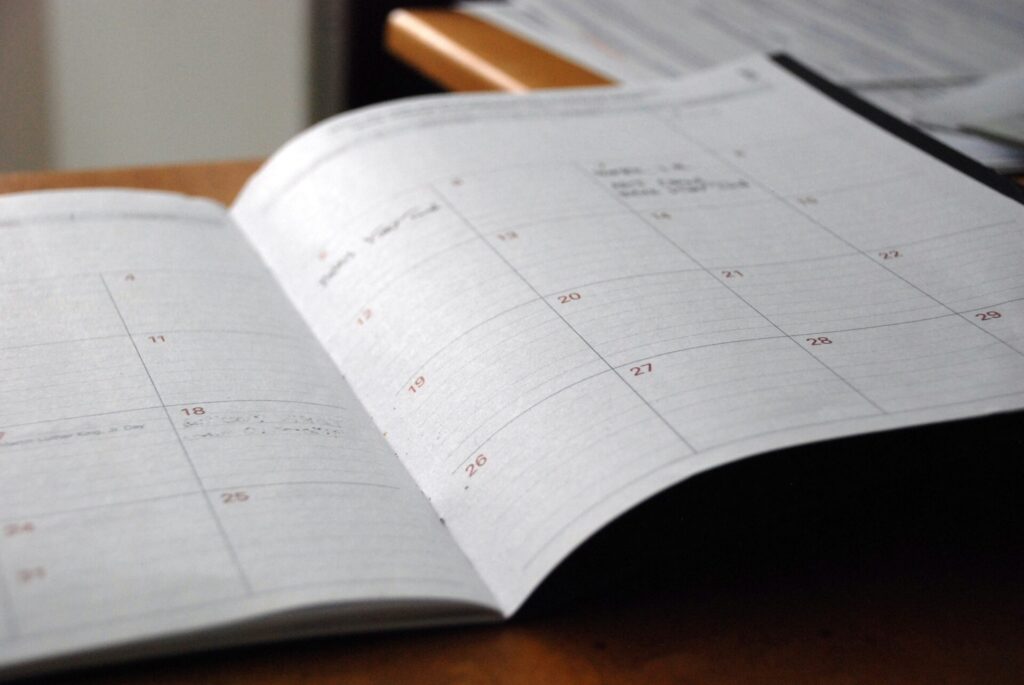
公務員と一口に言っても、働き方や1日の流れは所属する組織によって大きく異なります。
ここでは、市役所職員・県庁職員・国家公務員の代表的な1日のスケジュールを具体的に紹介し、それぞれの勤務時間や特徴を把握することで、自分に合った公務員像を描けるようにお手伝いします。
- 市役所職員のスケジュール例
- 県庁職員のスケジュール例
- 国家公務員のスケジュール例
① 市役所職員のスケジュール例
市役所職員は、地域住民にとってもっとも身近な公務員です。日常的に行政手続きや地域課題への対応に取り組んでいます。勤務時間は8:30〜17:15が基本で、民間企業の定時とほぼ同じでしょう。
たとえば、総務課の職員であれば、出勤後にメールを確認し、書類の整理から1日が始まります。午前中は市民対応や庁内の打ち合わせが中心で、午後は資料作成や予算関連の業務を進めます。
部署によっては窓口対応が多く、住民の来庁が重なると定時を過ぎて対応するかもしれません。
ただし、常に長時間労働というわけではなく、比較的安定した働き方が可能です。地域とのつながりを日々実感できる点が、大きなやりがいとなるでしょう。
市役所職員の1日スケジュール(例)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:15 | 出勤・メールチェック |
| 8:30 | 朝礼・スケジュール確認 |
| 9:00 | 窓口対応・電話応対 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 資料作成・庁内会議 |
| 15:00 | 市民相談対応 |
| 17:15 | 退勤(残業がある場合も) |
② 県庁職員のスケジュール例
県庁職員は、市町村や関係団体との調整役として、より広域的な業務を担っています。勤務時間は基本的に8:30〜17:15で、市役所と同様に規則的な勤務が一般的です。
たとえば、農林水産部門に所属する場合、朝は課内ミーティングとメール確認から始まり、午前は現地視察や出張の準備にあてられます。
午後は市町村との打ち合わせや進行中の事業に関する調整・管理業務が続きます。時期によっては、国との調整業務や会議が立て込むこともあり、残業が発生することも。
計画的に動けることが多いため、生活リズムを保ちやすい点は魅力です。地域全体の発展に携わる責任と達成感がある仕事です。
県庁職員の1日スケジュール(例)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:20 | 出勤・メールチェック |
| 8:30 | 課内ミーティング |
| 9:00 | 現場対応・資料準備 |
| 11:00 | 市町村と打ち合わせ |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 進捗管理・報告書作成 |
| 16:00 | 関係部局と協議 |
| 17:15 | 退勤(必要に応じて残業) |
③ 国家公務員のスケジュール例
国家公務員は、国全体の政策や制度に関わる業務を担います。職種や所属する省庁によって、働き方は大きく異なります。
たとえば、中央省庁の総合職であれば、朝は7時台に出勤して会議資料を作成し、国会対応の準備を進めることがあります。
日中は法案作成や他省庁との調整業務、各種審議への対応が続きます。特に予算編成の時期や国会開催中は多忙を極め、終電近くまで残業が続くこともあるでしょう。
働き方には厳しさも伴いますが、そのぶん政策の中枢に関われる意義は非常に大きく、社会に与える影響も大きなものです。
高い専門性を身につけ、将来のキャリアを広げたい人にとっては、大きな挑戦となるはずです。
国家公務員の1日スケジュール(例)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00 | 出勤・資料チェック |
| 8:00 | 会議資料の修正・共有 |
| 10:00 | 省内打ち合わせ・説明対応 |
| 12:00 | 昼食(省内で簡単に) |
| 13:00 | 法案準備・答弁資料作成 |
| 16:00 | 他省庁との調整会議 |
| 19:00 | 上司への報告・最終確認 |
| 22:00 | 退勤(時期により深夜退勤も) |
公務員の残業事情|平均時間や職種ごとの差

公務員は配属先や職種によって残業時間に大きな差があり、忙しい部署では民間企業と同等かそれ以上の残業が発生することもあります。
国家公務員全体の平均残業時間は月20〜30時間程度ですが、税務署や法務局では年度末に40時間を超えることも珍しくありません。
警察官・消防士・自衛官などは24時間体制で突発的な対応により時間外労働が発生しやすく、「公務員は楽そう」という先入観ではなく具体的な業務内容を把握して後悔しない就職選びにつなげることが重要です。
公務員の勤務時間と休日の関係

公務員の勤務時間や休日は、民間企業と比べて安定している印象があるかもしれません。実際、勤務時間は明確に定められており、ワークライフバランスを重視する人には魅力的な働き方といえるでしょう。
ただし、職種によって例外も多いため、実態をよく理解しておかないと「思っていた働き方と違う」と感じてしまう恐れも。
ここでは、公務員の年間休日数や土日勤務の実態、週休3日制の導入状況について具体的に解説します。
- 年間休日数
- 土日祝に勤務するケース
- 「週休3日制」の導入状況
① 年間休日数
公務員の年間休日数はおおむね120日以上に設定され、民間企業と同等か以上の水準です。
週休2日制が基本で祝日・年末年始・夏季休暇・有給休暇が整備されており、有給消化率も比較的高い傾向にあります。
ただし窓口業務や対人対応が多い部署では希望日に休めないこともあり、交代制勤務の職種では休日が平日にずれ、友人や家族と休みが合わない場合も。
制度面だけでなく実際の勤務実態にも目を向けておくと安心です。
② 土日祝に勤務するケース
「土日祝は確実に休める」というのは一部の職種に限られます。
一般的な事務職では平日のみ勤務ですが、警察官・消防士・自衛隊員などは24時間365日体制で夜勤や当直勤務がありますよ。
図書館や児童館なども週末開館のため土日勤務が必要で、交代制による振替休日制度が適用されます。
配属される職場によって勤務形態は大きく異なるため、勤務スケジュールにどの程度柔軟に対応できるかを自分自身でも見極めておくとよいでしょう。
③ 「週休3日制」の導入状況
働き方改革により民間企業を中心に「週休3日制」への関心が高まり、一部自治体では週4日勤務制度が試験的に導入されています。
主に育児・介護との両立支援が目的で、東京都や大阪府などでモデルケースが見られますが、まだ広く浸透しておらず一般職員には身近な選択肢ではありません。
窓口業務中心の部署では人員不足の恐れがあり、1日あたりの負担増加も課題です。制度の導入状況については各自治体の公式情報を随時確認することが大切ですよ。
公務員の勤務時間に関するポイントを押さえよう

公務員の勤務時間は原則として8:30〜17:15が基本ですが、職種や配属先によって大きく異なります。
教員・警察官・消防官などは業務の性質上、早朝出勤や夜間対応、休日勤務が発生し勤務時間が長くなりがちです。
残業の有無や平均残業時間、休日の取りやすさ、週休3日制の導入状況も踏まえると、公務員の働き方は多様化しており一概に「楽」とは言えません。
これらを総合的に理解することで、公務員としての働き方や将来設計に役立てられるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










