企業選びの軸の伝え方|質問の意図や企業選びの軸の見つけ方も紹介
「企業選びの軸って、どんなふうに答えたらいいの?」
就活でよく聞かれる「企業選びの軸」は、自分にとってどんな会社が理想かを明確にするための大切な考え方です。でも、いざ面接で聞かれると、どう伝えたらよいか悩んでしまうこともありますよね。
この記事では、企業選びの軸とは何か、面接で聞かれる理由、軸の見つけ方や伝え方のコツ、さらには具体的な例文までわかりやすく紹介します。
企業研究や自己分析に悩んでいる方も、自分らしい就活軸を整理するヒントが見つかるはずです。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
企業選びの軸とは?

会社選びの基準とは、就活時において「自分が何を大切にして働きたいか」という価値観に基づいた判断基準を表したものです。
仕事内容、給与、福利厚生、働く人の雰囲気、企業理念など、重視するポイントは人によって大きく異なってきています。
自分にとって譲れない条件が何なのかを把握しておかないと、企業選びに迷いやブレが生じやすくなってしまいます。
たとえば、周囲が有名企業を目指しているからという理由で選考を受けても、自分の理想とする働き方と合っていなければ、入社後に違和感を抱くことになるかもしれません。
就職活動は、「内定をもらうこと」そのものがゴールではなく、自分とマッチする企業で長く活躍するためのプロセスです。
その第一歩として、企業選定の軸をはっきりさせることが、納得感のあるキャリア形成につながるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
企業選びの軸を定めるべき理由

就職活動を成功させるには、どんな企業へ勤めたいかという迷いをクリアにするのが不可欠です。軸が定まっていれば、自分に合う企業が判断しやすくなり、選考対策にも統一感が出てきます。
ここでは「就活の効率化」「就職後のギャップ防止」「志望動機の説得力向上」という3つの観点から、その必要性を見ていきましょう。
- 就活を効率的に進められるようになる
- 入社後のズレを回避できる
- 志望動機の説得力が高まる
① 就活を効率的に進められるようになる
就職先の選定軸があると、就職活動の進行がスムーズにできます。自分に合わない企業を早い段階で候補から外せるため、エントリー先を絞りやすくなるからです。
たとえば、「成長できる環境」を重視する人なら、それに見合わない企業を説明会前に除外できます。
限られた時間の中で、本当に志望する企業に集中して対策を立てられる点も大きなメリットです。また、自分の考えを整理しながら軸を作ることで、就活中の判断に迷いが出にくくなるでしょう。
② 入社後のズレを回避できる
勤めたい理由を明確にすることで、入社後の後悔を減らせます。価値観や希望する働き方を整理しておけば、職場とのギャップに悩まされにくいです。
たとえば「ワークライフバランス」を大切にする人が、長時間労働が当たり前の企業に入ってしまうと、早期退職に繋がる恐れも。
事前に「譲れない条件」と「妥協できる点」を整理しておくと、入社後も納得感を持って働きやすくなってきます。自分らしく働ける環境を選ぶためにも、軸を持つことが重要です。
③ 志望動機の説得力が高まる
会社選びの軸を持つと、面接での志望理由に納得感が生まれます。単なる憧れや条件ではなく、自らの価値観に沿って話せるため、面接官にも本気度が伝わりやすくなるからです。
たとえば、「社会課題の解決に貢献できる仕事を望んでいる」という考えをもとに、その企業の具体的な事業内容と結びつけて話すと、理解の深さや意志の強さが伝わるでしょう。
企業側は、学生がどんな基準で企業を選んでいるのかを重視して見ています。軸がはっきりしていれば、堂々とした姿勢でアピールできるはずです。
面接で企業選びの軸を尋ねられる理由

企業が面接の場で「企業選びの軸」について質問するのは、応募者の価値観や志望度を深く理解するため。
これは単なる形式的な質問ではなく、自社との相性や将来的な活躍を見極める重要な視点です。的確に答えることで、企業への理解度や熱意を伝えられる機会にもなるでしょう。
ここでは、なぜ面接で就活生へ個々の選定基準を問うのかについて具体的に説明します。
- 入社意欲の高さを見極めるため
- 企業との価値観の一致を確認するため
- 長期的に働けるかどうかを確認するため
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
① 入社意欲の高さを見極めるため
企業が学生に対して問う最大の理由のひとつは、その企業に対する本気度を測るためです。
志望動機がはっきりしているかどうか、なぜ数ある会社の中からその会社を選択したのか、しっかり説明できる学生は入社後も意欲的に働いてくれると期待されます。
逆に、「雰囲気が良さそうだった」「なんとなく興味があった」といった曖昧な回答では、志望度が低いと受け取られてしまうおそれがあるかもしれません。
企業は、限られた面接時間の中で応募者の本音を探り、採用後のミスマッチを避けたいと思っています。
だからこそ、学生が何を重視して企業を比較し、何に重きを置いているのかを見定めようと試みているのでしょう。
② 企業との価値観の一致を確認するため
企業が尋ねるのは、応募者の価値観が自社と合っているかどうかを確認するためでもあります。
たとえば、「自身の成長を求めている」という希望を持つ学生が、挑戦を歓迎し、教育体制の整った企業を志望していれば、考え方に共通点があると判断されやすくなってしまいます。
一方で、「福利厚生が充実しているから」など、表面的な理由ばかりを軸にしてしまうと、企業文化との結びつきが感じられず、評価が下がることも。
大切なのは、自分が何を大事にしているかをしっかり理解し、その価値観が企業のどの部分とつながっているかを具体的に伝えられるかどうかです。
これによって、「この会社で働くことに納得している」と企業に感じてもらえるため、選考通過の可能性も高まるでしょう。
③ 長期的に働けるかどうかを確認するため
企業が志望者の軸を通じて確認したいもう1つのポイントは、「この応募者が長く働き続けてくれそうかどうか」です。
新卒採用には多くの時間とコストがかかるため、せっかく採用しても早期に退職されてしまっては、大きな損失になってしまいます。
だからこそ、短期的な視点だけで会社を選んでいないかを、軸の内容から発見しようと考えているでしょう。
たとえば、「大手だから安心」や「実家から近いから」といった要因を企業選びの基準にしている場合、より良い条件の企業が見つかればすぐに転職してしまうのではないかと懸念されるかもしれません。
自分がどんな未来を描いているのか、そのためにどんな環境が必要なのかを明確に言語化し、自分自身の選定基準として伝えましょう。
企業選びの軸のパターン
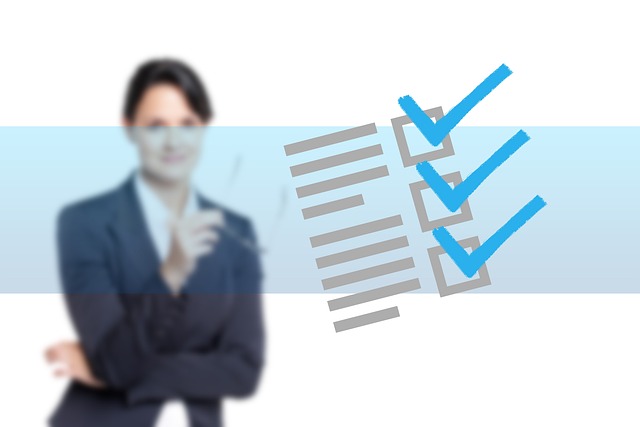
企業選びで自分に合った会社を見つけるには、明確な「軸」を持つことが大切です。軸があることで企業との相性がわかりやすくなり、就活の方向性もはっきりしてきます。
ここでは、企業選びでよく使われる3つの軸の考え方を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を見つけてみてください。
- 自分の強みを軸にするCan軸
- やりたいことを軸にするWant軸
- 譲れない条件を軸にするMust軸
① 自分の強みを軸にするCan軸
Can軸とは、自分が得意なことやできることを基準に企業を選ぶ考え方です。たとえば、人前で話すのが得意なら営業職、論理的に考えるのが好きならコンサルや企画職などが向いているかもしれません。
この軸の良いところは、自分の能力を発揮しやすい環境を選べる点です。
自然と成果も出やすくなり、仕事に対する自信や満足度も高まるでしょう。企業にとっても、応募者の「何ができるか」は注目ポイントです。
ただし注意したいのは、「得意なこと」と「やりたいこと」は必ずしも一致しない点。強みを活かせるだけでなく、自分がやりがいを感じる仕事かどうかにも目を向けてください。
自分の過去の経験や成功体験を振り返ることで、Can軸を判断できるでしょう。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
② やりたいことを軸にするWant軸
Want軸は、自分のやりたいことや挑戦したい分野を基準に企業を選定する方法です。たとえば、「地方を元気にしたい」という思いがあるなら、地域活性化に力を入れる企業が選択肢になるかもしれません。
この軸の魅力は、自分の想いを原動力にできる点です。面接でも気持ちが自然に伝わりやすく、企業との相性も見えやすくなってきます。
目的がはっきりしている人ほど、採用側にも印象づけやすいでしょう。一方で、理想だけで会社を志望してしまうと、実際の仕事内容や働き方とのギャップに悩む可能性が見られます。
だからこそ、「本当にその仕事が自分に適しているのか」を事前に調べることが大切でしょう。
Want軸を定めるには、興味のある分野を掘り下げ、企業研究を丁寧に行うことがポイントです。
③ 譲れない条件を軸にするMust軸
Must軸は、自分が絶対に外せない条件を基準に企業を選ぶ方法です。たとえば、「地元で働きたい」「年間休日が120日以上」など、生活スタイルや価値観を重視した判断軸です。
この軸の利点は、入社後の満足度や働きやすさにつながる点にあります。いくら仕事内容が魅力的でも、自分にとって重要な条件が合わなければ、長く働き続けることは難しいでしょう。
ただし条件面ばかりにとらわれすぎると、大切な要素を見落としてしまう危険性が存在します。
たとえば、「給与が高い」だけで選んだ結果、仕事の内容に興味を持てず後悔するケースもあるかもしれません。
Must軸は現実的な視点を持てる反面、視野が狭くなりがちです。だからこそ、何を優先し、何を妥協できるのかを整理して考えることが重要です。
自己分析から導く企業選びの軸の見つけ方

就職活動では、自分にぴったりの企業を見つけるために「企業選びの軸」を明確にする必要性が非常に高いです。
ここでは、自己分析を通じて自分の軸を見つける方法を紹介します。
- 自分の価値観や強みを言語化する
- 業界の特徴を調べて志向性を整理する
- 職種ごとの働き方を比較して適性を確認する
- OB・OGの話を聞いてリアルな情報を得る
- インターンに参加して実体験から気づきを得る
- 説明会で企業ごとの違いを比較・分析する
① 自分の価値観や強みを言語化する
企業選びの軸を定めるには、自身の価値観や強みを言語化しておく必要があるでしょう。なぜなら、これが企業との相性を判断するための出発点になるからです。
たとえば、「人と関わるのが好き」「安定した環境で働きたい」「挑戦できる職場がいい」といった希望は、自分が何に重きを置いているのかを表しています。
しかし、多くの就活生はこうした思いを漠然としか把握しておらず、選考でうまく伝えられないことも少なくありません。
そうした事態を避けるには、モチベーショングラフや自己分析ツールを活用し、自分の経験を振り返ることが効果的です。
言語化に手間はかかりますが、その積み重ねが信頼される軸の根拠になります。
② 業界の特徴を調べて志向性を整理する
志望業界を考える際は、それぞれの業界の特徴を理解していることが大切です。というのも、業界ごとに求められる資質や働き方に大きな違いがあるため、自分に合った選択をするには比較が欠かせません。
たとえば、IT業界はスピードや柔軟性を求める傾向があり、金融業界では正確性や信頼性が重視されます。こうした特徴を把握していないまま選ぶと、入社後にミスマッチを感じる可能性があるでしょう。
そのため、有価証券報告書や業界研究セミナー、業界地図などを活用し、客観的な視点で情報を集めることが重要です。
③ 職種ごとの働き方を比較して適性を確認する
企業を選ぶ際には、職種ごとの働き方の違いを知ることが不可欠。なぜなら、同じ業界でも職種によって仕事内容や働くスタイルが大きく異なるからです。
営業職は対人対応が中心であるのに対し、企画職や開発職では資料作成や内部調整などの業務が多くなります。
自分が「人と話すのが得意」と思っていても、それが営業に向いているとは限らないかもしれません。
そのギャップを防ぐには、職種ごとの業務内容やキャリアパス、求められるスキルなどを具体的に調べ、自分の適性と照らし合わせることが必要です。
無理なく力を発揮できる職種を選ぶことが、納得のいく企業選びにつながります。
④ OB・OGの話を聞いてリアルな情報を得る
企業の実情を知るには、OB・OG訪問が非常に有効です。というのも、実際にその会社で働いている人の声は、公式サイトやパンフレットからはわからないリアルな情報だからです。
たとえば、「若手に裁量がある」「残業が多くて大変だった」などの話は、実際の職場環境を知る手がかりになります。
ただし、一人の話を鵜呑みにするのではなく、複数の人の話を聞いて共通点を見つけましょう。
質問をする際も、「どんなときにやりがいを感じるか」「入社前と後でギャップはあったか」など、自分の知りたい情報にフォーカスするのが大切です。
こうしたやり取りから、自分の軸に対する確信も深まっていくでしょう。
⑤ インターンに参加して実体験から気づきを得る
企業選びの軸を固めるためには、実際に働く経験を通じて自分に合う環境を見極めることが効果的です。その点で、インターンシップはとても有意義な機会になります。
実際に業務に携わることで、職場の雰囲気や社員の姿勢、仕事内容などを肌で感じられます。
多くの学生が「インターンの経験が企業選びの決め手になった」と話すのも、実体験だからこそ得られる気づきがあるからです。
ただし、体験だけに満足せず、「なぜ印象に残ったのか」「何を感じたのか」を振り返ることが重要です。この振り返りを通して、自分に合う環境や価値観がよりクリアになります。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
⑥ 説明会で企業ごとの違いを比較・分析する
企業説明会は、同じ業界でも企業ごとにどのような違いがあるのかを知る絶好の機会です。理念や社風、評価制度など、企業ごとの独自性を見抜くための情報が集まります。
説明会では、採用担当者や若手社員の話を直接聞けるため、公式サイトでは得られないリアルな情報を手にできますよ。
ただ聞くだけで終わらせず、自分の軸に照らして疑問を持ち、質問する姿勢が大切です。
また、複数の企業説明会に参加することで、自分なりの比較軸ができ、判断基準も明確になっていきます。説明会の活用方法次第で、企業選びの精度が大きく変わってくるでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
企業選びの軸を伝えるときのポイント

企業選びの軸を尋ねられた際、「どうすれば分かりやすく面接官に伝えられるのかな」と悩みますよね。
ここでは、企業選びの軸を効果的に伝えるためのポイントを4つに整理して紹介します。
- 結論から伝えて印象を強める
- エピソードを使って軸の背景を説明する
- 企業との共通点を示してマッチ度を強調する
- 入社後の姿を描いて将来像を伝える
① 結論から伝えて印象を強める
面接は時間が限られているため、企業選びの軸はまず「結論」から話しましょう。
たとえば「私はチームでの協働を重視しています」と最初に伝えると、聞き手はその前提で内容を理解しやすくなります。
はじめに結論を述べることで、軸が明確に伝わるでしょう。そのうえで、理由や背景を補足すれば、より納得感のある説明になるはずです。
特に複数の企業を受ける場合には、話し方に一貫性を持たせる意味でも、結論から述べる構成が有効といえるでしょう。
② エピソードを使って軸の背景を説明する
軸を言葉で伝えるだけでは、相手に深く理解してもらうことは難しいかもしれません。そこで、自分の価値観がどんな経験から生まれたのかを、具体的なエピソードとともに語ることが大切です。
たとえば「主体性を重視している」という志望を伝えるとき、サークル活動やアルバイトで自主的に動いた経験があると、話に説得力が出ます。
経験の中で感じたことや学んだことを言葉にすることで、自己分析がしっかりできていると印象づけられるでしょう。
軸の裏にあるストーリーがあることで、面接官にも記憶に残りやすくなります。
③ 企業との共通点を示してマッチ度を強調する
企業選びの軸を伝える際には、企業との共通点を示してマッチ度を強調することが効果的です。
たとえば「顧客第一の姿勢に共感した」と話すなら、企業の理念やサービスの方針と一致していることを具体的に伝えてください。
ただし、表面的な言い回しやこじつけは逆効果になりかねません。企業研究をしっかり行い、自分の軸と企業の考えがどうつながるかを整理しておくことが重要です。
企業視点を加えることで、志望動機としての一貫性が生まれ、「入社後のイメージが湧いた」と感じてもらいやすくなるでしょう。
④ 入社後の姿を描いて将来像を伝える
軸を伝えるだけでなく、それが将来的にどうつながるのかも語ることで、より具体的で印象に残る自己PRになります。
例えば、「新しい価値を作りたい」という考えがあるなら、具体的にどんな仕事をやりたいか、どういう風に働きたいかも一緒に伝えましょう。
将来の自分を描けている学生は、目的意識を持って取り組む印象を与えられます。また、企業側も「この人はうちでどう成長するか」が想像しやすくなるはずです。
「軸→背景→将来像」の流れで伝えることで、面接全体に一貫性が出て説得力も高まります。
【種類別】企業選びの軸の例文

企業選びの際、「自分に適した企業とは何か?」という疑問を抱く方は多いでしょう。
ここでは、企業選びの軸をさまざまな観点から具体例とともに紹介します。
- 社風や企業文化を重視する軸
- 福利厚生や働きやすさを重視する軸
- 成長機会や研修制度を重視する軸
- 社会貢献や公共性を重視する軸
- キャリアパスや将来性を重視する軸
- 企業理念やビジョンを重視する軸
- 報酬や待遇を重視する軸
- グローバル展開や国際性を重視する軸
- 人間関係やチームワークを重視する軸
- 挑戦の機会やイノベーションを重視する軸
①社風や企業文化を重視する軸
企業の雰囲気や働く人たちの人柄は、入社後の満足度に大きく関わるポイントです。ここでは、社風や企業文化に魅力を感じたきっかけを伝える例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、サークル活動で新入生歓迎イベントの運営を担当した際、メンバー全員が対等な立場で意見を出し合い、自然と協力体制が生まれた経験が印象に残っています。 この経験から、上下関係に縛られず、自由に意見交換ができる風通しの良い環境でこそ、自分の力を発揮できると感じました。 企業説明会で社員同士が気さくに話している様子や、若手社員の声が尊重されているというお話を伺い、その社風に強く惹かれました。 だからこそ、私は企業を選ぶ際に、働く人同士の関係性や職場の雰囲気を大切にしたいと考えています。 |
《解説》
サークル活動のような誰もが経験しやすいエピソードを通じて、社風への価値観を自然に伝えています。実体験に基づいて「なぜそう思うか」を書くことで説得力が増します。
②福利厚生や働きやすさを重視する軸
労働環境の良さや福利厚生制度は、長期的に安心して働くために重要なポイントです。ここでは、それを重視するようになった背景を交えた例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、家族が体調を崩して入院したことがありました。その際、学業と家庭の両立の難しさを実感し、「働く上でも生活とのバランスが取れる環境が大切だ」と強く思うようになりました。 就職活動中にある企業の社員インタビューを読み、フレックス制度や有給休暇の取得率が高いこと、さらには産休・育休制度の活用事例が紹介されていたのを見て、「こういう職場なら将来のライフイベントにも柔軟に対応できる」と感じました。 仕事に全力を注ぎながらも、自分や家族の生活を大切にできる環境で働きたいと考え、福利厚生や働きやすさを企業選びの基準にしています。 |
《解説》
家庭の事情という多くの人が共感しやすい出来事を通じて、価値観が変化した流れを丁寧に示しています。個人的な体験を起点に、企業制度への関心をつなげる構成が効果的です。
③成長機会や研修制度を重視する軸
自分の成長を実感できる環境で働きたいと考える学生は多くいます。ここでは、そう感じるようになったエピソードを交えた例文を紹介します。
《例文》
| 大学3年の時に参加したインターンシップで、実際の業務に近いプロジェクトに取り組む機会がありました。 最初は分からないことだらけで戸惑いましたが、社員の方から丁寧なフィードバックを受けながら試行錯誤を重ねる中で、自分の成長を実感できたことが印象に残っています。 この経験を通して、社会に出ても常に新しいことを学び続けたいと考えるようになりました。 企業説明会で、入社後の研修が充実していることや、定期的なフォローアップ体制が整っているという説明を受けたときに、「ここなら安心して挑戦し続けられる」と感じました。 成長を後押ししてくれる制度があるかどうかを、企業選びの大切な軸としています。 |
《解説》
インターンシップをきっかけに「成長」を意識した過程を丁寧に描いています。自分の経験と企業の制度を結びつける構成が読みやすく、説得力につながります。
④社会貢献や公共性を重視する軸
「自分自身の仕事が社会の役に立っている」と実感できる環境を望む学生は少なくありません。ここでは、社会貢献を重視するようになった背景を示す例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、地域の子ども食堂でボランティアを経験しました。 そこでは、家庭の事情で十分な食事がとれない子どもたちが安心して集まれる居場所が提供されており、活動を通じて自分の関わりが誰かの支えになることを実感しました。 この経験を通じて、社会の課題を自分ごととして捉えるようになり、将来の仕事でも誰かの生活や未来にプラスの影響を与えられる役割を担いたいと考えるようになりました。 企業説明会で、事業を通じて地域貢献を推進しているという話を聞いた際には、「この企業で働けば、自分の思いを形にできそうだ」と感じました。 社会への影響力を持つ企業で働くことを、企業選びの大きな軸としています。 |
《解説》
身近なボランティア経験を出発点に、「社会に貢献したい」という想いが自然に伝わる構成です。仕事とのつながりを具体的に書くと、志望動機としても強くなります。
⑤キャリアパスや将来性を重視する軸
将来的にどのように成長していけるかを重視する学生も多いです。ここでは、自身の経験からキャリアパスの重要性に気づいた例文を紹介します。
《例文》
| 大学2年のとき、先輩の紹介でベンチャー企業の短期インターンに参加しました。 社員の方々が入社後数年でリーダーを任されるなど、明確なステップで成長している姿に触れ、「自分もこんなふうにキャリアを積んでいきたい」と強く思うようになりました。 また、その企業では自身の希望や挑戦を尊重する風土があり、働く人が自分の目標に向かって前向きに進んでいる姿が印象的でした。 この経験から、将来的なキャリアの描きやすさや、それを支える制度・風土が整っているかどうかを重視するようになりました。 企業説明会では、キャリア支援制度や職種転換の柔軟性について質問し、納得できた企業に魅力を感じました。 |
《解説》
具体的なインターン経験を通じてキャリアへの意識が高まった流れが自然です。自分の成長意欲と企業の制度を結びつけることで、志望理由としても説得力が増します。
⑥企業理念やビジョンを重視する軸
企業が掲げる価値観や事業方針に自分が納得できるかどうかは、働く上でのモチベーションにも直結します。ここでは、その重要性に気づいたきっかけを描いた例文を紹介します。
《例文》
| 大学のゼミ活動で、地域の高齢者支援に関するプロジェクトに参加しました。 活動の中で、「誰も取り残さない社会をつくる」というテーマを掲げていたNPO法人と連携し、その姿勢に深く共感したことが印象に残っています。 自分の行動が誰かのためになっているという実感は、学業とは違った大きなやりがいを感じさせてくれました。 就職活動を通して、企業がどんな理念を持ち、どんな未来を目指しているのかを重視するようになり、企業説明会ではビジョンに関する質問を欠かさず行っています。 理念に共感できる企業でこそ、自分の仕事にも誇りを持ち、長く働いていけると感じています。 |
《解説》
ゼミ活動を通じた共感体験から価値観が形成された流れが自然です。企業理念とのつながりを自分の経験から語ることで、説得力のある軸として伝わります。
⑦報酬や待遇を重視する軸
安定した生活を送りながら長く働くためには、報酬や待遇の充実も重要な要素です。ここでは、その価値観を持つに至った背景を交えた例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、学費を自分で賄うためにアルバイトを掛け持ちしていた時期がありました。生活費や学費をやりくりする中で、「収入の安定」は自分にとって大切な要素だと気づきました。 就職先を考える上でも、成果に応じた報酬制度や、住宅手当・福利厚生など、働いた分だけ評価される仕組みが整っている企業に魅力を感じるようになりました。 企業説明会で、年収モデルや評価制度の透明性について詳しく説明してくれた企業には安心感を覚え、「長く働けそうだ」と思えました。 そのため、報酬や待遇が明確で納得できるかは、自分にとって会社を選ぶ時の核となる価値観です。 |
《解説》
アルバイト経験を通じて金銭面の価値観が形成されたことが明確に伝わります。待遇に関する軸を書くときは、自分にとってどうして大切なのかを具体的に説明してください。
⑧グローバル展開や国際性を重視する軸
異文化への関心や語学力を活かしたいという思いから、国際的な事業展開をしている企業に魅力を感じる学生もいます。今回はそのような価値観を持つきっかけとなった例文を紹介します。
《例文》
| 大学の語学研修プログラムで、1ヶ月間アジアの現地大学に通う機会がありました。英語での授業や現地学生との交流を通して、多様な価値観に触れたことが大きな刺激となりました。 日本とは異なる考え方や働き方を学ぶ中で、自分の視野が広がるのを実感し、「将来は国際的な環境で活躍したい」という気持ちが芽生えました。 企業説明会で、海外拠点があり多国籍な人材と協働する機会がある企業を知り、「自分の経験や語学力を活かせそうだ」と感じました。 そのため、グローバルに事業を展開している企業かどうかを、企業選びの重要な軸としています。 |
《解説》
語学研修という身近な経験を通じて国際的な志向を持った経緯が明確です。自身の思いや背景を具体的に描くことで、志望理由に深みが出ます。
⑨人間関係やチームワークを重視する軸
職場の人間関係やチームでの協力体制は、働く環境の満足度を左右する大切な要素です。ここでは、それを重視するようになった背景を描いた例文を紹介します。
《例文》
| 大学のゼミで行ったグループ研究では、メンバーとの意見の違いから何度も議論が停滞しました。 しかし、話し合いを重ねていくうちに、お互いの考えを尊重しながら意見をすり合わせることの大切さを学び、最終的には全員が納得できる発表を作り上げられました。 この経験を通じて、周囲と信頼関係を築きながら協力することの価値を実感しました。 企業説明会で、チームで成果を出す風土や、年次に関係なく意見を言いやすい文化があると聞いた企業には強く惹かれました。 働く上では、良好な人間関係とチームワークを大切にできる職場を選びたいと考えています。 |
《解説》
ゼミ活動を通じてチームでの経験から得た価値観を明確に伝えています。職場での人間関係やチーム連携を優先する軸においては、「その考えに至った背景や経緯」を明確に示すことが重要です。
⑩挑戦の機会やイノベーションを重視する軸
新しいことに挑戦できる環境や、自分のアイデアを活かせる職場を求める学生も多くいます。ここでは、そのような価値観を持つようになったきっかけを紹介します。
《例文》
| 大学の学園祭で実行委員を務めた際、従来とは異なる形式のイベントを提案しました。 最初は前例がないことで反対意見もありましたが、仲間と一緒に試行錯誤を重ね、最終的には多くの来場者から好評を得られました。 この経験から、自分のアイデアを形にしていく過程にやりがいを感じ、今後も変化や挑戦を楽しめる環境で働きたいと考えるようになりました。 企業説明会で、新しい取り組みに積極的な社風や若手の意見が採用されやすい風土がある企業を知り、「ここなら自分の可能性を広げられそうだ」と感じました。 挑戦の機会を与えてくれる企業かどうかを、企業選びの重要な軸としています。 |
《解説》
学園祭の実行委員という身近な経験から挑戦意欲をアピールしています。アイデアを出して形にしたプロセスを具体的に描くと、主体性が伝わりやすくなります。
【業界別】企業選びの軸の例文

業界によって企業の特徴や求められる資質は大きく異なります。「自分に合う業界がわからない」と悩む方も多いでしょう。
ここでは、主要な業界ごとに企業選びの軸の具体例を紹介します。自分の価値観や志向にマッチする業界を見つけるヒントとしてご活用ください。
- メーカー業界における企業選びの軸
- 商社業界における企業選びの軸
- 金融業界における企業選びの軸
- コンサル業界における企業選びの軸
- 不動産業界における企業選びの軸
- IT業界における企業選びの軸
- サービス業界における企業選びの軸
- 小売業界における企業選びの軸
- 広告・出版・マスコミ業界における企業選びの軸
- インフラ業界における企業選びの軸
①メーカー業界における企業選びの軸
メーカー業界を志望する学生にとっては、「モノづくりへの興味」や「社会貢献性」が企業選びの軸になりやすい傾向が見られます。
ここでは、大学での経験をもとにモノづくりに関心を持つようになった学生の例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学で参加したロボット製作のプロジェクトを通じて、チームで一つの製品を形にしていく過程に大きなやりがいを感じました。 試行錯誤を重ねて完成に近づく過程では、自分のアイデアが目に見える成果になる喜びを何度も味わいました。 この経験から、技術力を活かして社会に役立つ製品を生み出す仕事に携わりたいと思うようになりました。 特に生活に身近な製品を手掛けるメーカーであれば、自分の関わったモノが多くの人の暮らしを支えるという実感を得られると考えています。 ものづくりの面白さと、社会への影響力を両立できる環境で働きたいという思いが、企業選びの軸となっています。 |
《解説》
具体的なプロジェクト経験を通じて得た気づきや感情を丁寧に描写することで、軸に説得力が出ます。自分の体験と企業の特徴がどうつながるかを明確にしましょう。
②商社業界における企業選びの軸
商社業界を志望する学生の中には、スケールの大きな仕事に惹かれたり、海外とのつながりを重視したりする人も多いです。
ここでは、留学経験をきっかけに商社への関心を深めた学生の例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代に半年間の留学を経験し、多様な価値観や文化に触れたことが、私の視野を大きく広げてくれました。 現地では日本の製品が高く評価されており、日本と海外をつなぐ仕事の重要性を実感しました。 帰国後、そのような架け橋となる役割を担いたいと考えるようになり、グローバルに事業を展開する企業に興味を持ち始めました。 特に商社は、国や業界を越えて人・モノ・情報をつなぐ中核的な存在であり、私が目指す「多様な文化を理解しながら新たな価値を提供する」という姿勢と一致すると感じました。 このような背景から、世界を舞台に活躍できる環境を軸に企業を選んでいます。 |
《解説》
留学や国際交流の経験を、企業選びの理由とどう結びつけたかが明確に書かれています。自分の価値観と企業の特徴をリンクさせることが重要です。
③金融業界における企業選びの軸
金融業界を目指す学生の中には、数字への強みや人を支える仕事への関心を軸にする方もいます。ここでは、家族の経験を通じて金融の役割に気づいた学生の例文を紹介します。
《例文》
| 私が金融業界に関心を持つようになったきっかけは、父が起業した際に金融機関のサポートを受けたことでした。 資金面の不安があった中、担当者の丁寧な対応と的確なアドバイスが支えとなり、事業を軌道に乗せることができた姿を間近で見てきました。 その経験から、「お金」という形で人や企業の挑戦を支える金融の仕事に魅力を感じるようになりました。将来は、自分自身もお客様に寄り添いながら最適な選択を導ける存在になりたいと考えています。 このような思いから、信頼関係を大切にしながら、お客様の人生や事業を支えるという観点で企業を選ぶことを軸としています。 |
《解説》
身近な出来事から金融への関心が生まれた背景を明確に示すことで、軸にリアリティが出ます。実体験を通じて感じた想いを中心に据えることがポイントです。
④コンサル業界における企業選びの軸
コンサル業界に興味を持つ学生の多くは、課題解決への関心や論理的思考を活かしたいという思いを持っています。ここでは、学生時代のゼミ活動をきっかけにコンサルに惹かれた例文を紹介します。
《例文》
| ゼミで地域企業の経営課題に取り組むプロジェクトに参加した際、現場の声をもとに課題を整理し、改善策を提案する活動に強いやりがいを感じました。 最初は意見がまとまらず苦労しましたが、議論を重ねて提案を形にする過程で、チームでの分析力と提案力の重要性を実感しました。 この経験から、複雑な課題に対して柔軟にアプローチし、最適な解決策を導く仕事に携わりたいと思うようになりました。 コンサル業界は、さまざまな業界の企業と関わりながら、広い視点で物事を考える力が磨ける点に魅力を感じています。 そのため、成長機会が豊富で、多様な課題に挑戦できる環境を企業選びの軸としています。 |
《解説》
プロジェクト経験を通して得た学びと、自分の志向を結びつけている点がポイントです。課題解決への姿勢と業界の特徴を関連付けて表現しましょう。
⑤不動産業界における企業選びの軸
不動産業界を志望する学生の多くは、地域社会への貢献や、人の生活に深く関わる点に魅力を感じています。ここでは、自身の引っ越し体験をきっかけに不動産業界に興味を持った例文を紹介します。
《例文》
| 大学入学時に初めて一人暮らしを始めた際、物件選びに不安を感じていた私に、担当の方が親身に相談に乗ってくれたことが印象に残っています。 予算や立地、生活スタイルまで丁寧にヒアリングしてもらい、自分に合った住まいを見つけられました。 その経験から、「住まい」が人の暮らしの安心や充実に直結することを実感し、不動産の仕事に関心を持つようになりました。 住まいを提供するだけでなく、人生の大きな節目に関わる責任ある仕事に魅力を感じています。 そのため、人に寄り添いながら最適な選択肢を提案できる環境が整っているかどうかを、企業選びの軸としています。 |
《解説》
自分自身の体験を通じて気づいた価値を起点に志望動機へつなげることで、説得力が高まります。エピソードは具体的に描写するのがポイントです。
⑥IT業界における企業選びの軸
IT業界を目指す学生の多くは、技術への関心や社会を便利にする仕組みへの憧れを持っています。ここでは、大学のプログラミング授業をきっかけにITに興味を持った学生の例文を紹介します。
《例文》
| 大学のプログラミングの授業で、自分の書いたコードが実際に動作し、便利なツールとして形になることに大きな達成感を覚えました。 特に、友人のスケジュール管理を助けるアプリを作成した際に「使いやすい」と喜んでもらえた経験が、ITの力で人の課題を解決できることの面白さにつながりました。 それ以来、ITを通じて誰かの役に立てる仕事がしたいと考えるようになりました。 企業を選ぶ際には、最新の技術に積極的に取り組みながらも、実際のユーザーにとって価値あるサービスを生み出しているかを重視しています。 人の暮らしをより便利に、快適にする視点を持ち続けられる環境を軸に企業を選んでいます。 |
《解説》
実体験から「なぜITなのか」が自然に伝わる構成です。具体的なエピソードと、それによって生まれた価値観を丁寧につなげることが大切です。
⑦サービス業界における企業選びの軸
サービス業界に関心を持つ学生には、人と直接関わることへのやりがいや、誰かの役に立ちたいという思いを持つ人が多いです。ここでは、アルバイト経験を通して得た気づきを軸にした例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、飲食店での接客アルバイトを通して、お客様に「ありがとう」と言ってもらえる瞬間にやりがいを感じるようになりました。 特に忙しい時間帯でも、笑顔を忘れず丁寧に対応した結果、常連になってくださった方がいたことが印象に残っています。 この経験から、人と直接関わりながら信頼関係を築いていく仕事に魅力を感じ、サービス業界に興味を持ちました。 企業を選ぶ際には、お客様一人ひとりに向き合う姿勢を重視しているか、社員がやりがいを持って働ける環境かどうかを重視しています。 人とのつながりを大切にし、心のこもったサービスを提供できる職場を軸にしています。 |
《解説》
身近なアルバイト経験をもとに、人と関わることへの価値観を伝えている点が効果的です。感情の動きや学びを具体的に描くことがポイントです。
⑧小売業界における企業選びの軸
小売業界に興味を持つ学生は、「人との接点」や「現場での工夫」に魅力を感じていることが多いです。ここでは、販売のアルバイト経験から企業選びの軸を見つけた学生の例文を紹介します。
《例文》
| アパレルショップでのアルバイトを通して、お客様に合った商品を提案し、喜んでもらえた経験が印象に残っています。 特に、悩んでいたお客様が私のアドバイスで購入を決め、「ありがとう、助かったよ」と笑顔で帰られたとき、自分の接客が誰かの役に立つという実感を持ちました。 この経験から、ただモノを売るのではなく、お客様の気持ちに寄り添ったサービスを提供できる環境で働きたいと考えるようになりました。 企業を選ぶ際には、現場の声を大切にしながら、お客様との関係性を重視しているかどうかを軸としています。現場の工夫や提案が反映されやすい社風にも魅力を感じています。 |
《解説》
現場での実体験をもとに、お客様との関わりから学んだ価値観を明確に示せている点が重要です。接客で得たやりがいを企業選びにどう活かすかがポイントです。
⑨広告・出版・マスコミ業界における企業選びの軸
広告・出版・マスコミ業界に興味を持つ学生は、「伝えること」や「表現すること」に強い思いを持っていることが多いです。ここでは、学生時代の発信活動をきっかけに志望軸を見出した例文を紹介します。
《例文》
| 大学で広報サークルに所属し、学園祭の告知ポスターやSNS運用を担当しました。 どんな言葉やデザインが人の目に留まり、行動を促すのかを考え抜き、実際に多くの来場者があったときには大きな達成感がありました。 この経験を通じて、情報を発信することの力や影響力を実感しました。世の中に必要な情報や魅力を、わかりやすく、心に届く形で届ける仕事に携わりたいという思いが芽生えました。 そのため、企業を選ぶ際には、表現力を活かして社会に価値を届けられるかどうか、そして自分のアイデアを発信できる環境かどうかを重視しています。 |
《解説》
自分の発信が人に影響を与えた経験を軸につなげており、志望理由に筋が通ります。「伝える力」や「影響力」に注目した構成が効果的です。
⑩インフラ業界における企業選びの軸
インフラ業界を志望する学生には、「安心して暮らせる社会を支えたい」という想いを持つ方が多いです。ここでは、自然災害を通してインフラの重要性を実感した学生の例文を紹介します。
《例文》
| 大学1年のとき、大きな台風で自宅周辺が停電した経験がありました。 電気や水が使えず、当たり前にあった生活が一変した中で、復旧作業にあたる人々の姿を見て「誰かの暮らしを支える仕事」の大切さを強く感じました。 この経験をきっかけに、人々の生活基盤を守るインフラに関心を持つようになりました。生活に直結するサービスを安定的に届けるには、目立たないけれど確かな責任感と技術力が必要だと感じています。 そのため、企業を選ぶ際には、社会的な使命感を持ち、安定したサービス提供に力を入れているかどうかを軸としています。 |
《解説》
身近な災害体験を通じて感じた社会貢献意識を軸にしています。生活と密接に関わるテーマなので、自分の言葉で実感を語ることがポイントです。
企業選びの軸を伝える際のNG例文

企業選びの軸は、自分の価値観や志向を企業に伝える大切な要素ですが、伝え方を間違えるとマイナス印象を与えてしまうこともあります。
ここでは、実際にありがちなNG例文を紹介しながら、どのような点が問題なのかを具体的に解説していきます。
①企業研究が不足している場合のNG例文
企業選びの軸を語る際、企業研究が不十分だと説得力のない内容になってしまいます。ここでは、企業理解が浅いまま話してしまったNG例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学時代にゼミ活動を通じてチームで成果を出す喜びを知りました。 その経験から、私は「チームワークを大切にする企業で働きたい」と考えるようになりました。御社は多くの社員が活躍しており、雰囲気も良さそうだと思ったため志望しました。 また、貴社の事業内容も幅広く、いろいろなことにチャレンジできそうだと感じました。自分の成長にもつながると考えています。 将来的には、プロジェクトのリーダーなどにも挑戦していきたいと思っています。 |
《解説》
この例文では、「チームワークを大切にする企業」「雰囲気が良さそう」といった曖昧な表現が多く、企業研究が浅いことが伝わってしまいます。
評価されるには、企業の具体的な制度や文化、業務内容に触れた上で、自分の価値観や経験との接点を明確に示すことが重要です。
企業研究が不十分なままの軸は、採用担当に「どこでも言える話」と捉えられてしまうので注意しましょう。
②待遇面ばかりを強調するNG例文
就活では「安定」「給与」「福利厚生」など待遇面を軸にしたくなる気持ちは自然ですが、それだけを前面に出すとマイナス評価につながります。
ここでは、待遇面だけに焦点を当てたNG例文を紹介します。
《例文》
| 私は将来的に安定した生活を送りたいと考えており、そのためには給与や福利厚生が整っている企業が理想的だと感じています。 貴社は業界内でも高い水準の給与を提供していると知り、安心して長く働ける環境だと思い志望しました。 また、住宅手当や休暇制度なども充実しており、自分のライフスタイルを大切にできると感じています。 働くからには安定が一番重要だと考えているので、待遇の整った企業で自分の時間も大切にしながら働きたいです。 |
《解説》
この例文は、志望理由がすべて「待遇ありき」で構成されており、仕事への意欲や企業とのマッチ度が伝わりません。
企業選びにおいて待遇を重視するのは悪いことではありませんが、それだけでは「やりがい」や「成長意欲」が見えにくくなります。
まずは仕事内容や企業の理念など、自分との接点を伝えた上で、補足的に待遇面に触れるようにしましょう。
③抽象的すぎる表現を使ったNG例文
就活の軸を語る際に「やりがい」や「成長」といった抽象的な表現を使いすぎると、何を伝えたいのかが不明瞭になります。ここでは、意味が曖昧な言葉ばかりで構成されたNG例文を紹介します。
《例文》
| 私は学生時代に飲食店でのアルバイトを通じて、社会人としての基本を学びました。 その経験から、社会に出ても人とのつながりを大切にしながら、やりがいを持って働ける会社に入りたいと思うようになりました。 御社は働きやすい環境が整っており、社員同士のつながりも強いと聞いています。そのため、自分の成長につながると思い、志望しました。 将来は、多くの人と関わりながら社会に貢献できるような仕事をしていきたいです。 |
《解説》
この例文では、「やりがい」「つながり」「成長」「社会に貢献」といった抽象的な言葉ばかりで構成されており、何を軸にしているのかが伝わりにくくなっています。
評価されるためには、自分の経験をもとに、なぜそれを重視するようになったのか、そして企業のどんな要素に共感したのかを具体的に示すことが重要です。
曖昧な表現は避け、自分の言葉で語るようにしましょう。
④主体性が感じられないNG例文
企業選びの軸を語る際に、受け身の姿勢が強調されすぎると「他人任せ」な印象を与えてしまいます。ここでは、主体性が感じられないNG例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学生活を通じて、まだ自分が何をやりたいのか明確にはなっていません。しかし、周囲の友人たちが就職活動で御社に興味を持っていると聞き、自分も関心を持ちました。 説明会に参加した際、働きやすそうな印象を受けたので、ぜひ自分も挑戦してみたいと思いました。特に、先輩社員が優しそうだった点が魅力的でした。 まずは環境が整っている企業で社会人経験を積み、自分に合った働き方を見つけていきたいと考えています。 |
《解説》
この例文では「自分が何をやりたいのか明確ではない」「友人の影響で志望した」など、軸が他人に依存しており、自主的な意思が感じられません。
企業選びの軸は、自分の経験や価値観をもとに構築してみてください。自分の言葉で語ることが、主体性と意欲を伝える鍵になります。
何をしたいのか分からない場合でも、過去の経験を深掘りして「なぜそれに惹かれるのか」を考えるようにしましょう。
⑤企業との関連性が弱い軸を挙げたNG例文
企業選びの軸がその企業と無関係な内容だと、説得力に欠けてしまいます。ここでは、自分の価値観ばかりが先行し、企業との接点が弱いNG例文を紹介します。
《例文》
| 私は学生時代から音楽が好きで、バンド活動に力を入れてきました。人に感動を与えることにやりがいを感じた経験から、就職先も「感動を届けられる仕事」に就きたいと考えています。 御社は安定しており、業績も好調と聞いています。働く環境も整っていると感じたため、感動を届ける仕事ができるのではないかと思い志望しました。 将来的には、自分のアイデアで多くの人に驚きや喜びを与えるような仕事に携わりたいです。 |
《解説》
この例文は、「感動を届けたい」という軸に対して、企業の具体的な事業や価値との関連づけが弱く、なぜその企業でなければならないのかが伝わってきません。
評価されるには、企業の提供する商品やサービス、理念と自分の軸がどうつながるのかを具体的に説明する必要が存在します。
企業理解を深めたうえで、軸との接点をしっかり言語化しましょう。
自分らしい企業選びの軸を明確にしておこう!

企業選びの軸を定めることは、就職活動において非常に重要。なぜなら、軸が明確になることで、志望動機に一貫性が生まれ、面接でも説得力のあるアピールができるからです。
また働き出してのズレを防ぎ、長期的に活躍できる企業と出会いやすくなるでしょう。企業側も、面接で選びの軸を確認することで、価値観の一致や入社意欲の高さを見極めています。
Can・Want・Mustの3つの観点から自分に合う軸を見つけるためには、自己分析や業界研究、インターンなどの体験が欠かせません。
軸を伝える際は、結論を先に述べ、エピソードで具体性を加えることで、企業とのマッチ度を効果的にアピールできます。
軸を明確に持つことが、納得のいく企業選びと、将来のキャリア形成の第一歩となるのです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









