最終面接の結果が遅い理由とは?連絡が来ない時の対処法やその際の注意点も紹介
「最終面接を終えてから数日…まだ連絡が来ない。もしかして落ちたのかな?」就職活動の中でも、最終面接の結果待ちは特に不安が募る時間ですよね。
合否の連絡がなかなか来ないと、「もうダメだったのかも」とネガティブに考えてしまいがちですが、実は結果が遅いのにはさまざまな理由があるのです。
この記事では、最終面接の結果が遅れる理由や企業の特徴、そして連絡が来ないときの適切な対処法を詳しく解説します。
さらに、結果待ちの間に就活生がすべきことや、問い合わせの際の注意点・例文も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る最終面接の結果が届くまでの目安はいつ?

最終面接の結果は、一般的に3営業日から1週間以内に届くのが目安です。この目安を知っておくことで、いたずらに不安になることを防げます。
最終面接のあとは他社の選考や内定承諾の判断を控えている人も多いため、結果がいつ届くかをあらかじめ把握しておくことは非常に重要です。
たとえば、ベンチャー企業や中小企業の場合は翌営業日など早期に連絡が届くことも。
一方で、大手企業では社内手続きやスケジューリングの都合から、平均して5営業日程度かかるケースが通例となります。
また、面接時に「1週間以内にご連絡します」と伝えられた場合は、その期間を基準に判断すると安心です。
このように、最終面接後の結果通知は、早い場合は3日、遅くとも1週間前後がひとつの目安。土日祝を除いた営業日ベースで日数を数えることで、より正確な感覚で待てるでしょう。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
最終面接の合否通知が遅くなる主な理由とは?
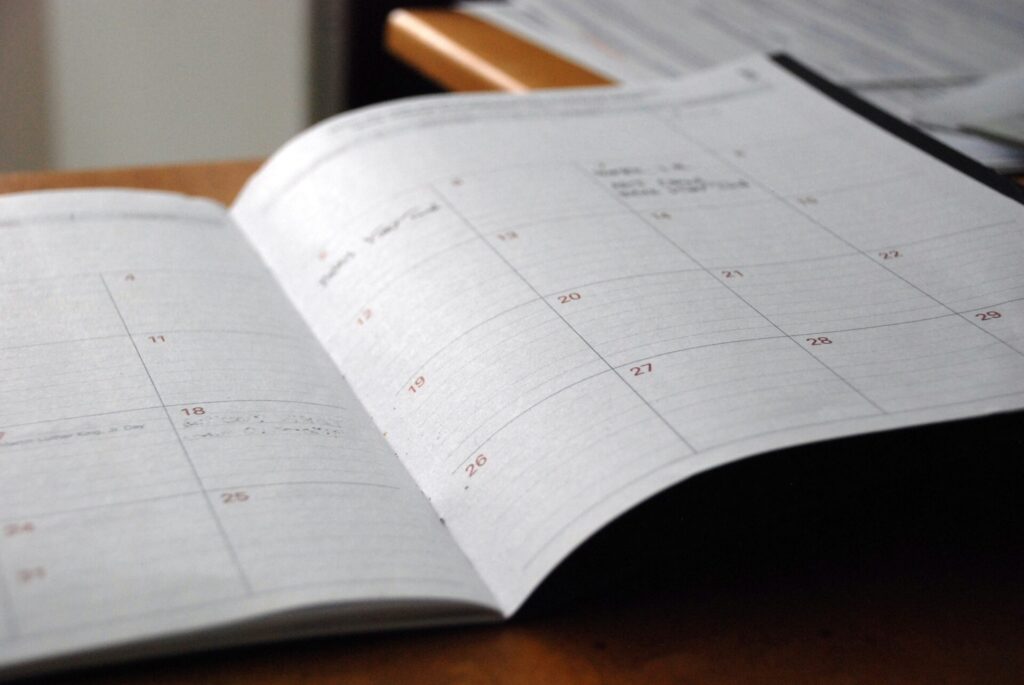
最終面接を終えたあと、結果連絡を待つ時間は不安が膨らむものです。とくに数日たっても通知が来ないと、「落ちたのでは」と心配になる方も少なくないでしょう。
ただ、応答が早くないのは企業側の事情があります。ここでは、最終面接の合否通知が遅くなるよくある理由を理解して、無用な不安を減らせるようにしましょう。
- 応募者全員の選考が終了していないため
- 選考結果の判断が社内で一致しないため
- 補欠合格として保留中のため
- 採用担当者が多忙で対応が遅れているため
- 先に合格者へ連絡を行うため
- 不合格者への配慮で連絡が後回しになっているため
① 応募者全員の選考が終了していないため
企業では最終面接を複数日に分けて実施することが多く、すべての候補者の面接が終わるまでは合否の判断ができません。
自分の面接が早く終わっていたとしても、他の候補者の面接を待ちます。これは公平な選考のために当然ともいえる対応です。
通知が来るまでの期間に気をもむのは自然なことですが、焦っても結果は変わらないため、企業側からの正式な連絡があるまで静かに待つ姿勢を心がけましょう。
また、面接の順番は選考結果に影響しないことが一般的ですので、早く面接が実施されたこと自体を気にする必要もありません。
実際に私たちも、全員の面接が終わるまで判断を下せないことが多いですね。複数の部署や役員が関わる場合には全員の意見を聞くため、より連絡が遅れてしまうこともあります。
また、先に受けた人も後に受けた人も同じ基準で評価しているため、面接の順番は気しなくて大丈夫ですよ。連絡を待っている間に、業界研究や面接の振り返りを進めましょう。
② 選考結果の判断が社内で一致しないため
最終面接では複数の面接官が同席し、それぞれが応募者に対して独自の視点で評価を行います。
全員の意見が一致すればスムーズに結論が出ますが、ときには評価が分かれ、合否を決めるために再度社内で審議が実施されることもあるのです。
このような場合、追加の面談や会議の調整に時間がかかることがあり、結果通知もその分遅れがちになります。
評価が割れているというのは、あなたに強みがある証拠でもあるため、マイナスにとらえずに前向きに受け止めましょう。
判断の処理が遅れているからこそ、慎重に検討してもらえている証といえます。
評価が割れた時には、最終決定権を持つ役員や部門長との会議の日程を合わせるのに決定に時間を要し、連絡が遅くなってしまうことがあります。特に大手企業では関係者が多く、より時間がかかることも。
実際に私たちも判断に迷った際に追加面談を行うことがあります。追加面談はお互いのミスマッチを防ぎ納得できる結論を出すための機会なので、あまり気負わずに参加してくださいね。
③ 補欠合格として保留中のため
企業の中には、最終面接後にすぐに合格・不合格を出さず、一定数の候補者を補欠として保留にしておく場合があるかもしれません。
これは他の内定者の辞退や辞退率の予測を考慮し、採用予定人数を柔軟に調整するための戦略のひとつです。
通知が来ないことで「不合格なのでは」と不安に思うかもしれませんが、補欠合格という可能性も十分あります。
実際に補欠から繰り上げで内定となることも多く、焦って自ら問い合わせたり落ち込んだりする前に、まずは冷静に状況を見守ることが大切です。
会社によっては補欠でも丁寧に扱うところもあり、チャンスは残されています。
④ 採用担当者が多忙で対応が遅れているため
就職活動の繁忙期には、多くの企業で人事担当者の業務が集中します。
エントリーシートの精査や面接の日程調整、社内との連絡、さらには内定者への対応まで、多岐にわたるタスクを抱えているのが実情です。
したがって、結果通知が滞るのは業務の都合上やむを得ないこともあります。
特定の候補者だけに限らず、全体的に連絡が遅れているケースも多く見られるため、他の就活生と比較して自分だけが遅れていると早合点するのは避けたいところです。
一定期間が過ぎても連絡がない場合は、確認の連絡をする前にまず企業側の状況を想像して、数日間は余裕を持って待ちましょう。
⑤ 先に合格者へ連絡を行うため
採用活動では、まず第一に内定を出す相手に迅速に連絡することが重視されます。なぜなら、優秀な人材ほど他社からも声がかかっているため、連絡が遅れれば内定辞退のリスクが高まるからです。
そのため、合格した者には迅速に通知を送り、それ以外の候補者には後から連絡する方針をとる企業も起こり得ます。
これによって通知の時期に差が出ることがありますが、それは選考結果とは関係のない事務的な優先順位によるものです。
自分が後回しにされたと感じても、悲観的に受け取る必要はありません。
⑥ 不合格者への配慮で連絡が後回しになっているため
企業が不合格の通知を出す際には、慎重な対応を取る傾向が見られます。
とくに、熱意をもって面接に臨んだ学生に対しては、丁寧な文章を用意したり、電話で直接伝えたりと、気遣いを込めた対応を行うこともあるのです。
その準備に時間を要するため、返答が遅れることもあります。不合格通知が遅いからといって、企業の誠意がないことに該当しません。
むしろ、丁寧な対応をしたいという気持ちの表れともいえるでしょう。
すぐに結果が来ないからと焦らず、企業の意図をくみ取ることで、気持ちを少しでも落ち着けることができるはずです。
面接が不安な人必見!振り返りシートで「受かる」答え方を知ろう

面接落ちを経験していくと、だんだんと「落ちたこと」へのショックが大きくなり、「どこを直せばもっとよくなるんだろう?」とは考えられなくなっていくものですよね。
最終的には、まだ面接結果が出ていなくても「落ちたかも……」と焦ってしまい、その後の就活が空回ってしまうことも。
「落ちた理由がわからない……」「次も面接落ちするんじゃ……」と不安でいっぱいの人にこそおすすめしたいのが、就活マガジンが無料で配布している面接振り返りシートです!
いくつかの質問に答えるだけで簡単に面接の振り返りができ、「直すべき箇所」「伸ばすべき箇所」がすぐに分かりますよ。また、実際に先輩就活生が直面した挫折経験と、その克服法も解説しています。
面接の通過率を上げる最大の近道は「過去の面接でどうして落ちた・受かったのか」を知ることです。面接の振り返りを次に活かせれば、確実に通過率は上がっていきます。
「最終面接の結果が遅くてどうしたらいいかわからない……」と思っている人も、まずは面接振り返りシートで、「次の面接への活かし方」を学んでいきましょう。
最終面接の結果が遅い傾向のある会社の特徴

最終面接の結果が届かず、不安になる就活生は多いでしょう。企業によって通知までのスピードに差があり、「なぜこんなに遅いのか」と疑問に感じる場面もあります。
ここでは、結果通知が遅くなる企業の特徴について、具体的に紹介します。
- 採用人数が多い大手企業
- 応募者が殺到する人気企業
- 採用担当者が少ない中小企業やベンチャー企業
- 繁忙期と選考時期が重なっている企業
- 決裁権が海外にある外資系企業
- 採用予定人数が少ない企業
- 職種別に選考を行っている企業
- 社内決裁フローが長い企業
① 採用人数が多い大手企業
大手企業は採用規模が大きいため、選考規模が大きくなりやすいです。
最終面接後は、多数の候補者の評価を集計し、全体を比較して判断する必要があるかもしれません。
そのため、合否連絡に時間がかかることはありがちなことです。不安な場合は、企業の採用ページで合否通知の目安期間を確認しておくと安心でしょう。
大手企業では、部署ごとに採用枠が細かく設定されていることが多いです。そのため、最終面接後に各部署からの評価を集めて全体調整を行う必要があり、結果連絡まで1〜2週間かかってしまうこともあります。
また、採用人数が多い大企業では、内定承諾率の見込みも重視されていますよ。内定を出しすぎても調整が難しいため、候補者同士を慎重に比較していることが多いです。焦らずに連絡を待ってくださいね。
② 応募者が殺到する人気企業
人気企業では応募者が非常に多くなります。
この場合、面接官のスケジュール調整や評価の集約に時間がかかりやすく、結果通知も遅れがちです。
通知が届かないからといってすぐに不合格と決めつけず、余裕を持って待つことが大切でしょう。
人気企業では、一次から最終面接までの各段階で、膨大な応募者データが集まります。これを部門ごとに評価し、最終的な判断をするためには、どうしても時間がかかってしまうのです。
また、採用のピーク時は、会議の日程調整に時間がかかってしまうこともあります。企業は「合否を出す速さ」よりも「納得できる判断」を重視しているので、連絡が遅くても心配しないでくださいね。
③ 採用担当者が少ない中小企業やベンチャー企業
中小企業やベンチャーでは、人事担当者が少人数で複数業務を兼任していることがよくあります。
このため、選考から通知までに時間を要するケースが存在します。
担当者の負担が大きい背景を理解しておけば、必要以上に焦らずに済むでしょう。
④ 繁忙期と選考時期が重なっている企業
企業の業務が忙しい時期と選考が重なると、合否の連絡が滞りやすくなります。
特に年度末や期末のような繁忙期では、面接官や決裁者が本来の業務に追われ、選考が優先されないこともあります。
遅れがあっても落ち着いて対応してください。
実際に私たちも、繁忙期に最終面接が行われた場合、合否の連絡が遅れることがあります。年度末や期末は最終判断を下す役員や部門長のスケジュール確保が難しいこともあり遅れがちです。
特に大手企業などは、1人の判断待ちで全体の進行が止まってしまうこともあります。面接評価はすでにまとまっていて、正式に連絡に時間がかかっているということもあるので焦らず連絡を待ってくださいね。
⑤ 決裁権が海外にある外資系企業
外資系企業では、合否の最終判断が海外本社にあることもあります。
そのため、国内の選考が終わっても、本国からの承認を待つ必要があり、通知が遅れる原因になるのです。
時差やビジネスの予定の違いも関係するため、日数がかかるのは当然ともいえるでしょう。
⑥ 採用予定人数が少ない企業
採用予定人数が限られてしまっている企業では、1人の採用が社内に与える影響も大きいため、慎重に判断になりやすい傾向にあります。
このため、結果の決定が長引くことが多いのです。
通知が遅れても、丁寧に選考してもらっている証拠だと前向きに捉えてみてください。
⑦ 職種別に選考を行っている企業
職種ごとに選考フローが異なる企業では、部署間の調整が必要になるケースが発生します。
その影響で、結果通知までのスピードにばらつきが出ることも少なくありません。
同じ企業でも、職種によって合否連絡の時期がずれている場合もあります。
⑧ 社内決裁フローが長い企業
採用関係者が多く、複雑な組織を持つ企業では、決裁に関わる承認プロセスも多段階になります。
このため最終面接後も社内での調整が続き、結果通知に時間がかかる場合があるでしょう。
これは構造上避けにくいため、焦らずに待つことが必要です。
最終面接の結果が届かない場合の対応方法

最終面接を終えてから数日経っても連絡がないと、不安や焦りを感じる方が多いかと思います。しかし、合否通知が遅れている理由は様々で、自分だけで結論を急ぐのは早計です。
採用活動には予想以上に時間がかかることもあり、まずは冷静に状況を確認することが何より大切です。
ここでは、最終選考の合否が届かない場合に取るべき対応を、段階を追って詳しく紹介します。無用な不安を避け、適切な判断と行動をとるための参考にしてください。
- 面接日から2週間以上経過しているか確認する
- 迷惑メールや不在着信のチェックをする
- 他の連絡手段がないか確認する
- 採用ページに連絡方針が記載されていないか確認する
①面接日から2週間以上経過しているか確認する
選考結果の通知は、企業によってタイミングが異なります。
一般的には1週間から10日ほどで連絡が来るとされていますが、役員面接など社内調整が多い場合や、候補者が多数いる場合には、さらに数日を要することも。
したがって、面接から1週間程度で連絡がないからといって、即座に不安になる必要はありません。また、祝日や連休を挟むと、通知が遅れることは珍しくないです。
社内で複数部門の意見をまとめている途中という可能性も考えられるため、最低でも2週間は待つ姿勢が望ましいでしょう。
どうしても気になる場合でも、2週間を目安にして問い合わせるようにすれば、企業側に失礼なく確認を行うことができます。
面接後の2週間は、社内で評価を確認している可能性が高いです。他候補者と比較に時間がかかっていて、正式な判断がまだ決まっていないこともあるので、早すぎる連絡は避けましょう。
面談で結果連絡の話を聞くと、「結果が出るまでの期間は業種や時期によって異なる」と言っている就活生も多いです。決算期や採用ピーク期は2週間を過ぎるケースもあるのであまり焦らなくても大丈夫ですよ。
②迷惑メールや不在着信のチェックをする
「連絡が来ていない」と思い込んでいても、実際には通知が届いているケースも珍しくありません。
たとえば、GmailやYahoo!メールでは、就活生へ届くメールが迷惑メールフォルダに自動で振り分けられてしまいます。
また、スマートフォンの通知設定がオフになっていたり、PCのプロモーションタブに埋もれていたりすることもあるため、フォルダを分けて使っている方は念入りにチェックしましょう。
加えて、電話連絡の可能性にも注意が必要です。不在着信や留守番電話のメッセージを確認し、必要であれば折り返し連絡することで、連絡の行き違いを防げますよ。
私たちも相談を受ける中で、「メールや着信を見落としていた」という人をよく見かけます。迷惑メールに分類されないように、受信許可リストに企業のドメインを登録しておくと安心ですよ。
また、サーバー遅延で通知が遅れていることもあります。迷惑メールや不在着信の確認は一度だけでなく、時間をおいて再確認する習慣をつけるようにしましょう。
③他の連絡手段がないか確認する
選考先から届く連絡は、必ずしもメールや電話だけとは限りません。
特に大手企業では、エントリー時に登録したマイページや、就職エージェント経由での通知、LINE公式アカウントなど、さまざまな連絡手段が使われることがあるはずです。
マイページ上にログインしなければ確認できない形式を取っている企業も多く、通知が来ないと思っていても、実はページ上にすでに表示されているということも起こり得ます。
また、エージェントを介して応募した場合には、企業から直接ではなくエージェントの担当者を通じて連絡が来ることがあります。
自分がどの手段で応募したかを整理し、それぞれのチャネルを定期的に確認しておくと安心です。
こうした確認を怠ると、合否結果を見逃してしまうリスクがあるため、あらゆる可能性を一度洗い出しておきましょう。
④採用ページに連絡方針が記載されていないか確認する
多くの企業では、選考ページやFAQに合否連絡の方針を明記しています。
たとえば、「選考通過者のみにご連絡いたします」「3週間以内に結果をご案内します」などの記載がある場合、それを確認することで不要な問い合わせを避けられます。
問い合わせる前に一度企業の公式サイトを見直してみましょう。さらに、マイページを作成している企業の場合は、ログイン後にしか確認できない連絡方針が記載されていることも。
場合によっては、「〇月〇日までに連絡がない場合は不採用とご判断ください」という明確な案内がある場合もあるので、採用に関する情報は見落としのないよう確認をしましょう。
必要であれば、スクリーンショットなどで保存しておくと後々役立ちます。これらの対応を取ったうえで、それでも連絡がない場合には、はじめて問い合わせを検討しましょう。
最終面接の選考結果を問い合わせる際の注意点

最終面接のあと、結果がなかなか届かず不安になる就活生は多いでしょう。ただ、企業に連絡を取る際には、慎重な姿勢と丁寧な言葉遣いが欠かせません。
問い合わせ方によっては、企業に不信感を与えてしまう可能性もあるため、正しいアプローチが求められます。
ここでは、選考結果を問い合わせる際に気をつけたいポイントを、具体的なシチュエーションとともに3つの観点から丁寧に解説します。
社会人としてのマナーや印象にも関わる場面だからこそ、細かな点にも注意を払いましょう。
- 連絡する時間帯を配慮する
- 相手を責めない丁寧な表現を使う
- 連絡手段や内容を状況に応じて選ぶ
①連絡する時間帯を配慮する
企業に問い合わせを行う際は、相手が業務に集中している時間帯や、忙しい時間を避けることが重要。たとえば、始業直後は朝の会議やメール処理、終業前は日報作成や業務整理などで多忙な時間帯です。
そのため、午前10時〜11時や午後2時〜4時のような、比較的余裕があるとされる時間帯を選ぶとよいでしょう。
また、曜日にも気を配ることができればさらに良い印象を与えられます。月曜日の午前中や週末の直前は避け、火〜木曜あたりに連絡するのが無難です。
連絡する際には、急ぎでなければまずはメールで概要を伝えておくことがおすすめです。メールなら忙しくても空いた時間で確認できますし、その後に電話する際もやり取りがスムーズになります。
また、月曜は会議ラッシュ、金曜は翌週準備で慌ただしいことが多いです。私たちも電話を受ける側の立場だと、火曜や水曜の午後は余裕を持って対応できると感じるので曜日も意識してくださいね。
②相手を責めない丁寧な表現を使う
選考結果を待つ間、不安や焦りの感情が募るのは当然のことです。しかし、その感情をそのまま問い合わせ文に反映させてしまうと、企業に対して圧をかける印象を与えてしまいます。
特に「まだですか?」「急いでいるので早く返事をください」といった言い回しは、非常に高圧的に受け取られるシーンも見られます。
問い合わせの際は、常に相手の状況を思いやった表現を心がけましょう。
たとえば、「お忙しいところ恐縮ですが、選考結果のご状況についてご教示いただけますと幸いです」といった言い回しは、丁寧でありながら要点も明確です。
また、自分がどの選考段階にいたのか(例:〇月〇日の最終面接を受けた〇〇と申します)を明記することで、相手の確認作業もスムーズになります。
連絡をする前に一度、伝えたい内容の「下書き」や「メモ」を書いてみてください。書いた後に読み直してみて、「丁寧な表現になっているか」「相手に失礼な表現がないか」確認すると安心ですよ。
また、相手がすぐに回答できない状況を踏まえた表現にしてみましょう。例えば「お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いします」と記載すると「丁寧な人」という印象を持たれやすいですよ。
③連絡手段や内容を状況に応じて選ぶ
選考結果の問い合わせには、メールを基本としつつも、状況に応じて電話の活用も検討する必要があります。
メールは記録が残るためトラブル防止にもなりますし、相手に考える時間を与えるという利点もあります。
ただし、メールを送っても数日間返信がない場合や、早急な返答が必要な場合は、電話連絡を視野に入れましょう。
その際もいきなり電話をかけるのではなく、まずは「お電話にてご連絡差し上げてもよろしいでしょうか」とメールで事前に確認を入れるとより丁寧です。
また、問い合わせ内容についても、単に「合否を教えてください」と尋ねるのではなく、「ご連絡予定日について確認させていただけますでしょうか」といった、企業の判断を尊重した聞き方が好印象です。
最終面接の選考結果を問い合わせる際の例文

面接後、結果の連絡がなかなか届かず不安になっている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、そんな状況で選考結果を丁寧かつ適切に問い合わせる方法について、メール・電話それぞれの例文を交えて解説します。
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
①メールで問い合わせる場合
最終面接後、なかなか結果の連絡が来ず不安に感じている方向けに、選考結果を丁寧に問い合わせるためのメール例文をご紹介します。相手に失礼なく気持ちを伝える文章構成がポイントです。
《例文》
| 件名:選考結果についてのご確認(〇〇大学 氏名) 株式会社〇〇 人事部 採用ご担当者様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の氏名と申します。 先日は最終面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。 選考結果についてご連絡をいただけると伺っておりましたが、まだご返信をいただいておらず、念のためご確認させていただきたくご連絡いたしました。 ご多忙のところ恐縮ですが、選考状況につきまして差し支えなければご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
《解説》
相手への感謝と配慮を前提に、問い合わせの理由を簡潔に伝えることが大切です。件名はシンプルに要件が伝わるものにしましょう。
メールでの問い合わせは、読み手が一目で内容を理解できるようにすることが大切です。件名で「誰から」「何の件で」連絡が来たのか瞬時にわかるようにすると、企業側がメールを見落とすことも少なくなります。
また、本文は事実を簡潔にまとめるのが基本ですが、最後の締め方も重要です。「ご多忙のところ恐れ入りますが~」のように配慮を示すと、企業側からの好印象を保ちやすくなりますよ。
②電話で問い合わせる場合
最終面接から数日以上経過しても連絡がない場合、電話での問い合わせも選択肢の一つです。ここでは、緊張せず丁寧に問い合わせるための会話例をご紹介します。
《例文》
| (電話がつながった後) 「お忙しいところ恐れ入ります。〇〇大学〇〇学部の氏名と申します。 先日、最終面接を受けさせていただきました件でお電話いたしました。 選考結果についてご連絡をいただけるとのことでしたが、まだ拝受しておりませんでしたので、念のため確認させていただきました。 担当の方はいらっしゃいますでしょうか?」 (担当者につながった場合) 「お世話になっております。〇〇大学の氏名です。 先日はお時間をいただきありがとうございました。 ご多忙のところ大変恐縮ですが、現在の選考状況についてお伺いできればと思いご連絡させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。」 |
《解説》
電話では名乗りと要件を簡潔に伝えることが重要です。丁寧な言葉遣いと、相手への配慮を意識した一文を入れると印象がよくなります。
電話での問い合わせは、採用担当者が不在の場合も想定しておきましょう。「伝言で済む内容」と「直接聞くべき内容」を区別しておくと、スムーズな連絡ができるので意識してみてください。
また、問い合わせの時間帯にも注意が必要です。午前は会議や打ち合わせ、午後は来客対応が多い企業もあります。業務が落ち着きやすい昼過ぎなど、相手が出やすい時間にかけるようにしましょう。
最終面接の結果待ちの間に就活生がやるべきこと

最終面接の結果を待つ時間は、不安や焦りが募るものです。しかし、この期間を有効に使うことで、今後の選考やキャリアに良い影響を与えられます。
ここでは、結果待ちの間に取り組んでおきたいことを紹介します。
- 最終面接の内容を振り返って改善点を整理する
- 他社の選考準備やエントリーを進める
- 志望企業の入社後を想定し懸念点を整理する
- 現在の選考状況と志望度を見直す
① 最終面接の内容を振り返って改善点を整理する
最終面接の結果を待っている間は、面接でのやりとりを冷静に思い返す良い機会です。緊張して言葉が詰まった場面や、うまく答えられなかった質問などを振り返り、原因を分析してみてください。
たとえば、企業研究が浅かったと気づいた場合は、今後はその点を重点的に準備するとよいでしょう。振り返ることで、自分の課題が明確になり、次の面接への対応力が高まります。
結果に一喜一憂するだけでなく、経験を成長につなげる意識が大切です。また、面接官の反応や雰囲気を思い出すことも、自己分析の手がかりになります。
どの回答で興味を示してくれたのか、自信を持って答えられた質問は何だったかを整理することで、自分の強みを再認識できるでしょう。
面接直後は記憶が鮮明なので、振り返りをするのにぴったりな期間です。特に「曖昧だったな」と思う回答や「根拠が話せなかった質問」は次回に向けて改善できるようにしましょう。
私たちも面談で就活生に「面接官が深掘りした質問は何か」を確認しますね。面接官の反応や表情の変化も思い出せれば、「自分のどこに魅力を感じてくれたのか」を知るいい機会になりますよ。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
② 他社の選考準備やエントリーを進める
結果を待っている時間に気持ちが停滞してしまうのはもったいないことです。合否に関係なく、他社の選考を同時に進めることは、選択肢を広げるうえでとても重要です。
ただ待っているだけでは時間を無駄にしてしまいますし、複数の企業を比較することで本当に自分に合う企業に出会える可能性も高まります。
さらに、他社の情報収集や企業研究をしておくことで、業界全体の理解も深まります。幅広い視点を持つことは、結果として自分の志望動機をより具体的にする材料にもなるでしょう。
③ 志望企業の入社後を想定し懸念点を整理する
最終面接を終えた今こそ、その企業で働くことを現実的に考えるタイミングです。勤務地や業務内容、人間関係など、入社後の生活を具体的にイメージしてみましょう。
期待していたことと現実とのギャップに気づけるかもしれません。たとえば、福利厚生やキャリアパスについて改めて調べてみるのも良い手です。
内定をもらったときに即断するのではなく、自分にとって本当に納得のいく選択ができるよう、今のうちに整理しておきましょう。
加えて、その企業でどのように成長していきたいかを考えることも大切です。
自分の目標に向かってキャリアを積んでいけるか、社風に自分がなじめそうか、将来的な異動や転勤の可能性はどうかなど、多角的な視点で検討することで、不安要素をあらかじめ洗い出しておけます。
選ぶ側としての視点を持つことで、後悔のない選択につながるはずです。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④ 現在の選考状況と志望度を見直す
複数の企業と選考が同時進行していると、自分の中での優先順位が曖昧になってくることもあります。
最終面接の結果を待つ今こそ、自分の選考状況を整理し、志望度の高い企業や希望条件を見直してみましょう。
どの企業に最も魅力を感じているのか、どんな働き方をしたいのかを明確にすると、次の面接や意思決定の場面でも自信を持って話せるようになります。
軸がはっきりすれば、迷いや不安も少なくなるでしょう。さらに、これまでの応募先企業に共通する特徴を分析することで、自分でも気づいていなかった志向や価値観が見えてくるかもしれません。
その傾向を把握することで、今後の企業選びの精度も高まりますし、選考に臨む際の志望動機にも深みが出るでしょう。
最終面接の結果が遅いときこそ、前向きに行動しよう!

最終面接の結果がなかなか届かないと、不安になるのは当然です。結論から言えば、遅れにはさまざまな理由があり、落ち着いて対応することが大切です。
たとえば、応募者全員の選考が終わっていなかったり、社内で判断が分かれていたり、担当者の多忙や社内決裁の遅れが影響しているケースがあります。
そのため、まずは面接から2週間以上経過しているかを確認し、迷惑メールや不在着信のチェックを行いましょう。企業の採用ページに記載された連絡方針を確認することも有効です。
問い合わせる際は、相手に配慮した丁寧な言い方で、合否ではなく連絡時期について確認するのがポイントです。結果を待つ時間は無駄ではありません。
不安な時こそ前向きに、自分の可能性を信じて行動していきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














